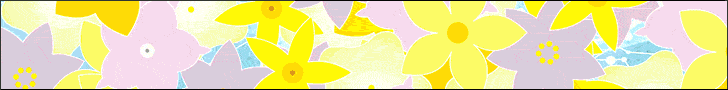どこへいった? 農産物への軽減税率導入論 2015年9月16日
このままなら痛税感から買い控え懸念も農業経営をさらに圧迫
消費税を10%に引き上げる際には、食料品などに軽減税率を導入することを自公両党は議論してきたが、9月初めに財務省は酒類を除く飲食料品にかかる2%分はマイナンバーカードを使って、後から消費者に「還付」する案を公表した。
低所得層をはじめ消費者の負担を軽減する「日本型軽減税率制度」だというが、この案では飲食料品もすべて消費税10%に引き上げられ、購入の際の痛税感は緩和されない。また“還付”制度などというがそもそも消費税の納税義務者である事業者(=農業者)への還付はない。「聞こえのいい“還付”という言葉を使い、実のところはマイナンバーカードの普及策に過ぎないのでは」、「食品も10%引き上げ。買い控えが起きて、結局は消費税分を転嫁できず農業経営を圧迫することにならないか」などの批判の声が高まっている。
◆改めて消費税とは?
「消費税の仕組みのトリックを使ったまったく論外の話です」。
今回の財務省案をこうばっさり斬るのは元静岡大学教授で税理士の湖東京至氏だ。本紙では消費増税が議論された3年前、湖東氏からわれわれが誤解しやすい消費税の根本的な問題を提起してもらった。改めて整理しておく。ポイントは3つだ。
(1)消費税の納税義務者は消費者ではなく「事業者」とされている。一方、「担税者」という規定もない。
(2)したがって、担税者の規定がないから消費税とは消費者だけが払っているわけではなく、消費者と事業者、あるいは事業者同士の立場や力関係で負担が決まる。
(3)消費税法には「転嫁」という言葉はない。導入時(平成元年)の税制改正法に「円滑かつ適正に転嫁するものとする」とあるだけ。
実際、納税義務者である事業者は、1年間の(売上高×消費税率)-(仕入高×消費税率)を計算して納税する。これが消費税である。本紙は繰り返し指摘してきたが、法人税であれば人件費を差し引いた結果、赤字であれば課税されないが、消費税は仕入れたモノから生み出された付加価値(売上高-仕入高)に課税される。つまり、赤字の零細企業にも課税される。
「消費税とは事業者の努力によって納められている税です。多くの人が基本を誤解している」(湖東氏)のだが、今回の財務省案はまさにその誤解を悪用しているといえる。つまり、消費税の仕組みを考えれば負担軽減のための還付は納税義務者にも手当されるべきなのに、そこを避け「面倒くさい」(麻生財務相)と消費者への還付という話で済まそうとしてしまっているのだ。
消費税はそもそも廃止すべき税制だという立場の湖東氏は、諸外国で広く導入されている軽減税率にも反対で「国民の批判をかわす延命策でしかない」と批判する。しかし、「今度の案はそれ以上にひどい。消費税引き上げで低所得者をはじめ国民に迷惑をかけるというなら消費税とは関係なく一律に一家庭いくら支給するという方式のほうがずっといい。この案はマイナンバーカードの普及と定着のために、少しメリットをつけてやろうという"筋違いの話"でしかありません」と手厳しく指摘する。
◆価格転嫁は困難
 税率が複数になる軽減税率を導入すると事業者にとって負担になるという見方もある。
税率が複数になる軽減税率を導入すると事業者にとって負担になるという見方もある。
それでもJAグループが軽減税率の導入を求めたのは川下のバイイングパワーが強く、農業者は消費増税分の価格転嫁ができない状況にあると判断したからだ。
冒頭に述べたように消費税の負担は、消費者と事業者、あるいは事業者同士の力関係で決まる。電気、ガスのような独占的な公共料金なら消費者の負担になる。払わなければ電気が止められるだけだ。
一方、農産物は価格競争下にあり、売れなければ農業者は再生産もくらしも成りたたないから、消費増税分を簡単に価格転嫁できないのが実状だ。
実際、昨年4月に消費税が5%から8%に引き上げられて中小企業はどの程度価格転嫁できているのか。日本商工会議所は8月に「中小企業における消費税の価格転嫁に係る実態調査(第3回)」を発表している。
それによると約6割の事業者が「すべて転嫁できた」と回答しており、「一部転嫁できた」と合わせて約9割の事業者が転嫁できたとなっている。しかし、売上高1000万円以下の事業者では「転嫁できた」との回答が半分以下(46.9%)にとどまっている。売上高が小さくなるほど「まったく転嫁できなかった」という回答が多くなり、1000万円以下の事業者では25.2%と4分の1を占めている。
農業者は売上高1000万円以下が92%を占める。このアンケート結果からも農業者の価格転嫁が厳しいことは明らかだ。しかも、生鮮食料品はセリで価格が決まり、もともと生産資材価格の高騰や消費増税分を販売価格に反映できない状況にある。 こうした状況のなか、食品等への軽減税率が導入されれば、(販売高×軽減税率)-(仕入高×通常税率)となるから、その差額が「還付」されることになる。
具体化にはさまざまな課題があるにしても、農業者にとって価格転嫁できなくても農家の手取りが圧縮されない仕組みとなり得る。また、消費者にとっても痛税感が軽減されることになる。
◆食料と農業への配慮を
今回の財務省案はこうした軽減税率の導入は見送る方向だ。つまり、食料品の購入も10%の消費税がかかることになる。後で還付されるといっても、購入時の痛税感は緩和されない。しかも、マイナンバー・カードを利用して買い物記録をするということから、個人情報漏れの心配もあり、さらに麻生大臣の言う「面倒くさい」手続きを消費者に押し付けるだけで、結局、高齢者をはじめ還付を受ける人が少なければ消費者に買い控えが起きることも懸念される。「そうなると農業者にとって余計に価格転嫁しづらくなるという負のスパイラルに陥りかねない......」と心配する声もある。 消費税にはそもそも問題の多いとしても増税が既定ならば、国民にとっての食料・農業への配慮から軽減税率の問題を検討してきたのではなかったのか、といま一度問うべきだ。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -
 農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日
農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -
 世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日
世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日 -
 米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日
米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日 -
 (467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日
(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日 -
 【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日
【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日 -
 JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日
JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日 -
 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日 -
 日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日
日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日 -
 石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日
石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日 -
 【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日
【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日