|
変化のなかで経営自立を模索
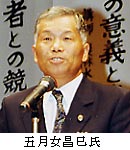 「今の変化をどう受け止め、どう独立していくか。われわれはいかなるときでも前向きに取り組まなくてはならない」。開会の挨拶で全国稲作経営者会議の五月女昌巳会長はこのように参加者に呼びかけた。 「今の変化をどう受け止め、どう独立していくか。われわれはいかなるときでも前向きに取り組まなくてはならない」。開会の挨拶で全国稲作経営者会議の五月女昌巳会長はこのように参加者に呼びかけた。
今年の総会では「水田農業確立に向けてのアピール」を採択した。そのなかで「水田を中心とした土地利用型農業活性化対策大綱」の実施を踏まえ、「単に政策の受け手としてだけでなく、責任をもって積極的に参画していくこと」を強調し、「消費者ニーズにあった作物生産」や「米以外の作物に転換する農業者の経営の安定」などを訴えている。
同会議は、米生産を経営の主軸とする稲作経営者の集まりだが、米価が低迷するなか自らの経営確立のため他作物も含めた計画的な生産、販売をいかに実現するかが参加者大きなの課題となっていると感じられた。
 基調講演では、今後の農業経営を考えるための参考として、富山県出身で米国で養鶏業を営む(株)イセの伊勢彦信会長が「アメリカの養鶏業者の競争と協調」と題して話した。 基調講演では、今後の農業経営を考えるための参考として、富山県出身で米国で養鶏業を営む(株)イセの伊勢彦信会長が「アメリカの養鶏業者の競争と協調」と題して話した。
伊勢氏によると、「アメリカでも日本のように卵価は安く、それをどう克服するかは同じ」と指摘。現在、アメリカでは50の養鶏業者で全米の生産を担っている。
そのなかで、経営を発展させるには、販売力を持った納入先と契約して生産することだという。「納入先は資産になる。スーパでもコンビニエンスストアでも、一度契約したら長期間契約は続ける律儀さがある」、「アメリカ社会のほうが競争的だと言われるが、日本ではブランド力のない基礎的食品は毎月のように仕入先を変えるようなことを納入先にされて生産者側が不安に駆られているのとは大きな違い」とアメリカの特徴を紹介した。
その一方で「同業者が話し合って利益を確保するために価格を決めるような行動は反社会的なことと受け止められている」と日本の農業もアメリカの競争と協調のあり方に学ぶべきこともあるなどと指摘した。
現場からの政策提言を
 農林水産省の高木勇樹事務次官は新基本法の制定過程と今後めざすべき農業について語った。 農林水産省の高木勇樹事務次官は新基本法の制定過程と今後めざすべき農業について語った。
そのなかで、新基本法が打ち出していることとして、専業的な農業者に施策を集中することになったことを強調。「行政は、生産者の進取の精神の発揮を阻害するようなことはしてはならない」とし、「これからの農業は自立、自助を基本にしなければならな
い」と訴えた。
とくに水田農業については、需要にあった米生産と麦・大豆などの本作化を図ることで、「水田全体から所得を確保すること」が求められていることを踏まえ「需要が落ち込んでいるような作物にしがみついているようではまさに経営感覚が疑われる」と指摘した。
また、行政の姿勢としては、「政策が地に足のついたものかどうかを検証するには現場をみることが大切」としながら、逆に「現在の政策について現場で気に入らないことがあれば実力行使をしてもらってもいい。国との無用ないさかいは避けるべきだが、前向きで建設的な実力行使であれば農業経営の活性化につながる」などと語った。
生産調整の必要性を強調
 高木次官の講演後は会場から質問が相次いだ。 高木次官の講演後は会場から質問が相次いだ。
関税化された米については「アメリカなどは関税の引き下げを要求している。いずれ畜産物と同じように丸裸にされてしまうのでは」との不安の声が上がった。
これについて高木次官は「WTOのルールに基づいて関税率を設定した。また、現在、この二次関税を払ってまで日本に輸入されている米はほとんどない。今は、丸裸になることが国際化ではない、各国の農業が共存できることを国際ルールにすべきと多数の国に理解を求めているところ」と話した。
また、今後の米生産について会場からは「食糧法で作る自由、売る自由が認められたははず。生産調整はやめて自由に販売したい」との声も上がったが、高木次官は「市場原理とは非常に厳しい。自由に作って自由に売るといっても価格はどうなるのか考えなくてはならない。果樹でもつぼみの段階から生産量を調節している」などと計画的な生
産の必要性を強調した。
JA改革に対する注文も
 基調講演の後に全体会議には、来賓としてJA全中の山田俊男専務も出席。今年のJA大会議案には、地域農業づくりのために担い手を重視する姿勢を打ち出し、大口利用に対する対応もJAが実践することなどが盛り込まれていることを紹介した。 基調講演の後に全体会議には、来賓としてJA全中の山田俊男専務も出席。今年のJA大会議案には、地域農業づくりのために担い手を重視する姿勢を打ち出し、大口利用に対する対応もJAが実践することなどが盛り込まれていることを紹介した。
これに対して会場からは「これまで全中が方針を打ち出しても末端のJAにまで徹底していないことがあった。今回はJA段階まで徹底してほしい」という要望の声や米の生産については「輸入には反対だが、国内は自由化すべきだと思っている」という意見も出
された。
山田専務は「自立した農業者がこれから必要になるが、現状のまま市場原理に委ねれば米に値段はつかず大混乱になる。計画生産に取り組むことによって初めて経営安定が図れる」などとJAグループの取り組みに理解を求めた。
そのほか、JA合併によってJAの支所などが統廃合されJAが利用しづらくなったなどの声もあった。
会場の議論からは、大規模生産者や生産法人は地域農業の担い手として自負を持っていることも感じられた。各地のJAにとっても、今後、積極的な対話を通じてJAの新たな事業を具体的に作り出していくことも重要な課題だろう。
|
 大口利用対応などJAグループの改革にも期待
大口利用対応などJAグループの改革にも期待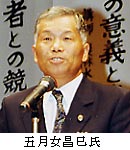 「今の変化をどう受け止め、どう独立していくか。われわれはいかなるときでも前向きに取り組まなくてはならない」。開会の挨拶で全国稲作経営者会議の五月女昌巳会長はこのように参加者に呼びかけた。
「今の変化をどう受け止め、どう独立していくか。われわれはいかなるときでも前向きに取り組まなくてはならない」。開会の挨拶で全国稲作経営者会議の五月女昌巳会長はこのように参加者に呼びかけた。
 基調講演では、今後の農業経営を考えるための参考として、富山県出身で米国で養鶏業を営む(株)イセの伊勢彦信会長が「アメリカの養鶏業者の競争と協調」と題して話した。
基調講演では、今後の農業経営を考えるための参考として、富山県出身で米国で養鶏業を営む(株)イセの伊勢彦信会長が「アメリカの養鶏業者の競争と協調」と題して話した。 農林水産省の高木勇樹事務次官は新基本法の制定過程と今後めざすべき農業について語った。
農林水産省の高木勇樹事務次官は新基本法の制定過程と今後めざすべき農業について語った。 高木次官の講演後は会場から質問が相次いだ。
高木次官の講演後は会場から質問が相次いだ。 基調講演の後に全体会議には、来賓としてJA全中の山田俊男専務も出席。今年のJA大会議案には、地域農業づくりのために担い手を重視する姿勢を打ち出し、大口利用に対する対応もJAが実践することなどが盛り込まれていることを紹介した。
基調講演の後に全体会議には、来賓としてJA全中の山田俊男専務も出席。今年のJA大会議案には、地域農業づくりのために担い手を重視する姿勢を打ち出し、大口利用に対する対応もJAが実践することなどが盛り込まれていることを紹介した。