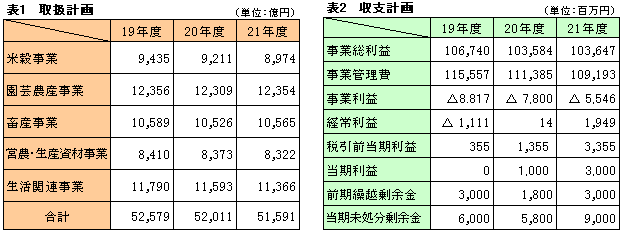出資配当減配の意味を考える
◆減配に厳しい批判も
3か年の取扱高は、米の販売価格など農畜産物価格の低下、生産・生活資材の需要の低迷、園芸直販部門や畜産販売部門の会社化などによって、19年度5兆2579億円、20年度5兆2011億円、21年度5兆1591億円を見込んでいる(表1)。
その一方で、肥料・飼料原料や原油などの国際的な需給構造の変化による価格高騰などの海外要因、事業管理コスト削減の遅れ、競争激化による事業収益力の低下などにより、18年度の収支は計画を下回ることが予測され、19年度以降についても事業利益段階で大幅なマイナスを計画せざるをえなかったとしている。とりわけ19年度については、当期利益0円、出資配当1%という厳しい内容となっている(表2)。
これに対して「5兆円もの事業分量があるのだから、最低2%は配当すべき」とか「全中の定義では、2期連続の事業利益赤字は“要改善JA”であり、3期連続赤字計画は全国連として問題だ」。あるいは「一定の利益を創出する計画を持っていないと計画途中で何か起きたときに対応できないのではないか」など、厳しい意見もある。
こうした意見は全農が株式会社であれば、当然な意見だともいえる。なぜなら、株式会社は当期利益を最大化することを目的にしているからだ。だから、当期利益0円という計画が示されれば、その会社の株価が暴落したり、株主総会で経営責任が問われたりすることになる。
だが、協同組合組織である全農を株式会社と同じ論理で評価していいのだろうかという疑問が起きる。
◆配当だけが協同組合組織の還元方法なのか
全農は「生産者と消費者を安心で結ぶ懸け橋になります」という経営理念を具現化するために、5つの使命を果たすことを新生プランで明示した。その一つが「生産者・組合員の手取り最大化」だ。そのため19年度では、新生プランで掲げた担い手対応強化30億円、米の手数料引下げ7億円、生産資材の手数料引下げ27億円、総額で64億円を実施することにしている。さらに20年度は約80億円、21年度は約90億円を実施することにしている。
これは協同組合組織としては株式会社と異なり、その収益を還元する方法として出資配当だけではなく、今回のような手数料の引下げとかサービスの向上など直接還元する方法もあることを示している。
また、担い手対応専任者として全国に150名余の人員を配置し、担い手対策・営農対策を通じた地域農業振興方策実現のための支援を行っている。これも全農の使命である「担い手への対応強化」の具体策の一つだ。これは必ずしも全農の売上げにつながるものではなく、人件費などコストがかかるもので、これを止めればおそらく人件費分だけでも出資配当を1%上乗せすることが可能になるのではないだろうか。
これも一般企業では考えにくい対応かもしれないが、現在の国内農業や農協組織の現状から見て、必要な還元方法であろう。
もちろんこれは「計画」なのだから、数字を操作することで当期利益をプラス計上することも、配当を従来通り2%にすることも可能だったはずだが、「事業計画は積み上げが基本であるという経営者判断」でこう計画したと加藤一郎専務はいう。
施設の売却など「特別損益を頼りにしたタコ足経営ではないか」という意見も聞くが、統合時に不稼動施設を売却することは決まっており「BS(バランスシート:貸借対照表)を圧縮するのも現代の経営戦略の一つの方法」ではないか。さらに全中の定義からみて…」という批判については「信用事業を行うJAと全農を同じ物差しで計っていいのか」と疑問を呈した。
◆協同組合のビジネスモデルを検討する時期に
こうみてくると「当期利益0円、出資配当減配」には、いくつかのメッセージが込められているように思える。
その一つは、直接的には何も書かれてはいないし語られてもいないが、「生産者手取りを最大化」するという経営理念を実現するために全農に求められている経営成果は何か。そのためのビジネスモデルはどういうものか。それは農家経営もJAの経済も厳しいときに、連合会が当期利益を最大化して高い配当をする株式会社と同じでいいのか。それとも手数料を引き下げることなどによって、還元することを含めたモデルなのか。そうしたことをこの機会に真剣に議論するべきではないだろうかということだ。
もう一つは、あえてこうした計画を出すことで、組織も子会社も含めた全農グループの全役職員も「いまは難局にある」という実態を「十分に噛み締めて」危機感を共有したうえで「不退転の決意」をもって、遅れている「事業管理コストの削減とシェアアップによって」19年度の早い時期に2%配当の財源を確保し、さらに20年度以降についても計画を上方修正していこうというメッセージではないだろうか。
◆県域・子会社含めた透明性ある経営管理を
これらと関連してこの3か年計画の実行段階で注目していきたいことがある。それは「事業単位・都府県本部単位を組合わせた新たな経営管理への移行促進」についてだ。
従来は、県本部収支均衡であったため、同じ事業であっても、県本部と全国本部が個別に経営管理をしていた。これでは同じ事業に携わっていても、本所の人間は県本部の仕事が分からないなど、一事業体としてみればおかしなことになっていた。
そこで、各事業ごとに縦串を通して、県固有の問題も含めて36県本部が統一的な戦略を共有化すると同時に、公平性も確保した経営管理・事業運営をしていこうとしている。そのことで、県域までを含めた事業ごとのコストが明らかになり、解決しなければならない課題や、今後伸ばしていくべき点なども分かりやすくなるといえる。具体的な内容はいま検討中で決まりしだい明らかにするということなので、それを待ちたい。
このことと関連するが、子会社についても各事業ごとに連結することで、各事業の全体像が明らかになるといえる。そして、事業ごとに県域・子会社を一体化したコストも含めた事業構造を情報開示することで「誠実で透明性のある事業運営」ができ、組合員・JAの信頼がさらに増すのではないだろうか。
そのことも含めて、多くの部門を会社化したいまの全農は「単体の事業計画」や、決算の連結だけではなく「全農グループとして統一した経営理念、統一した戦略でやっていく“連結経営”に脱皮していく契機にしたい」と加藤専務。それがどのように具体化していくのかも注目していきたい。そのときに、全農グループ全体としてのマーケティングや販売戦略はどこが担うのかも注目したい点だ。そしてこれは前にふれた全農型ビジネスモデルを考えるうえでも重要なことだといえる。
◆一人ひとりが達成感を実感できる職場風土を
最後に、これは釈迦に説法の類だが、「当期利益0円・出資配当減配」といういままでにない「難局」が全農職員や子会社の社員に示され、危機意識を共有して「不退転の決意」でこれを乗り切ろうというメッセージが発せられた。全職員・社員がモチベーションを高め一丸となってこの難局を乗り切るためには、こうしたトップダウンの目標だけではなく、一人ひとりの創意工夫でボトムアップができ、達成感が感じられるような職場風土、職場環境をつくっていくことが大事ではないだろうか。