TPP11と成長ホルモン問題2017年9月21日
「専門家が安全だと言っている」→「安全かどうかはわからない」
前回、お示しした「建前→本音の政治・行政用語の変換表」は、多くの人の英知を結集して、さらに改訂・拡充していきたいと考えているので、訂正すべき点や、これを加えたほうがよいとの意見があったら、ぜひ、ご教示いただきたい。
そこで、さっそく、追加したいのが、下記の2つである。
●大義名分 = 後からとってつける建前の理由。
例えば、今回急浮上した衆議院解散の真の狙いは保身・延命との見方が与野党にある。「〇〇の〇〇による〇〇のための解散。イメージの悪化した〇〇総理では選挙は困難とみて、すべての責任を総理に取ってもらったのちに総理交代によってイメージを一新して選挙に臨むとの流れが与党内で加速してきたため、先手を打って、延命を図っただけだ」というのである。有権者がこれをどう受け止めるか。
●専門家が安全だと言っている = 安全かどうかはわからない。
なぜなら、「安全でない」という実験・臨床試験結果を出したら研究資金は切られ、学者生命も、本当の命さえも危険にさらされる。だから、特に、安全性に懸念が示されている分野については、生き残っている専門家は、大丈夫でなくても「大丈夫だ」と言う人だけになってしまう危険がある。この事態を打開するのは、恐れずに真実を語る人々と消費者の行動である。
「大義名分」については解説するまでもないので、「専門家・・・」について、実例で解説しよう。
◆もう一つの成長ホルモン問題
成長ホルモン(エストロゲンなど)の肉牛への投与による牛肉への残留問題に比べて、乳牛に対する遺伝子組み換え牛成長ホルモン(rBST、recombinant Bovine Somatotropin または、rBGH、recombinant Bovine Growth Hormone)のことはあまり議論されていない。米国ではrBSTのほうが一般的な呼称だが、成長ホルモンという言葉のネガティブなイメージを考慮して、否定的な見解の人はrBGHと呼ぶ傾向がある。だから、rBGHという呼び方をしていれば、否定的な見解の人だとわかる。
BSTは牛に自然に存在するが、これを遺伝子組み換え技術により大腸菌で培養して大量生産し、乳牛に注射すると一頭当たりの牛乳生産量が20%程度増加する(一種のドーピング)ため、牛乳生産の夢の効率化技術として登場した。ただし、乳牛は「全力疾走」させられて、搾れるだけ搾られてヘトヘトになり、数年で屠殺される。
米国では、人や牛の健康への悪影響や倫理的な問題を懸念する消費者団体・動物愛護団体等の10年に及ぶ反対運動を経て、1993年に認可されたが、日本やEUやカナダでは認可されていない。
◆日本は未認可でも素通り
rBST(商品名はポジラック)を開発・販売したM社は、農水省勤務当時の筆者を訪ね、日本での認可の可能性について議論した。とにかく何から何までいいことしか言わない。筆者は、「そんないいことばかり言っていたら、誰も信用しませんよ」と回答したのを覚えている。そして、かりに日本の酪農家に売っても消費者が拒否反応を示す可能性を話した。結局、M社は日本での認可申請を見送った。
ところが、認可もされていない日本で、米国のrBST使用乳製品は港を素通りして、消費者は知らずにそれを食べている。所管官庁と考えられる省は双方とも「管轄ではない(所管は先方だ)」と言っていた。
◆疑惑のトライアングル

筆者は、1980年代から、この成長ホルモンを調査しており、約30年前に米国でのインタビュー調査を行ったが、「絶対大丈夫、大丈夫」と認可官庁とM社と試験をしたC大学が、同じテープを何度も聞くような同一の説明ぶりで「とにかく何も問題はない」と大合唱していた。筆者は、図のような三者の関係を「疑惑のトライアングル」と呼んだ。認可官庁とM社は、M社の幹部が認可官庁の幹部に「天上がり」、認可官庁の幹部がM社の幹部に「天下る」というグルグル回る「回転ドア」の人事交流、そして、M社からの巨額の研究費で試験して「大丈夫だ」との結果をC大学の世界的権威の専門家が認可官庁に提出するから、本当に大丈夫かどうかはわからない。
つまり、逆説的だが、「専門家が安全だと言っている」のは、「安全かどうかはわからない」という意味になる。なぜなら、「安全でない」という実験・臨床試験結果を出したら研究資金は切られ、学者生命も、本当の命さえも危険にさらされる。だから、特に、安全性に懸念が示されている分野については、生き残っている専門家は、大丈夫でなくても「大丈夫だ」と言う人だけになってしまう危険がある。
米国では、認可前の反対運動が大きかったことを受けて、rBSTの認可直後には全米の大手スーパーマーケットがrBST使用乳の販売ボイコットを相次いで宣言した。しかし、rBSTが牛乳に入っているかどうかは識別が困難なこともあり、ボイコットは瞬く間に収束し、1995年には「rBSTはもはや消費者問題ではない」と多くの米国の識者が筆者のインタビューに答えて言った。
また、バーモント州が、rBSTの使用を表示義務化しようとしたが、M社の提訴で阻止された。かつ、rBST未使用(rBST-free)の任意表示についても、そういう表示をする場合は、必ず「使用乳と未使用乳には成分に差がない」との注記をすることを、M社の働きかけで、FDA(食品医薬品局)が義務付けた。例えば、次のように。
rBST/rbST-free, but, no significant difference has been shown between milk from rBST/rbST ‐treated and untreated cows.
◆恐れずに真実を語る人々と消費者の行動が事態を動かす
ところが、事態は一変した。rBSTの注射された牛からの牛乳・乳製品にはインシュリン様成長因子 IGF-1が増加するが、すでに、1996年、米国のガン予防協議会議長のイリノイ大学教授が、IGF-1の大量摂取による発ガン・リスクを指摘し、さらには、1998年に「サイエンス」と「ランセット」に、IGF-1の血中濃度の高い男性の前立腺ガンの発現率が4倍、IGF-1の血中濃度の高い女性の乳ガンの発症率が7倍という論文が発表された。
ここから、事態は一変し、結局、スターバックスやウォルマートなどが、自社の牛乳・乳製品には不使用である、と宣言せざるを得なくなり、rBSTの酪農生産への普及も頭打ちとなって、もうからなくなったとみたM社はrBSTの販売権を売却する事態になった。
このことは、自身のリスクを顧みずに真実を発表した人々(研究者)の覚悟と、それに反応して、表示をできなくされても、遺伝子組み換え牛成長ホルモン入り牛乳である可能性があるなら牛乳を飲まない、という消費者の声と行動が業界を動かしたということだ。
その点で、もう一つ注目されるのは、ヨーグルトの世界的大手のダノンが、rBSTだけでなく、全面的な脱GM(遺伝子組み換え)宣言を米国でしたことである。ダノンは2016年4月、主力の3ブランドを対象に、2018年までにGM作物の使用をやめると発表した。これまでは砂糖の原料のテンサイや、乳牛のエサとなるトウモロコシなどにGM作物を使ってきたが、それ以外の作物に切り替えるという。
日本の酪農・乳業関係者も、風評被害で国産も売れなくなることを心配して、rBSTのことをそっとしておこうとしてきた。これは人の命と健康を守る仕事にたずさわるものとして当然改めるべきである。むしろ、消費者にきちんと伝えることで、自分たちが本物を提供していることをしっかりと認識してもらうことができる。
「TPPプラス」(TPPを上回る譲歩)の日米FTAが結ばれたら、rBST使用乳製品がさらに押し寄せてくる。TPPレベルで、米国政府試算では日本への乳製品輸出は約600億円増加すると見込んでいる。
しかし、恐れずに真実を語る人々がいて、それを受けて、最終的には消費者(国民)の行動が事態を変えていく力になることを我々は忘れてはならない。
(関連記事)
本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日
【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -
 米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日
米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日 -
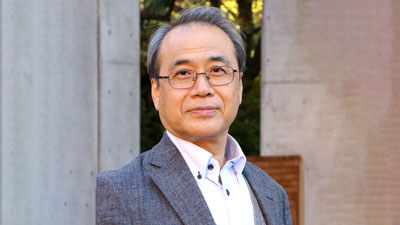 【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日
【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -
 米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日
米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日 -
 農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日
農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -
 備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日
備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -
 新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日
新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -
 JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日
JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -
 米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日
米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日 -
 農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日
農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -
 「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日
「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -
 「ホテルアークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日
「ホテルアークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -
 千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日
千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日 -
 【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日
【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日 -
 香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日
香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -
 京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日
京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -
 愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日
愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -
 リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日
リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日
































































