【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第66回 驚くべき日本の「百姓」の能力2019年8月29日
十数年前、私が東北大を定年になって東京農大オホーツクキャンパスに赴任した最初の年のことである。研究室の3年生の研修で網走周辺の畑作農家におじゃました。そのときある学生が農家にこう質問をした。農家が今生産しているジャガイモ、ムギ、ビートの三作のうちもっとも収益性の高いのはどれかと。そうしたらビートという答えが返ってきた。学生はさらに質問を続けた。それならなぜビートだけ栽培しないのか、収益性の低いイモやムギをなぜ生産するのか、経営者としておかしいのではないかと。

農家の方は親切に説明してくれた。ビートばかりでないのだが、作物を毎年同じ畑に栽培していると収量が落ちてくる、これを連作障害というが、それを避けるためにイモ―ムギ―ビートというように毎年違った作物を植えているのだと。
ちょっとショックだった。顔から火が出る思いをした。農大の学生が、しかも3年生にもなったものがこんな質問をするとは、連作障害も知らないとはと、農家の方に恥ずかしかったからである。
後で学生に聞いてみた、1~2年の講義で連作障害のことを習わなかったのかと。すると、経営系の学生のカリキュラムには自然科学系の講義がきわめて少なく、関心はあるのだが聞けない、だから知らないことが多いのだという。驚いた。それでその後のカリキュラム改訂のさいには自然科学の講義がもっと聴けるようにし、また農業技術に関する最低限の知識が得られる講義を新たに設けることにしたのだが、農業に関心をもって入学してきた学生ですら連作障害を知らないのだから、都会の消費者のほとんどはこういうことを知らないのではないだろうか。
商工業だったらもうかるものだけ対象にすればいいかもしれないが、農業はそういうわけにはいかないのである。それ以外にも農業独特のさまざまな特殊性がある。しかしそうし農業の特殊性をほとんど知らない政財界人、マスコミ関係者、消費者が増えてきた。そして商工業の経営でやっていることがそのまま農業に通用するものと考え、農業の生産性が低く、所得が低いのはアメリカ農業のように規模拡大しないからだ、早急に規模拡大せよとか、農家には商工業のような利益を追求する「企業」的精神がないから農業が発展しないのだ、企業を農業に参入させろなどというものすらいる。こうした農業技術に対する無理解が、農業の常識に対する無知が日本の農業をだめにさせているのではなかろうか。
それはそれとして、またさきほどの連作障害の話に戻るが、そうなのである、米以外の作物の多くは連作ができないのである(米は特別な作物なのである)。そうなると一作物だけでなくいろなろ作物を組み合わせて栽培しなければならなくなる。
また、日本の土地条件、気象条件はきわめて複雑、同じ地域でも多種多様、それに対応した作物を選択して生産しなければならない。
さらに消費者の需要も考えて作物を選択しなければならないし、自分の家で必要とする作物で自分の家で生産した方がいいものもある(交通条件等々からしてものの流通が不便なその昔などはなおのことそうだった)。
そうなると米ばかりでなく多くの作目を生産しなければならなくなる。
私の生家を例にとれば、都市近郊で米・野菜中心であるという特殊性はあるが、私の幼い頃(戦前)は、多少を問わず数えれば麦・大小豆・果菜・葉菜等々65種類の作物、3種類の家畜を育てていた。「百姓」という言葉は「百の作物を育てている人」からきているという説もあるようだが、私の生家は百に及ばなかったよう(わら工品や堆厩肥、刈り取った野草・雑草でつくった飼料、漬け物等々の生産物まで入れれば百品目以上になるかもしれないが)、それにしてもよくつくっていたものである(もちろん周辺の農家もほぼ同じだった)。
そうなると、どの作物がどういう土地を好むのか、いつどれだけの深さで耕し、どれくらいの畝をたて、いつ何粒くらい種をまき、水や肥料はいつごろどれくらいやり、中耕除草はいつごろやればいいのか、収穫はいつごろどのようにすればいいのか、収穫物をどう調整・加工し、保存・販売すればいいのか等々、作物によりすべて異なるので、それをすべて覚えておかなければならない。
同時に、どこの田畑はどのような性質をもち、そこにどのような順序でいつごろどういう作物を植えてきたかも覚えていなければならない。田畑の性質もすべて異なり、また連作障害の問題もあるのでそれに応じて植える作物、時期を考えなければならないからである。
当然のことながらどういう気象のときにどの作物にどのような対処をすればいいのかも知っておかなければならない。
家畜もその種類によって季節によって餌を始めとする飼育の仕方はすべて異なるが、それも知っていなければならない。農産加工もさまざまあるが、そのすべてを覚えておかなければならない。
こうしたすべてのことを「百」品目にわたって覚え、それをもとにして農作業の計画を立てるわけだが、よくもまあこれだけのことを知り、また実践してきたものだと驚くばかりである。そしてそれが日本人の食を、暮らしを支えてきた。養蚕などはその輸出で日本の工業発展の基礎をつくってきた。これも誇るべきことだ。
でも、おかげさまで年中忙しかった。ましてや手労働中心の時代、前に述べたように労働は厳しかった。にもかかわらず暮らしは貧しかった。
しかし、喜びもあった。豊かな自然に囲まれて作物や家畜を育てる喜び、収穫の喜びがあった。
そのほか、本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
重要な記事
最新の記事
-
 米価上昇止まらず 4月7日の週のスーパー販売価格 備蓄米放出効果いつから2025年4月21日
米価上昇止まらず 4月7日の週のスーパー販売価格 備蓄米放出効果いつから2025年4月21日 -
 【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日
【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日 -
 【人事異動】JA全農(4月18日付)2025年4月21日
【人事異動】JA全農(4月18日付)2025年4月21日 -
 【JA人事】JA新ひたち野(茨城県)新組合長に矢口博之氏(4月19日)2025年4月21日
【JA人事】JA新ひたち野(茨城県)新組合長に矢口博之氏(4月19日)2025年4月21日 -
 【浜矩子が斬る! 日本経済】四つ巴のお手玉を強いられる植田日銀 トラの圧力"内憂外患"2025年4月21日
【浜矩子が斬る! 日本経済】四つ巴のお手玉を強いられる植田日銀 トラの圧力"内憂外患"2025年4月21日 -
 備蓄米放出でも価格上昇銘柄も 3月の相対取引価格2025年4月21日
備蓄米放出でも価格上昇銘柄も 3月の相対取引価格2025年4月21日 -
 契約通りの出荷で加算「60キロ500円」 JA香川2025年4月21日
契約通りの出荷で加算「60キロ500円」 JA香川2025年4月21日 -
 組合員・利用者本位の事業運営で目標総達成へ 全国推進進発式 JA共済連2025年4月21日
組合員・利用者本位の事業運営で目標総達成へ 全国推進進発式 JA共済連2025年4月21日 -
 新茶シーズンが幕開け 「伊勢茶」初取引4月25日に開催 JA全農みえ2025年4月21日
新茶シーズンが幕開け 「伊勢茶」初取引4月25日に開催 JA全農みえ2025年4月21日 -
 幕別町産長芋 十勝畜産農業協同組合2025年4月21日
幕別町産長芋 十勝畜産農業協同組合2025年4月21日 -
 ひたちなか産紅はるかを使った干しいも JA茨城中央会2025年4月21日
ひたちなか産紅はるかを使った干しいも JA茨城中央会2025年4月21日 -
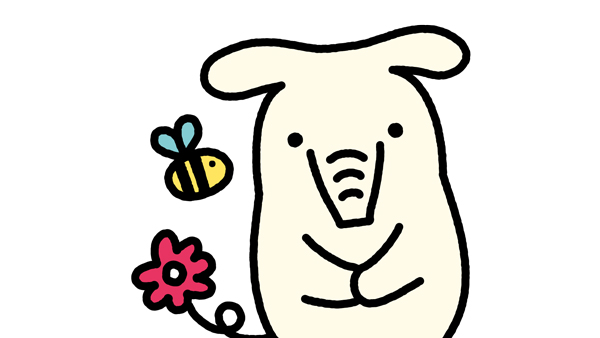 なじみ「よりぞう」のランドリーポーチとエコバッグ 農林中央金庫2025年4月21日
なじみ「よりぞう」のランドリーポーチとエコバッグ 農林中央金庫2025年4月21日 -
 地震リスクを証券化したキャットボンドを発行 アジア開発銀行の債券を活用した発行は世界初 JA共済連2025年4月21日
地震リスクを証券化したキャットボンドを発行 アジア開発銀行の債券を活用した発行は世界初 JA共済連2025年4月21日 -
 【JA人事】JA新潟市(新潟県)新組合長に長谷川富明氏(4月19日)2025年4月21日
【JA人事】JA新潟市(新潟県)新組合長に長谷川富明氏(4月19日)2025年4月21日 -
 【JA人事】JA夕張市(北海道)新組合長に豊田英幸氏(4月18日)2025年4月21日
【JA人事】JA夕張市(北海道)新組合長に豊田英幸氏(4月18日)2025年4月21日 -
 食農教育補助教材を市内小学校へ贈呈 JA鶴岡2025年4月21日
食農教育補助教材を市内小学校へ贈呈 JA鶴岡2025年4月21日 -
 農機・自動車大展示会盛況 JAたまな2025年4月21日
農機・自動車大展示会盛況 JAたまな2025年4月21日 -
 秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛の限定焼肉メニューは「真夏星」 JAタウン2025年4月21日
秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛の限定焼肉メニューは「真夏星」 JAタウン2025年4月21日 -
 「かわさき農業フェスタ」「川崎市畜産まつり」同時開催 JAセレサ川崎2025年4月21日
「かわさき農業フェスタ」「川崎市畜産まつり」同時開催 JAセレサ川崎2025年4月21日 -
 【今川直人・農協の核心】農福連携(2)2025年4月21日
【今川直人・農協の核心】農福連携(2)2025年4月21日




























































