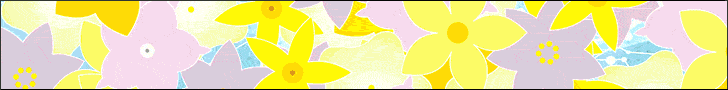【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第95回 わら草履・草鞋だった村の履物2020年4月9日
私の生家ではこれまで述べてきた縄、莚、菰、俵以外に草履(ぞうり)と草鞋(わらじ)、雪沓などの履き物をつくっていた。これらの履物は都市・農村を問わず明治以前の日本人の必需品だったのだが、農山村では昭和になっても生産・生活両面でなくてならないものだったからである。ただし、昭和に入るころから都市部の住民の履物は一般庶民も含めて徐々に変わりつつあった。

私の小さい頃、一里1時間と言ったものだった。一里(4キロ)歩くのに約1時間かかるというのである。だから10キロ離れているとなると徒歩2時間半の距離となる。今なら車で10分でいけるのに、新幹線なら山形から東京まで行ける時間なのに、昔の10キロはそれくらい遠かったのである。
私の生まれた山形市から北西に直線距離で10キロ、つまり徒歩で2時間半くらいかかるところに、OS村という純農村(現在は山形市に合併している)があった。その村の農家に生まれた高校の同級生のA君に先日会ったとき、何かの話からこんなことを聞いた、小学校のころ(1940年代)どんな服装をして学校に通ったかと。そしたら、着物を着てわら草履をはき、教科書・ノート(あのころは帳面と呼んだが)や筆入れ等は風呂敷に包んで背中に背負って通ったものだ、卒業まで全員そうだったと言う。学帽はと聞いたら、それはみんなかぶっていたとのことである。なお、冬の履き物はと聞くと藁(わら)沓(ぐつ)だったという。
驚いた、私たち市内の子どもたちは、農家であれ非農家であれ、新品かお下がりか中古品かは別として、全員五つボタンの学生服、ランドセル、ズックだったからである(革靴を履く子もいたが、それは町中心部のお金持ちの子どもだけ、私の学校にはいなかった)。また冬の履き物はゴム長靴だった。また、物不足になった敗戦前後は洋服ではあったものの着られるものを着るだけ、下駄履きになったし、学校内での下履きはわら草履になった。
都市と農村の間にはこれだけの経済的文化的格差があったのであり、10キロ・2時間半の距離はこれだけの差異を不思議にも感じさせなかったのである。
もちろん、都市の中でも農家と非農家の間に経済的文化的格差はあった。たとえば革靴はお役人や高給取りの勤め人しか履かず、農家が背広を着て革靴を履くなどと言うことは戦前まではなかった。そして一般庶民は農家も含めて普通は着物を着、下駄を履いていた。ただし徒歩での遠距離旅行は草鞋履きだった。
農家の農作業のさいの履き物は、市内であれ純農村であれ、稲わらでつくった草履、草鞋だった。地下足袋(これは便利なものだった)が普及しつつあったが、当時としては高価であり、しかも物不足時代になったので、やはり草履、草鞋が普通だった。
なお、草履は日常のまた軽作業時の履き物であり、草鞋は主要農作業・遠距離移動・旅行のさいの履き物として用いられた。
わら草履と草鞋、私たちの子ども時代はこれは普通に見られたもので、農家の子どもにとっては履くだけでなくつくるものでもあり、きわめて馴染み深いものだった。しかし今はほとんど見られなくなっている。テレビや映画の時代劇で見られるが、登場人物の足許をみんなとくに注意して見ているわけでもない。だから名前は知っていてもまともに見たことのない方も多かろう。実物はパソコンで検索して見てもらうことにして説明を試みてみると、「わら草履の緒を足の後ろの方に長く伸ばし、それを草履の縁(ふち)のところについている輪に通して足首に巻き、足の後部(かかとのところ)を縛って履けるようにしてある履物」ということになるだろう。
この草鞋は、鼻緒だけの草履にくらべて足に密着するので歩きやすく、また農作業もきわめてしやすく、農家にとっては必需品だった。私たちの子どもの頃は地下足袋が普及してきていたのでそれを履くようになっていたが、祖父は必ず草鞋、だから冬仕事に自分でつくっていた。また、山歩きや長距離の歩行のときにも非常に歩きやすいので、徒歩時代の昔は農家ばかりでなくすべての人の旅行や登山の必需品であり、荒物屋(今でいう雑貨屋)で売っていたものだった。
しかし惜しむらくは原料が稲藁、だからこそ軽くて履きやすくていいのだが、すぐに擦り切れてしまう。そこで遠くに行くときは履き替えられるように腰に何足かぶらさげて行ったもの、あるいは街道沿いの茶店などで売り物の草鞋を買って履きかえたものだった。
今茶店と言ったけれど、本当にそう呼んでいたか、どう呼んでいたのか思い出せない。菓子や飲み物、日用品など(当時の旅は歩き、その旅人が必要とするようなものが中心だったような気がする)を売っており、店先には縁台がおいてあって腰を掛けて休めるようになっており、主要道路に1~2キロおきくらいにあった。私も歩き疲れると店の縁台に座り、サイダーなどを注文して飲んだりしたものだった。そこで草鞋も売っていたのである。今考えてみたら、私の幼い頃、今から80年前というのは農家ばかりでなく都市住民も草鞋を履く時代だったのだ。すごくなつかしいが、今はもう車時代、こんな茶店はもう見られなくなり、コンビニに替わってしまった。コンビニがあればまだいい、車も人も通らない道路になったところすら出てきていることがさびしい。
草履・草鞋は稲わらだから軽いし、弾力性もあり、摩擦で底が滑らないし、夏は通気性があるので涼しく、寒いときは足袋を履けばいいだけなので温かく、履き物としてはいいのだが、欠陥は磨り減りやすく、使用期間が短いことだった。何日も履いていると擦り切れて使えなくなるのである。だから何足もつくらなければならない。しかし、農繁期の忙しいときに草履や草鞋をつくっている暇などない。そこで縄や莚、菰などのわら工品と同じように冬場の農閑期に何足もつくっておかなければならなかった。
私たち子どももその作り方を教わった。細縄2本を草履作り台または足の指にひっかけて4本になった細縄にわらを編み込んでいき、最後に鼻緒をつける。鼻緒をつけるのが難しく、ましてや不器用な私のこと、本当に不格好なできだった。残念ながらもう忘れてしまってつくることはできなくなっている。
草履すらまともにつくれないのだから草鞋などは難しくてつくれなかった(というよりは徐々に地下足袋に移行しつつあり、私の家では祖父しか草鞋を履かなくなっており、教えようともとしなかったのかもしれない)。それにしてもよくもまあ草鞋などという人間の足にぴったり合って履きやすく、歩きやすく、軽いものをつくったものだと感心する。履くとき、脱ぐときはちょっと面倒だったが。
そのほか、本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -
 農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日
農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -
 世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日
世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日 -
 米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日
米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日 -
 (467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日
(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日 -
 【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日
【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日 -
 JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日
JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日 -
 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日 -
 日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日
日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日 -
 石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日
石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日 -
 【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日
【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日