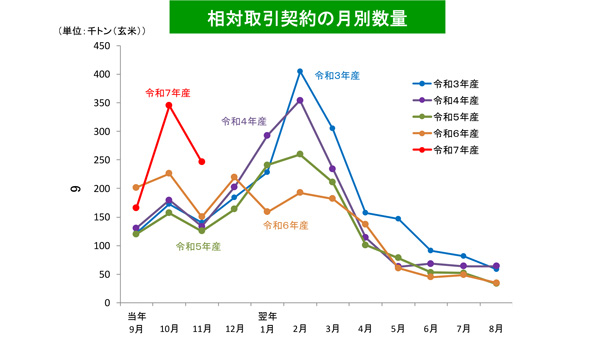【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第97回 機能的効率的だった簔笠2020年4月23日
「簔笠」、この言葉はかなり昔からあったようだが、これも屋外で働く農家にとってきわめて重要なものだった。

まず笠だが、雨や雪、直射日光などを防ぐ必要不可欠だつた。だから、地域、季節、使う場所などによって形状、大小、材料の異なるさまざまな笠があり、男女によっても違っていた。
私の生家の周辺では、花笠踊りでかぶっているような形の菅笠、それより一回り大きい菅笠と2種類あった。菅笠という名前からもわかるように菅で作られている笠もあったが、多くは稲わらだった。
また、稲わらの「みご」(わらの外側の葉や鞘を取り除いた茎の部分、細くつやつやとして美しく、しかも丈夫である)で編んだ笠もあった。狩猟のときに殿様がかぶる笠のような形をしており、これは男用だったが、何と呼んだか忘れてしまった。
同じくみごでつくった女性用のかぶり物の「ござぼうし」(「みごぼうし」とも言ったような気がするのだが)があった。この説明も難しいのだが、みごを60×30センチくらいの長方形に畳表のように織り、それを半分に折りたたみ、その片方を途中まで紐で編んで閉じたもので、閉じていない方を前にしてかぶり、あご紐で飛ばないように抑えておくというものであり(申し訳ないが、私の筆力ではうまく説明できない)、頭から顔まですっぽり覆われるので日除けなどには非常に良く、しかもしゃれており、まさに女性向けのかぶりもの、とってもかっこよく見えたものだった。
それから、稲わらでつくった帽子と背中を覆うマントをつないだような「みのぼうし」があった。これは冬用だが、私の地域にはなかった(さきほど言ったござぼうしをみのぼうしと読んでいた地域もあった)。
それ以外にも農山村には、麦わら、菅など地域の素材で編んだ笠、帽子があったが、いずれも軽くて通気性がよいなどきわめて合理的につくられていた。まさにこうした種々の笠は利用者と製作者のつまり地域の知恵の結晶ということができよう。
真夏、山々の間から遠くにもくもくと湧き出ているいくつかの白い入道雲のうちの一つが、やがて頭の上まで恐ろしく大きくのしかかってくるようになる。入道雲の外側は陽の光を浴びて青い空の中に真っ白く突き出てきれいだが、内側が真っ黒く下の方に垂れているようでちょっと怖く見える。
それを見ると祖母は、小学校高学年の私に、畑にいる祖父に蓑を持って迎えに行くよう命じる。私は自転車に乗り、蓑を後ろにつけて、急いで畑に向かう。山の麓にかかっている入道雲の下が雨で煙って暗くなっているのが遠くに見える。雷が鳴るときもある。あの雨が近づく前に祖父に会わなければならない。急ぐ。
空を見て畑から引き上げてきた祖父と途中で会う。ほっとして蓑を渡す。祖父は私の持ってきた蓑を肩から背中にかけて身に着ける。私はすぐに家路に急ぐ。しかし見る見るうちにすぐ後ろまで雨が迫ってくる。追いつかれないように逃げる。家に着いた頃に痛くて目をあけてもいられないくらいの大粒の雨が落ちてくる。何とか間に合った。しかし、歩いて帰る祖父はそうはいかない。あっという間にずぶ濡れとなる。しかし最初からかぶっていた笠と私の持っていった蓑があるので直接身体には雨水がかからない。もちろん身体の前の方は雨がかかるが、背中にはかからず、暖かいのでそれほど気にならない。やがて家に着き、蓑笠を脱ぎ、濡れた身体を拭いて着替え、囲炉裏の前に座って祖母の出した熱いお茶をゆっくりと飲みながら雨の止むのを待つ。そのうち蓑笠を用意して遠い田畑に出かけていた父母も帰ってくる。
田植えの時期にもこの蓑笠が大いに役に立つ。かつては6月の梅雨の真っ最中に田植えだった。当然雨が続く。しかし雨だからと言って田植えを休むわけにはいかない。適期に作業を終わらせないと大変なことになる。それで雨が降っても田植えをしなければならない。そのときに役立つのが蓑笠だ。屈んで田植えをするので、雨は背中に当たるが、それは蓑で防げるのである。頭は笠で防ぐ。もちろん今のような軽くて防水性のある雨具とは違うから大変である。しかし、当時としてはきわめて合理的な雨具だった。
この簑・笠は、雪国では防寒具、防雪具として役に立った。蓑を着ると本当に暖かかった。また身体の前があいているので仕事もしやすかった。しかし蓑は重く、また前半身はやはり寒かった。
なお、私の生家も周辺の農家も簔笠は自分の家でつくらず、周辺の農山村の農家が売りに来るのを買ったり、荒物屋から買ったりしていた。荒物屋にはさまざまなわら工品がいつも並んでいた。
いろいろ欠陥はあってもともかく便利だったことから、非農家のなかにも蓑笠を利用する人がいた。外(がい)套(とう)、帽子などが普及しつつはあったが、それで農作業はもちろん外での作業はできなかったし、さらにそんな高価なものを身につけられる人はほんの一握りだったからである。
子どもたちだが、農村部では、冬期間、簔笠もしくはさきほどいった「みのぼうし」を身につけ、藁沓もしくはつまごを履いて学校に通っていた。しかし、町場は(農家の子どもも含めて)帽子、マント、ゴム長靴だった(昭和になってからの話だが)。こうした格差が解消するのは戦後10年過ぎころからだった。
そのほか、本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
重要な記事
最新の記事
-
 【畜酪政策価格最終調整】補給金上げ実質12円台か 19日に自民決着2025年12月18日
【畜酪政策価格最終調整】補給金上げ実質12円台か 19日に自民決着2025年12月18日 -
 【11月中酪販売乳量】1年2カ月ぶり前年度割れ、頭数減で北海道"減速"2025年12月18日
【11月中酪販売乳量】1年2カ月ぶり前年度割れ、頭数減で北海道"減速"2025年12月18日 -
 【消費者の目・花ちゃん】ミツバチとともに2025年12月18日
【消費者の目・花ちゃん】ミツバチとともに2025年12月18日 -
 一足早く2025年の花産業を振り返る【花づくりの現場から 宇田明】第75回2025年12月18日
一足早く2025年の花産業を振り返る【花づくりの現場から 宇田明】第75回2025年12月18日 -
 笹の実、次年子・笹子【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第369回2025年12月18日
笹の実、次年子・笹子【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第369回2025年12月18日 -
 虹コンのレインボーファーム「農閑期は焼肉ぴゅあに行くっきゃない!」スタンプラリー実施 JA全農2025年12月18日
虹コンのレインボーファーム「農閑期は焼肉ぴゅあに行くっきゃない!」スタンプラリー実施 JA全農2025年12月18日 -
 「淡路島産白菜」使用 カレーとシチューメニューをハウス食品と提案 JAグループ兵庫2025年12月18日
「淡路島産白菜」使用 カレーとシチューメニューをハウス食品と提案 JAグループ兵庫2025年12月18日 -
 畜産の新たな社会的価値創出へ 研究開発プラットフォーム設立 農研機構2025年12月18日
畜産の新たな社会的価値創出へ 研究開発プラットフォーム設立 農研機構2025年12月18日 -
 佐賀の「いちごさん」表参道でスイーツコラボ「いちごさんどう2026」開催2025年12月18日
佐賀の「いちごさん」表参道でスイーツコラボ「いちごさんどう2026」開催2025年12月18日 -
 カインズ「第26回グリーン購入大賞」農林水産特別部門で大賞受賞2025年12月18日
カインズ「第26回グリーン購入大賞」農林水産特別部門で大賞受賞2025年12月18日 -
 軟白ねぎ目揃い会開く JA鶴岡2025年12月18日
軟白ねぎ目揃い会開く JA鶴岡2025年12月18日 -
 信州りんご×音楽 クリスマス限定カフェイベント開催 銀座NAGANO2025年12月18日
信州りんご×音楽 クリスマス限定カフェイベント開催 銀座NAGANO2025年12月18日 -
 IOC「オリーブオイル理化学type A認証」5年連続で取得 J-オイルミルズ2025年12月18日
IOC「オリーブオイル理化学type A認証」5年連続で取得 J-オイルミルズ2025年12月18日 -
 【役員人事】クミアイ化学工業(1月23日付)2025年12月18日
【役員人事】クミアイ化学工業(1月23日付)2025年12月18日 -
 油糧酵母ロドトルラ属 全ゲノム解析から実験室下での染色体変異の蓄積を発見 東京農大2025年12月18日
油糧酵母ロドトルラ属 全ゲノム解析から実験室下での染色体変異の蓄積を発見 東京農大2025年12月18日 -
 約1万軒の生産者から選ばれた「食べチョクアワード2025」発表2025年12月18日
約1万軒の生産者から選ばれた「食べチョクアワード2025」発表2025年12月18日 -
 兵庫県丹波市と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月18日
兵庫県丹波市と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月18日 -
 乳酸菌飲料容器の再資源化へ 神戸市、関連14社と連携協定 雪印メグミルク2025年12月18日
乳酸菌飲料容器の再資源化へ 神戸市、関連14社と連携協定 雪印メグミルク2025年12月18日 -
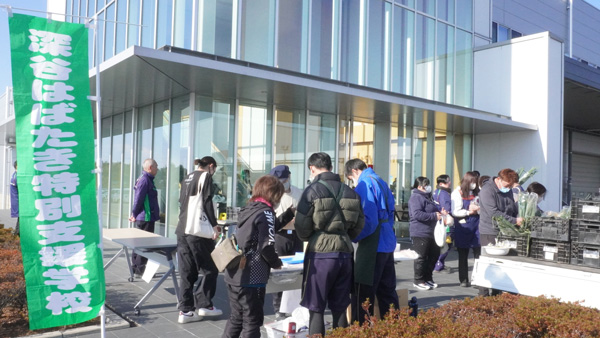 特別支援学校と深める連携 熊谷の物流センターで新鮮野菜や工芸品を販売 パルライン2025年12月18日
特別支援学校と深める連携 熊谷の物流センターで新鮮野菜や工芸品を販売 パルライン2025年12月18日 -
 東京の植物相を明らかに「東京いきもの台帳」植物の標本情報を公表2025年12月18日
東京の植物相を明らかに「東京いきもの台帳」植物の標本情報を公表2025年12月18日