足踏式・電動式縄綯い機の導入【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第102回2020年6月11日
私が小学校に入る前だったか後だったか(太平洋戦争開戦=1941年の前だったか後だったか)忘れてしまったのだが、いずれにせよその前後、私の生家に足踏式の縄綯い機(製縄機)が入った。どんなものか言葉だけで説明するのは難しいのだが、パソコンで足踏み縄綯い機を検索するとその何種類かの写真が出るので、それを見ながら以下の説明を聞いていただきたい。
 足踏み縄綯い機
足踏み縄綯い機
縄綯い機の前方、向かって左側に椅子をおいて縄を綯う人(綯い手)が座り、機械の下に並んでいる二枚の踏み板(ペダル)にそれぞれ左右の脚を置いてかわるがわる上下に踏む。同時に綯い手は左手に持ったわらの束からに二~三本のわらをとって、二つのラッパ管(ラッパの形=メガホンの形をした管)に左、右、左、右と代わる代わる連続して挿入する。すると、踏み板においた両足の上下方向の往復運動は種々の歯車やクランク、シャフト等の回転運動に変換されて挿入した二方向からのわらをよじり、そのよじられた二本のわらをねじって一本の縄にし、それについているわらの毛羽を切りとる。こうしてできあがった縄を回転しているドラムに引っ張って巻き取り、大きな円形(ドーナツ状)の縄の巻き束をつくる、というものである。
縄を機械が綯う、人の手でもむずかしい複雑な細かいことを、手でやるよりも何倍かの速度で作業機がやる、しかもできあがった縄は均質、手や指は手綯いのように荒れないですむ、最初見たときは驚いた。からくりのようなこの機器の動きは、覆いが被さっていないのではっきり見え、よくもまあ考えてつくったもの、日本人の器用さなのか、「からくり」人形の伝統をひいているのか、さすがからくり好きの日本人などと感心したものだった。
ただし、幼い子どもにはこの機器操作は難しかった。両手と両足を同時に代わる代わる動かすのが馴れるまで難しく、スピードについていくのが難しかったからである。
また、縄綯機でできる縄は少し太くて粗く、用途によってこれではだめな場合があり、たとえば細縄とかみご縄、太い縄、きめ細かい縄等は、今まで通りに手で綯わざるを得なかった。しかし、一般的な荷作り縄用などとしては十分に使えるものだった。
こうして縄綯いがスピードアップすると、わら叩き(木槌で藁を打って叩いて柔らかくする縄綯いの前段階の作業)の効率化を図ることが要求される。そうしないと円滑な縄の生産ができない、
そこで開発されたのが、「わら打ち機」だった。二つの金属製の円胴(ローラー)を上下に重ね、その狭い隙間に片方からわらを入れ、円胴に連結していて円胴を動かすハンドルを手で回す。すると二つのローラーが上下逆方向に動いてわらを呑み込んで潰し(柔らかくし)、二つの円胴の隙間から外に吐き出すというものである。ハンドルを回すのが重くて大変で、私たち子どもは両手でハンドルを持ち、全身の力で回したものだった。そのとき、何かの拍子で二つのローラーの隙間に指が入り、指が潰れてしまうのではないかと心配だった(鋭く大きい刃のある「押切り」よりは怖くなかったが)が、短時間にたくさんのわらが打て、縄綯い機の効率利用に大いに役立った。
この縄綯い機の原型は明治末期にできていたとのことだが、昭和初期の日中戦争の激化による縄の需要の増加から急速に普及したようである。
つまり、一方で丈夫で長持ちするマニラ麻をはじめとする麻縄の輸入が困難になる、他方で軍需産業の製品の梱包・運搬用の縄の需要の増加、それに対応する民需産業や家庭生活における縄の需要の増加等々がある、そこで軍需品としてわら縄が大量に買い上げられるようになった。ところが、農村部からの男子の徴兵・徴用による労力不足でその需要増に対応していけない。そこで政府が年寄りや女でも容易に速くできる縄綯機の導入を推奨したのではなかろうか。それに私の生家や近隣の農家が応じたものと思われるのである。
戦後も、復興過程でのわら縄の需要があり、縄綯い機の導入がさらに進んだ。それどころかその電化も進んだ。作業機の方はこれまでとほぼ同じだが、動力が人間の脚力から電力=モーターに変わったのである(わら打ち機も電動になった)。
電動式となった結果、動力源として足を動かさなくともよくなったので子どもでも簡単にできるようになった。もちろん、縄綯い機のスピードに合わせて左右にある機械の穴に代わる代わるわらを挿入するのはけっこう大変だったが。
このように、足踏み脱穀機から動力脱穀機への変化と同様、戦後の食糧難を始めとする物資不足への対応から機械化・動力化が進んだ。しかしこの縄綯いもポストハーベストの機械化であり、過重労働軽減のためというより国策遂行のためのものであり、しかも稲わらに対する地主の支配がなかったために導入が阻害されなかったためでしかなかった。
それでも私は高く評価したい、そもそも稲わらは副産物、本来なら日陰の身、それが主産物の作業に先駆けて機械化の対象にされるほど大事にされたということである。
だからこのころは稲わらにとって史上最良の時期だったのではなかろうか。70年代に入ると稲わらの加工、利用はなされなくなり、それどころか稻わらは邪魔者扱いされるようになったからである。農業の機械化・化学化、農業労働力の流出の進展、生活様式の急激な変化の中で、2000年にわたって築き上げてきた日本の「わらの文化」はほぼ完全に崩壊するに至るのである。そしてそれは日本の農業・農村・農家の崩壊の始まりを示すものでもあった。
電動縄綯い機が普及した1950年前後の頃、そんな時代が来ることを誰も予想だにしていなかった。稲わらは食糧増産にとって不可欠の生蚕資材として重視された。
そしてみんなみんな、生活は苦しかったけれど、食糧増産、明るい農村の建設へと希望に燃えていた。
重要な記事
最新の記事
-
 米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日
米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日 -
 鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日
鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日 -
 創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日
創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日 -
 花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日
花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日 -
 どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日
どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日 -
 劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日
劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日 -
 露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日
露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日 -
 徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日
徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日 -
 長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日
長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日 -
 新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日
新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日 -
 佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日
佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日 -
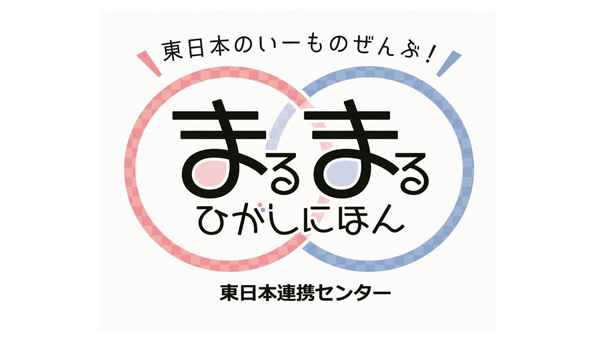 まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日
まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日 -
 日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日
日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -
 鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日
鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -
 人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日
人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日 -
 住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日
住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日 -
 埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日
埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日 -
 熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日
熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日 -
 外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日
外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日





































































