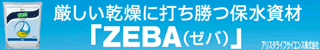多肥多收稲作の追求【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第128回2020年12月10日
戦後の混乱から立ち直りつつあった1950年代、農協に結集しながら消費者の需要に応えて野菜や果実の生産販売に取り組み始めたという話をしてきたが、主食の米はまだまだ不足、政府は増産を奨励、農家も懸命に増収に取り組んだ。前に述べた保温折衷苗代の導入による健苗育成、耕運機導入による深耕に加えて、肥料の増投にも力を入れた。

雪国の2月末ころ、まだ田んぼは一面の雪に覆われている。堆厩肥をそりに積み、牛に牽かせてそこに運ぶ。たまに、牛が牽くそりよりも一回り小さくて手綱をつけて人が引っ張るそりで運ぶ場合もある。そして雪に埋まった自分の田んぼの中の何ヶ所かに小さな山にして積んでおく。
さらに雪解けが近くなると、籾殻を燃料にする糠窯(ぬかがま)から出た真っ黒な灰などを苗代などの田んぼの雪の上に播く。雪解けを速めるためと肥料にするためである。
雪が解け、田んぼが乾き始めた頃、田んぼの中にあるダラ桶(肥だめ)から肥桶にダラ(下肥)を入れて天秤でかつぎ、あぜ道から柄杓でそのダラを田んぼに撒き散らす。また、堆厩肥を牛車に積んで運び、田んぼに散布する。
こうした堆厩肥、灰、下肥という昔からの肥料に加えて、耕起の直前に石灰窒素をまき、耕起してそれらを土と混ぜ合わせる。さらに代掻きの直前に硫安(硫酸アンモニウム)、過リン酸石灰、硫酸カリなどを散布する。
このような元肥(もとごえ)(播種や移植の前に施す肥料のことで、基肥とも書く)のなかでもっとも効果の高いのは硫安などの化学肥料だったが、食糧危機からの脱却・食料増産が至上命令だった政府は肥料工業の保護育成に取り組んだ結果1950年には戦前をしのぐ生産が可能となり、安価に大量に供給されるようになってきた。
50年代後半のいつごろだっただろうか、これまで見たことのなかった真っ白のきれいな粒の新しい肥料がそれに加わった。これは尿素と言って純粋な窒素分だけでできているので効率が高いと父が説明してくれたのを記憶しているが、それ以外にも熔成燐肥、塩化加里といった新しい肥料が見られるようになった。こうした肥料は無硫酸根肥料と呼ばれ、土に残った硫酸根が土壌を酸性化するという欠陥をもつ硫安のような硫酸根肥料に替わるものとして、これも安価に大量に供給されるようになってきた。
そして水稲に必要な肥料の三要素NPKは化学肥料の投入で十分に供給できるようになった。となるとダラ(下肥)や堆肥がなくともやっていける。そこで60年代後半から農家のダラ汲みはなくなってきた。きつい汚い労働から解放されたのである。また糞畜として飼っていた牛等がいなくともかまわなくなったので、どこの家にもあった畜舎が消えるようになった。そして真っ白な雪の上に堆厩肥の黒い塊がぽつぽつと置かれている風景も見られなくなってきた。
「尿素」、この名前を聞いたとき、尿からつくったわけではないだろうが、このことはこれまで散布してきた尿の価値、ダラ撒きの正しさを示すものとなにか誇らしく感じたものだった。しかし、その尿素とその仲間がダラ汲み、ダラ撒きを追放する、何か奇妙だった。決まった日になると雨が降ろうと雪が降ろうと朝暗いうに牛車でダラ汲みに行く労働から私の父が、多くの農家が解放されたのはうれしかったが。
いうまでもなく肥料は増収に直接結びつく。だから農家としては肥料をたくさん散布してさらに多くの収量を得たい。しかし、元肥で大量に散布すると窒素過多等で弱々しく育ち、倒れたり、病害虫の被害にあったりする。また、生育の後期には肥料が足りなくなったりする。
これを解決するためになされたのが「追肥」であった。この追肥の技術は、硫安のような速効性肥料が開発されたことを契機に山形県農試などの研究をもとに戦前開発された技術であるが、肥料のすべてを元肥として施すのではなく、稲の成長期や開花、結実時など、特に養分が必要な時期に必要な量だけ追加して施すというものである。なお、肥料を何回かに分けて施すことから「分施」とも呼ばれた。こうすると施肥効率はきわめて良く、しかも多くの肥料を投入できる。そして増収できる。かくして戦前からの多肥農業がさらに強化されることとなった。
この追肥と合わせて重視されたのが水管理だった。
まず、7月上旬の中干しがある。無効分蘖を抑制し、根に酸素を供給して根の健全化と倒伏軽減を図り、稲の生育後期の同化能力を落さないようにするために、田んぼの表面に軽くひびが入る程度まで水を落とすのである。また、何日間か湛水しては何日間か落水することを繰り返す間断灌漑がある。さらに、冷害回避、高温対応のための水管理もある。昔のように水さえかけておけばいい、そのために水を絶やさないようにするという水管理ではなくなってきたのである。
こうした周到綿密なきめの細かい肥培管理は収量を上昇させるものだが、逆に低下させる危険性ももっていた。
重要な記事
最新の記事
-
 【年頭あいさつ 2026】岩田浩幸 クロップライフジャパン 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】岩田浩幸 クロップライフジャパン 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】片山忠 住友化学株式会社 常務執行役員 アグロ&ライフソリューション部門 統括2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】片山忠 住友化学株式会社 常務執行役員 アグロ&ライフソリューション部門 統括2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】佐藤祐二 日産化学株式会社 取締役 専務執行役員2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】佐藤祐二 日産化学株式会社 取締役 専務執行役員2026年1月3日 -
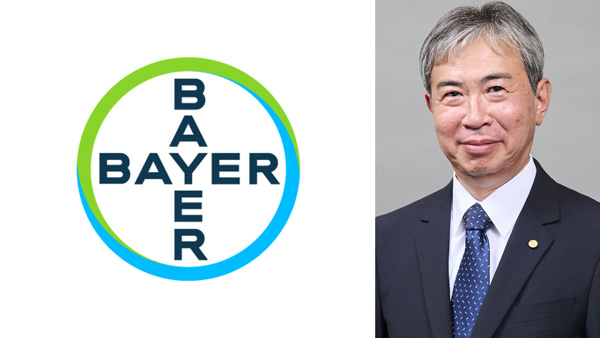 【年頭あいさつ 2026】大島美紀 バイエル クロップサイエンス株式会社 代表取締役社長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】大島美紀 バイエル クロップサイエンス株式会社 代表取締役社長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】栗原秀樹 全国農薬協同組合 理事長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】栗原秀樹 全国農薬協同組合 理事長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】佐藤雅俊 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】佐藤雅俊 雪印メグミルク株式会社 代表取締役社長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】雜賀慶二 東洋ライス株式会社 代表取締役2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】雜賀慶二 東洋ライス株式会社 代表取締役2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】松本和久 株式会社サタケ 代表取締役社長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】松本和久 株式会社サタケ 代表取締役社長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】冨安司郎 農業機械公正取引協議会 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】冨安司郎 農業機械公正取引協議会 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】増田長盛 一般社団法人日本農業機械工業会 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】増田長盛 一般社団法人日本農業機械工業会 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】菱沼義久 一般社団法人日本農業機械化協会 会長2026年1月3日
【年頭あいさつ 2026】菱沼義久 一般社団法人日本農業機械化協会 会長2026年1月3日 -
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確保に貢献 山野徹 全国農業協同組合中央会代表理事会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】将来にわたって日本の食料を守り、生産者と消費者を安心で結ぶ 折原敬一 全国農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】利用者本位の活動基調に 青江伯夫 全国共済農業協同組合連合会経営管理委員会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】金融・非金融で農業を支援 北林太郎 農林中央金庫代表理事理事長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】地域と共に歩む 持続可能な医療の実現をめざして 長谷川浩敏 全国厚生農業協同組合連合会代表理事会長2026年1月2日 -
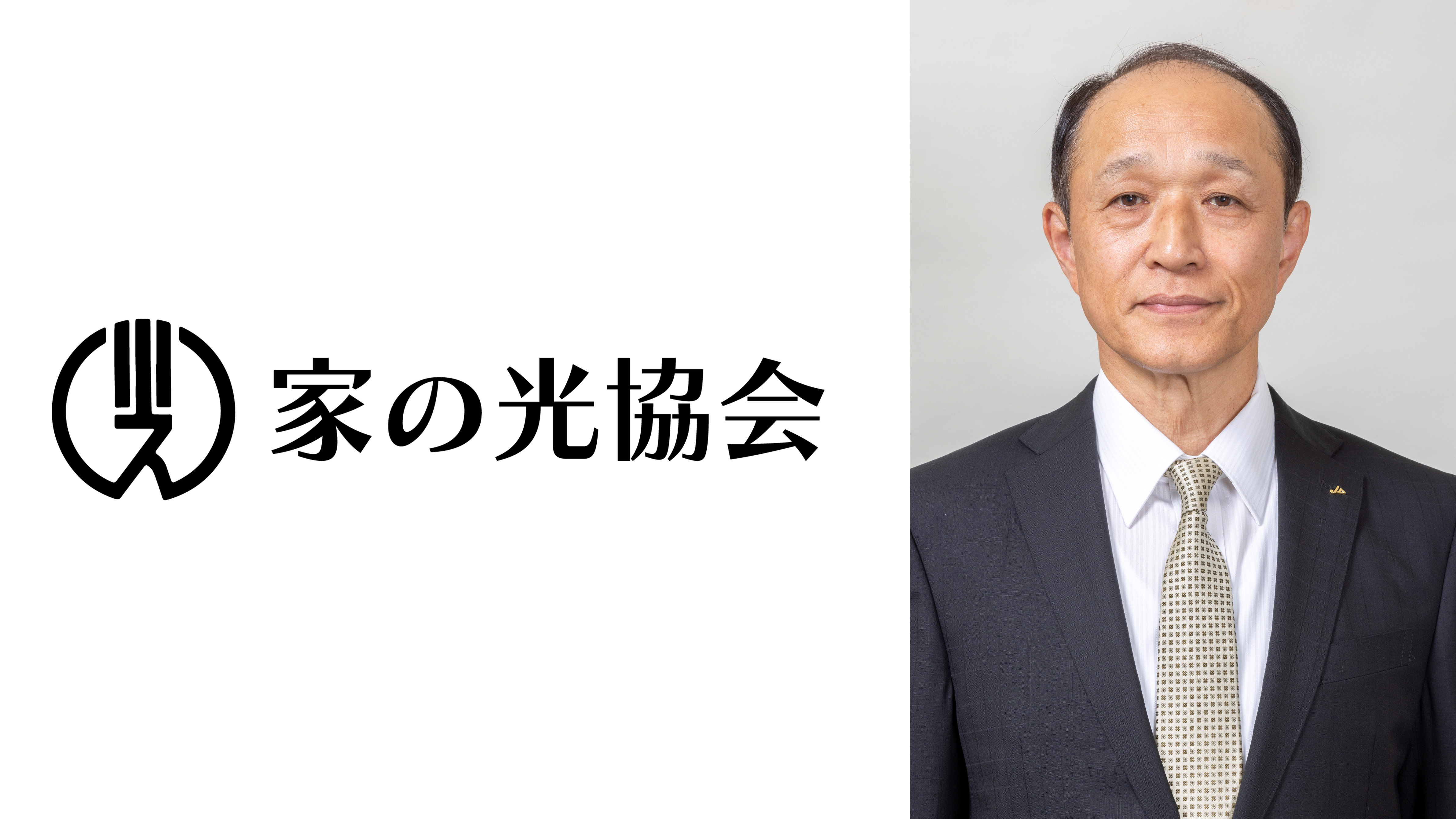 【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】「JAサテライト プラス」で組織基盤強化に貢献 伊藤 清孝 (一社)家の光協会代表理事会長2026年1月2日 -
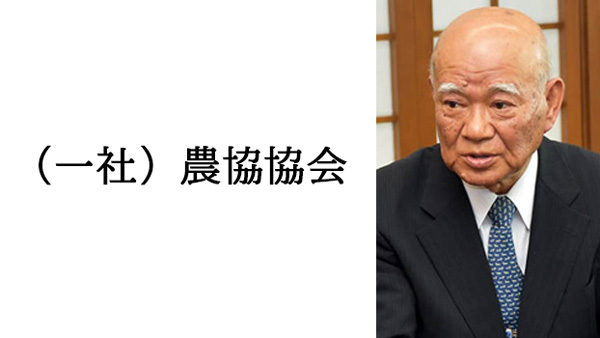 【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日
【年頭あいさつ 2026】協同の原点に立ち返る年に 村上光雄 (一社)農協協会会長2026年1月2日 -
 【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日
【年頭あいさつ 2026】食料安全保障の確立に全力 鈴木憲和農林水産大臣2026年1月1日 -
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日