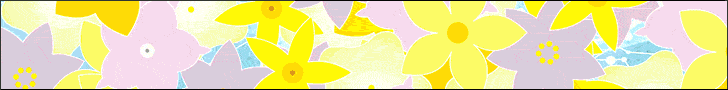ゴールなき規模拡大【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第160回2021年8月26日
1970年1月(つい先日のような気がしているのだが、もう半世紀も前になるのだ、私も年をとったものだ、などと余計なことを考えてしまう、困ったものである)、北海道最北の酪農の調査が終わって稚内から札幌に行く夜行列車に乗った。少し経ってから窓の外を見ると真っ暗である。町を過ぎて林野にでも入ったのだろう。そのうち、暗闇のなかにぽつりぽつりと電灯が見えてきた。平坦農地の地帯に入ったのだろう。そしてあの灯りはきっと酪農家だろう。この辺は酪農地帯だからだ。ともかく家がある、人がいると思うとほっとする。

こんなことをたまたま北海道の農協職員に言ったらこう言われた。
電灯が点いていることが人がいることを示すとは限らない。電灯を点けたまま夜逃げする酪農家もあるからだ。隣りの農家もそのことに気がつかない。家が遠いのでいつもめったに顔をあわせないから電灯が点いていれば人がいるものだと思っている。そして一ヶ月もたって初めて夜逃げしたとわかることもある。この夜逃げはいやおうなしの規模拡大のつけのせいだ、こう言うのである。
こうした状況は東北でも同じだった。50年代後半に1~2頭飼育で酪農を始めたのだが、乳価は60年代の高度経済成長下での急激な諸物価の上昇に追いつかず、労働報酬は他産業労賃の上昇に追いつかなくなり、経営は苦しくなってきた。
この乳価の低迷は脱脂粉乳や乳製品等の輸入に起因するものだった。
60年代後半、コーヒー牛乳とかフルーツ牛乳とかの色物牛乳、また濃縮牛乳とかの名前のついた加工牛乳が大量に出回った。色物牛乳は甘かった。濃縮牛乳は栄養がありそうに思えた。ところがこれには日本の酪農家が生産した牛乳は一切入っていなかった。それどころかまともな牛乳は一滴も入っていなかった。輸入された脱脂粉乳、乳糖、カゼイン、バターもしくは植物油脂を混ぜ合わせてつくった還元乳・合成乳だったのである。こうしたインチキ牛乳が飲用牛乳販売量の4割を占めた。そればかりではなかった。普通の市乳にも10~25%の脱脂粉乳が入れられていた。しかし消費者はすべてまともな牛乳だと思って飲んでいた。「牛乳」と書いてあるからである。
もう一方で、学校給食では日本の酪農家の生産した牛乳はまったく用いず、補助金付きでまずい輸入脱脂粉乳を牛乳として子どもたちに飲ませた。
このように日本政府の援助のもとにアメリカの脱脂粉乳が大量に輸入されていたことが、そして乳業資本がその脱脂粉乳などの安い輸入原料でつくったインチキ「牛乳」を大量に高く売って大もうけをし、また全国の子どもに学校が脱脂粉乳を飲ませたことが、まともな牛乳の消費量を減らし、牛乳が過剰なのだからやむを得ないと言って生産者乳価を抑えたのである。
こうしたなかで、酪農家は赤字を抱え、酪農をやめるか、一頭当たり収益の低さを多頭化によって補うかの二つの道のいずれかを選ばざるを得なくなった。
これに対して政府は多頭化の道を勧めた。そして1960年当時は、4頭以上飼育すれば他産業並みの所得が得られるとした。そこで農家は借金をして必死になって多頭化した。しかしそれでも経営は成り立たない。すると政府は、10頭以上でないと他産業並みの所得が得られない、そこまで規模を拡大しようと60年代後半になって言う。しかし10頭以上にするには畜舎の大幅な増改築、乳牛の購入が必要となる。さらには土地も必要となる。しかしそのために必要となる膨大な資金を自己資金でまかなうことはできない。当然借金が増加し、支払い利子は増える。
そればかりでなく、固定資本の減価償却費や飼料代等の流動資本も多くなる。それで一頭当たり所得が減少する。それを補うためには頭数の拡大しかない。そうすると労働が過重となる。また生乳の保存、衛生等も問題となってくる。それを解決するには機械・施設の高度化が必要となる。それを導入するとまた所得率が低下する。生活費をまかなうためにはまた頭数を増やさなければならない。やめればこれまでの借金を返せない。いくら政府や農協の長期低利資金といってもそれが累積しているからである。やめようと思えば夜逃げしかない。拡大か夜逃げか、どちらを選択するか。
やむをえず規模拡大する。しかしこの拡大はいつやめることができるのだろうか。それはまさに「ゴールなき拡大」であった。
当時の酪農家は自分たちの酪農のことを「かっぱえびせん酪農」と称した。当時流行った「やめられない とまらない かっぱえびせん」というテレビのコマーシャルと同じで、いつまでたっても拡大がやめられない、止まらないというのである。
これは養豚も養鶏も同じだった。しかし飼料作物の規模拡大は土地の限界からしてできない。そこで輸入飼料依存の施設型畜産で「ゴールなき拡大」を進めていくより他なかった。
こうした苦労のなかで家畜の飼育頭数が増えていく一方で、せっかく導入した家畜の飼育をやめる農家も増えてきた。もう役畜・糞畜はいなくなっていたから、家畜を飼育するのは本当に一にぎりになってしまった。多くの農家の暮らしは家畜の飼育とほぼ完全に分離してしまったのである。
このようなさまざまな問題を抱えて苦労をしながらも、農家はそれを乗り越えて新しい作目・部門を発展させようと努力し、新しい技術を導入しようと挑戦した。
まさに1960年代は、本格的な畜産の始まりを告げる年代であったし、野菜、果樹等の新たな発展の展望も開け始めようとする年代であったし、さらに機械化段階が本格化する年代でもあった。
さらに60年代は、いまだ不足していて食糧管理法で価格を保障してくれている安定作物の稲作の規模拡大と増収に取り組もうと努力し、大きな成果をあげた年代でもあった。
そしてもう一つ、農業・農村からの本格的な労働力流出=農家の首切りが始まった年代であった。
本コラムの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日 -
 米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日
米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日 -
 (467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日
(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日 -
 【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日
【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日 -
 JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日
JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日 -
 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日 -
 日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日
日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日 -
 石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日
石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日 -
 【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日
【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日 -
 GREEN×EXPO 2027の「日本政府苑」協賛を募集 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月26日
GREEN×EXPO 2027の「日本政府苑」協賛を募集 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月26日 -
 初の殿堂入り生産者誕生 産直アプリ「ポケットマルシェ」2025年生産者ランキングを発表2025年12月26日
初の殿堂入り生産者誕生 産直アプリ「ポケットマルシェ」2025年生産者ランキングを発表2025年12月26日 -
 災害時の食の備えを支援 新サイト「食の備え BOSAI」公開 コープこうべ2025年12月26日
災害時の食の備えを支援 新サイト「食の備え BOSAI」公開 コープこうべ2025年12月26日 -
 直営7工場で2026年元日一斉休業を実施「働き方改革」を推進 サラダクラブ2025年12月26日
直営7工場で2026年元日一斉休業を実施「働き方改革」を推進 サラダクラブ2025年12月26日