(340)中国の人口、ピークアウト?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2023年7月14日
10年前の日本では、人口減少の話をしても切迫感を感じる人はまだ少なかったかもしれません。最近はかなり変化が出てきました。ところで、国連の数字を見ると中国の人口もピークを迎えたようです。
国連の人口統計(World Population Prospects 2022)を見ると、中国の人口ピークは一昨年から昨年のようだ。1月1日時点で比較すると、2021年は14億2,586万2千人、2022年は14億2,592万5千人である。2021年の数字は発表当時の見込み(estimates)であり、2022年は発表時点から将来を見た中位推計である。国連は7月1日時点の数字も発表している。こちらは2021年が14億2,589万3千人、2022年は14億2,588万7千人で、ピークは微妙に異なる。そもそもこの規模の国家で統計に乗らない人数を含め、総人口を完全把握することが本当に可能かという議論はあるが、ここはデータを信じて話を進めたい。
多少のズレはあるが、一昨年から昨年にかけて中国が人口ピークを迎えたことはほぼ間違いないであろう。以下、話を簡単にするために1月1日時点の総人口を用いる。
さて、同じ統計によれば、日本の人口ピークは2010年の1億2,813万1千人である。13年後の2023年には1億2,362万5千人、450万6千人減少している。一般に、2点間の減少率は以下で求められる。
減少率=(開始時-終了時)/ 開始時 × 100
開始時を人口ピーク時(2010年)、終了時を現時点(2023年)あるいは将来の一定時点として計算し、数字を千人単位でまとめると、例えば、日本の減少率は以下のようになる。
(128,131-123,625)/128,131×100=3.5%
同じ時間軸で中国を見るとどうなるか。人口ピークを2022年の14億2,592万5千人とし、13年後の2035年の推定人口は14億148万9千人とすれば減少率は1.7%に過ぎない。ただし、絶対数は▲2,443万6千人である。
この違いの理由は、年齢別の人口構成の違いや平均寿命などの特性が影響しているのだろうが中身を精査しないと正確なことはわからない。言えることは中国の場合、ピークから13年後の減少率は日本の半分程度、つまり減少ペースが遅いということだ。
次に、1世代30年、さらに2世代60年で両国の減少率がどのくらい異なるのかを試算すると以下のようになる。減少率の右側は減少人数である。
(1世代:ピークから30年後)
日本: (128,131-111,534)/128,131×100 = 13.0% ▲16,597千人
中国: (1,425,925-1,299,186)/1,425,925×100= 8.8% ▲126,739千人
(2世代:ピークから60年後)
日本: (128,131-89,497)/128,138×100 = 30.2% ▲38,634千人
中国: (1,425,925-848,047)/1,425,925×100 = 40.5% ▲577,878千人
人口ピーク時から1世代、2世代、つまり子供や孫の代に至るまで、両国の人口減少のプロセスがやや異なることがわかる。ピークの余韻は中国の方が長そうである。それにしても、ピーク時から2世代で約4千万人の減少という日本に対し、同じ期間で約6億人の減少という中国の将来的な人口減少「規模」の凄まじさがわかる。
人が生きている以上、農地を含め生活に関わるあらゆるインフラは基本的にピーク時需要への対応が求められる。どうしても足りない分は外から調達(輸入)するにしても、基本は国内調達となる。
つまり現実対応として、中国は現在の14億人のニーズを満たす仕組みを、今後60年で8億人規模にスケールダウンしていくことが求められる。常に成長と拡大を指向している国にとり、これはかなりの難行であろう。かつて中国の人口が8億人に到達したのは1970年(811,787千人)である。今から半世紀前の8億人と今から2世代後、2082年の中国は、人口は同じでも人々の求める生活水準とニーズは全く異なるはずだ。
同じことは日本にも言える。2世代後の2070年の日本の人口は89,497千人、これは1955年の89,598千人水準である。現代の生活のうち、何を維持して何を削減していくか、10年や20年程度ではなく、もう少し長い視野で農業を含めた産業全体の戦略が求められるのはいずれの国も同じということだ。
* *
中国の人口ピラミッドを見ると、日本と同様、団塊の世代とそのジュニア世代があるのに加え、さらに孫の世代にもピークがあります。この最後の点が日本とは異なります。
重要な記事
最新の記事
-
 「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日
「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日 -
 2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日
2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日 -
 地震・原発・アホ大将【小松泰信・地方の眼力】2026年1月7日
地震・原発・アホ大将【小松泰信・地方の眼力】2026年1月7日 -
 節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日
節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日 -
 暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日
暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日 -
 厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日
厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日 -
 【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日
【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日 -
 高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日
高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日 -
 JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日
JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日 -
 JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日
JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日 -
 爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日
爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日 -
 雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日
雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日 -
 産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日
産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日 -
 JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日
JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日 -
 福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日
福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日 -
 CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日
CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日 -
 新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日
新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日 -
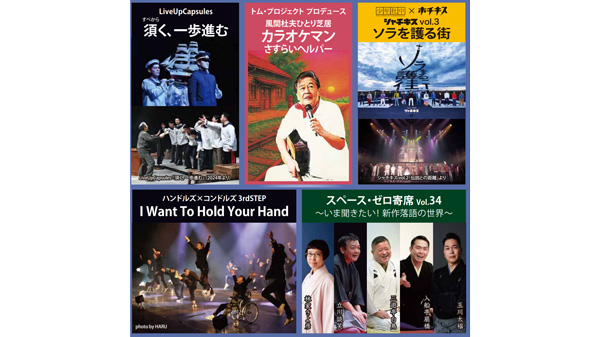 「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日
「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日 -
 酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日
酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日 -
 福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日
福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日




































































