「地水ビール」(?)からの脱却を【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第251回2023年8月10日

1990年代、地ビールブームで全国各地にたくさんの地ビール会社がつくられた。そのなかには、麦もホップも輸入、技術はドイツや日本の大メーカーからの直輸入、つまり地元産品は水と空気と単純労働力だけというようなところが多々あった。
ビール麦もホップも日本でつくれるにもかかわらずである。これでは地ビールとはいえず、大メーカーと変わりない。工場がいわゆる地方にあるというだけの「地方ビール」、水が地元産というだけの「地水ビール」とは言えるだろうが。
だから、せめて日本ではあまりなじみのないピルスナー、ヴェイツェン、アルト、スタウトなどの製品で大メーカーと差別化するくらいしかできない。しかしそれも全国各地の「地方ビール」がいずこも同じとなれば差別化にもならない。
これでは四大メーカーと太刀打ちできるわけはない。しかも地元の人たちは自分たちの地域のビールとして飲んで応援しようとも思わないし、愛着も持てない。こうしたところに大メーカーによる価格の安い発泡酒の攻勢を受けた。それで廃業せざるを得なくなった地ビール会社が数多く出たとのこと、それは当然のことだろう。
本来の「地ビール」ではなかったからなのである。日本は大麦も小麦も穫れる、ホップも穫れる(前にも書いたがその野生種すらあるのだ、もちろん北国だけだが)、それを活用してこその地ビールなのである。
ちょっとここで、私が1999年から7年間勤めさせてもらった東京農業大学生物産業学部と地ビールについて、宣伝をさせていただきたい。
北海道網走市のオホーツクキャンパスにあるこの学部は89年に創設されたのだが、その開設のときに大学として日本で初めてのビール試験製造免許を取得し、食品加工技術センターを設置してビールに関わる教育研究を開始した。
同時に地元の要望を受けて地ビールの研究も進め、その成果を基礎にして98年網走ビール株式会社が設立され、地ビールの生産販売を開始した。そして原材料に地元網走産の麦芽を100%使用した「ABASHIRIプレミアム」、冬の網走を代表する流氷を仕込み水にしたオホーツクブルー色の発泡酒「流氷DRAFT」などを開発し、また網走産のジャガイモ、ナガイモ、トウモロコシ、ニンジンなどの農産物、コンブやホタテなどの海産物を副原料とする発泡酒も製造して好評を博してきた。
さらに数年前には、農大の学生が地域の方から土地と重機の提供を受けて畑を開墾し、そこでビール麦を育て、そのビール麦と付属寒冷地農場で栽培したホップを用いたビールの醸造を網走ビール株式会社の協力を得ながら学生が行なうビールを完成させた。そして「学生ビール」と名づけて販売するに至ったが、このオール網走産のビールこそまさに『地ビール』の名に値するといえよう(自画自賛かな?)。
先年網走に行ったとき、この「学生ビール」をごちそうになったが、大メーカーのビールに負けない味、本当にうれしかった。
もちろん他の地ビールもおいしいのだが、たった一つ誉めなかったものがあった。干したホタテの味をつけたビールを試飲をしたときだ。こう評したのである、「とってもいい味だけれども、ホタテはつまみにしてビールはビールで飲んだ方がもっとうまい」と。
なお、こうした各種ビールと網走名物の料理を提供する「網走ビール館」が市内で営業しているが、道東の旅行のさいにはぜひお立ち寄り願いたい。そして緑なす麦畑をはじめとする広大な畑、オホーツクブルーの海の味を堪能しながら、本物の「地ビール」を味わっていただきたいものである。
この学生ビールをきっかけに網走地方でのビール麦・ホップの生産がさかんになり、「網走ビール」が本来の地ビールとして評価され、それを契機に全国各地の「地ビール」もその存在する地域の農業と結びついた本来の地ビールに発展していくようになれば、同時に農大の食品加工技術センターや農場でのビールに関する研究教育がさらに発展してそれに寄与できるようになれば、と私は願っているのだが、コロナ禍のもとでの観光客の減少(それに昨年春の知床観光船の事故が拍車をかけていないだろうか)、巨大都市からの遠隔地で進む過疎化の進展のなかでどうなっているか、旧網走市民として心配しているところである。
それはそれとして、今がんばっている地ビールが何とかもう一頑張りして地元でホップとビール麦を栽培し、顧客みんなであるいは地域ぐるみでそれを育て、みんなでそれを愛飲するということも考えていいのではなかろうか。それは素人の考えること、現実は厳しいと言われたら一言もないのだが
それはそうと、オホーツク海に流れ込む流氷が近年少なくなっているそうだ。地球温暖化の影響らしい。このまま行ったら見られなくなるかもしれない。網走に行くならなるべく早く、流氷が見られなくなる前に「流氷DRAFT」を飲みに行くことをお勧めしたい(などと言うのはけしからん、いつまでも流氷が見られるように、温暖化を食い止められるように努力すべきだ、と怒られるかもしれないが)。
さて、ここで童心に帰り、今から約80年前、戦前昭和のころの村と町の子どもたちの遊びについて、次回以降語ることにしたい。
重要な記事
最新の記事
-
 「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日
「なくてはならない全農」への決意 消費促進へ牛乳で乾杯 全農賀詞交換会2026年1月7日 -
 2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日
2026年賀詞交換会を開催 クロップライフジャパン2026年1月7日 -
 地震・原発・アホ大将【小松泰信・地方の眼力】2026年1月7日
地震・原発・アホ大将【小松泰信・地方の眼力】2026年1月7日 -
 節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日
節水型乾田直播問題で集会 2月24日2026年1月7日 -
 暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日
暴落防ぎ適正価格へ着地めざす JA新潟中央会の伊藤会長 「最低保証額」、今年も早期に2026年1月7日 -
 厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日
厚生連病院の差額ベッド料 上限額を引き上げ 2026年税制改正2026年1月7日 -
 【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日
【2026新年号】鈴木定幸常陸大宮市長インタビュー 常陸大宮市にコウノトリが飛来する日2026年1月7日 -
 高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日
高校生が和牛飼育の取り組み競う「第9回和牛甲子園」15日から開催 JA全農2026年1月7日 -
 JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日
JAタウン「新鮮ぐんまみのり館」で 「お年玉抽選付き新年初売りキャンペーン」開催2026年1月7日 -
 JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日
JAタウン「ココ・カラ。和歌山マルシェ」で新春お年玉キャンペーン開催2026年1月7日 -
 爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日
爽やかな甘酸っぱさが人気「国産キウイフルーツフェア」9日から開催 JA全農2026年1月7日 -
 雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日
雪国から届く冬のぬくもり「新潟県産さといもフェア」8日から開催 JA全農2026年1月7日 -
 産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日
産地直送通販サイト「JAタウン」公式アプリ ダウンロードキャンペーン実施2026年1月7日 -
 JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日
JAタウン「祝!会員100万人突破!新春生活応援キャンペーン」スタート2026年1月7日 -
 福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日
福島の新しいいちご「ゆうやけベリー」JA直売所などで試食販売フェア開催2026年1月7日 -
 CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日
CES2026に出展 クボタグループ2026年1月7日 -
 新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日
新年のメロン初めに冬の新作パフェ 7日から登場「果房 メロンとロマン」2026年1月7日 -
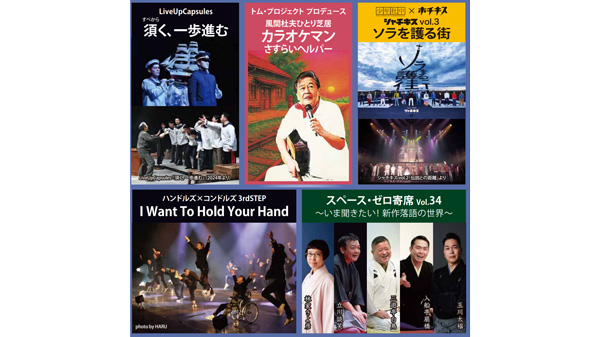 「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日
「こくみん共済 coop 文化フェスティバル2026」3月18日に開幕2026年1月7日 -
 酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日
酪農生産者へ利用者のメッセージを添えて「タオルを贈る運動」12日から パルシステム2026年1月7日 -
 福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日
福利厚生「ふるさと住民登録促進制度」を新設 雨風太陽2026年1月7日




































































