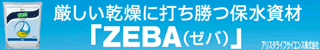その昔の雪国の子ども【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第270回2023年12月21日
今年の夏は暑かった。この冬はどうなるのだろうか。私の幼い頃、昭和初期の雪国の冬はもっと寒く、長く、雪が多かったものだが。

寒くなった12月のある日、どんよりと曇った空から一片二片と雪が落ちてくる。すると子どもたちは初雪だと大騒ぎをする。そして降ってくる雪を追いかけて口に入れて喜ぶ。
おかしなもので根雪になる日は何となくわかる。年末近くなると今日の雪は根雪になるなとみんなで予測し、子どもたちは雪が積もったらこうして遊ぼう、ああして遊ぼうと楽しみにして待ったものだった。
しかし問題は、雪が降ったり風が吹いたりすると外では遊べないことだ。今のようにテレビはなし、ラジオもなし(あってもすべての時間放送しているわけではない)、本なども少ない。こたつに入ってカルタをしたり、綾取りやお手玉をしたり、もう読み終わった本をまた読み返してみたりするしかない、力がありあまって兄弟げんかをして怒られたり、さんざんである。
だから、天候が治まると子どもたちは一斉に外に出て雪遊びだ。
といっても雪は生活にとってはじゃまものである。したがって、遊ぶ前にそれを片付ける手伝いが課せられる。
まず、雪かきである。家の玄関先はもちろん、家の前の道路の雪かきもしなければならない。今のように除雪車が来てくれる時代でもないので、いくら雪かきをしても雪は道路に積もっていき、圧雪されて固くなり、それは春まで消えない。新しくその上に積もった柔らかい雪を道路脇に寄せるだけである。大雪のときは大人が雪かきをし、子どもが通学できるように雪道をつくってくれる。
屋根の雪下ろしの手伝いもある。屋根に登るのは普通は怖いのだが、おかしなものでこのときだけは怖くない。雪が下に積もっているので屋根と下の距離が短く見えるし、たとえ下に落ちても雪があるから痛くなく、けがもしないだろうからである。下ろした雪が積もって高くなるので、屋根から下に飛び降りて遊ぶ。冬以外は屋根が高くて飛び降りるなどということはできないが、それができることが珍しく、何度も何度も飛び降りて遊ぶ。これは楽しい。
その雪下ろしの雪と雪かきをした雪で庭や道路脇に坂(高い山)をつくり、その上からそりや竹下駄(孟宗竹を半分に割り、鼻緒をつけたもの、これは男の子用)、すべり下駄(女の子用のぽっくり下駄の底に細く切った竹を何枚も張り合わせたもの、下駄屋さんで売っていた)を穿いて坂の上から滑り降りて遊ぶ。
竹スキー(青竹を30cmくらいの長さに輪切りにし、さらにそれを5㌢くらいの幅に割り、先の方を火であぶってスキーの先のように曲げたもの)を片足の下におき、もう片方の足で蹴って道路をすべる。当時は除雪車などはなかったので雪は十分に道路にある。これに乗るとすごく速い。遠距離の中学にこれで通学すると、いつもの三分の一くらいの時間で着いた。もっと楽で速いのはバスの後ろのバンパーにつかまって竹スキーですべることだ。これは危険だということで学校から禁止令が出されたが。
それからトーチカつくりだ。秋田などで言う「かまくら(=雪でつくった家)」であるが、当時は戦争の影響もあってトーチカ(=銃火器などを備えた鉄筋コンクリート製の防御陣地)と私たちは呼んでおり、山形言葉でそれをそもそもどう言っていたのか思い出せない(困ったものだ、年は取りたくないものだ)。
もちろんのこと雪だるまつくりや雪合戦がある。
さらに「雪玉割り」という遊びがある。この遊びの説明は難しいのだが、氷のかけらなどを芯にしてそれを足でころがしながら下の雪をそれにくっつけていき、固めながら少しずつ大きくし、固い堅い雪玉をつくっていく。野球のボールくらいの大きさになったとき、みんなで集まってその玉のぶっつけ合いをする。雪の上においた相手の雪玉に自分の雪玉をかわるがわるぶつけあう。当然やわらかい方の雪玉は割れて遊びには使えなくなってしまう。そうなると負けである。だからいかに固い雪玉をつくるかが子どもたちの創意工夫となる。
足で強く踏んで固くするために努力するのはもちろん、土間の土を付けてみたり、雪の中に一晩入れてあるいは水で濡らしておいて凍らしてみたりして、ガラス玉のようにガチガチに固くするのである。これをぶつけ合うのだから一部が鋭い破片となって飛び散り、目などに入ったら大けがをするということになる。
この遊びは雪国の人間でないとわからないかもしれない(もしかすると山形内陸の人間だけ?)。家内が東北大学病院に勤めていたとき、雪玉遊びで目をけがしたという子どもが山形から担ぎ込まれてきた。何で雪の玉でけがするのかが医者や家内たちはわからなかったという。雪合戦の雪玉を考えるからである。あんな柔らかい雪の玉でけがするわけはない。氷のようになっている雪玉をぶっつける遊びで、当てたときに欠けた尖った氷の破片が跳ねて目に刺さったのだという説明を聞いてようやく納得したという。
ゲーム等々遊び道具の多くなった今はもうこんな遊びはしなくなったようだが。
冬の夜、栗や銀杏(ぎんなん)をいろりで焼いて食べる。栗は少し皮を剥いて、銀杏はからを奥歯でパリンと割って、燃えているいろりの火の下の灰のなかに火箸で入れる。そうしないと破裂するからだ。それでもときどきバンと破裂して灰と火の粉が飛び散る。それがまたスリルなのだが、子どもたちは大騒ぎする。ときどき灰の中に入れてよそのことをやっている間に、真っ黒焦げになって食べられなくなり、がっかりすることもある。
また、母や祖母がニンニクをいろりや火鉢の灰のなかに皮付きのまま入れてじっくりと焼きあげ、風邪の予防薬として食べさせてくれる。甘く、熱く、ほくほくして本当に美味しかった。
もうこんな冬を送る子どもや家などはもうないだろうが、本当になつかしい。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -
 農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日
農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -
 世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日
世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日 -
 米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日
米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日 -
 (467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日
(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日 -
 【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日
【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日 -
 JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日
JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日 -
 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日 -
 日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日
日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日 -
 石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日
石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日 -
 【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日
【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日