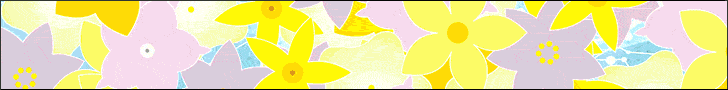むらの掟【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第289回2024年5月2日

前回述べたようなむらの管理運営は全員一致が原則だった。
ともに同じ権利をもっているわけだし、しかも全員一致で取り組まないと全員の生産、生活に支障が起きるからである。
たとえば水路の管理について多数決で決め、少数派に不満が残ってその決定にしたがわないとなると、少数派も多数派も困ることになる。そこで論議や決定の前に根回しがなされる。そしてみんなのためということでがまんさせたり、不服はあっても反対はしないことを約束させたりする。あるいは深く突っ込んで議論せず、「まあまあ」でおさめようとする。まともに論議してけんかにでもなったら困るからである。
こうした原則でいとなまれるので、むらは「まあまあ社会」、「馴れ合い社会」、「根回し社会」であり、個々人の意見をみんなの力で抑える「足引っ張り社会」、「悪平等社会」であるとも言われた。
もちろん、むらの運営原則や共同のしかたはむらによって千差万別である。むらの成り立ちの経過、水田中心か畑中心か、山が近いか遠いかなどの地域性、宗教や階級支配の形態などでかなり異なる。
たとえば何百年かさらには何千年前かに1~2戸の少数の入植から始まってその分家や孫分家等でむらが成立した場合、これは山村や畑作地帯に多かったが、ここでは本分家関係による序列が強く、平等制はきわめて弱かった。
岩手県遠野市(北上山地南部、「遠野物語」で名高い」)の高清水牧野を見ればそれがよくわかる。ここでは明治末に利用(採草)の持ち分を配分したが、そのさいの基準は馬の所有頭数だった。当然馬を多く所有しているのは本家筋であり、彼らが多くの持ち分『株』を所有し、馬をもっていない分家などは権利を持たないことになる。したがってこの配分方法は本家群の強い意見で決められたのであろう。もしも分家が人並みに株をもとうとすれば、馬をもつしかない。しかしそんな資力はなく、本家から援助してもらうより他ない。この分家からの願いに対して本家は、分家が自分のところで10年間働くことを条件にして、馬一頭と牧野の株を譲ったという。こうして権利者が増えたが、すべての分家が権利を本家から譲り受けられたわけではない。本家の経済事情によって、また本家にどれだけ手伝いなどでつくしているか等の従属の程度によって左右されたようである。このように、ここの牧野はむらぐるみの共有ではなく、本家群と本家に認められた分家の共有であった。当然その運営では本家群の意見が強くなる。牧野ばかりでなくむらの運営においても本家と分家との間に大きな格差があったことだろう。つまり本家、なかでも総本家がむらのなかで大きな権限をもち、むらを実質的に支配していたのである。
青森県南部の田子村(後に町となる)などはその典型だったようである。かつて総本家がそこから分かれた本家、分家、孫分家を下におくピラミッドの頂点に立って支配し、村は何戸かのこうした総本家の連合によって支配されていたという。しかもその総本家の間での争いがあってむらが分裂していた。そしてこっちの総本家が何かいうとそっちの総本家は必ず反対するというように、何か決めようとしてもなかなかまとまらず、それで農業の発展もかなり立ち後れたらしい(1970年代になってむらの民主化が進み、ニンニクの産地形成等で全国的に有名になった)。
もちろんこうした本分家関係は山間畑作地帯にかぎらずどこにでも多かれ少なかれあった。そしてそれは本家と分家の間の経済的格差を基礎にしていた。すなわち、本家は自らの経営と生活の維持と家としての面子を保つために一定の土地と資産をもたなければならず、分家に独り立ちできるほどの土地や資産を分けてやることはできない。それで分家はいつも生活が苦しく、何かあると本家に援助をお願いすることになる。そのお願いを聞いてもらうためには本家の言うことをいつも聞いていなければならない。また援助の御礼に本家から言われれば何をおいても手伝いにいかなければならない。かくして経済的格差は経済的社会的支配従属関係となってくる。さらにそれは本家と分家の間での村落等の運営における発言権の差となり、本家が村落を支配するようになってくる。それに加えて、当時の生産・生活様式の維持には古い伝統やしきたりを大事に守ることが必要だったので、村落では古いものが大事にされ、そのために歴史の長い本家は格が高い家とされ、村落社会における地位は高く、その発言が重視されることになる。かくして社会的な地位、権限の格差が生まれ、本家の村落支配関係が成立するのである。
しかし、明治以前は分家を禁止している集落がかなりあったし、貨幣経済の未進展のもとでは農家間にそれほど大きな経済的格差がなかったので、このような本分家の支配関係がそれほど強くないところも多く、明治以降いろいろ変わってはくるけれども、やはりむらは平等運営を原則としていたと思われる。
一方、庄内平野のように何十戸かが一斉に入植・開拓して集落ができたところでは、むらびとはきわめて平等であった。もちろん時代が進んで経済的な格差が出てくるなかで、むらの寄り合いで座る順序がたとえば土地所有面積で決まるというように変化はしてくる。しかし、平等運営が基本であったという。
このように地域的なさまざまな差異はあるが、これまで述べてきたことはそうしたさまざまな事例から共通するものを抜き出したものであり、基本的にはむらは平等が原則だったということができる。そしてそれに基づき、むらはむらにかかわるさまざまなことを決めてきた。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日
シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日 -
 農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日
農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日 -
 スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日
スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日 -
 【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日
【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日 -
 新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日
新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日 -
 「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日
「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日 -
 鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日
鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日 -
 米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日
米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日 -
 (465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日
(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日 -
 VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日
VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日 -
 いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日
いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日 -
 「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日
「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日 -
 生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日
生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日 -
 「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日
「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日 -
 【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日
【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日 -
 福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日
福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日 -
 冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日
冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日 -
 宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日
宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日 -
 なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日
なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日