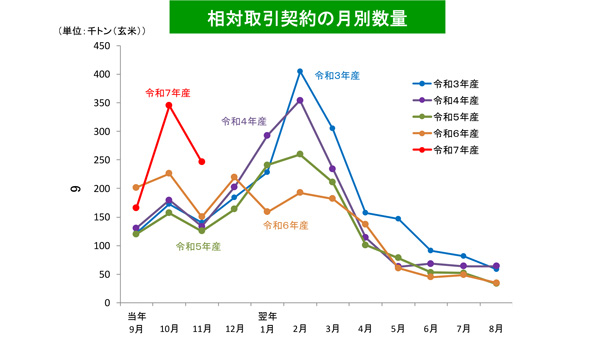【地域を診る】調査なくして政策なし 統計数字の落とし穴 京都橘大学教授 岡田知弘氏2024年11月21日
今地域に何が起きているのかを探るシリーズ。京都橘大学教授の岡田知弘氏が解説する。今回は農業振興に欠かせない「統計数字」を取り上げ、政府が推進する情報システムの「RESAS(リーサス)はどこまで信頼できるか」と題し問題提起する。
 京都橘大学教授 岡田知弘氏
京都橘大学教授 岡田知弘氏
石破茂首相が、初代地方創生担当大臣になったときに、強く打ち出した政策手法がデータの活用と「見える化」であった。これは、RESAS(リーサス)という情報システムとして、経済産業省と内閣府の歴代地方創生推進事務局が、各省庁のデータや民間企業が提供する統計情報をグラフ化するなどして、自治体が政策の立案や検証に使うよう促してきた。高校や大学で、このリーサスを使った情報分析をしてもらい、全国的なコンテストも行われている。
言ってみれば、その場限りの思いつきによる政策立案ではなく、証拠に基づく政策立案(エビデンス・ベースト・ポリシー・メイキング)を進めようというものであり、いかにも科学的で合理的なやり方のように見える。
私は、これまで2年に1回のペースで、特定の自治体の地域経済構造の調査、分析を行ってきたが、このリーサスの信頼性に疑問を感じ、ほとんど使わなくなっている。誤った、あるいは根拠の薄い推計データを使うと、人間の健康診断結果と同様に、誤診を招き、むしろ地域経済社会がかえって疲弊する可能性もあるからだ。
例えば、農村部を擁する自治体で最も重要な指標は、農業統計であろう。ところが、リーサスでの市町村別農業産出額は推計値である。かつては、農林水産省の統計情報事務所が正確な情報把握を行い、市町村別に信頼できる作目別データがとれていたが、国の行政改革のやり玉となり、大幅に人員削減されてしまった。都道府県も独自の把握をしようとしているが、平成の大合併もあり、県の出先機関は農業担当職員数が大幅に削減されており、市町村別ではなく市町村圏別の推計データしかないところもある。しかも、市町村合併と農協合併が進んだ結果、管轄範囲がズレてしまい、農業経営体の経営動向を自治体が把握することが極めて難しくなっている状況にある。このような中で、本統計を使って自治体が科学的な農業・農村政策を立案することは極めて困難であるといえる。
また、政府が有料で買い取っている民間提供データの場合、サンプルになっている経済主体に偏りがあり、必ずしも当該自治体の経済活動の全体像を正確に反映していない場合も見られる。
さらに、問題なのは、政府が第一期地方創生政策の売り物として、各市町村別の「地域経済循環率」という指標をもとにした政策づくりを奨励したことである。これは、各市町村内で生産された所得が、どの程度、当該市町村内に還流しているかを示す指標であるとされる。数式で書くと単純で、市町村内総生産を市町村民所得で割った数字である。例えば、2013年時点では、帯広市が87%で、東京23区が185%という数字となる。帯広市の場合、13%分が、他の地域から所得が移転してきて地域経済が成り立っているということになり、東京23区と比べ、自律度が低く、「地域経済循環率」が低いという判定となる。
しかし、ここで疑問がでてくる。この数字は、本当に「地域経済循環」の程度を示しているのだろうか。例えば、大都市近郊都市では、都心で稼いでくる通勤人口が受け取る雇用者所得が分母を大きくしている。これに対して、当該都市での雇用も取引関係もほとんどない大企業の本社の生産高が分子のほとんどを占めている自治体がある。実態的には「地域内経済循環」が存在しないのに、統計上、それがあるかのように錯覚してしまう可能性がある。この数字が示しているのは、推計データである市町村内総生産と市町村民所得の差額であり、互いに何の関係もなく、とても「循環」とはいえないものである。
地域の実態調査をすれば、どのような企業や農業経営体、農協が、どれだけ地域内で取引しているかがわかるのに、PC上で過去の推計データを積み重ねて簡単に計算しただけの「循環率」を元にしても、とても「証拠」に基づく政策形成にはならないし、政策の対象も明確にならないのである。むしろ、リーサスの加工統計をもって「わかったもの」とみなして、地域経済の実態の調査、分析をしなくなってしまう傾向があることこそ、問題であろう。いかにも「タイパ」重視の世情にあったやり方である。
さらに、あまり知られていないことだが、市町村民所得は、新たに生産された付加価値を示しており、再分配所得である年金は算入されていない。高齢化率が高まり、集落の構成員のほとんどが年金暮らしである農村部が増えている。農業生産も自家消費用が中心であり、販売していない元農家も少なくない。
この「年金経済」の実態を把握しなければ、現代における農村部の地域経済の成り立ちを知ることもできないし、その世帯や集落がもつ生活上の課題や健康の問題、あるいは地域の鳥獣害や防災上の不安などの質的な地域課題を知ることもできない。各自治体や農協で、そのような調査を自律的に行うようになれば、政策課題や地域における解決主体も見えてくる。まさに、「調査なくして政策なし」である。
重要な記事
最新の記事
-
 (466)なぜ多くのローカル・フードはローカリティ止まりなのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月19日
(466)なぜ多くのローカル・フードはローカリティ止まりなのか?【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月19日 -
 福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘」フェア 19日から開催 JA全農2025年12月19日
福岡県産ブランドキウイフルーツ「博多甘熟娘」フェア 19日から開催 JA全農2025年12月19日 -
 「農・食の魅力を伝える」JAインスタコンテスト グランプリは、JAなごやとJA帯広大正2025年12月19日
「農・食の魅力を伝える」JAインスタコンテスト グランプリは、JAなごやとJA帯広大正2025年12月19日 -
 国内最多収品種「北陸193号」の収量性をさらに高めた次世代イネ系統を開発 国際農研2025年12月19日
国内最多収品種「北陸193号」の収量性をさらに高めた次世代イネ系統を開発 国際農研2025年12月19日 -
 福岡市立城香中学校と恒例の「餅つき大会」開催 グリーンコープ生協ふくおか2025年12月19日
福岡市立城香中学校と恒例の「餅つき大会」開催 グリーンコープ生協ふくおか2025年12月19日 -
 被災地「輪島市・珠洲市」の子どもたちへクリスマスプレゼント グリーンコープ2025年12月19日
被災地「輪島市・珠洲市」の子どもたちへクリスマスプレゼント グリーンコープ2025年12月19日 -
 笛吹市の配送拠点を開放「いばしょパル食堂」でコミュニティづくり パルシステム山梨 長野2025年12月19日
笛吹市の配送拠点を開放「いばしょパル食堂」でコミュニティづくり パルシステム山梨 長野2025年12月19日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月19日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年12月19日 -
 子牛の寒冷ストレス事故対策 温風式保育器「子牛あったか」販売開始 日本仮設2025年12月19日
子牛の寒冷ストレス事故対策 温風式保育器「子牛あったか」販売開始 日本仮設2025年12月19日 -
 香港向け家きん由来製品 北海道からの輸出再開 農水省2025年12月19日
香港向け家きん由来製品 北海道からの輸出再開 農水省2025年12月19日 -
 群馬県千代田町・千代田町商工会と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月19日
群馬県千代田町・千代田町商工会と包括連携協定を締結 タイミー2025年12月19日 -
 岡山県吉備中央町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月19日
岡山県吉備中央町と農業連携協定 生産地と消費地の新たな連携創出へ 大阪府泉大津市2025年12月19日 -
 フィリピンで創出のJCMクレジット フェイガーと売買契約締結 ヤンマー2025年12月19日
フィリピンで創出のJCMクレジット フェイガーと売買契約締結 ヤンマー2025年12月19日 -
 AGRISTキュウリ収穫ロボット「第6回いばらきイノベーションアワード」で優秀賞2025年12月19日
AGRISTキュウリ収穫ロボット「第6回いばらきイノベーションアワード」で優秀賞2025年12月19日 -
 「いちごグランプリ2026」出品生産者を全国から募集中 食べチョク2025年12月19日
「いちごグランプリ2026」出品生産者を全国から募集中 食べチョク2025年12月19日 -
 冬限定「野菜生活100北海道産旬にんじんmix」新発売 カゴメ2025年12月19日
冬限定「野菜生活100北海道産旬にんじんmix」新発売 カゴメ2025年12月19日 -
 【畜酪政策価格最終調整】補給金上げ実質12円台か 19日に自民決着2025年12月18日
【畜酪政策価格最終調整】補給金上げ実質12円台か 19日に自民決着2025年12月18日 -
 【11月中酪販売乳量】1年2カ月ぶり前年度割れ、頭数減で北海道"減速"2025年12月18日
【11月中酪販売乳量】1年2カ月ぶり前年度割れ、頭数減で北海道"減速"2025年12月18日 -
 【消費者の目・花ちゃん】ミツバチとともに2025年12月18日
【消費者の目・花ちゃん】ミツバチとともに2025年12月18日 -
 一足早く2025年の花産業を振り返る【花づくりの現場から 宇田明】第75回2025年12月18日
一足早く2025年の花産業を振り返る【花づくりの現場から 宇田明】第75回2025年12月18日