地域社会に不可欠な共通財産2015年6月12日
伊藤澄一・日本共済協会専務理事に聞く
「共済」という言葉を聞くと本紙の読者の多くは「JA共済」を思い浮かべるのではないだろうか。しかし、日本にはJA共済以外にも、協同組合が運営する多くの共済が存在し、主な共済団体が加盟しているのが、(一社)日本共済協会だ。日本の共済事業は、全体で加入組合員7600万人、契約件数1億5000万件に達するという。そこで、日本の共済事業について、伊藤澄一日本共済協会専務理事に聞いた。
◆多様な協同組合が横軸で連携
日本共済協会は平成4年(1992年)に設立され、現在の会員は、13会員団体4賛助会員団体。会員団体の所管官庁は、JA共済連やJF共水連(漁協)は農林水産省、コープ共済連(生協組合員)、全国生協連(県民共済元受)、全労済(労働者組合員)など生協法関係は厚生労働省、中協法(中小企業等協同組合法)関係の中小企業者を対象にした日火連、全自共(自動車)などは経済産業省となっている。
所管官庁や根拠となる法律は異なるが共通していえることは、農業者や漁業者あるいは中小企業などモノづくりをする生産者やそこで働く労働者、そして地域でくらす生活者・消費者ごとの集団が、それぞれ相互扶助精神に基づいて協同組合をつくり、その「共済分野の多様な協同組合が横軸連携で集合した組織体」が日本共済協会だといえる。
日本の共済事業の組合員数は7600万人、共済契約件数は1億5000万件、保障共済金額1070兆円、受入共済掛金8兆円、支払共済金4兆6000億円という規模になっている。
◆「減災」や「防災」を共済が担う
これはただ単に数字が大きいということではなく、協同組合の共通理念が各共済制度に貫かれ、「協同組合の組合員の助け合いや結びつく小さな力がまとまることで揺るぎない力になる」という「積小為大」(せきしょういだい)という言葉の通りだと伊藤専務は考えている。
その具体的な表れが東日本大震災の時に会員団体合計で1兆2430億円の共済金・見舞金等が支払われたこと、さらに、阪神淡路大震災や東日本大震災を契機に、「地域ごと、生活者のまとまりごとの『減災・防災』をテーマとする互助・共助などの後押しをする新たな動きが、各共済団体にでてきている」ことを指摘する。
伊藤専務は「社会システムとして見ても、保障の質・量として見ても、共済制度は協同組合をベースとした地域社会の共通財産だといえる。それぞれの職域・地域に生活者がいて、その構成員がモノづくりや生活の基盤をもち、その協同組合の組合員として共通性をもち、互いに助け合っている。それが協同組合の共済だ。不特定多数の誰もが保険料を払えば保障される『保険』との役割の違いがある」と強調する。
◆米国保険会社には邪魔な存在
これは日本の保険共済市場をターゲットする米国の保険会社にとっては目の上のたんこぶ的な存在だともいえる。だから、米国企業の利益のために代弁して活動するACCJ(在日米国商工会議所)はかねてから日本政府に対して「保険商品を提供する協同組合と、金融庁規制下にあり免許を付与されている保険会社との間に規制面で平等な環境を確立するよう要請する」と主張してきた。 「日本政府は共済を外資系保険会社と同等の規制下に置くべきである。…保険会社と共済が日本の法制下で平等な扱いを受けるようになるまで共済による新商品や既存商品の改定といった保険事業拡大を一切禁止すべきである」と提言してきた。同様な主旨は「農協改革」についての意見書でも述べられ、さらに農協は「本来の使命である農業の強化に貢献できるよう、改革を進めるべきである」と述べ、規制改革会議農業WGの意見書を支持し「日本政府及び規制改革会議と緊密に連携し、成功に向けてプロセス全体を通じて支援を行う準備を整えている」と結論している。
◆「農協改革」の動向今後を左右
したがって、「農協改革」の論議は、農協=JA共済だけの問題ではなく、いずれは順番に他の協同組合への攻勢となり、協同組合共済に波及してくる重大な問題だとの理解が、日本共済協会の会員団体にも広がっている。
さらに「地方創生には農村での准組合員やその地域の生活者の参加が必須だといえる。地域こそ、何かを共通項として相互に心配し合い、助け合うことが必要であり、多様な協同組合がそれを担ってきているし、これからも担っていくべき」だと伊藤専務は、JA全中常務の経験をも踏まえて語る。
だから、10月の第27回JA全国大会とそれへ向けた議論のなかでJA綱領や協同組合原則などの確認、さらには3.11の被災地の復興努力に学びたい。全国の7000余のJA支店ごとに、「おらとこの強みは何か」を探し、特産物や歴史的な遺産や先駆者の教えなど、地域を代表するモノや精神、人と人のつながりなど、「農業を基軸とした地域の協同組合」としての農協の在り方を確立して欲しいと願っている。その先に、多様な協同組合間の協同、自治体・学校・消防・警察・病院等との平時・有事の連携が見えてくる。日本社会においては、多様なリスクから「命を守る」ことが、どこかで「地方創生」の喫緊さとも重なり合っている。
今後のJAのあり方論議は、世界でもっとも成功したと評価されている相互扶助精神に貫かれた日本の協同組合、協同組合共済の今後の道を示すモデルづくりだと伊藤専務は語る。
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
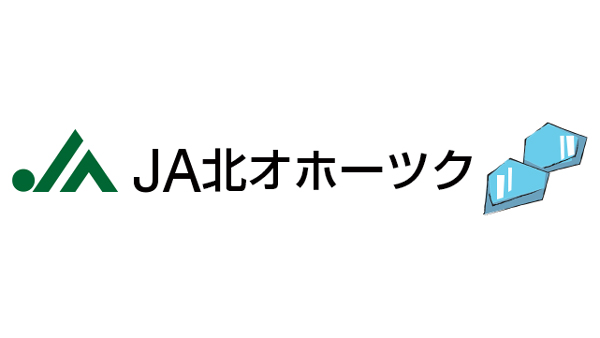 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































