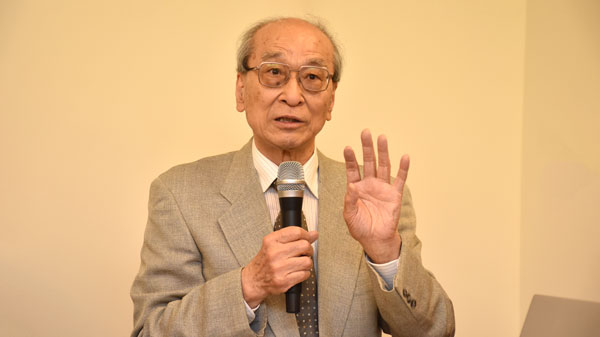米:持続可能な水田農業の確立を
地域農業と担い手の発展へ 水田フル活用の推進を2016年1月13日
「売れるものを作る経営感覚が大事」
28年産に向け飼料用米等の一層の取り組みを
(株)ヤマヨ組代表取締役社長小竹行哉氏(三重県稲作経営者会議副会長、2008年度JA全青協副会長)
需要に応じた水田活用作物の生産を推進することによって主食用米の需給改善を図ろうと、JAグループは飼料用米の生産拡大を軸にその取り組みを全国で進め、27年産では全国全体で過剰作付けを解消するなど、需給改善に向けた一定の成果を得た。28年産米の取り組みでも地域の水田をフル活用し飼料用米など需要に応じた生産をさらに推進することによって地域農業と農業者の経営安定を図っていく必要がある。そこで28年産の取り組みを進めるために、地域の水田農業の担い手に水田フル活用のこれまでの取り組みや、今後の展望などを聞いた。
◆土地条件を ふまえ選択
 三重県多気郡明和町で水田農業を展開する(株)ヤマヨ組。代表取締役の小竹行哉さんは、現在、県稲作経営者会議の副会長で、2008年度にはJA全青協副会長も務めた。平成23年に父親との家族経営を法人化した。
三重県多気郡明和町で水田農業を展開する(株)ヤマヨ組。代表取締役の小竹行哉さんは、現在、県稲作経営者会議の副会長で、2008年度にはJA全青協副会長も務めた。平成23年に父親との家族経営を法人化した。
27年産の水田作付けは水稲68ha、麦と大豆27haの合計95ha。そのほかに大豆の作業受託を5ha請け負った。
明和町は伊勢湾に近く低湿地帯が多い。
「麦、大豆が作りにくい地帯で転作作物には苦労していました。しかし、飼料用米など米での転作も認められたことで取り組みやすく、きちんと経営の計画も立てられるようになりました」と小竹さんは話す。
麦・大豆は作付けに適した水田が限られているため、ここ最近は27ha分はほぼ固定し連作している。
一方で規模拡大しながらの主食用米の生産調整には、飼料用米、米粉用米など非主食用米への取り組みで対応してきた。
27年産では水稲作付け面積68haのうち、飼料用米4.5ha、米粉用米4ha、加工用米2.3haで残り57haほどを主食用米とした。 小竹さんが自分の経営で非主食用米に取り組んだのは10aあたり8万円水準の助成が施策として実施された平成20年度から。三重県内で初めて米粉用生産に取り組んだ生産者だという。
小竹さんが自分の経営で非主食用米に取り組んだのは10aあたり8万円水準の助成が施策として実施された平成20年度から。三重県内で初めて米粉用生産に取り組んだ生産者だという。
「当時はまだ親世代の農家も多く、がんばって米作りをやっていて、やはり主食用以外の米づくりには抵抗があるという感じでした。しかし、高齢化が進むにつれて水田を担い手に任せるようになると、担い手として経営を維持していくには非主食用米の生産に取り組むことが大切になってきたということだと思います」。
周囲の大規模担い手農家の間でも飼料用米を政策的に支援することは生産調整のひとつの手段として評価が高く「今は主食用米を自由に作っていくという農家は少ないのではないか。生き残っていくためには、むしろ水田のフル活用が必要だという意識は浸透している」という。
◆100ha経営で 地域を担う
 小竹さんが就農したのは平成2年。20歳のとき。父親と2人で10haの経営だった。平成23年に法人化したが、そのときの経営規模はまだ47ha。最近では高齢化の進行で毎年、10ha~15haほどのペースで委託される水田が増えているといい、28年産では利用権設定面積は100haを超えるという。
小竹さんが就農したのは平成2年。20歳のとき。父親と2人で10haの経営だった。平成23年に法人化したが、そのときの経営規模はまだ47ha。最近では高齢化の進行で毎年、10ha~15haほどのペースで委託される水田が増えているといい、28年産では利用権設定面積は100haを超えるという。
地権者に地代をしっかり支払って経営を維持・発展させていくには水田活用の直接支払交付金を有効に活用していくことが重要になる。飼料用米では標準単収で10aあたり8万円を確保し、さらに畜産農家との連携で耕畜連携助成の交付も得るなどの取り組みも行い、作物の販売価格とあわせて「10aあたり10万円の売上げになることが経営目標です。28年産では100haを超す見込みですから売上げ1億円が目標になります」という。
それを実現するにはJAや連合会との連携が不可欠となる。
JA三重中央会のまとめによると三重県の飼料用米の作付け面積は26年産で691haだったが27年産では1405haと2倍以上に増えた。ただ、小竹さんの飼料用米作付けは26年産が8haで27年産は4.5haだった。その分、26年産では作付けをしなかった米粉用米を4ha作付けし、そのほかにも加工用米を生産した。
こうした飼料用米等の作付け計画は、全農県本部と県下JAで調整している。飼料用米については全農県本部取扱いは加工用米と一体的に推進するのが基本方針。地域内流通は畜産農家と飼料用米生産農家のマッチングを進めることを重視している。
こうした方針のもと地域全体の非主食用米の生産を調整する役割を担いながらJAとの話し合いで作付け計画を決めてきた。そのため飼料用米の専用品種での作付けは行わず、27年産では飼料用米には「みえのゆめ」、「コシヒカリ」から出荷した。飼料用米の収量は約8俵で地域の標準単収は確保したという。
米など生産物はすべてJAの施設に出荷するほか、一部は乾燥施設を持つ地域内の他の大型農業法人に委託するなど、「地域内で協業」を実践している。毎年の作付け、出荷等の計画づくりなどはJAと協議しており「JAは自分の経営にとってのコンシェルジュ」だという。
◆安定した 生産の確保
 JA多気郡は平野部と中山間部を管内としている。中山間部には松阪牛の肥育農家もいる。小竹さんは以前から肥育農家とたい肥と稲わらの交換を行ってきた。自ら生産した飼料用米が供給されるまでには至っていないが「稲わらを使ってもらい、自分はたい肥を撒いていると米を作っているだけではなく松阪牛生産も手助けしている、という気持ちになる」と話す。
JA多気郡は平野部と中山間部を管内としている。中山間部には松阪牛の肥育農家もいる。小竹さんは以前から肥育農家とたい肥と稲わらの交換を行ってきた。自ら生産した飼料用米が供給されるまでには至っていないが「稲わらを使ってもらい、自分はたい肥を撒いていると米を作っているだけではなく松阪牛生産も手助けしている、という気持ちになる」と話す。
その観点から、子牛不足と飼料価格高騰など肥育農家の厳しい状況について「しっかりした畜産生産基盤を支える政策が必要で、それがないとわれわれが生産した飼料用米も行き場を失う」と強調する。
経営を安定させるため、規模拡大と同時に栽培技術も重視してきた。同社の従業員は現在、通年雇用で8人。20~30歳代で6人と過半を占めるため、若い従業員にしっかり栽培技術を身につけてもらうことが重要と考えている。低コスト化も重要なテーマで、たとえば直播栽培への取り組みを課題とする地域も多いが、この地域はジャンボタニシの発生が多いなど、基本的な栽培管理の徹底が重要だという。ほ場は地元集落とその周辺にあり、車で10分以内の地区にほぼまとまってはいるが、それでも500筆近くある。栽培期間中に目をどう行き届かせるかが課題で、小竹さんは「収量減のリスクを避けることが大事。それを考えるとしっかり人を育てて栽培管理し、収量を確実に確保することを重視したい」と話す。
飼料用米の交付金は数量払いとなっていることなどをふまえ、しっかりと収量を確保する政策のメリットを経営に取り込んで対応していきたい考えだ。
今後の水田農業の方向について、小竹さんは「主食用米は残念ながら毎年8万tずつ需要が減少するのが現実。作りすぎれば米価が大きく下落する。売れるものを作っていくという経営感覚を大事にして主食用米と飼料用米などの戦略作物を組み合わせていきたい」と話している。
(写真)三重県明和町の水田地帯。山間部では松阪牛の肥育も盛んだ、(株)ヤマヨ組代表取締役社長 小竹 行哉 氏、地域内の農地集積状況をまとめた地図。ほ場は500筆近くある
重要な記事
最新の記事
-
 米 推計19万tが分散して在庫 農水省調査2025年3月31日
米 推計19万tが分散して在庫 農水省調査2025年3月31日 -
 【人事異動】農水省(4月1日付)2025年3月31日
【人事異動】農水省(4月1日付)2025年3月31日 -
 【注意報】さとうきびにメイチュウ類西表島、小浜島で多発のおそれ 沖縄県2025年3月31日
【注意報】さとうきびにメイチュウ類西表島、小浜島で多発のおそれ 沖縄県2025年3月31日 -
 【注意報】かんきつ、びわ、落葉果樹に果樹カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 静岡県2025年3月31日
【注意報】かんきつ、びわ、落葉果樹に果樹カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 静岡県2025年3月31日 -
 農業は恰好いいと示したい トラクターデモに立った農家の声 「令和の百姓一揆」2025年3月31日
農業は恰好いいと示したい トラクターデモに立った農家の声 「令和の百姓一揆」2025年3月31日 -
 4月の野菜生育状況と価格見通し 果菜類、ほうれんそう、レタスなどは平年並みへ 農水省2025年3月31日
4月の野菜生育状況と価格見通し 果菜類、ほうれんそう、レタスなどは平年並みへ 農水省2025年3月31日 -
 農林中金 総額6428億円の増資を実施2025年3月31日
農林中金 総額6428億円の増資を実施2025年3月31日 -
 25年産米「概算金のベース」 あきたこまち60キロ2万4000円 全農あきたが情報共有2025年3月31日
25年産米「概算金のベース」 あきたこまち60キロ2万4000円 全農あきたが情報共有2025年3月31日 -
 「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスなど公表 農水省2025年3月31日
「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスなど公表 農水省2025年3月31日 -
 北アルプスの水と大地が育む米「風さやか」使用 ツルツル食感の米粉麺はスープも含めグルテンフリー JA大北2025年3月31日
北アルプスの水と大地が育む米「風さやか」使用 ツルツル食感の米粉麺はスープも含めグルテンフリー JA大北2025年3月31日 -
 特産の小松菜をバームクーヘンに 試食した市長も太鼓判 JAちば東葛2025年3月31日
特産の小松菜をバームクーヘンに 試食した市長も太鼓判 JAちば東葛2025年3月31日 -
 三鷹キウイワイン 市内のキウイ使った特産品 JA東京むさし2025年3月31日
三鷹キウイワイン 市内のキウイ使った特産品 JA東京むさし2025年3月31日 -
 地域の営農継続へ JA全国相続相談・資産支援協議会を設置 JA全中2025年3月31日
地域の営農継続へ JA全国相続相談・資産支援協議会を設置 JA全中2025年3月31日 -
 中央支所担い手・若手農業者研修会を開く JA鶴岡2025年3月31日
中央支所担い手・若手農業者研修会を開く JA鶴岡2025年3月31日 -
 全国の農家へ感謝と応援 CM「Voice」フルバージョン配信開始 JA全農2025年3月31日
全国の農家へ感謝と応援 CM「Voice」フルバージョン配信開始 JA全農2025年3月31日 -
 セメント工場排ガスから分離・回収した二酸化炭素の施設園芸用途 利用へ取組開始 JA全農2025年3月31日
セメント工場排ガスから分離・回収した二酸化炭素の施設園芸用途 利用へ取組開始 JA全農2025年3月31日 -
 カナダで開催の世界男子カーリング選手権 日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年3月31日
カナダで開催の世界男子カーリング選手権 日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年3月31日 -
 JA鶴岡「もんとあ~る」dポイント加盟店に 4月1日からサービス開始2025年3月31日
JA鶴岡「もんとあ~る」dポイント加盟店に 4月1日からサービス開始2025年3月31日 -
 JA全中「健康経営優良法人2025」に認定2025年3月31日
JA全中「健康経営優良法人2025」に認定2025年3月31日 -
 「佐賀牛 生誕40周年記念キャンペーン」開催中 数量限定40%OFF JAタウン2025年3月31日
「佐賀牛 生誕40周年記念キャンペーン」開催中 数量限定40%OFF JAタウン2025年3月31日