【クローズアップ】前田前Jミルク専務に聞く 酪農乳業の過去・現在・未来(下)〈存在意義〉を内外に示す 栄養に加え社会・歴史の役割 農政ジャーナリスト・伊本克宜2021年12月13日
前田浩史・前Jミルク専務に、業界の過去・現在・未来でインタビューした。<下>では、脱炭素対応をはじめ、今後の国内酪農乳業発展への課題と展望を聞いた。強調したのは酪農乳業の〈存在意義〉の可視化と価値化だ。
 前・Jミルク専務
前・Jミルク専務
前田浩史 氏
■脱炭素へJミルク国際参加
――Jミルクは10月末、国際酪農組織が進める脱炭素への「酪農乳業ネットゼロ」活動に参加すると発表しました。国内の生産者団体・企業が一致して表明したのは初めてです。気候変動対応、国連食料システムサミットを踏まえた対応ですが、実践には課題が多いのが実態です。
今後のキーワードは「持続可能性」だ。国内外の関係者・団体と親和性を持ち、環境調和型の酪農乳業が問われる。
Jミルクは、国際酪農組織GDPが中心となって進める脱炭素の取り組み「酪農乳業ネットゼロへの道筋」に参加する。
酪農乳業セクター全体で、気候変動に対応するもので、具体的な基本方針は六つある。このうち、自然の生態系を保護する生産方法の強化、牛の飼料やふん尿管理などの慣行改善、温室効果ガス(GHG)排出量測定し緩和策を計画し進捗(しんちょく)監視の三つは特に重要だ。
国内酪農は、輸入飼料依存の「加工型畜産」の生産体系が多く資源循環型への転換には土地利用の制限など課題は山積している。今後は放牧型など草地酪農推進をはじめ「環境調和型酪農」確立が問われる。
「酪農ネットゼロ」の取り組みには、乳牛由来のメタン削減をどうするかとセットで議論する必要がある。乳牛の遺伝的改良、飼料設計での改善、放牧への転換など生産現場の対応はこれからだが、先進技術は徐々に形になってきた。
温帯モンスーン地帯の日本固有の問題もある。水田との連携で、自給飼料を確保する水田酪農の構築、地域循環型の低炭素酪農への技術革新などはこれからの課題を着実にクリアしていく必要があるだろう。
■役割大きい「乳の学術連合」
――研究者などが加わり提言するJミルクの「乳の学術連合」は、他業界にはない先進的な取り組みですね。
先の「戦略ビジョン」で強調した三本柱の一つ、社会性は今後、特に重要となる。
栄養の高い食品を提供する業界だが、共通価値の開発と共有化はさまざまな意見、知恵を統合して説得力あるものにしなければならない。そのためにJミルクが立ち上げたのが「学術連合」だ。業界だけでなく、消費者や医師、教師らに対して、なるほどと納得でき説得力のある価値や情報を集めて発信していく。
また、情報発信に関連しては、記憶に残るコンテンツづくりに力を入れ、着実に形となってきた。これまでの一般消費者向けから一歩踏み出し、牛乳・乳製品のファンや購買行動に影響力のある主婦を核とした層に、健康や栄養などを切り口に価値ある情報を提供してきた。この結果、JミルクのSNSやウェブサイト閲覧は1000万にのぼり、他業界にない成果を上げている。
酪農・乳業界の持続的な発展のためには、業界のパーパス、存在意義の再確認と、その可視化と価値化を底上げする努力が欠かせない。戦略部門を担うのが「乳の学術連合」だ。
■流通への正確な情報提供
――環境負荷で家畜の問題点も指摘されています。その絡みで植物性由来の代用肉、代用乳なども次々製品化されてきました。酪農・乳業界にも今後、大きな影響を及ぼしかねません。
脱炭素、環境重視の中で家畜のメタンガス、げっぷの問題が関心を高めている。業界はメタン削減に具体的な数字を示し削減行動を行う。
フードテックで代用食品が次々誕生するのは当然だ。今後の課題として、小売り、流通業界に対して、健康、栄養、価値を中心に正確な牛乳・乳製品の情報を伝えることがますます必要となる。可視化と価値化の並進だ。誰もが納得する科学的な根拠、エビデンスに基づいた牛乳・乳製品の情報を積極的に提供していくためにも、Jミルクの役割は今後ますます需要となる。
■酪農乳業150年 歴史に学び難局突破
――歴史との関連も大事です。Jミルクは、政府の事業の一環で2018年の明治維新150年に絡め酪農・乳業産業史の深掘りを進めました。収集した膨大な史料を、今後の酪農・乳業界の発展にどう生かしますか。
貴重な文献、書籍、地方乳業も含め社史など史料は1000点に達する。取り巻く情勢が大きく変わる中で「次の100年」を展望したい。過去を知ることは、現在、そして未来を知ることだ。読み解き、業界の共有財産としてデータベース化を進め、今後の持続可能な酪農・乳業の確立に役立てたい。
――酪農・乳業史は日本近代化150年と重なります。どう見ますか。
産業としては、半世紀前の加工原料乳不足払い制度を通じた北海道での生産振興が大きい。歴史的には生乳需給の波があり、不需要期の「余乳」をどう処理していくかの歴史でもあった。今は北海道がその機能を担う。今後は北海道と都府県酪農の均衡発展が課題だ。いずれにしても、商品特性から生産から処理、販売まで一貫した仕組みがますます問われる。
――今、大きな岐路に立っています。歴史から何を学び、今後にどう役立てますか。
大切なのは「戦略ビジョン」で明示した成長性、強靱性、社会性の三つ。国際化という新局面の中で、技術革新で品質、環境を最重視した戦略が欠かせない。自給飼料確保は大きな課題だ。水田を生かし、地域内での飼料確保に知恵を絞りたい。環境に配慮した持続可能な国連開発目標(SDGs)への具体的な対応も急ぐ。今こそ、その時々の課題と向き合い「柔軟性」「適応力」を発揮し難局を突破した歴史に学びたい。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日
シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日 -
 農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日
農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日 -
 【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日
【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日 -
 イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日
イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日 -
 農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日
農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日 -
 (429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日
(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日 -
 米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日
米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日 -
 「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日
「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日 -
 JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日
JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日 -
 素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日
素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日 -
 JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日
JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日 -
 真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日
真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日 -
 3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日
3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日 -
 自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日
自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日 -
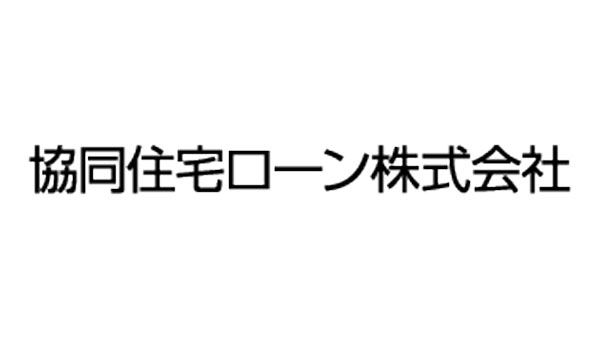 【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日
【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日 -
 大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日
大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日 -
 【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日
【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日 -
 鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日
鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日 -
 全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日
全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日

































































