【クローズアップ・25年度生乳需給】再び前年度割れ 6月にもバター追加輸入判断か2025年2月3日
Jミルクは、2025年度生乳需給で約729万トン、前年度対比で99・2%の減産見通しを示した。離農が加速する都府県は「300万トン割れ」が目前の緊急事態となっている。用途別ではバター需要が強い半面、脱脂粉乳の過剰在庫が引き続き課題だ。農水省は輸入枠据え置きとしたが、6月にもバター追加輸入を判断するとの見方が出ている。(農政ジャーナリスト・伊本克宜)

牛乳消費は、値上げが一巡し前年並みで推移しているが、価格の「両極化」も進む
■24年度は3年ぶり増産
Jミルクが示した24年度生乳生産は、3年ぶりに増産となった。全国生乳生産の約6割を占める北海道が増産計画に転じたことが大きい。
◇2024年度生乳生産動向
・全国 7350(100・4)
・北海道4243(101・6)
・都府県3108( 98・7)
◇2025年度生乳生産見通し
・全国 7288(99・2%)
・北海道4234(99・8)
・都府県3054(98・3)
※単位千トン、カッコ内は前年度実績対比、24年度生産のうち25年1~3月は見通し
24年度は、北海道が前年の猛暑で牛の分娩時期が後ズレしたものの、8月以降は前年水準を上回って推移している。一方、都府県は7月以降、前年水準を下回っているが、年末から年度末に向けて減少幅が縮小してきた。このため、全国の生乳生産量は3年ぶりに前年度を超す見通し。
ただ、ここで注視するのは、月齢別乳用雌牛頭数の動き。特に生産の主力となる2~4歳(24~59カ月齢)。北海道は9月に35万頭近くをピークに、年度末に向かって縮小してきた。25年3月には34万3000頭にとどまると見込まれる。
■25年度減産は搾乳牛減響く
25年度生乳生産はどうなるのか。Jミルクは需給見通し算定に当たり、全体需給を大きく左右する夏場の気温を、前年度に引き続き「猛暑」で試算した。
ただ、このところの「猛暑」から一転し「冷夏」などになれば、生乳需給は逆に増産と消費低迷で乳製品過剰が一挙に深刻化する。気象学者のなかには猛暑の一方で冷夏の備えを警告する声もある。
25年度生乳生産見通しは、全国で728万8000トン(前年対比99・2%)と730万トン割れとなる。北海道が423万4000トン(同99・8%)、都府県が305万4000トン(同98・3%)。大きく生産に関係するのが雌牛の動きだ。北海道の2~4歳の雌牛は、24年度後半から減少を続け、その傾向が25年度に入ってさらに加速する。25年度末には33万4000頭にまで落ち込む。24年度に比べ9000頭も少ない。
理由を内橋政敏Jミルク専務は、脱粉在庫削減へ北海道で22、23年度に減産計画に踏み切り、酪農家が所得確保のため「乳牛への受精卵移植で和牛生産を増やしたことが大きい」と強調する。
今後、生乳生産の主力となる北海道の2歳未満雌牛は夏以降、徐々に増える。25年度末には34万8000頭と、24年度末に比べ2000頭増とわずかに上回る。乳量を減少していく5歳以上(60カ月齢以上)の雌牛は、北海道で25年度末に14万5000頭とここ数年で最も多い。生産コストを下げ効率経営を進めるため、国も支援する「長命連産」で搾乳を長く続ける傾向が強まっていることを裏付ける。
■都府県「300万トン割れ」目前
都府県に注目すると、25年度は305万4000トン(前年度対比98・3%)と、4年連続の減産となる見込み。
都府県の24年度は310万8000トンで、1年間で5万トン以上減る計算だ。「酪農家1万戸割れ」が大きな話題となったが、特に都府県で離農率が高止まりしている。個数減少と歩調を合わせる形で「都府県300万トン割れ」が迫っていると見た方がいい。
25年度の北海道から都府県への移入必要量(道外移出量)は59万2000トン(前年度対比111・2%)と1割以上の増加が必要となる。
■輸入枠13・7万トンは「仮置き」か
今後の生乳需給で焦点となるのがバター対応だ。生乳需給緩和の中で、農水省は24年度に4年ぶりのバターの緊急追加輸入に踏み切った。
国家貿易品目の乳製品は国際約束の低関税輸入枠「カレントアクセス」(CA)分の生乳換算13万7000トン。25年度は同数を設定したが「仮置き」との見方が強い。これを超えた追加輸入の有無の判断は通常1、5、9月に、直近の需給動向を踏まえ決定する。
24年度は4000トン(生乳換算5万トン)と大量のバター追加輸入枠を新たに設定した。しかも、決定時期は通常国会閉会直後の異例の6月26日。野党からは、改正基本法審議を優先するため国会での問題追及を避けたい政治的判断があったのではないかと疑念の声も出ていた。
1月31日の会見で農水省の須永新平牛乳乳製品課長は「24年度はぎりぎりまで需給動向を精査した結果、バター最需要期の12月に輸入到着船便が間に合うように6月末とした」とする一方、「今後の輸入枠について慎重に検討していく。1、5、9月にこだわらず柔軟に対応していきたい」とした。
こうした中で、前年度と同様に6月末にもバター追加輸入を判断する可能性が高い。今年は通常国会の会期末が6月22日。東京都議選、参院選挙など6、7月は国政を左右する政治日程が立て込んでいる。
■ヨーグルト好調とバター不足
25年度の用途別販売は、飲用牛乳等向け389万トン(前年度対比100・3%)と下げ止まった。
飲用乳価の連続引き上げ、大手乳業のNB牛乳を中心に牛乳小売価格値上げで消費低迷したが、24年8月以降、価格改定から一巡してほぼ前年水準で推移している。生鮮品、食品が全般的に値上がり、牛乳の割高感が薄れたことも大きい。
生乳需給にとって好材料は、機能性などが評価を高めているヨーグルト需要の高まり。特にドリンクタイプは好調で、健康志向を受けプレーンヨーグルトの大容量タイプも底堅い。発酵乳の需要増加につながっている。脱粉需要にも結び付く。
しかし、脱粉在庫は重いまま。単年度需給ギャップは1万6800トン、25年度末在庫量は7万1200トン、6・6カ月分に達する。
脱粉過剰の半面でバター需要は強い、「脱・バ需給不均衡」の構図は続く。国産バターは単年度の需要量が供給量を上回る状況だ。そこでたんぱく質など無脂乳固形分(SNF)を使用した製品の需要創出・拡大も重要となっている。次期酪肉近で5年後生乳生産目標(2030年度)は現行780万トンの「現状維持」とする方向だ。
重要な記事
最新の記事
-
 「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日
「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -
 政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日
政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -
 備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日
備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -
 米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日
米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -
 瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日
瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -
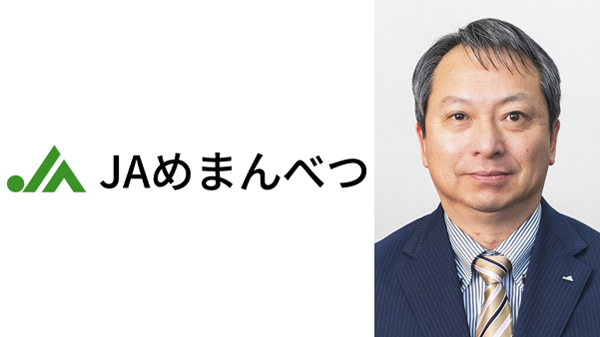 【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日
【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -
 初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日
初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -
 秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日
秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -
 日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日
日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -
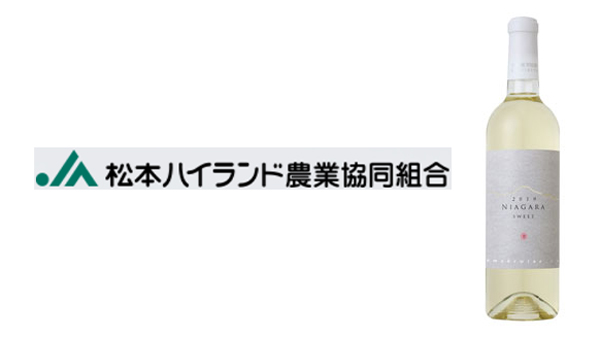 地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日
地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -
 温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日
温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -
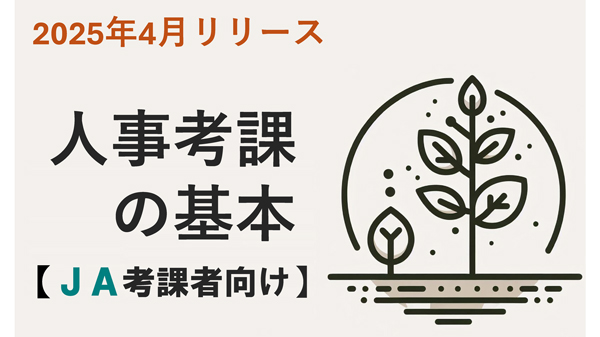 JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日
JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -
 【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日
【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -
 【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日
【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -
 ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日
ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -
 世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日
世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日 -
 【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日
【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日 -
 日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日
日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日 -
 X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日
X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日 -
 新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日
新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日
































































