本紙に『読書』面を新設 書評委員 座談会2013年2月22日
本紙は『読書』とのコーナータイトルで新たに書評や新刊書籍などの情報を伝える面を月に1回掲載する。これまでも書籍等の紹介は随時紙面で行ってきたが、今後は委員長を梶井功東京農工大学名誉教授に依頼した書評委員会を設け、JAグループ関係者に役立つ農業、経済全般の動き、さらには世界の動向などの情報を書籍紹介を通じてどう提供すべきかを検討しながら紙面づくりをしていくことにした。今回は新たな紙面づくりにあたって書評の方針などをテーマに議論をしてもらった。
3月10日号からスタート
ホームページ「JAcom」でも積極的に発信
梶井 『読書』と題して書物に関する紙面をこの『農業協同組合新聞』に新たにつくっていこうということです。今日は今の時代、農業、農村、JAにとってどんな書物が待望されているのかも含め、この紙面のいわば編集方針といったものをみなさんで話し合いたいと思います。
私としては今の農業や農政の動きをビビッドに捉えている本を取り上げ、読者のみなさんに読んでみたいな、という気を起こさせるような書評になればいいと思いますが、皮切りに最近注目される動きをあげると、たとえば、2010年農業センサス結果を分析した成果が出版されるようになってきました。
実は今回のセンサス結果には問題となる数字がある。それは05年センサスから調査対象の考え方が変わり、とくに集落営農組織でも経理一元化などを行っていれば経営体としてカウントするようなったことです。しかし、これを経営体にすると組織を構成している農家は全部、非農家になってしまう。したがって集落営農が非常に盛んなところは、農家数は大きく減少しその代わりに経営体が増えるということになり、数字としては大変な構造変動が起きていることになる。しかし、果たして本当に現場ではそうなのか。この点に着目して分析した研究書も出版されています。たとえば、こんな書籍もこの書評委員会なりの問題意識で紹介し、ぜひとも各地で実践しているJAの役職員で議論を深めてもらえるような情報提供ができれば、と思いますね。
◆農協、協同組合論―実践に役立つ書物を期待
A 農協論、あるいは協同組合論を積極的に取り上げていきたいと思います。
梶井 私が問題だと思うのは2001年の農協法改正で、それまで明記されていた協同組合についての組合員への教育および営農指導という事項をなくして、営農指導だけを第10条の1号事業に格上げをしたことです。組合員の協同組織であるということの意味を組合員に絶えず教育しなければならないということが書かれていたにも関わらず、それを追放してしまい、営農指導は協同活動との関連のなかで位置づけられていたのに、それを営農指導だけを抜き出し農協を指導機関にしてしまった。
B そこは農協論にとって重要な点ですね。営農指導事業論のなかには基本的には組織強化や営農改善、生活改善、教育情報の強化などの内容があります。
だから、たとえば青年農業者とこれからどう地域農業をつくっていくかの議論をすると、JAは金融事業ばかりやっているという批判が出てくるわけですが、そこで大事になるのは農協の金融事業の成り立ちを説明することです。そういったところから組合員教育が始まっていく。
梶井 まさに組合員教育と営農指導がくっついていなければならないわけですね。
C その意味でもこの紙面で着目したいのは、たとえば営農指導事業とは本来何か、というようなテーマです。実際、今指摘されたように農協法改正で営農指導事業はトップに出てきますが極論すればそれはお題目だけで、基本的に農協の事業のなかではいちばん最後の事業になってしまっている。本来、行き詰まってしまった農協をどう建て直すかといった場合は、それは農協の元をつくるという点ですから営農指導事業論が大事になってくる。それは協同組織の育成ということになるという議論が必要なんだと思います。
JAグループの課題をどう捉えるか
A JAに関しては支店活動の強化というテーマも考えていかなくてはならないと思います。これは農協合併は失敗だったのかどうかということなのか、合併問題も総括する必要があるでしょう。
B 「支店を中心に」という今回の課題をどう理解していくか。つまり、支店とはJAが事業を展開していくにあたって求めている拠点なのか、それとも地域の組合員を集める拠点としてニーズを吸い上げるという意味で支店の強化か。
実際は都市部と農村部、中山間部ではまったくニーズが違う。つまり、金太郎飴のような支店の強化策はないということです。自分たちのオリジナリティをつくってわがJAの支店の強化策はこうするというもの打ち出すことだと思いますね。
◆視野を広げ知識を深める
D TPP(環太平洋連携協定)やアベノミクスも含め経済問題関する書籍についても重要です。
梶井 TPPについては多数の本が出ていますが、私はこれまであまり触れられていない問題をこの際指摘したいと思います。
それは、今のWTO(世界貿易機関)交渉それ自体が行き詰まり状態になっていますが、それを招いたのがまさにアメリカの政策だということです。
しかし、考えてみれば行き詰まった今のWTO交渉は、ドーハ開発ラウンドと名付けれてスタートしている。わざわざ“開発”と入れたのには意味があって、ウルグアイ・ラウンド合意は途上国にほんんどプラスにならない、経済が好転したのは先進国だけだという途上国の抵抗があったからです。しかし、その途上国の開発に資するような合意案を示すとアメリカがそれをつぶしにかかってきたから交渉は暗礁に乗り上げたのであって、この問題とTPPとの関連を見る必要があります。
D 世界の経済の動きや東アジアの動きなど、JAの役職員にはぜひ読んでほしいという本があれば取り上げていきたい。
◆地方の出版物にも注目したい
C 生活改善や消費生活というテーマも重要だと思いますし、福島の原発問題も終わってはいない、忘れないという意味でも注目していかなければいけないテーマだと思います。
梶井 地方ということでいえば、地方出版物もぜひ取り上げたいと思いますね。
編集部 各地の農協史なども出されています。ぜひ小紙に各地の情報を寄せていただきたいです。
梶井 たとえば松山大学が産業組合の歴史を語るときに欠かせない岡田温の『岡田温日記』を復活させています。そこには東京に出る前の活動が記録されています。こういう出版物は取り上げたい。
D 同時に農業に関しては中央の視点から規制緩和や競争力強化だけのを求める多くの出版物もあり、それが農業政策論議でかなり話題になっているものもあります。しかし、なかには現場の実態とはかなり違うと思われるものもあり、その種の本をどう評価して考えを深めていけばいいのかと思う関係者も多いと思います。
梶井 確かに農政や農協の歴史について明らかに誤った事実に基づくものもありますから、議論の混乱を避け本当に論ずべきは何かを明らかにするような労作にこそ焦点を当てるという問題意識は持ちたいですね。
A 紙面としては必ずしも書評欄やブックガイドという形式にこだわるものではなく『読書』面として、ときには話題の書物をテーマにした座談会にしてもいい。
B 月刊誌などの記事にも注目すべきだと思います。この雑誌○月のこの記事は目を通すべきだ、といった紹介も大事ではないかと思います。
梶井 そうですね。できるだけ幅の広いテーマを取り上げていきたいと思います。
編集部 地方出版物についての情報はぜひ編集部にお寄せいただきたいと思います。また、この『読書』欄はホームページ『JAcom』での紹介にも力を入れていきたいと考えています。
ありがとうございました。
重要な記事
最新の記事
-
 「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日
「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -
 政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日
政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -
 備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日
備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -
 米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日
米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -
 瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日
瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -
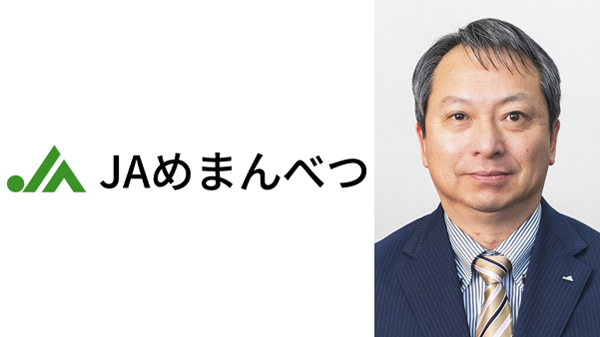 【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日
【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -
 初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日
初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -
 秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日
秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -
 日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日
日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -
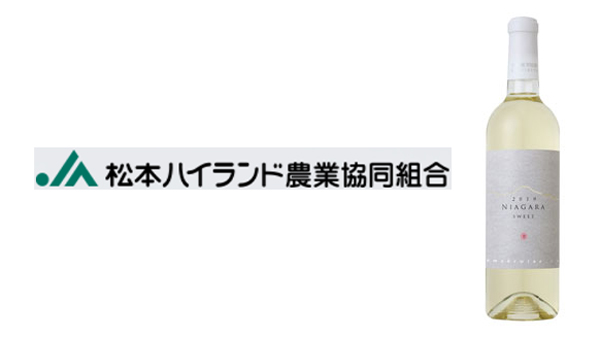 地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日
地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -
 温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日
温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -
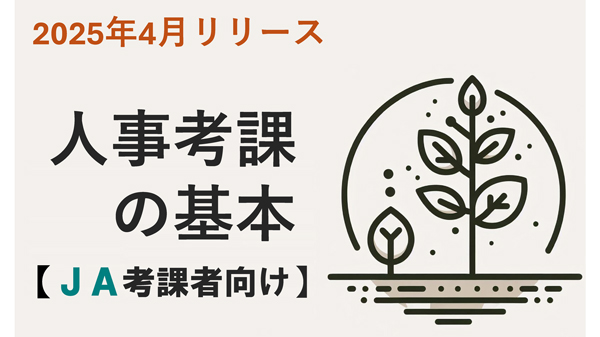 JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日
JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -
 【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日
【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -
 【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日
【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -
 ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日
ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -
 世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日
世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日 -
 【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日
【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日 -
 日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日
日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日 -
 X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日
X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日 -
 新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日
新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日
































































