農中総研 設立30周年 調査分析・発信に高まる期待2020年10月27日
農林中金総合研究所は今年設立30周年を迎えた。新型コロナ感染症の拡大は、農林水産業やJAをはじめとした協同組合にも影響を与え、大きな転換点となるなか広く社会経済を分析し情報発信するJAグループのシンクタンクとして同研究所への期待は一層高まっている。
 齋藤真一 代表取締役社長
齋藤真一 代表取締役社長
設立30周年を記念して9月には「持続可能な農業・地域社会に向けて~コロナ禍を踏まえて」をテーマに東京・大手町で記者等懇談会をオンライン方式を併用して開催した。記者懇談会は2008年から毎月1回開いているもので、同研究所の研究員が農林水産業や協同組合、国際情勢などをテーマに研究成果や情勢を報告、貴重な勉強の場となっている。30周年記念として開いた今回は148回め。平澤明彦取締役基礎研究部長による「日本とスイスの食料安全保障政策」と、内田多喜生常務取締役による「地域農業・社会の持続性と協同組合~地域の課題を解決してきた歴史から、産業組合から総合農協への120年の軌跡を中心に」をテーマに講演が行われ、ジャーナリストやJAグループ関係者、官庁など100名以上が参加した。
齋藤真一代表取締役社長は「コロナ禍の今、農林水産業、食品関連産業、系統への影響などを注視しているが、痛感させられることはコロナ前から抱えていた課題がより明確に、より重くなったこと。デジタル化、スマート化の必要性が強く意識されるようになり、当社も生産、加工、物流、消費におけるこうした動向についてフォローを始めた」と述べるとともに、日本学術会議が10月にスマート農業についての提言を発表したことに触れ、「提言では従来型の個別技術による個別の課題の解決ではなく、生産や流通、さらに地域社会の仕組み全体にわたる課題解決が求められる時代になっていると主張している。これは食と農林水産業、環境など日本全体のビジョンに思いを致すことにつながるのではないか。当社30年の歴史はほぼ平成の歴史と重なる。農林中金調査部設置からの70年は戦後日本の歴史と重なっている。コロナ禍の今年、新しい時代に踏み出す。農中総研は農林水産業、地域社会、協同組合への貢献を心に刻みながらシンクタンクとしての機能発揮に邁進していきたい」と述べた。
 平澤明彦 取締役基礎研究部長
平澤明彦 取締役基礎研究部長
日本 食料安保具体策を
講演で平澤部長はスイスの最近の農業政策の変遷と食料安保への取り組み、そして日本の課題を解説した。
国民が発議し憲法改正を頻繁に行うスイスでは、1996年に憲法に農業条項となる104条を新設した。農政の目的を従来からの国民への食料供給の保障を第一とすることは変わらないものの、自然資源の保全と農業景観の維持も目的に農業の多面的機能の発揮のための施策を打ち出した。その際、直接支払いで農業者を支援するが、環境保全を要件とした。
しかし、穀物生産の減少や草地面積の減少から輸入飼料の増加を招いた。そのため政策の軌道修正を図り、農業者に食料生産を持続してもらうための供給保障支払いを軸とし、さらに2017年には憲法に食料安保条項を新設した。とくに食料安保を憲法に位置づける改正では国民投票で8割が賛成し国民的合意を得た。新条項には国による農地の保全のほか、食品ロスの削減なども掲げている。
一方、1999年に制定された日本の食料・農業・農村基本法は国際化が進展するなかで食料の安定供給の確保、多面的機能の発揮、農業の持続的な発展、農村の振興を理念としている。食料安保の観点では「国内生産の増大を基本とし輸入と備蓄を適切に組み合わせる」(第2条2項)を基本としているが、平澤氏は国内生産の増大を裏づける政策は明示されていないと話す。自給率目標は掲げているものの、「農業の持続的な発展」のために示されているのは「経営強化などミクロの視点が中心」で、競争力を強めても経営体数が減れば全体の生産量や農地面積は維持できないと指摘する。昨今の農政は産業政策(個別経営の競争力重視)と地域政策(水田維持や多面的機能発揮)を両輪とすると言われているが、平澤氏は、その2本に加えて全体の需給や生産基盤強化といった食料安全保障政策が必要だと強調した。
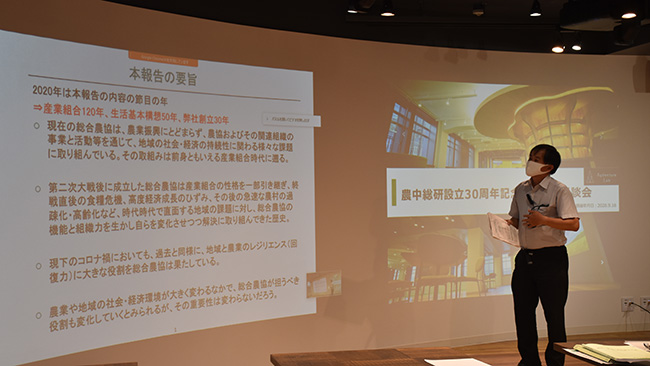 内田多喜生常務取締役
内田多喜生常務取締役
生活基本構想から50年
内田常務は2020年は「産業組合120年、生活基本構想50年」との観点から、農業振興だけでなく地域の課題を解決してきた総合農協の役割を報告した。1900年に制定された産業組合法はその後の改正で信用、販売、購買に加えて医療を含む生活関連事業を幅広く展開できるようになる。戦後の農協はこうした戦前の産業組合に営農指導部門も持つ総合農協として誕生した。農協は多数の自作農を組織して食料難克服のために食料供給の役割を担い、高度成長期以降は、農業近代化と生産力拡大の両面で大きな役割を果たしたと内田氏は指摘する。とくに品目ごとに生産を担う生産部会を営農指導員とともに立ち上げてきたことや、共同利用施設の整備などが近代化を担った。
しかし、一方で農村の生活改善は遅れ、都市と農村の格差の広がり、過疎化や高齢化の進行、農業機械事故など健康障害や公害などが大きな課題となった。
こうしたなか50年前の1970年、第12回全国農協大会では「農協は人間が人間らしい生活をしていくための運動の中核体となり、人間連帯にもとづく新しい地域社会の建設をめざして運動しなければならない」とする生活基本構想を決議した。その後、生活関連事業と活動が伸び、内田氏は農協は農業生産活動を担うだけでなく農村の生活向上に非常に大きな役割を果たしたと指摘する。また、「生活基本構想が掲げた課題は現在に通じる」として、SDGsが掲げる教育、子ども、女性などへの支援、環境の維持など現在と共通する課題を提示したという。
コロナ禍でも食料の安定供給に農協は大きな役割を果たすなど力を発揮した。来年10年を迎える東日本大震災をはじめ多発する自然災害などへのJAグループ挙げた支援が続いている。内田氏は「1人が万人のために、万人が1人のためにという理念そのものが危機から回復する力となる。とく日本の総合農協は農業だけでなく、多様な事業と人的資源を通じ地域社会・経済と深く結びついている」と強調し、今後の役割発揮に期待した。
重要な記事
最新の記事
-
 兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日
兜の緒締め農政を前に 鈴木農相2026年2月10日 -
 【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日
【人事異動】JA全農(4月1日付)2026年2月10日 -
 持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日
持続可能な食に貢献 受賞団体を表彰 第1回サステナブルガストロノミーアワード2026年2月10日 -
 5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日
5年契約で「最低保証」 先見通せる米作りに JAえちご上越2026年2月10日 -
 米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日
米価高騰でも購入「堅調」 2025年 節約志向で安い米にシフト2026年2月10日 -
 おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日
おいしいご飯は「研いだらすぐ炊飯」に驚き 食育の重要性も アサヒパックと象印マホービンがお米マイスターと意見交換会2026年2月10日 -
 コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日
コメ先物市場は先行きを示す価格指標になり得るのか?【熊野孝文・米マーケット情報】2026年2月10日 -
 農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日
農水省「重要市場の商流維持・拡大緊急対策」事業 公募開始2026年2月10日 -
 本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日
本日10日は魚の日「剣先イカ」や「あわび姿煮」など140商品を特別価格で販売 JAタウン2026年2月10日 -
 日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日
日本の「おいしい」を食卓へ「つなぐプロジェクト」ライフ首都圏店舗で開催 JA全農2026年2月10日 -
 2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日
2025年「農業」の倒産は過去最多を更新 初の80件超え 帝国データバンク2026年2月10日 -
 【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日
【人事異動】北興化学工業(3月1日付)2026年2月10日 -
 売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日
売上高14.6%増 2026年3月期第3四半期決算 日本農薬2026年2月10日 -
 電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日
電気自動車用(EV用)充電器 コメリ27店舗に設置2026年2月10日 -
 宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日
宮崎県産みやざき地頭鶏とピーマン使用「宮崎ケンミン焼ビーフン」販売開始2026年2月10日 -
 宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日
宮崎県「こだわりの業務用農水産物加工品」紹介イベント・商談会を開催2026年2月10日 -
 「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日
「2025年度 こくみん共済 coop 地域貢献助成」50団体に総額約1996万円を助成2026年2月10日 -
 累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日
累計出荷本数200万本超「のむメイトーのなめらかプリン」数量限定で復活発売 協同乳業2026年2月10日 -
 養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日
養豚DXのEco-Pork「インパクトレポート2026」を公開2026年2月10日 -
 農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日
農業温室・畜舎・工場向け「ドローン遮光・遮熱剤散布DXサービス」全国で提供開始 オプティム2026年2月10日





































































