【農業改革、その狙いと背景】暮らしに向けられる規制改革「ドリルの刃」 増田佳昭・滋賀県立大学教授2014年8月8日
・錯綜する思惑、真の意図は?
・企業の自由化は「魔法の杖」か?
・アベノミクスに醒めた目が大切
政府の「農業・農協改革」については、現場の実態を知らない議論、あまりにも唐突な問題提起だ、などといった批判が起きた。しかし、それが平然と議論されたのはなぜか? 増田佳昭滋賀県立大教授は政権の経済政策、すなわちアベノミクスから改めて検証する必要があると強調している。
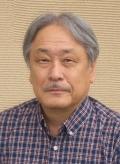 5月14日に規制改革会議農業ワーキング・グループ(WG)が「農業改革に関する意見」をとりまとめてからほぼ3か月。中央会制度の見直しや全農株式会社化など農協改革に目が行きがちだが、アベノミクスと称する経済政策の流れの中で考えてみる必要もありそうだ。
5月14日に規制改革会議農業ワーキング・グループ(WG)が「農業改革に関する意見」をとりまとめてからほぼ3か月。中央会制度の見直しや全農株式会社化など農協改革に目が行きがちだが、アベノミクスと称する経済政策の流れの中で考えてみる必要もありそうだ。
◆錯綜する思惑、真の意図は?
まず農協改革についてである。規制改革会議農業WGの「意見」には、検討経過でほとんど議論されていなかった「中央会廃止」が盛り込まれて大いに耳目を集めたが、さまざまな関係者の動機が混在したもののようだ。
第1は、アベノミクスを強引に推し進めようとするいわゆる「官邸」である。TPPの推進は、規制改革による成長戦略を第3の矢に掲げる現政権にとって至上命題といっていい。そのTPPに「頑迷」に反対するJAグループ、とくにその頂点に位置するJA全中は格好の標的になったということであろう。
第2は、信共事業分離など懸案の農協制度問題に決着をつけたいという農水省の動機であろう。それが農水省全体の意向かは知るよしもないが、規制緩和が議論されるたびに俎上にあげられてきた懸案を一気に解決できるとすれば、大変魅力的であろう。
ただ農業WGが出した単協信用事業の農林中金への移管、単協の専門農協化論は、あまりにも暴論であった。「経済農協」の経営的な不安定性は、わが国の専門農協の歴史の中で証明済みであるし、ドイツでのライファイゼン系総合農協の再編経過をみても明らかである。また、組合員組織を持たない農林中金にリテール金融機関としての競争力を期待することには無理があろう。
当然のことながら、農業面事業に特化した「経済農協」に、信用事業への組織面でのサポートを期待するのもまた困難であろう。「規制改革会議答申」では事業譲渡、代理店方式といったJAバンク法の活用で決着したが、今後の動向を見極める必要がありそうだ。
第3は、規制緩和によるビジネスチャンスを期待する経済界の動機であろう。これは、企業による農地所有や企業の農業参入など、農業にかかわる規制緩和、自由化を通じてビジネスチャンスを創り出そうというものである。また、農協改革についても、「経済界との連携を対等の組織体制の下で迅速かつ自由に行うため」に全農の株式会社化が、また「経済界・他金融機関との連携を容易にする観点」から農林中金、信連、全共連の株式会社化が進められようとしているように、提携関係を通じたビジネスチャンスの創出が強く意識されている。
規制改革会議答申にはいろいろなグループの思惑が盛り込まれているだけに、個別の論点ごとに注意深い対応が必要であろう。
◆企業の自由化は「魔法の杖」か?
同時に考えてみたいのは、アベノミクスの基調とその中での農業・農協改革の位置である。安倍首相は、今年1月にスイスで開催されたダボス会議で、自らをドリルの刃と称して、「いかなる既得権益も私のドリルの前に無傷ではいられない」と講演を行った。また6月には英紙フィナンシャル・タイムス誌に「私の第3の矢は日本経済の悪魔を倒す」と題した寄稿を行って、法人税率の引き下げ、規制の撤廃、エネルギー、農業、医療分野の外資への開放を言明した。「ドリルの刃」にしても「悪魔」にしても、ビジュアル好きの安倍首相らしい表現だが、いずれも規制緩和による企業活動の自由化を意味しており、その対象は農業、エネルギー、医療サービス、労働制度などである。
アベノミクスの論理は、企業活動の活性化が日本経済の成長をもたらし、元気のない日本を「再興」するというものだ。企業活動の活性化こそが、すべての出発点なのである。そのためには、企業が自由に活動できる環境整備が必要で、規制緩和=岩盤崩しが必要だというわけである。ついでに、岩盤にへばりついている既得権者も弓矢で退治しようということだろう。
ドリルの刃がむけられている分野は、いずれもわれわれの生活に密接な関係のある分野だが、それぞれの分野が深刻で構造的な課題を抱えているのは間違いない。たとえば農産物価格の低迷と農業者の低所得問題、医療保険制度問題、働き過ぎ問題や非正規労働者問題など、それぞれが専門家による真剣な分析と検討、対策が必要な大きな問題である。
◆アベノミクスに醒めた目が大切
ところが、アベノミクスは、それらの根本的な問題に正面から向き合うことなく、もっぱら企業の参入、ビジネスチャンスの創出に活路を見いだそうというのである。そこでは、「規制緩和」、「企業活動の自由化」は、あらゆる問題を解決する「魔法の杖」のようである。
常識的に考えても、そのような「魔法の杖」があるはずがない。むしろ懸念されるのは、企業活動の規制緩和がもたらす負の側面である。おそらく、医療分野の規制緩和は製薬会社と保険会社などの内外大企業の利益に貢献し、医療サービスの格差拡大と医療弱者を増大させることになろう。ホワイトカラー・エグゼンプションなどの労働制度改革は、むしろ働き過ぎを助長することになろう。法や制度によって守られてきた「くらし」が方々で切り崩されていくのである。農業でもそうである。地域に根ざす家族農業経営でなく企業経営重視の政策姿勢、企業による農地の野放図な所有と利用は、地域社会に深刻な影響を与えるであろう。ドリルの刃が切り崩そうとしているのは、ほかでもない国民生活なのではないだろうか。
これからの超高齢化社会を、規制緩和や企業活動の自由化といった「競争」の論理で、はたして乗り切れるのだろうか。これから必要なのは、地域に根ざした「共助」と「共存」の論理ではないか。協同組合は本来、庶民のくらしに根ざし、くらしを守るための協同の組織である。くらしの立場からの声を、悪魔になぞらえて力まかせに押しつぶそうというのは、あってはならないことである。
多くの国民は、アベノミクスのうさんくささに気づき始めている。先日行われた滋賀県知事選で、アベノミクスのブレインを自称する自民党候補が敗れたのも、集団的自衛権問題とともに、そのあらわれとみていいだろう。一部のマスコミに振り回されない、国民の醒めた目を期待したい。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日
【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -
 3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日
3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -
 地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日
地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -
 主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日
主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -
 米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日
米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -
 「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日
「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -
 (431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日
(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -
 JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日
JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -
 商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日
商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -
 JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日
JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -
 地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日
地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -
 冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日
冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -
 農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日
農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -
 農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日
農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -
 日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日
日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -
 森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日
森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日 -
 つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日
つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日 -
 日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日
日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日 -
 森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日
森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日 -
 「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日
「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日






























































