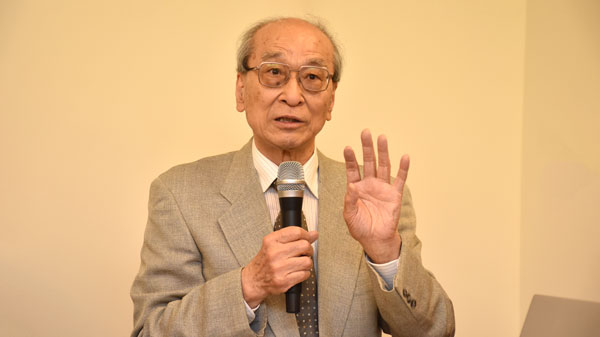JAの活動:しまね協同のつばさ
今、日本の農協が直面している問題とは何か?2013年1月4日
1.総合農協は日本独特のかたち
2.専門農協論の台頭
3.地域協同組合とは何か
本紙昨年の9月30日第26回JA全国大会特集号では、太田原高昭・北海道大学名誉教授に「日本型総合農協のあゆみと実績」と題した提言で日本社会における協同組合の果たしてきた役割を論じてもらった。それをふまえ本紙では2013年の新連載として太田原教授に「農協のかたち」を執筆をお願いした。
この連載では農協について、日本だけでなく世界各地の協同組合の歴史を農業の歴史と重ね合わせながら俯瞰し、日本の協同組合の現状と、これからめざすべき「農協のかたち」を骨太に論じてもらう。
第1回は今の日本の農協が直面している問題が、「信用・共済事業分離論」から総合農協を批判し専門農協へと分解するかどうかの問題と、農協から「農」の文字をなくして「地域協同組合」にするかという2つの面があることを指摘し、問題の構図とその背景を描く。
1.総合農協は日本独特のかたち
国論を二分したTPP参加問題では「この国のかたち」が問われているが、農協界でもそれと密接な関連をもって「農協のかたち」が問われている。農協のかたちとは農協の組織、事業のあり方を決める基本原理のことで、わかりやすく言えば総合農協のままでいいのか、専門農協の方がいいのか、はたまた地域協同組合にするべきなのかという問題である。論争は今も熱く闘わされているが、ここではこの問題を歴史にさかのぼって落ち着いて考えてみたいと思う。
◆日本では大部分が総合農協
わが国の農協の大部分は総合農協であり、信用や共済などの金融事業、農産物の共同販売や生産資材の共同購入などの経済事業、生活資材の店舗やガソリン・スタンドなどの生活関連事業から病院経営まで実に広範囲の事業を兼営している。販売事業で扱う農産物も米をはじめ畜産物、野菜、果物などおよそその地方で販売目的に栽培されている品目すべてが農協事業の対象になっている。
こうした総合的な事業方式は、その地方の農業者がまるごと1つの農協に加入するゾーニングと呼ばれる組織形態と関連している。多様な経営の多様なニーズに応えるためには総合農協にならざるをえないからである。
◆世界では専門農協がほとんど
私たちはこれが当たり前の農協だと思っているのだが、世界を見渡すとこのような農協のかたちは実はきわめて珍しいのだ。厳密に言うと日本の他には韓国と台湾の農協がよく似たかたちを取っているだけである。欧米の農協は事業別、作目別の専門農協が普通であり、農村信用組合、農業共済組合、肥料購買組合、小麦販売組合、酪農組合、ワイン醸造組合など多種多様な農協が分立している。
農業者の方は小麦も植えればブドウも作り牛も飼うという複合経営が普通だから、必要に応じて複数の組合に所属している。加入したい組合が自分の村になければ他村の組合に入るのだからゾーニングもない。
アジアやアフリカにも農協はあるが、欧米の影響が強いので専門農協がふつうのかたちになっているようだ。こうした中でなぜ日本だけが総合農協という独自のかたちをとっているのか、考えてみると不思議である。日本だって農協の前身である戦前の産業組合はドイツの農協に学び、ドイツの法律を翻訳して出発しているのだからますます不思議だ。次回からはしばらくこの謎を追って見ようと思う。
2.専門農協論の台頭
しかしわが国にも専門農協は存在した。存在したどころか戦後の農協制度発足当時には、数の上では専門農協の方が多かったのだ。総合農協が主要食糧である米麦を重点としていたのに対して、専門農協は畜産や青果の部門で優越していた。
総合農協は発足早々に全般的な経営悪化に見舞われて再建整備の大ナタをふるわれ、経営再建後もあつものに懲りてナマスを吹くの態でますます米麦に依存していった。一方で専門農協は農業基本法が畜産、青果を成長農産物と位置づけたことで勢いづいていた。
◆信用・共済分離論からの批判
1964年に出版された『総合農協と専門農協』という本の中で、時の農林次官小倉武一は自ら序言を書いて「総合農協主義の基盤は主として米麦生産の零細農耕であり食糧管理である」とし、農基法農政の担い手として総合農協と専門農協の何れが優れているかという問題を提起した。この本については後ほどまた触れようと思うが、総合農協か専門農協かという問題についての重要な議論として記憶にとどめておきたい。 その後専門農協の多くが総合農協に吸収され、この問題にはケリがついたかと思われた。 しかし、最近また同じ問題が「信用・共済分離論」というかたちで政府機関において論議されるようになった。現在は行政刷新会議に設置された「規制・制度改革に関する分科会」とその下の「農業ワーキンググループ」というところで検討が続いている。
◆専門農協で農協問題を解決できるか
農協制度の改革についての決着をみないまま野田内閣は退陣したが、この問題はTPP参加問題とからんでこれからもくすぶり続けるだろう。そして制度改革の焦点は、農基法農政の時代とはまた違った意味で「総合農協か、専門農協か」に絞られつつあるようにみえる。今日の専門農協論とはどのようなものであるか、それが果たして農協問題の解決に資するのか、「農協のかたち」をめぐる最もホットな論点として検討しなければならない。
3.地域協同組合とは何か
1970年代になると地域協同組合論が登場した。これは雑誌『地上』における鈴木博と佐伯尚美の論争となってかなりの話題を呼んだ。鈴木らの主張は農協法の第一条を「農民の組織」から「地域住民の組織」に改訂して、農業者に限らず地域住民なら誰でも入れる協同組合とせよというものであり、戦前の産業組合が一つのモデルとなっていた。
地域協同組合論は、農協だけでなく信用組合や生協、中小企業協同組合などの分野別、職能別の区別をなくして一般協同組合法を制定することを主張していたから、協同組合制度そのものの抜本的改革を提起していた。ヨーロッパにはこうした一般協同組合法を採用している国もあるから、この議論は単なる戦前回帰ではなく、制度改革の一つの方向を打ち出していたといえる。
◆農業関連事業を後退させる地域協同組合論
しかし、その後の展開においてはこうした論点は忘れられ、議論はもっぱら正組合員と准組合員の区別の当否という方向に向いていった。都市農協を中心に准組合員は増える一方であり、正組合員数をはるかに上回る農協も珍しくなくなっていた。こうした実情を背景に地域協同組合論は准組合員の権利拡大のための理論となったのである。そのことが農協事業における農業部門の後退と非農業部門の拡大という現実と関連していることは言うまでもない。
◆歴史の事実と現在の実態に沿って考えよう
地域協同組合論は農協の現場ではかなりの影響力をもち、研究者の間にも一定の支持がある。こうしてわが国の農協制度をめぐって総合農協論、専門農協論、地域協同組合論の三つが交錯しているのが現状であることは冒頭に述べた通りである。しかし、その論点が十分に整理されているとは思えないし、思いつきに過ぎないような議論も横行している。次回からはこの問題を歴史的かつ実証的に解きほぐしていきたい。
重要な記事
最新の記事
-
 米 推計19万tが分散して在庫 農水省調査2025年3月31日
米 推計19万tが分散して在庫 農水省調査2025年3月31日 -
 【人事異動】農水省(4月1日付)2025年3月31日
【人事異動】農水省(4月1日付)2025年3月31日 -
 【注意報】さとうきびにメイチュウ類西表島、小浜島で多発のおそれ 沖縄県2025年3月31日
【注意報】さとうきびにメイチュウ類西表島、小浜島で多発のおそれ 沖縄県2025年3月31日 -
 【注意報】かんきつ、びわ、落葉果樹に果樹カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 静岡県2025年3月31日
【注意報】かんきつ、びわ、落葉果樹に果樹カメムシ類 県内全域で多発のおそれ 静岡県2025年3月31日 -
 農業は恰好いいと示したい トラクターデモに立った農家の声 「令和の百姓一揆」2025年3月31日
農業は恰好いいと示したい トラクターデモに立った農家の声 「令和の百姓一揆」2025年3月31日 -
 4月の野菜生育状況と価格見通し 果菜類、ほうれんそう、レタスなどは平年並みへ 農水省2025年3月31日
4月の野菜生育状況と価格見通し 果菜類、ほうれんそう、レタスなどは平年並みへ 農水省2025年3月31日 -
 農林中金 総額6428億円の増資を実施2025年3月31日
農林中金 総額6428億円の増資を実施2025年3月31日 -
 25年産米「概算金のベース」 あきたこまち60キロ2万4000円 全農あきたが情報共有2025年3月31日
25年産米「概算金のベース」 あきたこまち60キロ2万4000円 全農あきたが情報共有2025年3月31日 -
 「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスなど公表 農水省2025年3月31日
「農山漁村」インパクト可視化ガイダンスなど公表 農水省2025年3月31日 -
 北アルプスの水と大地が育む米「風さやか」使用 ツルツル食感の米粉麺はスープも含めグルテンフリー JA大北2025年3月31日
北アルプスの水と大地が育む米「風さやか」使用 ツルツル食感の米粉麺はスープも含めグルテンフリー JA大北2025年3月31日 -
 特産の小松菜をバームクーヘンに 試食した市長も太鼓判 JAちば東葛2025年3月31日
特産の小松菜をバームクーヘンに 試食した市長も太鼓判 JAちば東葛2025年3月31日 -
 三鷹キウイワイン 市内のキウイ使った特産品 JA東京むさし2025年3月31日
三鷹キウイワイン 市内のキウイ使った特産品 JA東京むさし2025年3月31日 -
 地域の営農継続へ JA全国相続相談・資産支援協議会を設置 JA全中2025年3月31日
地域の営農継続へ JA全国相続相談・資産支援協議会を設置 JA全中2025年3月31日 -
 中央支所担い手・若手農業者研修会を開く JA鶴岡2025年3月31日
中央支所担い手・若手農業者研修会を開く JA鶴岡2025年3月31日 -
 全国の農家へ感謝と応援 CM「Voice」フルバージョン配信開始 JA全農2025年3月31日
全国の農家へ感謝と応援 CM「Voice」フルバージョン配信開始 JA全農2025年3月31日 -
 セメント工場排ガスから分離・回収した二酸化炭素の施設園芸用途 利用へ取組開始 JA全農2025年3月31日
セメント工場排ガスから分離・回収した二酸化炭素の施設園芸用途 利用へ取組開始 JA全農2025年3月31日 -
 カナダで開催の世界男子カーリング選手権 日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年3月31日
カナダで開催の世界男子カーリング選手権 日本代表チームの食事をサポート JA全農2025年3月31日 -
 JA鶴岡「もんとあ~る」dポイント加盟店に 4月1日からサービス開始2025年3月31日
JA鶴岡「もんとあ~る」dポイント加盟店に 4月1日からサービス開始2025年3月31日 -
 JA全中「健康経営優良法人2025」に認定2025年3月31日
JA全中「健康経営優良法人2025」に認定2025年3月31日 -
 「佐賀牛 生誕40周年記念キャンペーン」開催中 数量限定40%OFF JAタウン2025年3月31日
「佐賀牛 生誕40周年記念キャンペーン」開催中 数量限定40%OFF JAタウン2025年3月31日