JAの活動:今村奈良臣のいまJAに望むこと
【今村奈良臣のいまJAに望むこと】第70回 地域を支え、地域経済・地域農業も動かす直売所―第17回農林水産物直売サミット和歌山大会の紹介とその焦点―2018年11月24日
「農産物直売所は農業6次産業化のトップランナー」
このタイトルのもとで前述のように、私は第6分科会で「特別講義」を行ったが、前回の続きとして、前回示した「10点満点を目指す努力を!」として示した「P-Six」の図を参加者に判りやすいように、かつ実践してほしい課題とあわせて取り組んでもらいたい実践路線について話を行った。
(1)Agro Polis(アグロ・ポリス)。
これは各地域に「農業の拠点」を全力をあげて作り上げてほしいと強調したことである。農業労働力の減少、高齢化の進展などのなかで、いかに「大小相補」のシステムを作りあげていくか、また「老・中・青・婦」の連携・協力と相互扶助のシステムを作り上げていくか、さらにそれらの活動のうえに立って、いかに地域農業の組織化、法人化を進めていくべきかという課題を展開した。その典型・先進事例として長野県飯島町の(株)田切農産(代表・紫芝勉)の紹介とその活動の視点とポイントについて話したが、ここでは、このシリーズでもかつて展開してきたし、また拙著『私の地方創生論』(農文協刊、2015年3月)の第5章でも詳しく展開しているので、ここでは省略する。
(2)Food Polis(フード・ポリス)。
フード・ポリスとは、「農業6次産業化」の拠点のことである。この「農業6次産業化」という理論は、今から26年前に、大分大山町農協の農産物直売所「木(こ)の(の)花(はな)ガルテン」で約一週間にわたる調査の中で、農畜産物を生産している姿、加工している姿、そして直売所に買いにくる消費者の行動と意識を詳細に調査する中から、考えついたものである。当初は「1次産業+2次産業+3次産業=6次産業」と定義していたが、3年後に「1×2×3=6」と変えた。その理由は、農業が無くなれば、0×2×3=0と、6次産業の理論は成り立たなくなるからである。しっかりした農業があってはじめて「農業6次産業化」の理論は成立するのであると改めて強調して述べた。
さて、農産物直売所は「地産・地消」「地産・地食」という原点から、さらに「地産・都消」「地産・都商」へと展開しなければならないのではないか、と私は常々述べてきたが、こうした新しい展開を、さきの「木の花ガルテン」も展開してきている。消費者の多い大分市に3店、別府市に1店、福岡市とその近郊に3店、日田市に1店というように展開しており、大山町の本店から毎早朝8時定刻に運搬車を出している。
また、和歌山大会で報告のあった「よってって」を運営している田辺市の(株)プラス会長 野田忠氏によると、和歌山、大阪、奈良で23店舗を経営しており毎朝青果物や農産加工品等を着実に配送して都市の消費者に喜ばれていると述べていた。
また、島根県出雲市のJAしまね、販売戦略室、室長の須山一氏は、地元だけではなく週一回大阪の直売所に搬送をいまなお続けていると言っていた。
要するに"地産・地消"という枠組みを乗り越えて"地産・都商"へと展開していること、と合せて、多彩な地域の"伝統食"を都市の消費者の皆さんにもたしなんでいただこう、そして自ら誇りを持つ農村へも訪ねてきてもらおうという方向が近年みられるようになってきている。
(3)Eco Polis(エコ・ポリス)。
これは景観と生態系の拠点という意味で、私はこのような表現にした。
端的に言えば、里地・里山の保全、農村景観の維持・修復、さらに水利や風力、太陽光など自然資源をエネルギー資源などに活用しようではないかという提案である。もちろん、その原点には生活、居住環境の整備も含まれる。さらにそれのみに止まらずに、新しい時代にふさわしいグリーン・ツーリズムの望ましい拠点を作り、都市の皆さんとりわけ若い女性の皆さん、子育て中の皆さんにも訪ねてきてもらおうではないか、という提案でもある。直売所があれば相乗効果をもつであろう。
(4)世界農業遺産を活かす
さて、FAO(国連食糧農業機関)では、「みなべ・田辺の梅システム」を世界農業遺産として認定している。その認定の根拠として"持続可能な梅を中心とする農業システム"の成立をあげている。400年前から受け継がれてきているこのシステムには4つのポイントがあるとされている。(1)紀州備長炭の薪炭林を残しつつ山の斜面に梅林を配置することで水源の確保や崩落防止などの機能を持たせながら高品質の梅が生産されていること、(2)地域に生息するニホンミツバチによる受粉で梅が育っているという、梅とミツバチの共生関係、(3)梅の生産者が収穫した梅を白干しにする一次加工と高品質の梅干しの加工業者との連携システム、(4)土壌の崩落や流出防止による総合的な自然環境の保護による多様な生き物の生存する生態系の保全と維持、という4点があげられている。和歌山県の誇るべきことだと開催地の皆さんに紹介した。
ちなみに、世界農業遺産は世界16ヶ国にわたり37地域が認定されている(2017年1月現在)。わが国では中国に次いで多く、実に8地域が認定されている。参考までに列挙しておこう。
(1)トキと共生する佐渡の里山、(2)能登の里山里海、(3)静岡の茶草場農法、(4)阿蘇の草原の維持と持続的農業、(5)クヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環、(6)清流長良川のアユ、(7)みなべ・田辺の梅システム、(8)高千穂郷・椎葉山の山間地農林業複合システム―の8地域である。この8地域を思い浮かべつつその特質を一言で表現するならば阿蘇の草原を除けば私なりの表現によれば「谷ごと農業」と表現しうる特徴を見出すことができる。谷を単位としてはるか昔の先祖から営々と開田、開畑されてきた地域で、日本を代表すると言われるような関東平野や新潟平野のような地域ではない。これが世界農業遺産として将来にわたって残し保全すべきと国連機関からも評価されているのである。そういう視点からも、私の提案しているEco-Polisのことを考えてみていただきたいと思う。
(5)Medico-Polis ならびにCulture-Polisについては、時間がなかったので省略させていただくことにしたが、いずれも重要なことは言うまでもないが、特にカルチュアー・ポリスの中の最近とみにみられる小学校の廃校の進展とその新しい時代にふさわしい活用法については、是非とも考えていただきたい。小学校は各地域の皆さんの心の拠り所でもあったわけで、まちむら交流きこうとしても、廃校の利活用について、特別プロジェクトを立ち上げ、実態調査を進め、すぐれた先進事例の調査に取り組もうとしているので、皆さんからも、情報をいただきたいし、調査にも伺いたいと考えている。
また、メディコ・ポリスについては、長野県の佐久総合病院の活動ならびに関連する多彩な活動については、前掲拙著で詳しく展開してあるので参照して頂きたい。
(6)5角形を10点満点の取れる姿にするよう全力をあげてほしい。5ポリス構想の前掲図を見ていただきながら自らの住んでいる地域、自らの活動している地域は、現状ではそれぞれの項目が何点であるかと点検しつつ、どこをどのように伸ばしていくべきか、そのためには何をなすべきか、ということを農産物直売所に集まった折に議論を深め、地域の望ましい姿、将来像をこの5角形で表現してみてほしいというのが私の提案である。是非とも実践して頂きたい。
本シリーズの記事一覧は下記リンクよりご覧下さい。
今村奈良臣・東京大学名誉教授の【今村奈良臣のいまJAに望むこと】
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
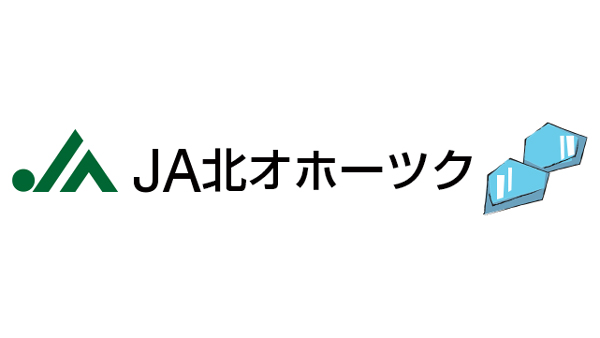 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































