JAの活動:創ろう食と農 地域とくらしを
家族農業と総合農協に誇りを 太田原高昭・北海道大学名誉教授2014年7月29日
・世界の95%が小規模家族農業
・小農経営に適合する総合農協
国際協同組合同盟(ICA)は、6月1日付で安倍政権の農業改革について「日本の農協と家族経営を脅かす改革案」という声明を発表した。10億人が加盟する世界最大のNGOであるICAが、一国の政府を正面から批判するのはきわめて異例のことであることをまず知っておかなければならない。
 声明文も短いが強烈である。「国際協同組合同盟は、協同組合の基本的原則を攻撃するとともに、国連の国際家族農業年という年に、農家による協同組織の結束と繁栄を脅かすような日本の農業協同組合の組織改革案を非難する。」ここでは日本の農政が「協同組合の基本原則への攻撃」とされている。先進国としてはこれだけで十分国辱ものであろう。
声明文も短いが強烈である。「国際協同組合同盟は、協同組合の基本的原則を攻撃するとともに、国連の国際家族農業年という年に、農家による協同組織の結束と繁栄を脅かすような日本の農業協同組合の組織改革案を非難する。」ここでは日本の農政が「協同組合の基本原則への攻撃」とされている。先進国としてはこれだけで十分国辱ものであろう。
もうひとつ「国連の国際家族農業年という年に」何ということをするのだという強い怒りが表明されている。国連は、今年2014年を国際家族農業年とする決議を採択した。世界の総人口が増加を続ける中で、食糧不足から免れるためには、特にアジア、アフリカの小規模家族農業の持続的発展が必要であり、そのための投資がなされなければならないということである。安倍農政はこうした趣旨に真っ向から反するものと非難されているのである。
ICAだけではない。国連の世界食糧保障委員会は、国際家族農業年の理論的バックボーンとなる報告書(邦訳、村田武・農林中金総研共訳『家族農業が世界の未来を拓く』農文協)をまとめているが、その日本語版への序文に次のような文章がある。引用が長くなって恐縮だが、ここは大事なところなので紹介しておきたい。
「低い食糧自給率と農業部門の高い高齢化率において、日本が置かれている状況は突出しているという点を指摘しておかなければならない。これは今日の日本では、輸入された食料、飼料及び農業資材によって需要がまかなわれており、国内の農業生産システムはますます脆弱になりつつあることを意味している。」
「こうした課題に取り組むために、日本の為政者たちは、農地の集約化と規模拡大に向けた構造改革をより徹底し、企業の農業生産への参入を促進するための規制緩和を行うというかたちで農業政策を方向づけてきた。しかし、こうした政策上の選択肢は、国民に対して十分な食料、雇用、および生計を提供できるのだろうか。食糧保障を実現できるのだろうか。そして日本社会の持続可能な発展に貢献できるのだろうか。こうした疑問が持ち上がっている。」
ここでも安倍農政は正面からの批判にさらされている。しかしこれは批判のための批判ではない。報告書はこれに続いて「一方で日本は、小規模農業部門の経験を諸外国に提供できる存在である」と述べている。
(写真)
太田原高昭・北海道大学名誉教授
◆世界の95%が小規模家族農業
わが国では、外国の農業というとアメリカやオーストラリアの大規模農業を思い浮かべ、日本農業の零細性を嘆くというパターンが出来ているが、実際は世界は小規模農業で満たされている。この報告書によれば、世界農業センサスが実施されている81か国のデータを見ると、全農業経営の73%は1ha未満であり、2ha未満は85%、5ha未満では実に95%となる。そしてそれは、アジアとアフリカで消費される食料の80%を生産している。
今世紀中に90億人に達すると予測される人口爆発の中心地はアジア、アフリカである。この地域の小規模家族農業が発展しなければ人類は飢餓に直面する。少数の大規模農業の生産力はもはや限界に達しているからである。そしてこのような小規模家族農業を近代化し、生産力を上げることに成功したほとんど唯一の経験を持つのが日本農業なのである。
日本は東アジアに共通する稲作農業を、江戸時代までは他国とあまり変わらない技術水準で行ってきた。近代に入るといわゆる「明治農法」によって単位面積当たり収量を倍加させ、戦後の農地改革を経てさらに倍加させた。そして高度経済成長の時期には小規模経営のままでの機械化と省力化に成功し、労働生産性を4倍に引き上げた。
この経験をそのまま途上国に持ち込んでうまくいくということにはならない。そうした試みはすでに様々に取り組まれ、制度的文化的な壁の厚さも経験してきた。しかし大切なことは、日本の経験が小規模家族農業の可能性を事実をもって示していることである。その意味では日本農業は人類史的な大実験を行ってきたのであり、それを中途で打ち切って企業農業に切り替えようとする愚行を、いま世界は糾弾しているのである。
世界の小規模農業の中でなぜ日本だけが近代化と生産力アップに成功したのか。農地改革と農地法、農協制度、農業改良普及制度、農業金融制度などのいわゆる戦後自作農体制といわれる諸制度がそれを可能にしてきた。とりわけ総合農協という独特のかたちを創造的に発展させてきたことが、日本の小規模農業を成功に導いた。
途上国にも多くの農協があるが、そのほとんどが欧米諸国の影響と指導の下で専門農協として組織されている。途上国の農協は概してうまくいっていないが、欧米とはきわめて異なった農業構造のうえに欧米型の専門農協を導入したことが不振の原因だといえないか。
◆小農経営に適合する総合農協
小規模家族経営が営む複合的農業、生活と経営の未分離、集落の形成など、日本の農協が総合農協という独自のかたちをとった諸要因は、多くの途上国と共通している。もちろん多くの違いはあるが、少なくとも独立自営農民の長い歴史の中で経営的・地域的に分化発達を遂げた欧米の農業よりははるかに共通性が高いといえよう。
したがって、日本型の総合農協制度を、それぞれの国の歴史的、構造的な特質に応じて導入することが、世界の小規模家族経営の発展のために有効である。このことをいち早く実行したのが韓国の農協と台湾の農会である。タイの農協もその中に入れてよいのではないか。
韓国と台湾は戦前日本の統治の下で産業組合や農会がおかれた歴史があるのだが、戦後も総合農協制度を残し、日本農業の技術革新をいち早く移転している。タイは、1968年にそれまでの専門農協を郡単位に合併して総合化するという農協法改正を行い、これによって農協の組織率を大きく伸ばすことに成功した。
注目すべきは中国の動向であろう。中国は最近新しい合作社法を制定したが、これは明らかに日本の農協法を下敷きにした総合農協方式となっている。中国には膨大な農地があるが、農家数もまた膨大で、一戸当たりの平均面積は0.6haにすぎない。中国政府は欧米や日本の農協制度を慎重に調査研究したうえで、総合方式の採用に踏み切ったのである。
以上のように、日本型総合農協の国際的普遍性、とくに小規模家族農業との親和性は十分に実証されている。そして国連もICAもそのことに強い関心と期待を抱いている。日本政府のなすべきことは、自国の小規模農業と総合農協に自信と誇りをもち、それを活用して、アジア・アフリカの農業の持続的発展と世界の食糧保障に貢献することであろう。
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
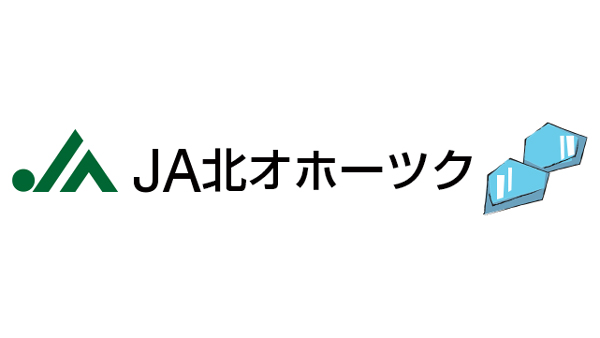 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































