JAの活動:創ろう食と農 地域とくらしを
地域を丸ごと幸せに 菅野孝志・JA新ふくしま組合長2014年8月6日
インタビュアー:小川理恵・JC総研基礎研究部
・復興に向き合い、真正面から挑戦
・次世代につなぐまず生産を再開
・JAだからできた綿密な土壌検査
・企業や行政にないJAの組織力発揮
・女性の継続性とパワーをフル発揮
・世界が認めるJA存在意義の再認識を
・分断から再生へ組合員に寄り添い
未曾有の大災害となった「3.11」の悲劇からもうすぐ3年半。被災地の岩手や宮城、福島県では、地域の人々の血のにじむような努力のもと、着実に復興が進みつつある。とりわけ原発問題を抱える福島県では、「風評被害」というバッシングに現在も立ち向かいながら復興に向け、一歩一歩、歩みを進めている。そのなかで、大きな影響力を持ち、地域を牽引してきたのがJAである。JA新ふくしまは、震災から目をそらさずに真正面から向き合い、JAの総合力をいかんなく発揮しながら、地域の幸せ創造のために前進し続けてきた。その復興への道のりから、私たちは何を学べばいいのだろうか。政府による一方的なJA改革論議が高まるなか、「JAとは何か」という命題を、震災復興をとおしてJA新ふくしまが果たしてきた役割から、いま一度考えたい。インタビュアーはJC総研基礎研究部の小川理恵氏。##
女性が支える協同活動
東日本大震災で示した
JAの“地域力”を次代に
【管野組合長からJAへの3つの提言】
○「農業者・生活者・地域」に常に目線を
○「本気・気力・助け合い」を合い言葉に
○「JAは地域の幸せ請負人」その誇りを忘れない
◆復興に向き合い、真正面から挑戦
――東日本大震災から3年半が経とうとしています。どのような3年半でしたか。復興の現状は。
あっという間の3年半でした。現在も復興対策は続いていますが、おかげさまで農産物の販売高は震災前の数値に戻りつつあります。地元農家の努力のたまものだと思います。
――福島県は、震災で原発問題という特別な悩みを抱えることとなりました。事故発生当初、不安を訴える組合員に、JA新ふくしまでは、どのように対応しましたか。
 原子力発電所が爆発したことで、福島の生産者は生活を脅かされかねない大きな不安に直面しました。その証拠に、震災後の4月初めに開催した営農集会に、例年なら2000人しか集まらないところ、3500人もの組合員が詰め掛けました。普段はJAと距離を置いている生産者も、放射能というモンスター相手には1人で太刀打ちすることはできず、JAを頼ってきたのです。だからこそ、これらの人たちの手をJAは離すことはしませんでした。一度手を離してしまったら、もう二度とつながり合うことはできないからです。
原子力発電所が爆発したことで、福島の生産者は生活を脅かされかねない大きな不安に直面しました。その証拠に、震災後の4月初めに開催した営農集会に、例年なら2000人しか集まらないところ、3500人もの組合員が詰め掛けました。普段はJAと距離を置いている生産者も、放射能というモンスター相手には1人で太刀打ちすることはできず、JAを頼ってきたのです。だからこそ、これらの人たちの手をJAは離すことはしませんでした。一度手を離してしまったら、もう二度とつながり合うことはできないからです。
地域のすべての農業者、そして生活者の未来のために、これから先の生産活動はどうするべきか真剣に考えました。
そこで、JA新ふくしまが打ち出したのは「とにかく作ろう」という結論でした。この状況で、なぜ生産するのか。それは、生産し販売することがJAの役割であり、脈々と引き継がれてきた農業の営みを、次世代につなぐためにも、今ここから逃げてはいけないと思ったからです。まずは作ってみて、しっかりと現状を把握し、問題を明確化して対策を練ることが肝心だと考えました。
(写真)
菅野孝志・JA新ふくしま組合長
◆次世代につなぐ まず生産を再開
――「作る」という提案に、反対意見はありませんでしたか。
 もちろん反対はありました。作ってみたところで売れなかったらどうするのか、という質問もたくさん受けました。でも「売れるにしても売れないにしても、皆さんの苦労が報われるように、JAが必ずやるから」と組合員と約束し、同意を得ることができました。
もちろん反対はありました。作ってみたところで売れなかったらどうするのか、という質問もたくさん受けました。でも「売れるにしても売れないにしても、皆さんの苦労が報われるように、JAが必ずやるから」と組合員と約束し、同意を得ることができました。
(写真)
直売所も復活
◆JAだからできた綿密な土壌検査
――今、復興に向けて着実に歩みを進めておられます。現在に至るまでに、どのようにして地域の農業を再生させたのか。具体的な取り組みについて教えてください。
生産者には不安な気持ちを押さえて生産していただくのだから、JAは本気で対策に乗り出しました。チェルノブイリへの視察にも参加し、適切な農地の除染方法を探しました。そこで、1台250万円する土壌の簡易測定器の存在を知り、すぐに導入。農地を1筆ごと、全部で10万件検査し、土地ごとの問題点を明らかにしたのです。それは国が行う土壌調査よりもずっと綿密な検査で、そこで得たデータを元に研究者など専門家とタッグを組み、営農に生かす施策としてまとめ上げました。
一方、JAを通して出荷・流通するすべての農作物については、出荷前の放射性物質検査を義務づけ、基準値を超えていないことを確認してから出荷するというラインを構築しました。「福島のものは安全だから食べてください」といくら声高に叫んでも、それを裏打ちするデータがなければ、消費者の心には届きません。ていねいに検査し、自信を持って全国の消費者に届けることができるものだけを出荷することで、福島県産農産物の応援者を徐々に増やすことができました。
さらに、生産者の健康対策として、当時5000円かかっていた健康診断の代金の半額をJAが負担し、農家組合員には積極的に健康診断を受けるよう促すなど、健康面からのサポートも行いました。
◆「誰のため」か考え いち早く対応を
――圃場管理、販売戦略、健康サポートの3面から農業者を支えている。地域の生命線をつなぐ存在としてのJAのあるべき姿ですね。復興の過程において、JAのすばらしさを実感されたことはありましたか。
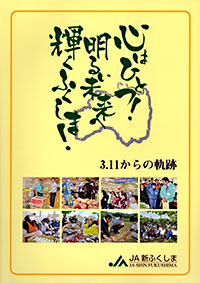 対応の早さと決断力には、行政との大きな違いが現れました。行政では、現場担当者が何ひとつ決断できないんです。何でも横揃えで、上からの指示がないと動けない。非常時には、その判断の遅さが命取りになります。例えば、震災発生当時、JAの女性部が中心となって、被災者におにぎりを提供しました。JAは普段の活動のなかで炊飯器などを自前で持っているから、こういう時にあっという間に対応ができました。これはすごいことです。しかし、それをとりまとめていた行政サイドが、「全部揃ってから。全員同時に」と後のばしにしているうちに、おにぎりを配るのが夜になり、せっかくのおにぎりが冷たくなってしまったのです。お年寄りや子ども、弱っている人へ優先的に配るといった配慮が全くありませんでした。これはなぜかというと、行政では「誰のためにやるか」という意識が薄いからだと思います。後で批判されることを恐れ、決まり通りのことしかやらない。
対応の早さと決断力には、行政との大きな違いが現れました。行政では、現場担当者が何ひとつ決断できないんです。何でも横揃えで、上からの指示がないと動けない。非常時には、その判断の遅さが命取りになります。例えば、震災発生当時、JAの女性部が中心となって、被災者におにぎりを提供しました。JAは普段の活動のなかで炊飯器などを自前で持っているから、こういう時にあっという間に対応ができました。これはすごいことです。しかし、それをとりまとめていた行政サイドが、「全部揃ってから。全員同時に」と後のばしにしているうちに、おにぎりを配るのが夜になり、せっかくのおにぎりが冷たくなってしまったのです。お年寄りや子ども、弱っている人へ優先的に配るといった配慮が全くありませんでした。これはなぜかというと、行政では「誰のためにやるか」という意識が薄いからだと思います。後で批判されることを恐れ、決まり通りのことしかやらない。
でもJAは違います。なぜなら「何のため」=「地域の人々みんなの幸せのため」という目的意識がはっきりしているからです。それは震災当時、役職員1人ひとりの行動にも現れていて、たいへん感動しました。
そこで、JA新ふくしまでは、震災時、現場にいる職員に、その時々で最良の方策を決断できる裁量を与えました。その代わり報告を徹底し、対策本部で全体の状況を把握できるシステムをいち早く構築しました。誰のためか、という目的を見失わなければ、判断を誤ることはまずありません。それでも間違ってしまったら、そのときは本気で頭を下げればいい。そのために組合長をはじめ役員がいるのです。
(写真)
「3・11からの軌跡」の冊子
◆企業や行政にないJAの組織力発揮
――地域目線のJAだからこそなし得たことが数多くあったのですね。一方、JAが全国組織だから果たすことのできた役割はありましたか。
JAの組織力はすごい。震災後、JA全中が中心となって、あっという間に100億円の援助金を集め、被災3県に分配してくれました。これには本当に助けられました。また、全国のJAからたくさんの救援物資を送っていただきましたが、そこには、被災者の心に寄り添う、生活に密着した支援を、という目線がありました。復興支援に関しては、一企業や行政では真似できない、地域全体を包括する総合JAの良さと、全国グループとしてのJAの組織力がいかんなく発揮されたと思います。
◆女性の継続性とパワーをフル発揮
――復興の過程では、女性たちはどんな活躍をしましたか。
震災の際のおにぎり作りは、県からの要請で行ったものでした。でもそれを一時のボランティアで終わらさずに、4月10日まで、のべ10万個のおにぎりを継続して作ったのはJA女性部を中心とした農業者・生活者である女性たちの意思でした。そしておにぎり作りのなかから、彼女たちはやりがいを見いだし、他に自分たちにできることはないかと次のステップへと移ってきました。その継続性とパワーには目を見張るものがありました。震災時に支援していただいたことをきっかけに、全国のJA女性部との交流もはじまり、それは新たな絆を構築しています。その絆は、次にどこかで不測の事態が起きたとき、必ずや強い結束力を発揮してくれるはずです。
――今、アベノミクスでも、女性の活躍促進が謳われています。女性の力の発揮について、組合長の意見を聞かせてください。
 そもそも生産現場を支えているのは半分以上が女性です。女性は「食」「暮らし」「育む」(はぐくむ)という目線で物ごとを捉えながら生産活動を行っています。今一番求められている「食の安全・安心」という意味で、女性が作る農作物はたいへん高いレベルだといえます。
そもそも生産現場を支えているのは半分以上が女性です。女性は「食」「暮らし」「育む」(はぐくむ)という目線で物ごとを捉えながら生産活動を行っています。今一番求められている「食の安全・安心」という意味で、女性が作る農作物はたいへん高いレベルだといえます。
また、女性は決断も早い。よけいなこだわりを捨て、今一番たいせつなことは何かを取捨選択する能力に長けています。それは生産現場でも、JAの職場においても活かされるべき必要な能力です。JA新ふくしまでも、積極的に女性の意見を取り入れながら、女性の活躍をいっそう後押ししたいと思います。
(写真)
女性が支える協同活動
◆世界が認めるJA 存在意義の再認識を
――今、JAグループは大変厳しい状況に置かれています。震災からの復興を実現させてきた経験から、この状況を打破するにはどうしたらよいと思いますか。JAは何を変えるべきですか。また反対に、変えるべきではない、守っていかなければならないことは何でしょうか。
そもそも世界が認めているJAを、日本の政府だけが認めないことには違和感を覚えます。そこには多くの誤解もあります。しかし批判は、いま一度自分たちの役割を確認するよいチャンスと捉えるべきです。JAは何のために存在するのか、それは地域のため、地域全体の幸せのためです。復興の過程において、それを私たちは身をもって示してきました。JAだからこそ成し遂げられたことが数多くあった。そんなJAの存在意義を、まずは、私たちJAに集う者たちが再認識すること。それが肝心だと思います。
一方、誤解を受けるにはそれだけの理由もあるのだということも忘れてはなりません。言っていることとやっていることが違うことはないか。反省すべき点は反省し、間違いがあれば正していく。その上で、おたおたせず冷静に、本気で方策を練るべきです。そして誤解があるのならば、組織的にその誤解を解いていく努力も必要だと思います。
◆分断から再生へ 組合員に寄り添い
――これからのJA新ふくしまの展望について教えてください。
原発はすべてを分断してしまいました。生産者と消費者はこれまではそれぞれが関わり合いながら共生し、生産者はやりがいを、消費者は安心をと、幸せを循環させながら地域をつくっていたのに、そのすべてが断ち切られてしまった。この分断された地域の循環を、いかに修復していくかがJAに問われています。循環を取り戻せるのは、政府でも、行政でもない、地域全体を包括するJAという存在しかありません。
組合員という絶対的なメンバーが求めているのは、今日よりも心豊かな明日です。それに寄り添うのがJAなのだという想いをもって、JA新ふくしまはこれからも前進していきます。
――ありがとうございました。
【インタビューを終えて】
JA新ふくしまを初めて訪れたのは、震災の爪痕も生々しい2013年秋のことだった。その時感じた「原発で失った地域の絆を、自分たちが必ず取り戻す」というJA新ふくしまの意気込みは、震災から3年半近くが経過した今、復興という形で着実に実を結んでいた。その根底にあるのは、「地域全体を支えることができるのはJAしかない」という、ぶれない誇りと信念だ。
「今日までの道のりは決して平坦ではなかった。しかし、歴史的な大惨事にJAはここまでやれたんだ、という証を後世に残したい。それは農業協同組合というロマンだよ」と笑顔で語った菅野組合長の言葉が忘れられない。
今も風評被害は根強く残り、依然として福島県の農業は厳しい状況に曝されている。その現実と真摯に向き合い、地域とともに歩み続けるJA新ふくしまの姿から、JAの役割とは何かを私たちは再認識しなければならない。そしてまた、JAグループの総合力で被災地を支え続けるからこそ、農協の価値が生きたものとなるということを心に刻みたい。
重要な記事
最新の記事
-
 「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日
「茨城らしさ」新ステージへ(2)JA茨城県中央会会長 八木岡努氏【未来視座 JAトップインタビュー】2025年4月16日 -
 政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日
政府備蓄米 第3回売り渡し 4月23日から入札2025年4月16日 -
 備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日
備蓄米放出 第2回入札も全農が9割落札2025年4月16日 -
 米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日
米の価格形成 コスト指標で「基準年」設定で合意2025年4月16日 -
 瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日
瑞穂の国から見ず穂の国へ【小松泰信・地方の眼力】2025年4月16日 -
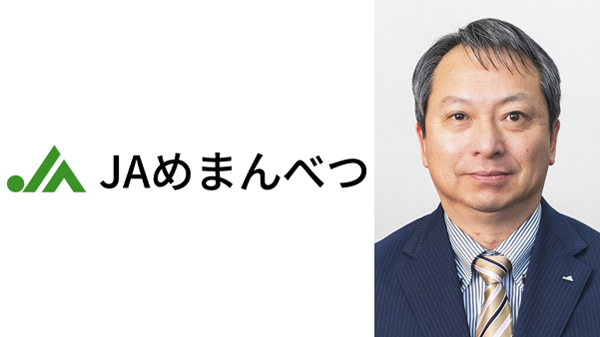 【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日
【'25新組合長に聞く】JAめまんべつ(北海道) 高橋肇組合長(4/8就任) 合理的価格形成に期待2025年4月16日 -
 初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日
初の「JA共済アンバサダー」に後藤晴菜さんを起用 JA相模原市のイベントを盛り上げる JA共済連2025年4月16日 -
 秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日
秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛肉について学ぶ JAタウン2025年4月16日 -
 日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日
日差しと土が育む甘さとコク 日本一の選果場から「三ヶ日みかん」 JAみっかび2025年4月16日 -
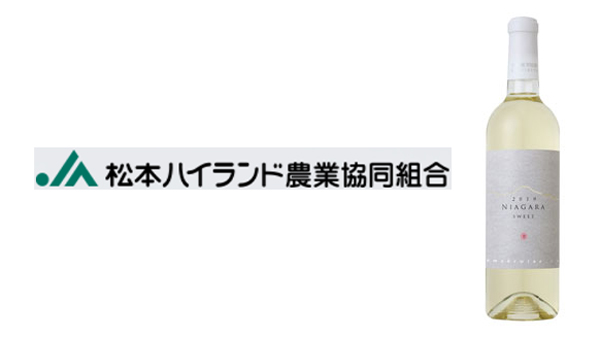 地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日
地元産ワインにこだわり 甘みと酸味が楽しめるNIAGARA SWEET JA松本ハイランド2025年4月16日 -
 温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日
温暖な島で潮風受け育つ ごご島いよかんはさわやかな香り JA松山市2025年4月16日 -
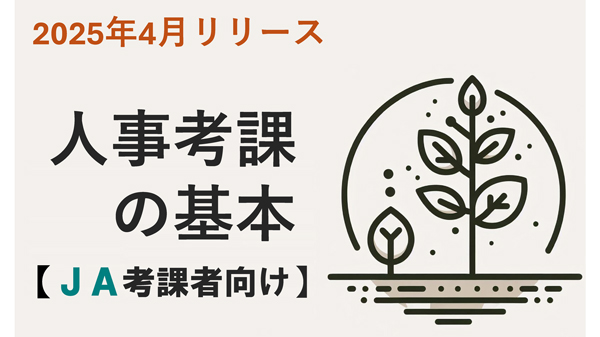 JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日
JA向け新コース「人事考課の基本を学ぶeラーニング」リリース 日本経営協会2025年4月16日 -
 【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日
【消費者の目・花ちゃん】ETC障害とBCP2025年4月16日 -
 【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日
【役員人事】東洋農機 新社長に山田征弘氏(4月4日付)2025年4月16日 -
 ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日
ドローン事業拡大でTHE WHY HOW DO COMPANYと業務提携 マゼックス2025年4月16日 -
 世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日
世界基準のワイン苗木の「原木園」設立へ 日本ワインブドウ栽培協会がクラウドファンディングを開始2025年4月16日 -
 【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日
【組織変更および人事異動】荏原実業(5月1日付)2025年4月16日 -
 日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日
日本文化厚生連が臨時総会 年度事業計画などを決定 病院の経営改善は待ったなし2025年4月16日 -
 X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日
X線CTを用いた水田のイネ根系の可視化 農研機構2025年4月16日 -
 新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日
新潟・十日町産魚沼コシヒカリ使用「米粉ろおる」ジャパン・フード・セレクションで最高賞2025年4月16日
































































