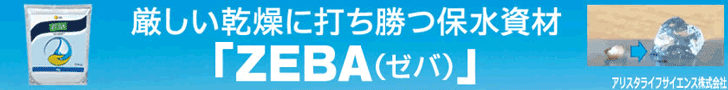JAの活動:第27回JA全国大会特集 今、農業協同組合がめざすこと
【提言】農業は北海道の"生命線" (一社)北海道地域農業研究所 特別顧問(前・北海道農政部長)竹林孝氏2015年10月6日
暮らし易い農村づくりJA大会を機に再確認
今、地方自治体にとっての最大の課題は、人口減少時代への対応と「地方創生」である。昨年5月に日本創成会議が、2040年までに日本の半分の市町村が消滅の恐れがあるとした、いわゆる「増田レポート」を公表した。この衝撃的な報告を一つの契機に、国は昨年11月に「まち・ひと・しごと創生法」を制定し、2060年までに1億人程度の人口を確保し、将来にわたり活力ある日本社会を維持するため、人口減少の克服と地方創生に本腰を入れることになった。
◆地方創生は農業で
 地方はこれまでも過疎化が最大の悩みであったが、直面している人口減少はより構造的で深刻であり、このままでは地域社会の維持が困難となる。人口減少の状況や原因は地域によって異なっており、国は、地域特性に応じた処方箋づくりを求めたことから、都道府県や市町村では地方版総合戦略づくりが進められている。
地方はこれまでも過疎化が最大の悩みであったが、直面している人口減少はより構造的で深刻であり、このままでは地域社会の維持が困難となる。人口減少の状況や原因は地域によって異なっており、国は、地域特性に応じた処方箋づくりを求めたことから、都道府県や市町村では地方版総合戦略づくりが進められている。
私もこの5月まで北海道庁でその策定に係わってきたが、ある首長が「これまでも一人でも多く住んでもらうために必死にやってきた」と言うように新たな即効薬は難しいが、北海道では、農業が基幹産業であるだけに農業振興による雇用の創出、暮らしやすい農村づくりは不可欠なものであることは間違いない。そして、総合戦略の策定・実践に向けては、農業・農村で総合事業を展開しているJAに対して積極的な関与が期待されている。
そうした中で、第27回JA全国大会の組織協議において、地方創生への積極参画を提起していることは正鵠を得たものである。この取組みを通じて、JAがこれまで以上に行政や住民等との関係を深めるとともに、地方版総合戦略の中に地域農業の課題や将来方向が適切に位置付けられるよう働きかけていくことが大切である。
◆多様な夢の実現を
 地方創生を目指す農業施策のあり方は、地域の条件や状況によって様々であろうが、「所得向上」は共通した大きな柱である。このたびの農協法改正ではJAの事業目的に明記され、JA全国大会でも最重点課題の一つに位置付けられている。
地方創生を目指す農業施策のあり方は、地域の条件や状況によって様々であろうが、「所得向上」は共通した大きな柱である。このたびの農協法改正ではJAの事業目的に明記され、JA全国大会でも最重点課題の一つに位置付けられている。
国の総合戦略では所得向上に向けて、輸出の拡大や6次産業化の推進を重点施策として掲げており、こうした「付加価値」を生み出す取組みは脚光を浴びやすいが、そのベースとなる農畜産物生産という農業本来の「基本価値」もしっかりと重視して欲しい。
また、効率と競争を優先し規制緩和や市場経済を重視するという最近の潮流が強まることによって、地方の疲弊がさらに加速するのではないかと私は危惧している。
もうこれ以上、農家の仲間を減らしたくない、若い人が残って欲しいという地域の思いに対して、提示される将来像が効率的な農業経営体ばかりでは夢がない。北海道の地方創生関連事業では、放牧酪農など小規模経営に農場リース方式での参入を支援する事業を創設した。誰かの一人勝ちでなく、等身大の夢を自己実現できる懐の深い地域農業を築くためには、協同組合の価値と倫理を、JA全国大会を契機にもう一度再確認することが大切と考える。
◆地域社会の担い手
地域の方々のJAに対する期待の一つに、地域社会を守る担い手としての役割がある。北海道は平成9年に「農業・農村振興条例」を制定した。国の基本法見直しに先んじたものであり、農業と並んで「農村」の振興を加えたのは、生活の場である農村地域が成り立たなければ、農業自体も維持できなくなるという危機感からであった。
道の調べでは、25年時点で65歳以上の高齢者が過半を占めるいわゆる「限界集落」が道内の地域集落の16%に達しており、10年後には66%になると推計している。過疎化に伴い、商店がなくなり、路線バスが廃止され、さらには高齢者介護福祉の担い手も見つからない中で、地方自治体にとってJAの存在は大変大きなものである。このたびの農協法改正では准組合員の利用規制が論点の一つになったが、金融窓口や生活店舗、ガソリンスタンド、さらには病院事業などJAの事業は、本道の農村社会を支える貴重な地域資源ともいうべきものである。
地方創生の取組みの中で、住民交流や福祉、買い物などの住民サービスを集約した「小さな拠点」の形成が提起されている。北海道では、JA生活店舗が核となり、商工会や自治体、福祉介護事業者などが連携して、コンパクトな形で生活を支える多機能型施設を整備する動きが出てきている。JAが地域社会と切り離すことができない存在であることを、地方行政からも発信していかなければならない。
◆外へ発信・連携を
 北海道にとって農業は、地域の最大の強みであり財産であることは、道民のコンセンサスとなっており、農業の維持・発展に向けてはいつも「オール北海道」で取り組んできた。TPP問題では、一次産業団体や地方自治体、地方議会はもとより、道経連、道商連といった経済界、消費者団体、労働界なども参画し農業を守る運動が進められてきた。
北海道にとって農業は、地域の最大の強みであり財産であることは、道民のコンセンサスとなっており、農業の維持・発展に向けてはいつも「オール北海道」で取り組んできた。TPP問題では、一次産業団体や地方自治体、地方議会はもとより、道経連、道商連といった経済界、消費者団体、労働界なども参画し農業を守る運動が進められてきた。
また、北海道米の需要を拡大するため、道外産米から北海道米に変える「米チェン」が道民運動として展開された結果、道内における北海道米のシェアは20年前の30%台から現在は約9割にまで高まった。住民がこれだけ農業を大切に思い、応援するのが北海道の特質である。
一方で、「農業」を大切に思う気持ちと「農協」に対するイメージに温度差があることを感じる。今日の北海道農業が形作られるに当たって、JAの果たした役割が極めて大きかったことを知っている者として、残念に思う。
食料自給率の向上や食の安全・安心に関する国民的な理解は深まっているが、JAに対しては今般の農協改革の議論に見られるような「いわれなき批判」が起こるのは、JAの発信力や組織外との連携に課題があるのではないだろうか。六次産業化、輸出促進や地域の活性化などは、JA組織だけのノウハウでは達成できない課題も多い。原点となる目的達成のためには、自己完結型にとどまらない様々な組織との積極的な連携が、JAに対する理解の促進、ひいては農家の利益に資することになると考える。
◆自信と誇り持って
 北海道は開拓の歴史の中で、石炭産業など様々な産業の盛衰があったが、農業については一貫して基幹産業であり、将来に向けても生存の基本である「食」を担う農業がなくなることはありえない。
北海道は開拓の歴史の中で、石炭産業など様々な産業の盛衰があったが、農業については一貫して基幹産業であり、将来に向けても生存の基本である「食」を担う農業がなくなることはありえない。
そして世界的にみても、農業を担う主体は家族経営であり、これを束ねて発展させてきたのは協同組合組織である。ニュージーランドの世界第4位の乳業・フォンテラは約1万戸の酪農家に所有されている協同組合であり、また、世界45ヵ国以上で約600種類の果物と果汁飲料を製造販売しているサンキストも6000名の組合を抱えるカリフォルニア青果協同組合で、利益は組合員に還元される非営利団体である。海外の例ばかりでなく、北海道においても協同の力による成功例が数多くあり、自信と誇りを持って然るべきである。
地方創生は、何か大きな経済が生まれお金がドッと落とされるのを期待するのではなく、一人一人が地域で等身大の営みを実現することにある。
第27回JA全国大会が、協同によるパワーをもう一度再認識し、自らの改革を進める中で、地に足をつけた真の地方創生に寄与するキックオフとなることを念願している。
(写真)北海道は日本の食料基地
(写真)オール北海道で農業を守る
(写真)北海道に憧れ就農する若者たちも(浜中町で)
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日
シンとんぼ(178)食料・農業・農村基本計画(19)農村の振興2026年1月31日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(95)JIRACの分類【防除学習帖】第334回2026年1月31日 -
 農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日
農薬の正しい使い方(68)エネルギー生成阻害タイプの除草剤【今さら聞けない営農情報】第334回2026年1月31日 -
 米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日
米の民間在庫量 338万玄米t 対前年比85万t増 12月2026年1月30日 -
 (471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日
(471)設計思想の違い2(牛肉:豪州と日本)【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2026年1月30日 -
 スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日
スーパーの米価 2週ぶりに低下 5kg4188円2026年1月30日 -
 【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日
【26年度ホクレン乳価交渉】飲用、加工とも「据え置き」2026年1月30日 -
 【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日
【農と杜の独り言】第8回 祭りがつなぐ協同の精神 農と暮らしの集大成 千葉大学客員教授・賀来宏和氏2026年1月30日 -
 【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日
【人事異動】農水省(2月1日付)2026年1月30日 -
 【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日
【肉とビールと箸休め ドイツ食農紀行】(5)アジアショップって何? 日本食はどこで買えるか2026年1月30日 -
 令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日
令和7年度スマート農業アクセラレーションサミット開く JA全農2026年1月30日 -
 「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日
「おかやま和牛肉」「ピーチポークとんトン豚」特価販売 JAタウン2026年1月30日 -
 2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日
2月9日「肉の日」石川佳純が「和牛を食べよう」トレインチャンネルで動画放映 JA全農2026年1月30日 -
 【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA全農(2026年3月1日付)2026年1月30日 -
 福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日
福島県産「あんぽ柿」至福のスイーツ登場 オンライン販売も JA全農福島2026年1月30日 -
 いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日
いわて牛が期間・数量限定で特別価格「いわての畜産生産者応援フェア」開催 JAタウン2026年1月30日 -
 三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日
三井不動産発行のグリーンボンドに投資 ライフサイエンス領域に充当 JA共済連2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日 -
 【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日
【役員人事】JA三井リース(4月1日付)2026年1月30日 -
 【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日
【人事異動】JA三井リースグループ(4月1日付)2026年1月30日