JAの活動:JAは地域の生命線 いのちと暮らし、地域を守るために 2017年今農協がめざすもの
【インタビュー・JA岩手県中央会 藤尾東泉会長】米の需給 行政の関与 不可欠2017年1月9日
水田農業を守り所得向上につなげる多様な生産に努力
聞き手:北出俊昭元明治大学教授
米産地の岩手県にとって30年産からの見直しは大きな課題となる。麦、大豆、野菜、飼料用米など水田の多様な活用で農業所得向上につなげることが重要だが、それを支える政策確立が不可欠と藤尾会長は強調する。(聞き手は北出俊昭・元明治大学教授)
――今年は30年産からの米政策見直しへの対応が重要になります。この問題に対するお考えからお聞かせください。
 やはり需給バランスがきちんと確立できるかできないかが大きな課題になるのではないかと思っています。今までの経験に照らせば、需給バランスが崩れると米価は大暴落します。日本の農家そのものが成り立たなくなる懸念があります。ですから、ここにどのくらい農水省がタッチできるか、が大きな課題ではないかと思っています。
やはり需給バランスがきちんと確立できるかできないかが大きな課題になるのではないかと思っています。今までの経験に照らせば、需給バランスが崩れると米価は大暴落します。日本の農家そのものが成り立たなくなる懸念があります。ですから、ここにどのくらい農水省がタッチできるか、が大きな課題ではないかと思っています。
今のところ県の農業再生協議会に全部任せるといっていますが、28年度は東北農政局の局長自ら東北各県を歩き、県ごとに転作の必要性を現場で訴え、具体的に飼料用米生産を誘導しました。そこまで関わったのです。
これによってどうにか需給バランスが取れたのが28年度の状況です。
一部マスコミなどに生産者に自由に生産させるべきだという主張があり、需給バランスのために予算をつぎ込むなという考え方もあります。飼料用米にも予算をつぎ込むなと。しかし、そんなことをすれば米の価格は大暴落し再生産できません。きちんとした需給バランスを確立しないと何ともならないのです。
――政府がいうように農協なり地域の団体だけで米の需給バランスは実現できるのでしょうか。
農水省は数字を示すと言っていますが、数字を挙げれば需給バランスがとれるということなどありません。行政の関与と飼料用米も含め所得がある程度見通せる支援策をきちんと財政的な裏づけをもってやっていくというかたちがない限り無理で、それがなければバランスは必ず崩れます。
これまで行政が強力に需給調整にタッチしながらも、なんとか需給バランスを保っているという状況ですから。
――行政の一定の関与が不可欠だということですね。
行政がタッチしてきたこれまでも、過剰生産の県はあったわけです。そういう経過があるから、当然、行政の関与を考えていく必要があると思っています。
――TPPはアメリカのトランプ次期大統領がTPP離脱を表明していますが、日本は協定承認案と関連法案を国会で成立させました。発効は不透明ではありますが、アメリカとオーストラリアに対して合計7万8000tの米輸入枠を設定することになっています。
 重要5品目に関しては絶対に守ると言っていたわけです。それがそれぞれの品目で輸入が増えるような内容に合意をしたのは間違いです。これは長年言ってきていることですが、結局、牛肉・オレンジの輸入自由化以来、ずっと輸入自由化が叫ばれ、それが農家の所得低下を招いてきた要因のひとつだと思います。だからわれわれはTPPはやるべきではないという姿勢を一貫してきました。
重要5品目に関しては絶対に守ると言っていたわけです。それがそれぞれの品目で輸入が増えるような内容に合意をしたのは間違いです。これは長年言ってきていることですが、結局、牛肉・オレンジの輸入自由化以来、ずっと輸入自由化が叫ばれ、それが農家の所得低下を招いてきた要因のひとつだと思います。だからわれわれはTPPはやるべきではないという姿勢を一貫してきました。
――厳しい状況のなか、地域に根ざした協同組合としての農協の活動がいっそう大事になっていると思います。それにも関わらず、昨年は規制改革推進会議が急進的な経済効率一辺倒の農協改革に関する意見を出しました。どう思われましたか。
まさに経済効率主義の徹底、新自由主義的な方向ですから徹底して対抗していかなければなりません。
改革集中期間は全農改革を中心に2019年5月まで、といっていますが、それまで規制改革推進会議として何もしないということはないと思います。まだ農協改革に関して意見を出てくるとみるべきです。
その指令は官邸主導で出ており、現場のみなさんからも今の官邸主導の政策決定は問題だ、農業の分からない人たちが簡単に農業とはこうあるべきだという話をすることについて心外だという声が聞かれます。もっとも、農政の中身が全部分かっていなければあのような規制改革推進会議の意見としてまとめて出てくるはずもありません。だから、今回は信用事業の事業譲渡問題が出されましたが、これもかねてから農政当局の考えにあったことです。それが今回、表に出てきたわけで引き続き動向には注視していかなければならないと考えています。
――単協の信用事業を事業譲渡すると総合事業を展開するJAとしての役割は非常に難しくなると実感されますか。
岩手県下7JAの組合長は、みなこぞって間違っても事業譲渡したら大変だ、と言っています。信用事業だけなく共済事業にもわれわれは真剣になってその事業にも取り組んでいます。
そのJAの信用・共済事業が問題にされるのは、そもそもアメリカの要望から郵政民営化問題が出てきたことと同じだということをみな分かっています。だから、それを許しては絶対だめだということです。
今の事業展開だからこそ信用・共済事業からの還元でJAは営農指導をきちんとできる。事業分割してしまえば、総合農協として営農指導をやることができなくなります。そこに県下のJA組合長たちは危機感を持っています。
――農政活動にしても営農指導にしても農協は組合員のために取り組んでいるからこそ、農家は農協を頼りにし貯金を預け共済にも加入するということだと思います。改めて農協はどうあるべきですか。
できるだけ組合員との懇談会を持ったり技術指導会を開くなど組合員の声を聞く努力をしている農協には組合員も集まってきます。それをせず組合員から遠ざかれば農協なんてあってもなくてもいい、ということになってしまう。
やはり農協はなくてはならない農協にならなくてはだめだ、これがJA改革だということだと私は言っています。
――具体的にはどういうことを大事にしなければならないでしょうか。
岩手県は米地帯で米に依存してきました。大事な農産物に変わりはありませんが、かつては1俵2万円が今は1万4000円です。一反9俵ほど穫れますから反当たり5万4000円下がっていることになります。
そこで強調しているのはやはりマーケット・インの発想で消費者は何を望んでいるのか考えて農業をしようということです。麦、大豆に加え野菜生産にも力を入れていますが、一例として最近推奨にしている品目にズッキーニがあります。これは愛媛県のある取引先からの要望です。かぼちゃの生産依頼もありました。まさに求められているものを生産するというかたちです。また今不足している子牛の生産も考えるべきだと思っています。
一方で米も新品種として「銀河のしずく」と「金色の風」の2品種を生産、販売します。食味で上位にランクされています。そうした産地の努力と同時にそれを支える政策を求めたいと考えています。
(ふじお・とうせん)
東京農業大学卒。平成12年岩手中央農協代表理事副組合長、20年同代表理事組合長、岩手県農協中央会理事、県信連経営管理委員会委員、県厚生連理事、全農岩手県本部運営委員会委員、全共連岩手県本部運営委員会委員。県農協中央会代表監事、副会長を経て、28年岩手県農協中央会会長。
【インタビューを終えて】
藤尾会長が強調されている米の需給安定には国の役割が必要なこと、農産物の輸入拡大で農業所得が低下したことなどは、米政策の見直しやTPPへの対応を考えるうえで銘記すべきことである。また、信用事業譲渡により総合経営が解体され、営農指導が困難になるという指摘も重要である。官邸主導の新自由主義的な政策が強化されている現在、農協は改めて組合員・地域本位の取り組みを一層徹底する必要があることを感じた。(北出俊昭)
重要な記事
最新の記事
-
 (432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日
(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -
 【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月25日
【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月25日 -
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
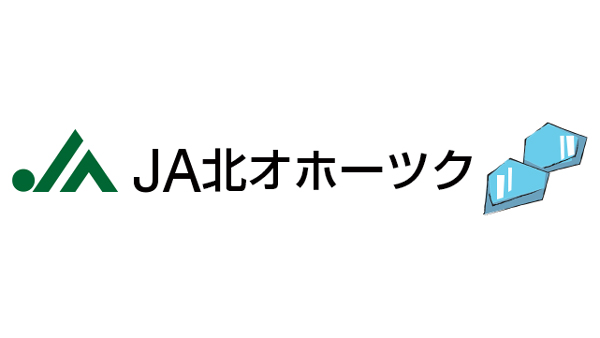 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日

































































