JAの活動:第64回JA全国青年大会特集
【インタビュー・大澤誠農林水産省経営局長】「自ら変わる」発想で農協の新時代を(後編)2018年2月16日
・農協改革は運動論
・事業環境の変化をチャンスに
・時代変化に即応した信用事業の姿を
・魅力ある農業、自分たちで
--時代が大きく変化するなかで、総合農協の意義と課題についてはどう考えますか。
◆事業環境の変化をチャンスに
総合農協というシステムは、このような経済環境の変化においても新しいチャンスとなり得ると同時に、しっかり対応しないとかえってリスクになるとも思っています。
今や組合員は同質的でないのですから、個別のニーズに応えて多様なサービスを提供していくのがこれからの農協の姿だと思います。むしろこれからはいろいろな事業、サービスが融合してくると思います。
たとえば、これからフィンテック革命が起きてきます。これによって銀行がなくなってしまうのではないかという懸念もありますが、農業者、組合員の立場に立てば、フィンテックによって売り先の情報が非常に分析しやすく整理しやすいかたちで手に入れられるというチャンスにもなります。ただし、すべての人がその技術を使えるわけではありませんから、農協がその技術を先行して使い、非常に新しい農産物の売り方を作り出すなど、金融サービスとも融合した事業をいち早く農村部で作っていく。こうしたことができれば総合事業の強みにもなりチャンスにもなると思います。
ところが従来の事業のやり方を続けていれば逆に非常にリスクになります。フィンテックの例でいえば店舗を持っていなくても金融サービスが受けられるという面だけ強調されてしまえば、農村部は他の金融機関の草刈り場になってしまうおそれもある。つまり、これから先の社会を見据え、農村部で農協が何を先行的にやっていくのかが求められていると思います。その際、総合事業であるということは、いろいろな新しい事業を融合させて組合員に最大限奉仕するというメリットを作る場として考えるべきではないかと思っています。
--現在までの自己改革の実践についてはどう評価しますか。
自己改革をしなければならないという認識が非常に広まってきたことと、テーマも具体的になり、肥料をどう安くしていくか、農産物の売り方をどうしていくかなど真剣に考える取り組みが出てきたことはプラスの面だと思います。
われわれ政府としてやるべきことは、そうした努力をある程度客観的なかたちで示すことだと思っており、そういう思いから昨年、自己改革に対する農協と、それから農業者へのアンケート結果を示しました。2年分を比較していますが、それぞれ1年前よりも肯定的な評価が増えています。
正直にいって農業者の評価がまだ低いようですが必ずしも農協の評価と数字がピタリ一致する必要はないと思います。これは主観的な評価ですから、たとえば改革によるメリットが組合員に広く薄く行き渡っている場合、個々の組合員としてはあまり評価していないというケースもあるでしょう。いちばん大事なことはトレンド、方向性だと思います。なるべく農業者の評価が高まるようにすることが大事だと思います。
各地の農協からいい事例も出てきていますが、それに呼応して全農でも、たとえば肥料の銘柄の集約と競争入札の導入によって仕入れ価格が1割から3割下がったと発表されました。一つの象徴的な成果だと思います。さらにこれを農家レベルでの引き下げにつなげていくということも大事です。販売事業についても体制づくりの段階だと思いますが、これから具体的な成果にしていくことが期待されます。
◆時代変化に即応した信用事業の姿を
--今後の取り組みのなかで信用事業の代理店化や、准組合員問題についてはどう考えるべきでしょうか。
 信用事業について代理店化、あるいは譲渡といった問題だけを議論するのはいかがなものかと思っています。いちばん大事なことは、信用事業はまず生活インフラとして非常に役立っているということを前提にし、先ほども指摘しましたが、この低金利や農村部の人口減少、さらにはフィンテックの進展等々に今後、どう農協の信用事業の姿を描いていくのか、ということです。それがあまり聞こえてこないというのが残念です。
信用事業について代理店化、あるいは譲渡といった問題だけを議論するのはいかがなものかと思っています。いちばん大事なことは、信用事業はまず生活インフラとして非常に役立っているということを前提にし、先ほども指摘しましたが、この低金利や農村部の人口減少、さらにはフィンテックの進展等々に今後、どう農協の信用事業の姿を描いていくのか、ということです。それがあまり聞こえてこないというのが残念です。
准組合員の問題については今の法律上、事業利用は員外利用ではないわけですが、各農協において准組合員とはどういう位置づけなのか、イメージがあるはずだと思います。協同組合としての自己改革に取り組んでいるわけですから、まずは各農協の側から、私たちは准組合員はこうあるべきだと考えているという意見をうかがたいというのが本音中の本音です。
法制度について、今のままであるべきだとか、ここを変えるべきだという議論にすぐ行くのではなくて、組合運動のなかで准組合員をどう位置づけるのか、その意見を謙虚にうかがうことから始めるべきではないかと考えています。
制度を変える、変えないという議論をまず封印して、どういう位置づけなのかを議論をする。位置づけをした後には、では准組合員からどのように意見を聞くのか、あるいは聞かないのか、どういう事業にどの程度准組合員が参加していくのか、意思反映はどうしていくかという議論になっていくと思います。
単に正組合員の事業を利用させるということであれば、協同組合一般の原則からは員外利用の制限があるということになります。しかし、今はそうではない仕組みとして准組合員制度があるわけですから、それについてもう一回、根底から考え直し、どういう位置づけなのかということについて、改めて社会に提案していただきたい。政府としては准組合員の利用状況についての調査は粛々とやっていくということになりますが、准組合員の位置づけということについてはまず農協の方々の意見を聞くということだと思っています。自分たちで考えて提案をしてほしいということです。
◆魅力ある農業、自分たちで
--それでは農協改革の実践も含め青年農業者に期待することをお聞かせください。
農業は今後5年、10年で大幅に変わっていきます。AI農業、ドローン、ロボットなど新世代の技術を駆使した農業がどんどん実用化に近づいています。それらを瑞々しい気持ちで導入を検討し、自分たちが新しい農業のかたちをつくるんだと思っていだだきたい。一方でそれは迫られていることでもあります。人口が減少し今でも人手不足なわけですが、魅力ある農業をつくっていかないと自分たちの思うような経営ができなくなっていきます。このことを頭に入れて、自分たちがいちばん魅力ある自由な職業をつくっている、自分で時間を自由に使え地域社会への貢献もできるんだ、という農業のいい面を発信できる農業者になっていただきたいです。
それによって農協も変わっていくと思います。新しい発想をどんどん取り入れていく人が農協に関与していけば、先ほどから強調している地域ごとに多様な農業、農村の現状、これにマッチした農協の自己改革の担い手にもなっていけると思います。そのように自ら変わっていくんだと気構えを持った方々が農協の新しい事業モデルについても提案や要望を出していただくことを期待します。
※この記事の前半部分は、【インタビュー・大澤誠農林水産省経営局長】「自ら変わる」発想で農協の新時代を(前編)をお読みください。
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
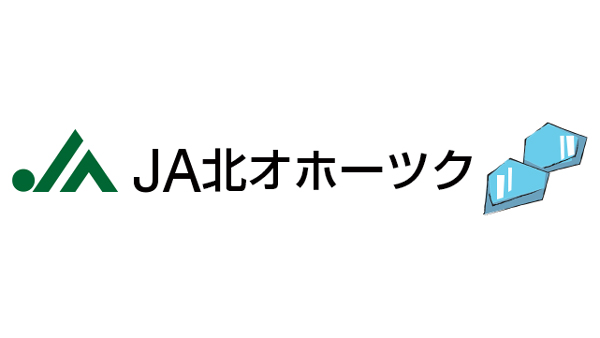 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































