JAの活動:食料・農業・地域の未来を拓くJA新時代
【インタビュー・元農相・衆議院議員 森山裕氏】地域政策あって産業政策 行政・商工との連携を2019年7月23日
・JAグループに望むこと
人口が減るなかで、地域の活力を維持・発展させるには、元気な農業をつくるのが本筋である。それを担っているのはJA組織であり、その役割は大きい。農協改革集中推進期間が終わり、農業所得の向上や農業生産の拡大など、経済事業のあり方、組合員とのコミュニケーションなど組織運営にとって、これから取り組むべき課題が見えてきたのではないだろうか。JAはこれから何をすべきか。農水大臣経験者の森山裕、齋藤健両氏に,特に地域政策について、「JAグループへの期待」を聞いた。今回は森山裕氏のインタビューです。(聞き手は,農業・農政ジャーナリストの榊田みどり氏)
※森山裕氏の「裕」は正しくは「ネ(示す篇)」に「谷」です。
JAは自己改革で3つの基本目標を掲げているが、森山氏は3つめの地域活性化への取り組みに期待を示した。高齢化が進むなかで、日本の地域社会をどうするか。その中で産業(農業)を位置付け、行政や商工業と連携した地域づくりの必要性を強調。その役割をJAに期待する。
 森山裕氏
森山裕氏
◆JA自己改革を評価
―JA改革で経済事業は語られますが、地域政策の議論が聞かれないように思います。JA改革集中推進期間が終わり、JAの自己改革をどのように見ますか。またこれまでJAグループが地域で果たしてきた役割をどう評価しますか。
単位農協や連合会が頑張り、JA改革の取り組みは評価できると思います。半面、農家のみなさんの不安も高まっています。これからの信用事業、あるいは准組合員の扱いをどうするか。地域政策としても大事なことです。
自民党として、准組合員の問題は組合員の判断に任せることとしましたが、これは正しいと思います。金融環境の悪化から民間銀行の合理化が進んでいますが、農村地域にとって農協の信用事業は大事です。〝金融過疎〟になってはなりません。
―農協は信用事業の利益で必要な地域政策の資金を確保してきた経緯があります。准組合員にも必要な事業だと思いますが。
農協の准組合員は、いまのまま准組合員でいることが当たり前になっています。政治家はそのことをよく知っておかなければなりません。一方、農協には長い歴史があります。かつては字(あざ)ごとに農協があり、助け合い組織としての役割を果たしてきました。今も農協は地域の福祉に積極的に関わってきています。また、生産部門でも、生産履歴をしっかり示すことができるのは日本の農業の強みですが、これも農協の生産者部会があってのことです。
―JAの地域貢献は評価できるとのことですが、配食サービスとか高齢者の送迎活動など、生活の分野で女性が活躍しています。それにしては女性の発言力が弱いように思いますが。
地方では買い物難民が出る状況で、農協の生活事業の努力は素晴らしいと思います。移動購買車では、お年寄りが道路に出るまでに時間がかかって間に合わないことがあるので、鹿児島県ではリヤカーで販売しているところがありますよ。
女性の発言力が弱いとのことですが、お父さんを通じて女性の声が農協に反映されているのではないでしょうか。女性理事を増やすことも大切ですが、家族団らんで出る声もまた大事だと思います。
◆地域マネジメントを
―平成の大合併で、市町村の行政サービスが希薄化しています。それを補う組織としてJAが果たす役割が重要になると思います。総務省では、地域マネジメント組織(地域運営組織)の機能支援に力を入れ始めましたが、JAはどのような形で行政と連携・リンクするべきでしょうか。
自民党の過疎対策特別委員会で過疎法の改正に携わりましたが、過疎地での対応は、地域リーダーと農協組織がどう連携するかが大事です。地域では住民の大半が組合員であり、役場も農協も一緒にみています。市町村長とどのようにタイアップするかがポイントで、農協と行政の連携が今後ますます大事になるでしょう。
―農業産出額、農業生産所得は増えていますが、生産者は減り、離農が増えています。一方で新規就農者は増えています。これをどのようにみますか。
先端技術を使った社会づくりで政府が進める「ソサエティ5・0」に農協はどのように対応するのでしょうか。それには農業基盤の整備を進め、経営を省力化・合理化する必要があります。一方で、それが難しい中山間地域があります。
今回できた棚田振興法でも分かる通り、農業は産業政策だけで成り立つものではありません。地域政策で中山間地域の農業にどのように対応するかです。そのポイントは家族経営で、これを大切にしなければなりません。
宮城県で昨年開かれた和牛能力共進会で最高の賞を得た鹿児島県の種雄牛を生産したのは80歳を超える家族経営の女性でした。こうした農家は、言わず語らずの技術を持っています。これを忘れてはいけません。
―そこのところを、農政はなかなかそれをうまくくみ取ってくれない。
この何年かの農政は大規模化であり、産業政策であったと思います。それも大事ですが、一方で多くの条件不利地、中山間地域があります。両方あっての日本の農業です。中山間地域は直接支払制度などで対応していますが、もう少し拡充しなければならないと思っています。それが地域を守ることであり、同時にこれは防災対策でもあります。
◆過疎地の〝宝探し〟

榊田みどり氏
―いま中山間地域の占める農地は4割くらいですが、経済のグローバル化で農産物の価格が下がると、条件不利地がもっと増えるでしょう。産業政策で生き残れる地域が5割を切るようになると、JAは何をすべきでしょうか。一方で、若い世代が農村に移住する田園回帰が増えています。そうした人の受け皿も必要だと思いますが。
日本で一番条件が悪いのは、私の地元の鹿児島の桜島だと思います。しかし昔から作っている桜島大根があります。いま、その成分の一つトリゴネリンが注目されています。普通の大根の60倍含み、動脈硬化や血管内皮の障がいなどに効果があります。また、やはり昔から葉が分厚くて降灰では簡単に枯れない椿があります。その椿油をいま、化粧品メーカーが注目しています。種子島にも素晴らしいタケノコがあります。地元の人はそうした過疎地の良さになかなか気がつかない面がありますが、宝物探しをしっかりやっていただきたい。
―産地化という視点だけでなく、幅広く若い移住者を受け止める上でもJAの役割があると思いますが、その意味では地域との接点が少ないように感じます。
鹿児島県のJAそお鹿児島では、全国の就農希望者を集めて、花やイチゴ、パプリカ、ピーマンなどに取り組みましたが、特にピーマンが成功しています。若い新規就農者は技術革新に積極的ですね。ビニールハウスの温度管理を科学的に行い、慣行栽培の1.5倍の収量をあげています。ピーマンは昼に収穫して夕方農協の選果場に持ち込めばその日の仕事はおしまいで、自由になる時間がとれます。地元の農家の刺激になり効果が出ています。生活面でも、病気をしたときは野菜を届けたり、子どもの弁当をつくったりするなど、助け合いの農村社会のいいところにも魅かれるようです。
―そうした共助の部分はGDPに反映されませんが、ストックとして大事なところです。それが農村の価値ですね。
その通りです。そこは農村が誇ってもよいところです。元気に長生きできる社会をめざすのが農協の役割です。厚生連が保険・医療で活躍していますが、身近には農協の支所などを使って、お茶飲み会やサークル活動などを行っています。農村社会でなければできないことだと思います。
◆現場知る人がリードを
―JA改革は、農業者所得の増大、農業生産の拡大、地域活性化の3つの基本目標を掲げていますが、主に最初の2つにエネルギーを投じているように感じますが。
地域の活性化は待ったなしです。政府の目指す方向と同じであり、それが地方創生です。どのような地方をつくるかが、これから重要です。そのことについて声を大にして言ってなかったのは役所にも我々にも責任があると思います。
私が農水大臣のとき、中山間地域ルネッサンス事業を行い、ある程度道筋をつくりましたが、もっとPRが必要です。地域政策なくして産業政策はないと思っています。逆ではないのです。そのことをしっかりと押えておくべきです。
それには農業の現場が分かっている知った人がリードしないと、政策が現場と乖離(かいり)します。JA改革のなかで農機や肥料の価格が問題になった時、比較対象となった韓国で調査しましたが、細かい作業をこなす日本の農機とは大きな違いがあり、特殊な土壌がたくさんある日本では、多様な肥料を使うのはやむを得ない面があります。単に価格を下げ、種類を減らすのではなく冷静に見ないと、正しい判断はできないのではないでしょうか。
―いまJAは広域合併を進めていますが、支店単位の活動を見直さないと地域に求められるJAに戻らないと思います。中山間地でも平野部でも農家人口は約2割。かつての農業者中心の協同組合と、非農家を含めた地域協同組合との視点のずれも開いてきました。
農協の効率化は大事です。しかし効率化で地域の過疎地とか、中山間地域、条件不利地の農業・コミュニティがダメージを受けるのは避けなくてはならないと思います。農村でも混住化が進み、農家人口が減って、地域協同組合的な性格が強まり、本当の農村・農家の意見が反映しにくくなっていると思います。うまく農業と地域のバランスをとり、農業と商業・工業の農商工連携をしっかりやっていただきたい。
◆生産面で女性増える
―最後に女性へ、期待のメッセージを送ってください。
農業は生活そのものです。その大部分は女性が担っています。女性の視点は農協の運営、事業に反映させるべきだと考えます。女性には母性愛というか、自分の命にかえても子どもを守ろうとします。これが、生産履歴が分かって安心・安全な農産物を求めることにつながり、それを女性が強く主張してきたから、日本は生産履歴の分かる農産物、畜産物として国際社会で高い評価を得ているのです。
肉用牛もそうです。鹿児島の和牛が日本一になったのも、増体と品質のバランスをとって品種改良を重ねた結果です。
その主役は女性です。牛は男の仕事ではなくなり、家畜市場でも女性の姿を多くみかけるようになり、生産部門でも元気です。これは、農家のみなさんと農業生産を基本に取り組んできた農協の努力の成果です。政府はこれから農家民宿に力を入れる方針ですが、この分野でも積極的に活躍していただけるものと期待しています。
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日
【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -
 米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日
米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日 -
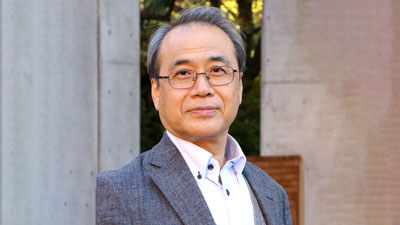 【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日
【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -
 米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日
米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日 -
 農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日
農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -
 備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日
備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -
 新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日
新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -
 JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日
JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -
 米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日
米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日 -
 農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日
農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -
 「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日
「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -
 「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日
「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -
 千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日
千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日 -
 【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日
【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日 -
 香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日
香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -
 京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日
京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -
 愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日
愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -
 リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日
リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日

































































