JAの活動:食料・農業・地域の未来を拓くJA新時代
【インタビュー・前農相・衆議院議員 齋藤健氏】農業救う輸出と6次化 消費の減少に危機感を2019年7月24日
JAグループに望むこと農業救う輸出と6次化消費の減少に危機感を
人口が減るなかで、地域の活力を維持・発展させるには、元気な農業をつくるのが本筋である。それを担っているのはJA組織であり、その役割は大きい。農協改革集中推進期間が終わり、農業所得の向上や農業生産の拡大など、経済事業のあり方、組合員とのコミュニケーションなど組織運営にとって、これから取り組むべき課題が見えてきたのではないだろうか。JAはこれから何をすべきか。農水大臣経験者の森山裕、齋藤健両氏に,特に地域政策について、「JAグループへの期待」を聞いた。(聞き手は、農業・農政ジャーナリストの榊田みどり氏)
※森山裕氏の「裕」は正しくは「ネ(示す篇)」に「谷」です。
人口が減少する中で、日本の農業がこれから力を入れるべきことは「輸出と農業の6次産業化だ」と齋藤健氏。これが農業・地域活性化の道であるとして、JAや農業の関係者はもっと人口減少、つまり消費の減少についての危機感を持つべきだと指摘する。
 齋藤健氏
齋藤健氏
―JA改革の取り組みをみると、経済事業に偏っているのではないかと感じますが、地域政策のなかで、農協の地域社会のインフラ機能をどのように評価しますか。
地域政策はもちろん重要で、JAの地域における貢献に期待すること大でありますが、農業が立ちゆかなくなるとそれもできない。人口が減れば当然ながら食べる人が減り、消費量が減ります。これに対してどうするのかが大きな問題です。国の農政を含め、JAにとってもそれを踏まえた上の地域政策でなければならないと思います。
人口減少に伴い農産物の国内販売量が減るなかで、農家の所得を確保するにはどうするか。方策は2つしかありません。国内の市場が縮小するのをカバーする輸出と、流通・加工から付加価値を得る6次産業化です。
◆生産減少に歯止めを
―カロリーベースで、日本の食料自給率は38%まで落ちています。大量の農産物が輸入されるなか、輸出振興だけでなく、足元の需要獲得に目を向けることも必要ではないでしょうか。一方で、生産量は減っても農業生産所得は増えています。所得の増加が生産基盤の強化に直接結びついていません。
足元の需要獲得といいますが、正直言って人口がどんどん減少するなか、容易ではない。条件の恵まれた平地で農業をしっかりやり、輸出にも力を入れることは、日本農業の価値を高めることでもあり、競争相手が減るわけですから同時にそれが中山間地域の農業を維持することにもつながるはずです。国の食料確保の面から考えても、生産量の減少は食い止めなければなりません。そのためにも輸出は重要です。
日本の農業は、今後、伸びる産業だと信じています。JAの自己改革は、この認識をもって取り組んで欲しいと思っています。そのためには農産物の輸出と、もうひとつ、農産物の付加価値を高める6次産業化がカギを握ると私は思っています。ゼロ金利が続いており、これからは金融事業もさらにきびしくなり、JAの経営も大変になります。経営が行き詰まれば、地域政策どころではなくなるのです。そのことを踏まえて、JAはしっかり頑張っていただきたい。
◆女性の感性を生かす
―そのとき、男性だけでなく、農業やJAに女性の知恵や活動が必要になると思いますが、女性の参加についでどのように考えますか。
女性の参加はすばらしいことです。女性は生活者であり消費者です。消費者を大事にするという意味でも、女性の感性を生かさない手はありません。
―JAは基本的には男性社会だと思います。運営に参加するにも女性は子育てや介護の問題があり、なかなかそうはいかないのが実情です。
それを助けるのもJAの役割です。農業生産活動の面でも、子育てや介護の支援はプラスに働くのではないでしょうか。男性の力はもちろん重要ですが、女性と若者が前面に出ると、消費者へのアピール効果も大きい。私の選挙区に社長が食料・農業・農村政策審議会の委員をやっている160haの大規模経営の染谷農場というのがありますが、女性と若者が中心になって、農業生産だけでなく農産物の直売所やレストランを企画、運営し、評判のアイスクリームを作ったりしています。女性や若者が活躍すれば、農業のイメージも変わります。
―女性たちの加工調理技術や、消費者・生活者としての視点をJAがもっと活用しなければもったいないということですね。
JAの女性役員はどのくらいいますか。女性の組合長が一人もいないというのは驚きですね。漁協では、女性が組合長になり活躍している地域もあります。ただ、JAは本当に多様です。都市部や中山間地域、ちゃんとやっているところとそうでないところと、様々です。なので、ひとくちでこうだとは言えないところもありますが。
◆JAは本業の確立を
―輸出と6次化が必要だとの指摘もそうですが、JA自身が自己改革で掲げている農業者の所得増大、農業生産の拡大、地域の活性化の3つの目標も、前の2つは経済事業です。規制改革推進会議も、経済事業に専念すべきだとしており、地域の視点が薄いように感じますが、どうでしょうか。
営農経済事業と地域政策は、どちらが大事かという問題ではなく、地域をよくするには、本業である営農経済事業をしっかりさせないと大変だよということです。いまその本業が大変なことになっているということです。
自民党が農協をいじめているとの指摘がありますよね(笑)。しかし、いま農協をいじめて自民党になんの得があるんですか。いま農業も農協も大変な局面にあるから改革が必要だということでやっているんです。米の生産調整もそうです。多用途米や飼料稲で需給調整しないと、人口が減る中でこれまでの生産調整を続けたらどこかで行き詰まり、価格の低下を招きます。そうなる前に手を打つということです。
―その飼料用米ですが、現場では水田活用の直接支払交付金がいつまで続くのか、不安の声が聞かれますが。
その点は心配しなくてもいいでしょう。財務省は渋っていても、飼料用米への誘導策こそが水田を守り、農業所得を守る唯一の方策だと確信しています。なので、農水省は不退転でこの予算を確保しますし、自民党も全力を上げます。将来のためにはEU型の直接所得補償の拡大が必要との意見もありますが、人口減少が激しい日本とEUとでは条件がちがい、日本の現状にはそぐわないと思います。
◆積極的に農地活用を
―最近、農村部では、いわゆる田園回帰で、田舎で暮したいという若い人が増えています。地域おこし協力隊の希望者も多く、任期の3年が終わっても残る隊員が6割います。それも農業専業ではなく、小さな起業をしながら農業も行う兼業・多業タイプです。新しい農のスタイルで、長野県の「一人多役」型の社会づくり、島根県の「半農半X」型などいろいろありますが、そうした動きとJAが連携できないのかなと思います。
なるほど、農の新たなスタイルとして大事なことです。兼業あるいは副業型でも、農地を有効活用することはよいことだと思います。この点では地方自治体が頑張っているように思います。JAも農地の有効活用のためにも積極的に取り組んでいただきたい。
―輸出について、中山間地域の農業では、実現性に否定的な声も多いと思いますが。
すぐに輸出といわれると難しいかもしれません。ただ、日本を訪れる海外観光客に農産物をPRすることが、輸出振興にも貢献すると思います。たとえば、日本の農産物の最大の輸出相手国は香港ですが、750万人の人口のうち、毎年のべ約220万人が日本を訪れます。彼らは日本で素晴らしい食を味わいます。お米や和牛、ブドウのシャインマスカットやイチゴなどは大変な人気です。それが香港国内での日本の農産物の人気と輸出拡大にながっていると私は見ています。来年はオリンピックで4000万人が訪日すると予測されています。このインバウンドを日本食のPRに活用しない手はないでしょう。
◆輸出の主力は農産物
―輸出への取り組みではそのような食品や輸出業者などとの連携が不十分ではないでしょうか。
輸出拡大をみんなで取り組む雰囲気づくりが必要です。それができると地域振興にもつながると思います。JAも応援する雰囲気を全国でつくってほしい。10年後の輸出を考えてみると、家電はもとより自動車、鉄鋼、ITと、今以上に輸出を伸ばせるか心もとない。農業は違います。必ず大きく輸出を伸ばしています。だから、農業は成長産業なんです。そうは言っても輸出ができる日本の農家は極めて限られています。でもそういう農家が増えれば、輸出できない農家にも大いなるメリットがあるのです。国内のライバルが減り、需要が締まるわけですから。そうした努力のできる農協であっていただきたい。農業はいま真に曲がり角にあるだけに、変革へのチャンスでもあるといえるのではないでしょうか。
インタビューを終えて

森山・齋藤両氏の話を聞き、改めて今回のJA改革に対する〝風圧〟は「経済事業」に限られた話で、JAの社会インフラとしての役割への評価や今後への期待は共通していると確認した。「農業は生活そのもの。まずは地方創生」という森山氏と「経済事業改革あっての地域政策」という斎藤氏の意見は、相反するようだが、結局は、地域政策と産業政策のバランスをどうとるか、農政もJAも問われているということだ。
もうひとつ注目したいのが「連携」という視点。平野部も中山間地も農家人口が約2割と混住化が進む中、地域づくりには、准組合員である地域住民はもちろん、行政を含めJA以外の組織との連携が重要になる。地域とどう向き合うかという点もJAの今後の課題と感じた。
(榊田みどり)
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日
【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -
 米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日
米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日 -
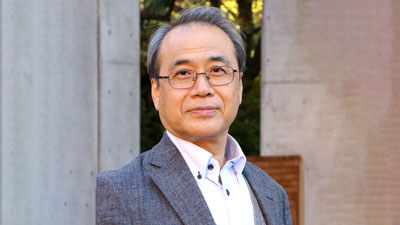 【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日
【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -
 米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日
米の品薄状況、備蓄米放出などコラムで記述 農業白書2025年4月22日 -
 農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日
農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -
 備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日
備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -
 新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日
新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -
 JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日
JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -
 米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日
米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日 -
 農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日
農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -
 「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日
「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -
 「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日
「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -
 千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日
千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日 -
 【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日
【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日 -
 香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日
香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -
 京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日
京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -
 愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日
愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -
 リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日
リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日

































































