JAの活動:今、始まるJA新時代 拓こう 協同の力で
【ホクレンの100年-1】食料基地・北海道農業を支え農と食の未来を担う(命と暮らしと地域を守る農業協同組合の戦い・歴史が証言する)2019年10月10日
1919(大正8)年、ホクレン(ホクレン農業協組合連合会)が発足して、今年で100年目を迎えた。食料自給率が世界の先進諸国で最低の37%にまで落ち込んだ今日の日本で、約200%の自給率を維持している北海道は、まさに「日本の食料基地」と呼ぶにふさわしい。それを支えているのは北海道の生産者、JAとともに、「農と食の未来を担う」の経営理念のもと、食料基地を維持・発展させているホクレンの力に負うところが大きい。その歴史を踏まえ果たしてきた役割を見る。
 広大な農地で可能性を秘めた北海道の農業
広大な農地で可能性を秘めた北海道の農業
◆規模拡大が進む
今年の8月、ホクレンは東京都内で記者会見を開き、創立100周年をアピールした。内田和幸・代表理事会長は、今年の北海道産の農産物の生育が順調であることを報告し、「100周年を機に、『つくる人を幸せに 食べる人を笑顔に』のスローガンのもと、国民の信頼に応えていきたい」と、食料基地をめざすホクレンの意気込みを示した。
この自信には北海道の農業の力の裏付けがある。北海道の耕地面積115万ha(2017年)で全国の26%を占め、販売農家戸数は3万6000戸で3%だが、農業産出額は1兆3000億円で13%のシェアを持つ。販売額で全国の半分以上のシェアを持つ品目は小麦67%、バレイショ80%、小豆93%、てん菜100%、タマネギ65%、生乳54%となっており、ほかにカボチャ、スイートコーン、ニンジンなども国内シェアの四分の一から三分の一を占める主要な品目となっている。



遠隔地のハンディをバネに ホクレンの意気を示すポスター
◆「報徳」の思想で
北海道の農業は規模拡大が進んでおり、農家一戸あたりの耕地面積は年々増加している。農業経営体(経営耕地面積30a以上)の平均は、2018年で29ha。都府県の約13倍で、2010年に比べ5ha以上増えている。
これは、「高齢化や後継者の確保ができなくなった農家が、仲間に農地を貸して離農するケースが多いため」(板東寛之・ホクレン専務)という背景がある。この結果、耕作放棄地も少なく、全国が9%に対して北海道は2%にとどまっている。
北海道の農業は1869(明治2)年、開拓使が設置され、蝦夷地を「北海道」と命名され、屯田兵や移住者の入植によって始まった。厳しい自然環境で、想像を絶する苦労のなか、1897(明治30)年には、二宮尊親(二宮尊德の嫡孫)が福島県相馬の人たち160戸を連れて十勝に入植。「100戸のうち1戸でも脱落すれば、それは残り99戸の責任である」と説き、二宮尊德の「報徳思想」に基づく相互扶助の精神を涵養した。
第1次世界大戦(1914~18年)後、世界的な不況で北海道も大きな影響を受け、北海道庁はその対策に報徳思想の普及を図った。ホクレンはそうした時代背景のもとに誕生した。設立当初は出資が少なかったうえに、認識不足もあって利用度が上がらず、一時的に事業を休止することもあったが、創立から6年後の1925(大正15)年には、地域によって価格・品質に大きな差があった肥料を、メーカーから直接購入することで全道の価格を統一し、品質のよい品物を安く供給。これが契機になって加入組合が増え、事業を拡大した。
◆ハッカ工場から
1931(昭和6)年には、米、でんぷん、ハッカなどで共同計算を採用。穀物類、鶏卵、タマネギ、除虫菊、ナタネ、デンプンなどに拡大した。ハッカは世界市場をリードするほどの生産量を誇ったが、生産者の手取りは少なかった。生産者の収入確保のためには、自ら加工工場をつくって販売する必要があり、こうした生産者の要望に応じて1934(昭和9年)年、ハッカ工場の操業を始めた。これが、ホクレンの最初に手掛けた農産加工事業となった。
その後、相次いで飼料配合工場、精米工場、製糖工場などを建設し、今日のホクレンが展開する主要な事業モデルとなった(年表参照)。特に1967(昭和42)年、当時ホクレンの専務だった太田寛一(のちに会長)が「酪農民のためには農民工場の建設が欠かせない」と考え、十勝の農協とともに設立した北海道協同乳業の設立などへとつながる。
ホクレン創立をリードしたのは、北海道報徳社の創立に尽力した当時の峰延信用購買販売協同組合の小林篤一組合長で、「農村の窮乏は産業組合によって救うべきである」と主張し、経済と道徳の一致による豊かな農村づくりをめざした。その思想は、現在の北海道のJAやホクレンに連綿と引き継がれている。

(写真)総合力フル活用で営農支援
◆運転手が不足に
北海道は大きな消費地に遠いことから、農業は農産物の加工・調整、貯蔵による販売に主力を置いてきた。一方で、北海道独自の輸送問題がある。現在、北海道の農畜産物は一日当たり約1万tを都府県に移出しているが、大型トラックのドライバー不足が深刻になっている。
2015年の調べで、道産農畜産物の道外移出は350万t。うち258万tがホクレンの取り扱いで、内訳は32%がJR貨物、47%がフェリー、19%が船舶・不定期船となっている。
問題は新幹線の高速化に伴って、貨物列車が青函トンネルなどの共用区間を通れなくなる恐れのあるJR貨物輸送にある。
民間研究所の試算によると、代替の船やトラックのドライバーが確保できなかった場合の農産物の損失は1500億円に達するという。北海道農業には、JR貨物輸送が欠かせない理由がある。かつて鉄道輸送が主力だったことから、特に量の多い青果物を扱う青果市場は貨物駅と近接しており、陸上輸送距離が短い。
また海上輸送は航路が限られており、港までの陸上輸送コストが増え、さらに陸上輸送に切り替える場合、トラックドライバーの確保が難しい。やはり民間研究所によると、北海道内で新たに700人、道外で1550人のドライバーが必要になると試算する。ホクレンは「JR貨物と新幹線の共用走行が維持されることが必要」と訴えている。

(写真)ドライバー不足に備えトラックの自走実証試験
◆ICT農業で
もう一つ北海道農業にとって大きな課題は、農業労働力の確保にある。ホクレンの内田会長は、「これまで消費ニーズに対応してきた北海道農業の方向と矛盾する」と言う。労働力不足は、機械化が可能で比較的労働力が少なくて済む耕種部門に戻ることを意味する。既にその傾向が見えており、手間のかかる園芸・野菜栽培の維持が難しくなる恐れがある。
そこでホクレンはいま、GPS(地理情報システム)やドローンなどICTを使った作業軽減の技術の開発・普及に力を入れている。GPS搭載の自動操舵トラクターや農業用ドローンの活用であり、スマート農業についての実証試験にも取り組んでいる。

重要な記事
最新の記事
-
 米農家(個人経営体)の「時給」63円 23年、農業経営統計調査(確報)から試算 所得補償の必要性示唆2025年4月2日
米農家(個人経営体)の「時給」63円 23年、農業経営統計調査(確報)から試算 所得補償の必要性示唆2025年4月2日 -
 移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日
移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日 -
 移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日
移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日 -
 JAみやざき 中央会、信連、経済連を統合 4月1日2025年4月2日
JAみやざき 中央会、信連、経済連を統合 4月1日2025年4月2日 -
 サステナブルな取組を発信「第2回みどり戦略学生チャレンジ」参加登録開始 農水省2025年4月2日
サステナブルな取組を発信「第2回みどり戦略学生チャレンジ」参加登録開始 農水省2025年4月2日 -
 JA全農×不二家「ニッポンエール パレッティエ(レモンタルト)」新発売2025年4月2日
JA全農×不二家「ニッポンエール パレッティエ(レモンタルト)」新発売2025年4月2日 -
 【役員人事】農林中金全共連アセットマネジメント(4月1日付)2025年4月2日
【役員人事】農林中金全共連アセットマネジメント(4月1日付)2025年4月2日 -
 【人事異動】JA全中(4月1日付)2025年4月2日
【人事異動】JA全中(4月1日付)2025年4月2日 -
 外食市場調査2月度 市場規模は2939億円 2か月連続で9割台に回復2025年4月2日
外食市場調査2月度 市場規模は2939億円 2か月連続で9割台に回復2025年4月2日 -
 JAグループによる起業家育成プログラム「GROW&BLOOM」第2期募集開始 あぐラボ2025年4月2日
JAグループによる起業家育成プログラム「GROW&BLOOM」第2期募集開始 あぐラボ2025年4月2日 -
 2025年クボタグループ入社式を開催2025年4月2日
2025年クボタグループ入社式を開催2025年4月2日 -
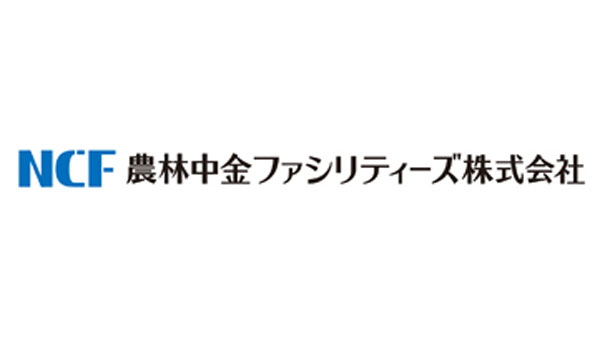 【役員人事】農林中金ファシリティーズ(4月1日付)2025年4月2日
【役員人事】農林中金ファシリティーズ(4月1日付)2025年4月2日 -
 【役員人事】PayPay証券(4月1日付)2025年4月2日
【役員人事】PayPay証券(4月1日付)2025年4月2日 -
 【人事異動】ヤンマーホールディングス(4月1日付)2025年4月2日
【人事異動】ヤンマーホールディングス(4月1日付)2025年4月2日 -
 【人事異動】コメリ(4月1日付)2025年4月2日
【人事異動】コメリ(4月1日付)2025年4月2日 -
 鳥インフル 英カンブリア州など3州からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年4月2日
鳥インフル 英カンブリア州など3州からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2025年4月2日 -
 片倉コープアグリ アクプランタと協業 高温・乾燥対策資材「スキーポン」を全国展開2025年4月2日
片倉コープアグリ アクプランタと協業 高温・乾燥対策資材「スキーポン」を全国展開2025年4月2日 -
 頭の体操「ゆっくり健康マージャン」宮前センターで初開催 パルシステム神奈川2025年4月2日
頭の体操「ゆっくり健康マージャン」宮前センターで初開催 パルシステム神奈川2025年4月2日 -
 鹿児島県志布志市へ企業版ふるさと納税 1100万円など寄附 渡辺パイプ2025年4月2日
鹿児島県志布志市へ企業版ふるさと納税 1100万円など寄附 渡辺パイプ2025年4月2日 -
 JA埼玉中央「農業従事者専用ローン商品」取り扱い開始 オリコ2025年4月2日
JA埼玉中央「農業従事者専用ローン商品」取り扱い開始 オリコ2025年4月2日






























































