JAの活動:負けるな! コロナ禍 今始まる! 持続可能な社会をめざして
末松広行農林水産事務次官 国内生産で食の安定供給(聞き手・姉歯曉駒澤大学教授)【負けるな! コロナ禍 今始まる! 持続可能な社会をめざして】2020年7月8日
3月に閣議決定した食料・農業・農村基本計画は中小経営や家族経営を含めた地域全体での農業生産の維持、発展と農村の活性化を打ち出した。新型コロナウイルス感染症の広がりを受けて、国民には自国の食料生産の確保に関心が高まってきた。今後の農政をどう考えるか。末松広行事務次官に聞いた。
 末松広行農林水産事務次官
末松広行農林水産事務次官
◆輸入ストップが現実味
姉歯 農業そのものの衰退の問題や、自給率をどう向上させるかといったコロナ禍以前から日本農業は多くの問題を抱えていますが、今日はコロナ後、もしくはコロナとの共生を見据えて、今後の日本の農業についての大きなビジョンを次官からお聞かせいただきたいと思います。
末松 今回のコロナ禍は農業が国民に対して食料を供給するという重要な役割を果たしていることを実感してもらう機会にもなったと思います。
日本は食料自給率がカロリーベースで37%まで下がり、われわれは63%を外国に依存しているわけです。しかし、今までは輸入が止まることなどないという前提で多くの国民は生活していたと思いますが、輸入が止まるかもしれないという事態にもなりました。食料安全保障は国内生産と備蓄と安定的な輸入を組み合わせるということですが、安定的な輸入も難しくなる事態もありえることから国内生産が大切だということが実感されたと思います。
ただ、2007年から08年にかけての食料危機との違いを冷静に分析すると、世界の穀物の期末在庫率は07年ごろは17%というぎりぎりの水準でしたが、現在は32%と世界全体でみれば穀物の在庫はあるという状況です。それから前回は石油価格が高騰し、エタノール原料に仕向けられるトウモロコシの価格が上がるという状況がありましたが、今回は石油価格が低迷していますから、エタノールの需要も落ちました。その意味では今回は2008年にくらべると落ち着いていると思います。
しかし、輸入は止まることがあり得るということを再認識させられたというのは非常に大きなことです。そこでわれわれは何をしなければいけないかということですが、今回は2つ意を用いたことがあります。
1つはやはり穀物をきちんと確保していくことです。米については備蓄がありますが、小麦など輸入しているものは、これからの必要量をきちんと輸入していく、あるいは輸入を多角化してしっかり確保するといったことです。
もう1つは緊急事態宣言が発出される前後、量販店から米がなくなったことがありましたが、卸業界に努力をお願いして店頭に並べてもらいました。そのほか小麦粉、冷凍うどん、パスタや即席麺などの製品がなくなることが予想されたので5月の連休中も生産を続けてもらいました。日本への輸入だけでなく国内への流通へも手厚く対応することで、国民のみなさんに大きな心配をさせることなく対応できたと思っています。
農林水産省の所管は食料ですから、きちんと供給しなければいけないという意識があって、そこは割とうまくいったと思っています。われわれは農家の所得を上げるということももちろん大切ですが、食料の安定供給がもっとも大切でそこはがんばったつもりです。
◆作り続ける体制を
末松 こういう状況のなか、3月末に食料・農業・農村基本計画を閣議決定しました。これは今後10年を見据えた5年間の農政の方向を示したものです。新たな基本計画においては、これまでどおり、農業の産業としての強さを追求していきますが、同時に農業者は地域を守っているということから、そこを重視し地域政策と産業政策は車の両輪だということを改めてきちんと打ち出しました。
これは江藤大臣のお考えもあって、やはり村のなかに強い農家が2軒だけあるというようなことではなく、小規模農家も含めてみんなが村にいて、かつその人たちが食べていけるようにすることが大切だという発想をしていくということです。
日本の農業はこれからも大切なのは間違いないですし、これは農家のためということではなくて、日本の国民全体のために、いざという時のためにもきちんと国内生産があることが大切だということです。地味ですがひたすら大切なことを続けていくということです。
姉歯 今回、コロナ禍にあっても、食料についてはあまり不安を抱かずに過ごすことができたのは他の国にくらべるとかなり成功したと思っています。国民の側でも諸外国からの物流が滞ったときに自国で食料が調達できることがどれほど大切なことかに改めて気づいたと思いますが、輸入が回復していったのち、喉元過ぎればということにならないように、どうこの経験を生かしていくかが課題だと思います。
末松 食料が大切だということと、そのためには日本の農業がしっかりしてもらうためにも国産のものを食べるという発想になっていただきたいという課題はありますね。
一方で今回、明らかになったことの1つに、農林水産業は旅行業と違って、人の胃袋は決まっていますから消費量はそんなに変わらず、インバウンドの部分が減ったということでした。ただし、ミスマッチは非常に出てきて、たとえば、高級品の牛肉が売れないといった事態になりました。そのほか東京都内では学校給食用に作っていた小松菜がまったく売れなくなったなどです。
長い目で考えたときには、農業においても需要に合わせて生産しなければならないと思います。米をあまり食べなくなっていたら、食べる量に合わせて生産し、他のものを作るなど、日本人が食べるものを生産していくように変えていくことが必要です。しかし、今回はそうではなくコロナ禍によって突発的に需要がなくなったということですから、需要は戻るという前提で生産基盤を維持することが必要で、そのために最大限の支援をしていいと思っています。今回、生産を続けるための支援はかなり思い切って出しています。そのなかで下がった花や牛肉の価格も少し持ち直してきていますから、そこはもう一度、需要が戻ったときに、牛肉であれば輸出やインバウンドに向けて生産を残し、小松菜も生産をやめてしまうのではなくて学校給食が再開したときのために作り続けるといったことが大切です。
他の産業と違い、一度工場を止めてしばらくしてから生産を戻すということは簡単にできませんから、作り続けるということを大切にしたいと思っています。
◆地域を守る人々を重視
姉歯 これまでは国の長期的な政策としては、農業はできるだけ少数の強力な担い手に集中して、小さな零細農家は淘汰されていくべきとの方向性が採られていましたが、今後についてはいかがでしょうか。
末松 農政の議論で、産業競争力のある農家とそれ以外の農家をどのように扱うかということについて、これからは規模を大きくして競争力のある農家を育てなくてはいけないということをずっと言っていました。すべての農家を一律に扱うことが難しくなっていくなかで、強い農家を育てるということは非常に大切だったと思います。
もちろん今もそれが求められる情勢はあると思いますが、地域というのはいろいろな方がいてコミュニティをつくっているわけです。いろいろな方々がそれぞれの特性を生かして地域を支えていくというのは大切ですから、地域政策と産業政策のいわば間の政策といったものがこれから非常に大切になってくると思います。
たとえば半分農業をして、半分はスキーのインストラクターでもいいと思いますし、6次産業化についてもいろいろなやり方があり、そこに価値もあるのではないでしょうか。女性と6次産業化については、女性が経営に参画して6次産業化に取り組んでいる農家や農業生産法人と、男性だけで経営している場合をくらべると女性が参画しているほうがうまくいっているという事実もあります。
姉歯 一方で農村にいる女性にもいろいろな出自があって、起業しようと思って農家とまったく関係のないところから農業、農村に入ってきた人もいますし、親の後を継いでなんとかやっていかなければ、という女性もいます。また典型的ですが結婚相手が農家の人だったのでという女性もいます。
みなそれぞれ農業に足を踏み入れる時には意欲はあるのですが、その意欲が削がれてしまうような農村の実態があります。また、インフラの圧倒的な不足と人口減少のサイクルを断ち切れない実態もあります。自分たちの子どもたちがみな農村から出て行ってしまうような生きづらい状況をそのままにして、村外から移住者を呼び込むというのは非常に難しいのが実態です。
しかし、本当はこれからの日本経済の将来を考えても、農村の存在は食料生産以外でも必要だと思うのです。私は新型コロナが発生する直前に中国の武漢大学の研究者たちと武漢郊外の農村調査を行っていました。中国では今、かつて都市部に出てきた労働者たちが都市部の人手が余るようになって行き場を失いつつあります。そんな中、退職後に都市部の住民が帰る先として農村機能を維持するべきだとの声をさまざまな場所で耳にしました。日本でも産業としての農村機能を残しておかなければいけないのではないかと思います。そのことを考えると起業できる若い女性の力を生かすだけでなく、今現在農村に暮らして、農村機能を実質的に担っている幅広い年齢層の女性たち全体の地位をどう上げていくかがかなり重要だと思います。
◆暮らしやすい環境を
末松 農村ではまだまだ男性社会でいろいろな役職や活躍する場所に女性が出ていきづらいということや、家事労働の負担など課題が多く、そこはずっと生活改善運動などに取り組んできましたが、まだまだ足りないところがあると思います。そこはこれからもきちんとやっていかなくてはなりません。
とくにコロナ禍で密を避けなければいけないとなると、人が散らばっていたほうがいいという時代に間違いなくなります。そのときに、戻った農村が実際にはインフラが整っていなかったり、女性が働きやすい環境になっていないという課題がまだ残っているので、何が問題かをしっかり見て政策を打っていくことが大事だと思っています。
これからは情報も含めたインフラを整備するということや、閉鎖的になっている農村の空気を打破するために、新規就農の支援が政策として大事だと思っています。現在は最長5年支援することになっていますが、そうした支援をして新規就農者が農業を中心に活躍して、そこに以前から住んでいる高齢の方から若い人まで地域を元気にしていくということはぜひ進めたいと考えています。
姉歯 自給率1%の東京に暮らす不安定さや、密でいることのリスクを、今回強く実感しました。都会では田舎にいる人たちがうらやましいと思った人たちも多かったので、そういう人たちの移住もこれから増えていくのではないかと思います。
末松 これからも国という拠点をもって海外と貿易することは大切ですが、グローバリーゼーションのもと国をなくして全部を一緒にしてしまうというのは非常にリスクがあるということが分かったはずですし、これからも貿易はしますが、足りないものを交換し合い、協力し合うという国際関係をつくっていかなければならないと思います。
日本はもう少し地域や国内の生産ということを考えていかなくてはいけないということで、今回、基本計画でもそこに重点を置いたわけですが、コロナ禍はこうした考え方の正しさを示していると思います。もちろんまだまだ効率化しなくてはいけない農業経営の課題もあり、改革に取り組んでもらうべき問題もありますが、効率一辺倒ではないということです。
姉歯 農協組織に対してどのような役割を期待されますか。
末松 地域の農業を振興するということは地域経済を回すということだと思います。金融事業で利益を農協として得るよりも、地域でお金が回っていろいろな関係業界の人が生活できるわけです。農協は地域に根ざすということと、基本的には販売を本気でやるということは大切だと思います。最近は優良事例を表彰したりして応援する取り組みもしていますが、そこはぜひ伸ばしてもらえたらいいと思います。
姉歯 ありがとうございました。
 姉歯曉駒澤大学教授
姉歯曉駒澤大学教授
【インタビューを終えて】
コロナ禍で「密」が避けられる農村の重要性が再認識されている。農村の再生には交通手段などのインフラ整備が必要だが、そんなことを言ってみたところで官僚は聞く耳を持たない......、そう思っていた私には末松事務次官の言葉は衝撃的だった。コロナ禍にあって食料の安定供給策を次々と打ち出し、自給率が大切だと語り、小規模農家も含めて多様な人々が構成するコミュニティを守るべきと語る末松事務次官に久しぶりに官僚の心意気を感じて嬉しくなった。(姉歯)
重要な記事
最新の記事
-
 【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日
【注意報】小麦、大麦に赤かび病 県内全域で多発のおそれ 滋賀県2025年4月22日 -
 米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日
米の海外依存 「国益なのか、国民全体で考えて」江藤農相 米輸入拡大に反対2025年4月22日 -
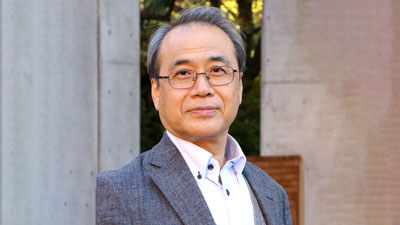 【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日
【地域を診る】トランプ関税不況から地域を守る途 食と農の循環が肝 京都橘大学学長 岡田知弘氏2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(1)2025年4月22日 -
 JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日
JA全中教育部・ミライ共創プロジェクト 子育て、災害、農業のチームが事業構想を発表(2)2025年4月22日 -
 農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日
農産品の輸出減で国内値崩れも 自民党が対策提言へ2025年4月22日 -
 備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日
備蓄米売却要領改正で小売店がストレス解消?【熊野孝文・米マーケット情報】2025年4月22日 -
 新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日
新入職員が選果作業を体験 JA熊本市2025年4月22日 -
 JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日
JA福岡京築のスイートコーン「京築の恵み」特価で販売中 JAタウン2025年4月22日 -
 米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日
米の木徳神糧が業績予想修正 売上100億円増の1650億円2025年4月22日 -
 農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日
農業×エンタメの新提案!「農機具王」茨城店に「農機具ガチャ自販機」 5月末からは栃木店に移動 リンク2025年4月22日 -
 「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日
「沸騰する地球で農業はできるのか?」 アクプランタの金CEOが東大で講演2025年4月22日 -
 「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日
「ホテルークリッシュ豊橋」で春の美食祭り開催 東三河地域の農産物の魅力を発信 サーラ不動産2025年4月22日 -
 千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日
千葉県柏市で「米作り体験会」を実施 収穫米の一部をフードパントリーに寄付 パソナグループ2025年4月22日 -
 【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日
【人事異動】杉本商事(6月18日付)2025年4月22日 -
 香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日
香川県善通寺市と開発 はだか麦の新品種「善通寺2024」出願公表 農研機構2025年4月22日 -
 京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日
京都府亀岡市と包括連携協定 食育、農業振興など幅広い分野で連携 東洋ライス2025年4月22日 -
 愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日
愛媛・八幡浜から産地直送 特別メニューの限定フェア「あふ食堂」などで開催2025年4月22日 -
 リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日
リサイクル原料の宅配用保冷容器を導入 年間約339トンのプラ削減へ コープデリ2025年4月22日 -
 【役員人事】カインズ(4月21日付)2025年4月22日
【役員人事】カインズ(4月21日付)2025年4月22日

































































