JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合
農業・農村の難局打開へ 個性的な地域JAの役割大きい 生源寺眞一氏に聞く【消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合】2023年9月28日
食料・農業・農村基本法の見直し具体化など農政が転換期を迎える中で、審議会会長など長く国の農政論議に関わってきた生源寺眞一・前福島大学食農学類長(日本農業研究所研究員)がインタビューに応じた。基本法見直しで多様な農業人材の明記を評価しつつ、現代社会を「成長」から「成熟」への転換ととらえ、改めて持続可能な農業・農村の存在価値を基本に据えるべきだとした。協同組合としての地域JAの役割発揮にも期待した。(聞き手は農政ジャーナリスト・伊本克宜)
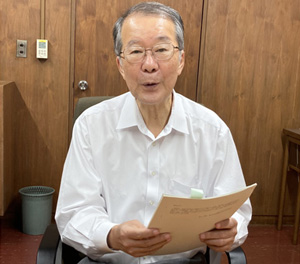 生源寺眞一・前福島大学食農学類長
生源寺眞一・前福島大学食農学類長
食料問題に国民的関心は好機
――農業生産基盤が音を立て崩れ、持続的な農業が危機的状況です。現状をどう見ますか。
ウクライナ問題もあり生産資材の高止まりなど、厳しい状況が続く。農業者の減少も目立つ。今後とも政府が機動的に支援措置を打つことが欠かせない。同時に農政を当面の緊急対応と中・長期の二つで分けて冷静に考える必要がある。
中・長期のトレンドは、少子高齢化の加速が特に地方で顕著だという点だ。為替相場も、高齢化社会の中で日本の国際的地位が徐々に下がっていくことを考えれば、国力を反映し円安が続くと見た方がいい。足りなければ輸入で補う構図は崩れる。生産資材や飼料もできる限り国内で確保することが問われる。
重要なのは、取り巻く環境変化の現状認識だ。農政改革、市場開放を進めた安倍政権は、農業を「成長」という視点のみでとらえ官邸主導で強引に変えようとした。だが日本社会の状況は、明らかに「成長」から「成熟」の時代に変わった。成熟社会を踏まえた持続可能な農業・農村の在り方こそが問われる。ウクライナ紛争を引き金に、食料問題に国民的関心が高まっている。これを好機ととらえ、持続可能な農業構築に結び付けたい。
「不測時の食料安保」は充実
――食料と農業を取り巻く環境急変の中で、現行基本法見直しの最終答申が出ました。どう評価しますか。
検証部会と名称をつけながら、過去の農政の検証が不十分だ。特に「官邸農政」と言われた2015年前後の農協改革、その後の酪農制度改革などは典型だ。農政の在り方を本来議論する場である食料・農業・農村政策審議会とは全く関係ない形で、急進的な改革が議論された。私が審議会会長だった2017年3月、農水省から一連の農政改革の報告があっただけだ。これでは事後報告で審議会軽視ではないか。そういった趣旨の苦情を申し上げた。当時の農水省幹部、例えば総括審議官、官房長を務めた荒川隆氏なども一連の農政改革に疑問を呈しているほどだ。検証部会のメンバー人選も課題があったのではないか。これまでの農政議論に関わった人が多く、過去の農政を批判、否定できる立場にはならないだろう。
基本法見直しの内容は見るべき点と不十分な部分に分かれる。全体的には全てを食料安全保障でくくるのは無理がある。評価すべき点は、国民が食料問題に関心が高まっている中で「不測時の食料安全保障」を、国家としての法体系整備まで言及し書き込んだ点だ。
議論となった担い手問題は、従来の大規模化路線とともに多様な農業人材の活用も明記した点は評価できる。現行基本法は大規模、効率的な担い手育成の一方で、農業の多面的機能を掲げていることが重要だ。担い手特化の政策遂行を掲げたわけではない。
一方で農村政策は全くと言っていいほど内容がない。農村政策は今回のテーマではなかったということだろう。だが、持続可能な食料・農業・農村とうたってある以上、不十分さがある。
今回の基本法見直しを指して基本法3・0という識者もいる。旧基本法を基本法1・0、現行基本法を基本法2・0としてその比較での名称だが、違和感がある。部分改正にしかなっていないのではないか。
適正価格と経営対策セットで
――基本法見直しと絡め、適正な農産物価格形成に期待が高まっています。
地方公聴会でも適正な価格形成で活発な意見が出たと聞いている。現状のコスト高を販売価格に十分に反映できない中で、生産者側から「再生産」を前提とした適正価格の期待が高まるのは当然だろう。ただ実際の対応となると、業界、品目ごとに複雑な事情を抱え、そう簡単には実現しないだろう。適正な価格形成論議と同時に品目によっては経営安定対策強化もセットで必要となる。
一方で、コストを価格に反映すれば販売価格が上がり、家計負担が増え買えない消費者も出てくる。食品アクセス、貧困問題は別の視点で政府支援を考えないといけない。
――生乳取引は、ホクレンなど指定団体がある程度コスト反映の期中価格改定を実現しています。現在のJミルクによる脱脂粉乳過剰対策を踏襲し、国も含め関係者による「酪農基金」創設で危機打開の意見もあります。
生乳は生産者と乳業メーカーが飲用乳価交渉で激しい議論を展開しながらも、酪農生産基盤を守るという一点で協調する唯一の品目だ。生処双方の長い歴史の蓄積がある。米や野菜など他品目に当てはめるのは難しいかもしれない。需給緩和時の国、生産者、メーカーが拠出し合う「基金創設」は持続可能な酪農のセーフティーネット拡充の一つだ。
多様な農業者の共存に活路
――現在の地域、農村の難局打開には何が重要でしょうか。「新しい農本主義」なども唱えられてきました。
「半農半Ⅹ」も含め多様な農業者の共存が新たな可能性を生む。例えば新規就農者の中身に注目したい。新規就農者の半分以上は60歳以上だ。規模拡大に直結しなくても、地域の持続可能な農業の維持には貢献するはずだ。30代までの若手就農者を見ると親元就農は半分以下。逆に言えば外部から農業、農村に入ってきている。外部の目を生かし人材を新たな農業振興の糧にすべきだろう。外部から農業に入る人は、さまざまな職業を経験しているからこその販売戦略、アイデア、現在の閉塞感を突破する視点があるかもしれない。多様な農業人材の共存を活性化にどう生かすのかは、過疎化を防ぎ今後の地域再生へのカギを握る。
「農本主義」の史的展開と分析は重要だ。若い研究者でも取り組み「新しい農本主義」を探る動きがある。有機農業や環境問題とも絡む。ただ「主義」と断定してしまえば、賛同しない層を遠ざけるなど広がりを欠くのではないか。「農本思想」と呼ぶべきかもしれない。
農業と密接な「grow」
それよりも農業、農村の良さをもっと別の表現、アプローチで評価した方がいい。本来の農業、農村の持つ良さに注目し、改めてその価値を訴え国民的理解と支援を得るようにしたい。インバウンド需要でも、農村の良さを生かした観光戦略も必要だ。
基本法見直しでも明記したが、食品アクセス、貧困対策も大きな社会問題となる。ジニ係数が上がり、子どもの貧困問題は深刻だ。農水省ばかりでなく厚生労働省など他省庁との連携で対応を急ぐ必要がある。
英語で農業や作物、植物にも関係の深いgrow(グロウ)という言葉は本質を突くように思う。growは「育つ」という自動詞と「育てる」という他動詞の二つを持つ単語だ。作物、植物は自ら「育つ」が、人が介して「育てる」という両方の側面を持つ。名詞は「成長」を意味するgrowth(グロウス)。作物栽培を通じた食農教育は人としての「成長」につながる。そこには、自然、環境、命の尊さと密接に絡む農業と、それを育む持続可能な農村を維持する大切さがあるのではないか。
JAに地域の「まとめ役」期待
――基本法見直しで、地域発展へJAの役割と関係機関との連携強化が明記されました。来秋には第30回という区切りのJA全国大会もあります。
確かに現行法では、団体の「再編整備」のみ記されていた。国は、全中の一般社団化など一連の農協改革を経て一定の「再編」は済んだという認識ではないか。現在の難局突破に地域JAの役割が大きいのは言うまでもない。協同組合としての地域JAがそれぞれの組織の個性を出しながら、持続可能な地域農業を作っていくことが重要だ。
ただ、一律的な方針で動くのでは地域実態に合わなくなる。農業外からの若手新規就農者が多いと先述したが、JA自ら率先してそれらの人材を地域に取り込みながら全体の農業生産底上げを図っていけないか。JAは総合事業の強みを生かし、准組合員も含んだ農村社会全体のまとめ役を担って地域活性化の役割を果たしてもらいたい。
基本法見直しの中で、区切りの全国大会に注目が集まるだろう。ただ29回大会議案を読んでも課題と方向でさまざまな事案を盛り込みすぎて、重点が分かりにくい。地域JAが真に参考になるように、簡潔、メリハリをつけた方針を示した方がいい。
環境重視どう「見える化」
――今後の農政は「みどりの食料システム戦略」に沿い環境と生産性向上の同時進行が求められますね。
基本法見直しと「みどり戦略」との関連がいま一つ分かりにくい。ただ、一連の異常気象を踏まえると気候変動対応、地球温暖化対策、環境保全は待ったなしの喫緊課題だ。国は法案化した「みどり戦略」に沿い農業の環境保全と生産性向上を同時にやる方針だ。生産性向上技術は、農業者にとって増産やコスト低減など経済的インセンティブが明確でわかりやすい。一方で環境対応は収量が減る一方でコストがかかる逆のインセンティブが働く。やはり環境対応には国の助成、支援が欠かせない。
基本法見直しでは消費者の行動変容も取り上げた。それだけ、行動変容は難しいということでもあろう。農業者が環境保全にどう具体的に取り組んだかを消費者に分かりやすく「見える化」できるか。多少高くても、農業者が丹精した環境に優しい国産農畜産物を積極的に購入する消費者が全体の2割にでもなれば、「みどり戦略」も本格化するだろう。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日
シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -
 農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日
農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -
 1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日
1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -
 【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日
【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -
 静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日
静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -
 25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日
25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -
 (432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日
(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -
 【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日
【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -
 水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日
水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -
 長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日
長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -
 【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日
【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -
 【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日
【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -
 第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日
第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -
 【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日
【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -
 宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日
宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -
 静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日
静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -
 静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日
静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -
 システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日
システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -
 神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日
神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日






























































