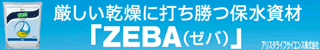JAの活動:消滅の危機!持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合
【提言】30年後の農協の姿検証を―食料・農業政策を福島から考える 福島大学食農学類教授 小山良太氏2023年11月6日
ロシアによるウクライナ侵攻やイスラエル・パレスチナ紛争など世界的な問題が浮上するなか、食料自給率が低く資源の多くを輸入に頼る日本の食料主権も切実な問題だ。持続可能な農業・農村の実現と農業協同組合はどうあるべきか、「農業・農村・農協のあり方を福島から考える」として福島大学食農学類教授の小山良太氏に寄稿してもらった。
デザインは復興論超え
1. 新たな産地形成とフードシステムの創造へ
 福島大学食農学類教授 小山良太氏
福島大学食農学類教授 小山良太氏
流通の効率化と消費の変化は、季節を問わず、同じ品質の農作物が日本では全国どこでも手に入ることを要求してきた。農作物の差別化や6次産業化による付加価値の増大が、競争の文脈として行われ、過度の「商品開発」に多くの労力が割かれる状況となっている。
原子力災害により後発産地としての位置づけに落ちた福島県農業は、不利な競争条件下に置かれており、通常の産地間競争にさらされる体力がない。特に営農再開途上にある浜通りの旧避難地域は深刻である。通常の市場競争とは異なる新たな生産、流通の仕組みを導入することが求められている。
原子力災害に対峙した福島県農業の教訓は、福島復興論を超えて、「これからの食料、農業政策はどうあるべきか」を提起する契機となった。すなわち、地域の資源を生かした個性豊かな食料循環(フードシステム)をデザインし、そこで生み出される農作物の新たな価値の評価を行うことで産地・地域同士の共存が可能な農業が構築できるのではないか。そこでは、①地域資源の空間特性(風土)→②産出農作物(持続可能な適地適作)→③食品市場(成分と機能)→④生活者の健康(消費行動)を一体のものとして捉え、詳細な組成分析と機能解析によって風土の違いに基づく農作物の特性(味、栄養・機能成分)を科学的に明らかにする必要がある。さらに、個々の農作物と消費者の嗜好(しこう)、健康とのマッチングを行うことで産地の個性を可視化することが可能となる。
2. 不確実な時代だからこそ地域内自給力の向上
震災の直後、福島県は米の一大産地にも関わらず、入手が困難な状況に直面した。福島県の米の自給率は約98%であるから、本来なら200万人の福島県民に全量供給できる計算になるが実際にはそうはならない。これが原料供給と広域流通に特化した産地の現実である。
新型コロナウイルスの流行におけるマスク問題やウクライナ紛争による物流の混乱でもわかるように、産消分離、広域流通に特化した構造はきわめてリスクが高い。そう考えると、今後は生産量に対し地域内での流通を一定割合確保する取り組みが重要になってくる。大半を広域流通に回したとしても、地域における食の安全が保障する仕組みとして地産地消、地消地産の取り組みが必要である。生産基盤がない都市部にたいし、地方では自分たちが消費し、生活で必要なものを自分たちで生産できるという仕組みは、不確実化が進む社会において、居住地選択の大きなアドバンテージとなる。
3. FEC自給圏の現段階的意義
グローバル化が進めば進むほど、災害や感染症、紛争のリスクは増していく。このような時代においては、人間が生きていくうえで欠かすことのできない食料やエネルギー、医療・福祉を一定程度自給でき、安全を確保できている地域づくりが必要である。経済評論家の内橋克人氏は、震災後の福島県において、地産地消ネットふくしまへの期待、エネルギーの転換、自給圏の創設について、原子力災害被災地だからこそできる、新しい社会・経済圏の可能性について言及していた。
FEC自給圏、食糧・食料(Foods)、エネルギー(Energy)、ケア(Care=医療・介護・福祉)を外部依存、中央依存の構造を打破し、新しい福島県の地域産業と社会構造を構築できないか、そこに協同組合組織の可能性があるのではないかという提言であった。
現在進行中のマネー資本主義、世界市場化という潮流に対抗するためには、F(食糧・食料)の自給圏創設が必要であり、それは地元産の農産物を域内で消費しようという直売所や地産地消運動を超えて、地域住民が地域農業の生産・流通・消費を支え合おうという姿勢にまで昇華されないと達成できない。
CSA(地域支援型農業)を本来の意味で導入するためには地域コミュニティーの理解が必要である。食料は人間が生きていくために必要不可欠な資源であり、輸入依存度の高い穀物類、家畜の肥料なども含め、食料主権に関わる資源を本当に自給する意志と覚悟が求められている。食料の安全保障は国のマクロ施策としても必要であるが、セミマクロ空間である各地域においても戦略的(地域計画として)に組み立てる努力が必要である。
E(エネルギー)に関しては、エネルギー資源の乏しい日本においてエネルギーの安全保障、リスク分散、国内生産の旗印の基、原発安全神話を進め、その結果、2011年の原発事故を起こしてしまった。その影響は12年が経過した現在にも及んでおり、廃炉、処理水問題は今後30~40年を要する。
福島県は再生可能エネルギー100%を政策目標に掲げているが、揺り戻しの動きも顕在化しつつある。ゼロ・エミッション、廃棄物ゼロ社会を目指すのであれば、協同組合間協同による発電、電力消費の切り替えなど、ビジネスモデルを超えた展開が必要である。
C(ケア)については、医療、介護、福祉の分野であり、地域生協、農協、労働者協同組合、医療生協、厚生病院など、地域の様々な協同組合組織が既に取り組んでいる分野である。地域共有の設備投資や地域間システムの創設が求められる。
内橋氏は、「被災地の復興というだけでなく、今の社会を覆いつつある市場原理至上主義的な流れに対し、人々の連帯と参加と共生によって自給圏を形成していく。そのような共通の理解や使命感を持って、人々が立ち上がっていく時代に入ったと思います」と締めくくっている。協同組合間協同により、いかに持続可能な仕組みを地域内で担保できるのかが問われている。
4.震災13年を向える福島県農業
東日本大震災・原子力災害から13年が経とうとしている。この間、復興庁の再編や、福島県産米全量全袋検査からモニタリング検査への転換が実施されたが、新たな産地形成に関する指針は明確ではない。この間の放射能汚染地域における風評被害状況および流通構造の変化を踏まえ、震災12年が経過した放射能汚染対策の総括とそれに基づく新たな産地形成の在り方を提示し、福島の産地において、既存の市場取引とは切り離した新しい生産構造と生産・流通システムを構築する必要がある。
自治体農政 在り方示し
福島県における原子力災害対策の成果は、①放射能汚染対策で培った土壌微生物や土壌成分の研究②放射性物質移行メカニズム研究により進められた作物の特性③全量全袋検査など広域検査体制により構築された安全性の担保と認証システム④健康への影響や配慮などである。これらを総合し風土の違いに基づく農作物の特性を証明し、新しい産地化へつなげることができないか。
まずは、震災12年の到達点を、農家、自治体、農業団体など関係者を交えて共通認識として確認することが必要だ。震災後実施されてきた放射能汚染対策、検査体制、風評流通対策の科学的根拠と到達点を確認し、新たな産地形成のための自治体農政のあり方を示す。30年後の日本農業の姿を見据えた農業団体・農協の機能と役割を検証することからはじめる必要がある。
【略歴】
こやま りょうた 1974年、東京都生まれ。1997年・北海道大学農学部卒、2002年・北海道大学大学院農学研究科博士課程修了。同年、博士(農学)学位取得。2005年より福島大学経済経営学類准教授。2014年同教授。2019年より食農学類教授。福島大学副学長補佐。現在に至る。東京大学大学院情報学環総合防災情報研究センター(CIDIR)客員教授、東日本大震災・原子力災害伝承館客員研究員、福島県地域漁業復興協議会委員、多核種除去設備等(ALPS)処理水の取扱いに関する小委員会委員(2020年まで)、日本学術会議連携会員。専門は農業経済学、地域政策論、協同組合学。主な著書、『福島に農林漁業をとり戻す』みすず書房2015年、『放射能汚染から食と農の再生を』家の光協会2012年など。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日
シンとんぼ(174)食料・農業・農村基本計画(16)食料自給率その他の食料安全保障の確保に関する目標2025年12月27日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(91)ビスグアニジン【防除学習帖】第330回2025年12月27日 -
 農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日
農薬の正しい使い方(64)生化学的選択性【今さら聞けない営農情報】第330回2025年12月27日 -
 世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日
世界が認めたイタリア料理【イタリア通信】2025年12月27日 -
 【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】キュウリ黒点根腐病 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日
【特殊報】ウメ、モモ、スモモにモモヒメヨコバイ 県内で初めて確認 高知県2025年12月26日 -
 【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】トマト黄化葉巻病 冬春トマト栽培地域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日
【注意報】イチゴにハダニ類 県内全域で多発のおそれ 熊本県2025年12月26日 -
 バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日
バイオマス発電使った大型植物工場行き詰まり 株式会社サラが民事再生 膨れるコスト、資金調達に課題2025年12月26日 -
 農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日
農業予算250億円増 2兆2956億円 構造転換予算は倍増2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(1)2025年12月26日 -
 米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日
米政策の温故知新 価格や流通秩序化 確固たる仕組みを JA全中元専務 冨士重夫氏(2)2025年12月26日 -
 米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日
米卸「鳥取県食」に特別清算命令 競争激化に米価が追い打ち 負債6.5億円2025年12月26日 -
 (467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日
(467)戦略:テロワール化が全てではない...【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月26日 -
 【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日
【スマート農業の風】(21)スマート農業を家族経営に生かす2025年12月26日 -
 JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日
JAなめがたしおさい・バイウィルと連携協定を締結 JA三井リース2025年12月26日 -
 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日
「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業」採択 高野冷凍・工場の省エネ対策を支援 JA三井リース2025年12月26日 -
 日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日
日本の農畜水産物を世界へ 投資先の輸出企業を紹介 アグリビジネス投資育成2025年12月26日 -
 石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日
石垣島で「生産」と「消費」から窒素負荷を見える化 国際農研×農研機構2025年12月26日 -
 【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日
【幹部人事および関係会社人事】井関農機(1月1日付)2025年12月26日