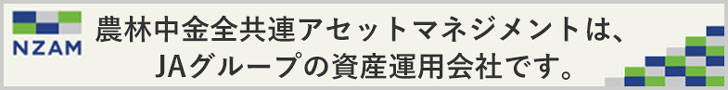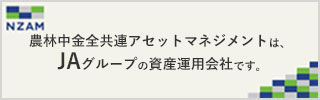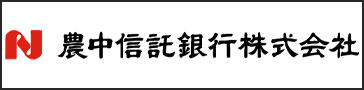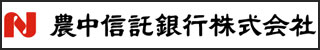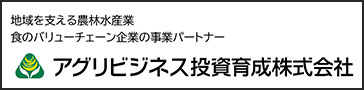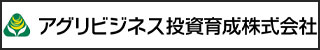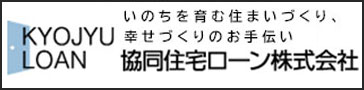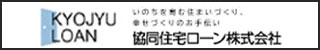JAの活動:【2024年新年特集】どうする食料・農業・農村・JA 踏み出せ!持続可能な経済・社会へ
【農林中金100周年】奥和登理事長に聞く 「農を支える土台に」② 農の「見える化」重要2024年1月9日
農林中央金庫が昨年12月に創立100年を迎えた。農村事情の変化とともに事業形態も変わりつつある。奥和登理事長に取り巻く情勢と課題など聞いた。聞き手はJA福島中央会最高顧問で前JA全中副会長の菅野孝志氏。
【農林中金100周年】奥和登理事長に聞く 「農を支える土台に」➀ 地域からの「いいね」追求 から
脱炭素意識 食でも大切
奥 ただ食べられればいいということであれば、エンゲル係数を落とした方がいいとなりますが、この食べ物にはどういう意味があるか、というレベルの対話が生産者と消費者の間でしっかりなされることが大切なことではないかと思います。私たちはこれだけの生産コストをかけて作っている、だから適正な価格で買ってくださいというだけではなく、生産者の手間や思いを分かってほしいと。JAグループをあげての「国消国産」の取組みは消費者に生産の現場を分かってもらうことでもあると思います。
 農林中央金庫 奥和登理事長
農林中央金庫 奥和登理事長
また、気候変動や脱炭素の取組みがとても重要だということについては、若者を中心に共通認識になりつつありますから、そういったことも意識した農法、農産物であるという価値に気づいてもらう。あるいはそれをきちんと発信していく。
海外から船で二酸化炭素を出しながら持ってきた食料や、あるいは海外で農地を収奪しながら生産した農産物を食べるのがいいのか、それともより身近な国内で作られ、輸送に二酸化炭素をより排出してないものを食べるのがいいのか、そういう価値観の話になる。そこが非常に大切だと思います。
菅野 今後はさらに担い手の育成が大事だと思いますが、農林中金としての担い手の支援についてはどのような取り組みをしていますか。
奥 まず農業をやってみようって思うような入り口づくりが大切で、さらにその志を持った人の農業を学ぼうという思いに対応する仕組みも大事です。
所得を上げるための要素としては、栽培管理、販売、労務管理などさまざまなものがあると思いますが、それを「見える化」することが大事で、日本農業経営大学校では、それらを盛り込むことができていると考えていますし、ウェブでも授業を受けることができるようになっています。
それからすでに農業を実践している人について、経営課題を分析して支援する担い手コンサルティングにも力を入れています。
家族農業ももちろん大切ですが、組織という面では、法人化してより働きやすい環境をつくることも重要で、そのためのサポートや、資金需要を金融のツールでサポートしていくということも私たちの役割だと思っています。
こうした取り組みを考えるには、役職員が農業の現場を感じないといけないということから、農協観光が行っている「JA援農支援隊」に金庫の役職員もボランティアで参加させてもらっています。これをある意味での運動にしながら職員が外に出ていく動機づけになればいいと、私自身も現場に出かけました。
菅野 どんなことを感じられましたか。
奥 中学ぐらいまで農作業をしていましたから、50年ぶりの農作業でしたが、非常に新鮮でした。農作業への没入感といいますか、すべてを忘れて作業をするという、人間の本来の部分を取り戻せた気もします。農業現場を感じたうえで業務をすることが大事だと思っています。
金庫の職員は机の上での仕事が多い。それを少しでも減らして現場や顧客、皆さまのところに行く時間を作るのが非常に大事だと思っています。そのために紙ベースの作業をどんどんデジタルに置き換え、行動できる時間を作っていくのが大切なのではないでしょうか。100周年がそのきっかけになればいいと思っています。
菅野 100年の歴史を経て新たな時代に向け、各会員、JAと一緒になって取り組もうという流れが一層深まったということですね。そのうえで今後、JAに対してどんな期待がありますか。
奥 ある組合長は、自治体や商業の関係者と、地域をどうやって元気にしていこうかと話をしていたら、実はみんなJAの組合員だったとおっしゃっていました。役所に勤めているが組合員、企業に勤めているが組合員、というように、地域ではJAと何らかの関係がきっとあるんだと思うんです。それは葉っぱでいう葉脈みたいなもので、地域とJAはいろいろな格好でつながっているということだと思います。
一方で、JA自身はその葉脈を意識する機会が必ずしも多くないのではないか、とも思っています。そういう関係性をもう一回浮かび上がらせたり、ある組織と組織をもう一回結びつけたりすることが、これからのJAに求められる非常に大きなことではないかと思います。
地域での営農支援活動は大切ですが、それと並ぶものとして、地域のなかでの関係の再発掘、再強化ということをやっていただくと、地域におけるJAの存在はより大きくなると思います。
菅野 私もみんなから、JAっていいね、と言われるような関係性を作っていくことだと思っています。地域のJAが総合事業を展開するにあたってこうした分野は大切だし、それができると本当に農林中金のめざす新たな金融仲介機能としての役割が発揮されることになるだろうと思います。
奥 仲介業というのは自分から仕事を取りにいくというよりは、まずは人と人との関係を掘り起こすことからだと思います。
たしかにJAの職員の数も限られるなかで、いろいろ議論する機会が少ないかもしれませんが、やはり自分たちの価値って何なんだと、ワイガヤしてみることは非常に大切ではないかと思います
菅野 基本的には職場は楽しくなければいけないと思います。しかし、ワイガヤが少なくなって、モクモクと仕事をすると逆に周りが見えなくなる問題があると思いますね。
さて、中期戦略のなかでの農業とくらしと地域、この三つの領域に関しての取り組み状況はいかがでしょうか。
奥 その三つは地域のなかで関連しており、農業はまさに先ほども話題になったように食料安全保障の観点から自給率を上げていくために、いかに農業者の所得を上げていくかをめざして、単に金融だけではなくて、販売なども含めてしっかりサポートしていこうということです。
一方でくらしの部分では、地域にお住まいの方は、組合員・非組合員に関わらず、金融サービスにどなたでもアクセスでき、JAはどなたにでも金融サービスを提供できるように、面としてくらしの機能を提供していこうということです。
三つ目の地域の部分は、これら二つが寄り添ったところをベースに、人がどう触れ合ったり、活動するかというということだと思いますので、人々が地域で何かイベントをやろうとしたり、あるいは部会活動なども活発にするといったことをサポートしていきたいという思いです。
エンジンは農業(金融・生産・所得)とくらしであり、地域の利用者からいかに信頼を預かっていくかというところにゴールを置いてやっていきたいと思っています。
最終的には、経営の見える化も含め、JAが地域の組合員、利用者から満足度といいますか、先ほど言われた「いいね!」がどれだけつくのか、という点も意識していくことが必要かもしれません。
菅野 やっぱりいいねJA、と言ってもらえるように頑張らなくてはいけないですね。
奥 それから先ほど言われたように、ワイガヤからモクモクになって他者を意識する機会が非常に減ったと思います。職場でも隣は何をしている人なのか、あの人はどう思っているかなど考えることが減ってしまうと、結局「いいね」を発信してもらえること自体も減るんですよ。ワイガヤは協同組織における定番中の定番ですし、そのように集まって話をする機会を提供できるのもJAならではかもしれない。
コロナ禍で気づいたことは、やはり私たちは会って語り合うことが大事なんだということです。そこを再認識していただけるといいと思います。
 前JA全中副会長 菅野孝志氏
前JA全中副会長 菅野孝志氏
菅野 今年は第30回JA全国大会があります。30回という区切りを迎えますし、国連は2025年を2回目となる国際協同組合年とすることを決めました。
奥 30回という大きな節目であるため、各JAが自分たちの地域における価値って何なのか、農業と地域と社会に自分たちはどういう価値を提供できるのか、ということを改めて追求することを強く望みます。
大会議案の構成でいえば食料・農業戦略やJAの経営基盤強化戦略などの各戦略の上に、JAグループの存在意義や創出する価値、協同組織の志を置き、これを夢も含めて語る、原点はそこだと思います。
同様に国際協同組合年については、協同組合とは人の助け合いの組織だとして、「今、何を助け合うのか」ということをもう一度問う必要があると思います。
農業者の協同組合とは、私の理解では、農業のおかれた厳しい状態のなかから、共同調達・共同販売していかに状況を良くするか、というところが原点だったと思いますが、この先はそれだけではなく、集っている人のウェルビーイング、幸せを追求する、あるいはそうでないところを少しでも改善していく、そのための助け合いの組織へともう一段上がることが求められていると思います。経済活動だけではなくて心の活動のところへ一段上がっていく。それが協同組織の価値になってくるのではないかと思っています。農福連携がその例ですが、ハンディキャップを持つ方も農作業を通じて生きがいを感じてもらうということや、都市生活者の心の充足はやはり自然に触れないとなかなか取り戻せないところもありますから、その点での心の充足を果たす役割もあると思います。
菅野 たしかに地域のなかで自分たちは何なのかと掘り下げて考えたことはあまりなかったと思います。新たな時代に向けて自分たちの存在を掘り下げる。大事な時期に来ていると思います。
奥 誰一人取り残さない、ということをJAが作り出せるかということでもあると思います。
菅野 最後に各JAにメッセージをお願いいたします。
支持される指標掲げて
奥 まず、当金庫が100周年を迎えられたことにつきましては、ひとえに皆さまのご理解・ご協力の賜物であり、心より感謝申し上げます。
私たちJAグループの価値は何かを考えると、一つはやはり食べ物を消費者にきちんと届けるということだと思います。昨年は非常に高温で農作物にも被害が出ましたが、このままでは食べ物を届けるということが成り立たなくなるかもしれません。ですから環境と調和した農法など、地球環境問題への取組みについても、ぜひ一緒に考えていきたいと思います。
その点において、JAが持つ力は莫大なものがあるわけですが、今後もJAが農業を支えていくためには、単に収支だけではなく、働いている職員がやりがいを持っているかという職員満足度や、地域・組合員からの満足度、そういった指標も含め、地域において今後もしっかりと役割を担っていただく必要があります。そのために農林中金はしっかりサポートしていきたいという思いです。
【インタビューを終えて】
中学生までの農業手伝いが、職員の「JA援農支援隊」への積極的な呼びかけと自ら支援員として農業現場に入られた姿勢に100年先を見た。農業協同組合のこの先にウェルビーイングそして「誰も取り残さない」をどう作り出せるかというくだりに、東日本大震災の被災時「農業・くらし・地域」をどうする? と進むべき道を示したこと思い起した。今こそ、JAの価値「人」の繋がりから未来を描き歩むことを預かった。
重要な記事
最新の記事
-
 旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日
旧暦・新暦の2回あった行事【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第334回2025年4月3日 -
 宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日
宮崎都城市が5年連続1位 2023年市町村別農業産出額 農水省2025年4月3日 -
 【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日
【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(1)2025年4月3日 -
 【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日
【現場で役立つ基礎知識】全農土づくりセミナー総合討論から 水稲の高温対策へ基本は根張り重視(2)2025年4月3日 -
 越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日
越後姫プレゼントキャンペーン開催中 応募は4月20日まで JA全農にいがた2025年4月3日 -
 乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日
乳しぼり体験と牛乳の飲み比べ「AKASAKAあそび!学び!フェスタ」に初登場 JA全農2025年4月3日 -
 JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日
JA全農「スキみる」マッチョによるスキムミルクレシピの料理動画を公開2025年4月3日 -
 開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日
開発途上地域の農林水産業研究を紹介 一般公開イベント開催 国際農研2025年4月3日 -
 「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日
「令和7年3月23日に発生した林野火災」農業経営収入保険の支払い期限を延長 NOSAI全国連2025年4月3日 -
 子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日
子どもの収穫米を子ども食堂に提供 新しいカタチのフードドライブ 相模原市2025年4月3日 -
 「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日
「放牧をまんなかに。」 ファームエイジが新ロゴとタグライン 創業40周年記念ロゴも2025年4月3日 -
 横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日
横浜ビジネスグランプリ2025で奨励賞受賞 YD-Plants2025年4月3日 -
 AIとスマホで農作業を革新するFaaSサービスを開発 自社農場で実証実験開始 アグリスト2025年4月3日
AIとスマホで農作業を革新するFaaSサービスを開発 自社農場で実証実験開始 アグリスト2025年4月3日 -
 亀田製菓とSustech PPAによる屋根上太陽光発電を開始2025年4月3日
亀田製菓とSustech PPAによる屋根上太陽光発電を開始2025年4月3日 -
 遠隔操作で農業ハウスの作業効率を向上「e-minori plus」新登場 ディーピーティー2025年4月3日
遠隔操作で農業ハウスの作業効率を向上「e-minori plus」新登場 ディーピーティー2025年4月3日 -
 【人事異動】全国酪農業協同組合連合会(4月1日付)2025年4月3日
【人事異動】全国酪農業協同組合連合会(4月1日付)2025年4月3日 -
 【役員人事】 マルトモ(4月1日付)2025年4月3日
【役員人事】 マルトモ(4月1日付)2025年4月3日 -
 セール価格での販売も「春のキャンペーン」開催中 アサヒパック2025年4月3日
セール価格での販売も「春のキャンペーン」開催中 アサヒパック2025年4月3日 -
 餃子に白ごはん 永瀬廉の食べっぷりに注目「AJINOMOTO BRANDギョーザ」新CM2025年4月3日
餃子に白ごはん 永瀬廉の食べっぷりに注目「AJINOMOTO BRANDギョーザ」新CM2025年4月3日 -
 酪農・畜産業界データ統合プラットフォーム「BeecoProgram」コンセプト動画を公開 丸紅2025年4月3日
酪農・畜産業界データ統合プラットフォーム「BeecoProgram」コンセプト動画を公開 丸紅2025年4月3日