【クローズアップ農政】農業と消費税増税 消費増税で農業滅びる2013年7月1日
・転嫁できない現実
・「自らかぶる」構造
・消費税は誰が払う?
・国からの補償制度を
・農業者の支援策も
消費税は来年4月に8%、2015年10月には10%に引き上げられることになっている。増税の判断は経済情勢を見極めるというのが政府の方針だが、そもそも増税は前政権の公約違反だとの批判もある。しかし、2ケタ税率は現実味を帯び、このままでは農業への影響が懸念される。
一方、欧州諸国では消費税など付加価値税を入れる際、農業への配慮と消費者負担を軽減するため、食料品などに対しては軽減税率が導入されている。日本も消費増税を実施するなら、まさに国として食料・農業をどう位置づけるか、その姿勢が問われるといえる。
食料や農業、あるいは暮らしにとって、TPP(環太平洋連携協定)が最大の焦点であることは間違いないが、一方でこの問題も「消費増税で農業が滅びた国にならないために」(青木宗明・神奈川大教授)重要なことだ。今回はJAグループの政策要求を軸に問題点を考えてみたい。
主要国、食料に軽減税率
◆転嫁できない現実
量販店で1袋399円で売られているトマトには、販売額の5%、つまり19円の消費税が含まれている。したがって、本体価格は380円だ。これが消費税が10%に引き上げられれば、消費税額は2倍の38円(380円の10%)となるから、税込み価格は418円へと値上げとなる。
しかし、デフレが続き価格は低迷するなかで、このような価格転嫁は可能だろうか。転嫁できず同額で販売しなければならないとなれば、消費税が10%へとアップしたら、逆にトマトの本体価格は380円から360円へと値引きをしなければならない。その分、利益は減ることになる。
本紙5月30日号では最近の米販売事情をレポート、そのなかで「5kg2080円と同1980円では売れ行きが倍も違う」と業界関係者は語り、販売価格が5kg2000円以下となるような仕入れ策を検討していることを紹介した。
つまり、生産コストが上昇しても、低価格が定着した量販店などからは、強引ともいえるほどの価格指示があり、値上げを要求すれば取引先からはずされるなど、とても消費増税分の価格転嫁などできない状況にあるのが実態だ。
◆「自らかぶる」構造
一方、消費税はすべての取引段階に課税される。したがって、生産に必要な種子や肥料、農薬などの生産資材の仕入れにかかる消費税も10%となる。これを農業者がかぶる必要はなく、当然、「川下」に転嫁すればいいのだが、先にみたようにそれは難しい。
しかも、野菜など生鮮食料品は、農業者が直接価格交渉を行っておらず、市場取引(セリ)で価格が決まる。もともと生産資材が高騰したからといって、それを価格に反映することができない状況にある。
そうなると「販売」では価格転嫁できずに値下げを強いられ、一方、「仕入れ」では消費税アップ分をかぶる、ということになる。現在は税率が5%だから深刻さをさほど感じないままだったかもしれないが、税率が10%になるということは仕入れでいえば消費税分として1割も上乗せされ、今のままではそれを自らがかぶるということになってしまう。
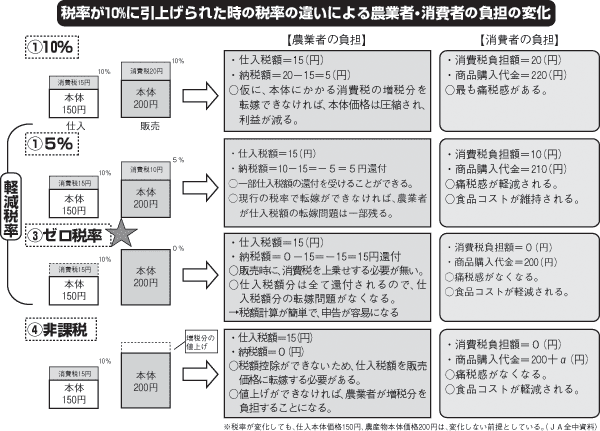
◆消費税は誰が払う?
このような事態をまねく消費税とはそもそもどんな税なのか?
本ホームページでは昨年5月、消費税の本質について解説した(消費税って何? 消費税は最大の不公平税制(2012.06.01)https://www.jacom.or.jp/archive03/closeup/agri/2012/agri120601-17024.html)。インタビューした元静岡大学教授で税理士の湖東京至氏の指摘をまとめると以下のようになる。
[1]消費税の「納税義務者」は、実は「事業者」とされている。一方、「担税者」の規定はない。
[2]そのため消費者だけが払っているわけではなく、消費者と事業者、あるいは事業者どうしの立場や力関係で負担が決まる。
[3]消費税法には「転嫁」という言葉はない。当時の税制改正法で「円滑かつ適正に転嫁するものとする」とあるだけ。
実際、消費税は事業者が「売上高×消費税率?仕入れ高×消費税率」の計算式で算定して納税する。法人税であれば人件費を差し引いた結果、赤字であれば課税されないが、計算式をみれば分かるように、消費税は売上高から仕入高を引いた粗利益、すなわち企業であれ零細な農業者であれ、1年間に生み出した付加価値に対して課税されるものである。
だから、そもそも消費者から消費税分を事業者が『預かって』、それを納税するという仕組みではない。「事業者の努力によって納められている税なのです。多くの人が基本を誤解している」(湖東氏)のである。
「公共料金のような独占的な価格のものであれば消費者の負担となりますが、農産物のように価格競争下にあるものは転嫁などできません。まずは売れなければ仕方がない、となって値下げして増税分をかぶることになる。結局、しわ寄せは弱いところに来ます」。
◆農業者の負担を軽減
JAグループはこうした問題に対応するため、JA全中が学識経験者による研究会を設置し、諸外国視察などや組織協議をふまえて政策提言をまとめ、関係方面に要請を行ってきている。
諸外国の事例で分かったことは、農業者と消費者に配慮したさまざまな措置が実施されていることだ。
上の表はJA全中がまとめた諸外国の軽減税率の導入状況である。食料品に関して軽減税率を適用する国のほうが多い。イギリスやアイルランドではゼロ税率が適用されている。
右の図で示したように税率が引き上げられたとき、食料品に軽減税率が適用されると農業者の負担は軽減される。標準税率が10%のとき、食料品は5%に軽減されると、本体価格200円とすれば売上高にかかる税額は10円となる。
一方、仕入高を150円とすると仕入れにかかる税額は15円となる(150円の10%)。したがって、納税額は「10円?15円」とマイナス5円、すなわち一部は還付を受けることができる。
これがゼロ税率であれば納税額は「0円?15円」とマイナス15円となるから、仕入れ税額分はすべて還付されることになる。ゼロ税率であれば仕入税額の計算だけすむから申告も容易で、もっとも農業者の負担を軽くすることができそうだが、軽減税率であっても消費者の負担を軽くすることになる。
非課税とゼロ税率の違いは、非課税は消費者の負担は軽くなり、農業者の納税額もゼロだ。しかし、仕入れ税額負担は残る。これを販売単価に上乗せできなければ、農業者が負担することになるという問題がある。
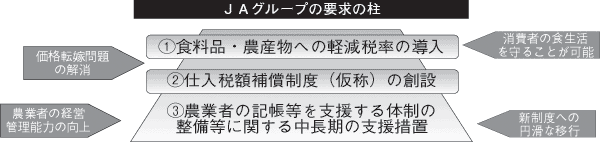
◆国からの補償制度を
こうしたことからJAグループとしては、まずは食料品への軽減税率の導入を求めている。ただし、先にみたようにゼロ税率でなければ仕入税額のすべてが還付されるわけではない。そこで農業生産資材については、ゼロ税率とすることも必要だとしている。
実際、カナダでは基礎的食料品をゼロ税率にすると同時に、肥料や農薬、農機の一部など生産資材にもゼロ税率を適用している。こうした措置を導入すれば販売段階と仕入れ段階ともに増税による「転嫁問題」は解消することになりそうだ。
ただし、電気、ガス、燃料など生産費の光熱動力費にあたるものでも標準税率が適用されるし、また、カナダでもトラックは農業生産以外にも使用される汎用性が高いと判断されている。
そうなると、零細経営のため免税とされている事業者は、仕入れ税額還付申請ができないうえに、公共料金などの税負担だけは増えるということになる。そこで対策として転嫁が困難な農業者の仕入れ税額分を国が補償する「仕入税額補償制度」の創設をJAグループは求めている。
具体的な姿はこれからだが、仕入れ額か、売上げ額に一定の割合をかけて算出するなど簡素な仕組みを求めている。
◆農業者の支援策も
同時に軽減税率などが導入されるとすれば、還付申請などを行わなければ実際のメリットが得られないことから、インボイス(各段階で納税した税額を明記した伝票)の導入や、農業者自身の記帳と税務申告(還付申告)も必要になる。
これまではこうした事務負担を問題とする議論もあったが、たとえばフランスではインボイスの代理発行を農協組織に認めるほか、その他の国でも会計処理ソフトの提供や、制度変更による納税事務負担を一定金額で補助するなどの例もあるという。
日本でも中小企業に対して国や地方自治体が納税事務を支援している。JAグループとしても農業経営管理能力の強化という面も見据えて、中長期の支援策が必要だとしている。ただ、同時にJAにとっても農業者の経営管理支援策が大切になる。
税制として問題の多い消費税だが、税率アップがいずれ避けられないのだとすれば、諸外国が採用しているような食料・農業に対する配慮をわが国も導入すべきだ。
この問題は食料・農業をどう位置づけるのかの問題でもある。カナダでも先に紹介した制度が導入されるまで3年以上の時間がかかったという。今後の議論を注視し積極的な提言をしていくことが求められている。
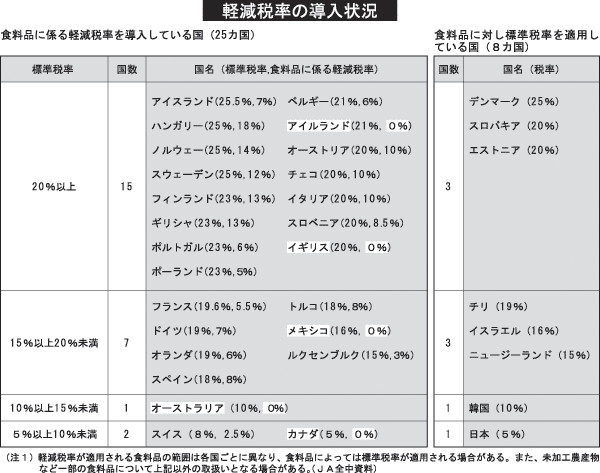
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日
シンとんぼ(172)食料・農業・農村基本計画(14)新たなリスクへの対応2025年12月13日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(89)フタルイミド(求電子剤)【防除学習帖】第328回2025年12月13日 -
 農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日
農薬の正しい使い方(62)除草剤の生態的選択性【今さら聞けない営農情報】第328回2025年12月13日 -
 スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日
スーパーの米価 前週から14円下がり5kg4321円に 3週ぶりに価格低下2025年12月12日 -
 【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日
【人事異動】JA全農(2026年2月1日付)2025年12月12日 -
 新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日
新品種育成と普及 国が主導 法制化を検討2025年12月12日 -
 「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日
「農作業安全表彰」を新設 農水省2025年12月12日 -
 鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日
鈴木農相 今年の漢字は「苗」 その心は...2025年12月12日 -
 米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日
米価急落へ「時限爆弾」 丸山島根県知事が警鐘 「コミットの必要」にも言及2025年12月12日 -
 (465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日
(465)「テロワール」と「テクノワール」【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年12月12日 -
 VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日
VR体験と牧場の音当てクイズで楽しく学ぶ「ファミマこども食堂」開催 JA全農2025年12月12日 -
 いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日
いちご生産量日本一 栃木県産「とちあいか」無料試食イベント開催 JA全農とちぎ2025年12月12日 -
 「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日
「いちごフェア」開催 先着1000人にクーポンをプレゼント JAタウン2025年12月12日 -
 生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日
生協×JA連携開始「よりよい営農活動」で持続可能な農業を推進2025年12月12日 -
 「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日
「GREEN×EXPO 2027交通円滑化推進会議」を設置 2027年国際園芸博覧会協会2025年12月12日 -
 【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日
【組織改定・人事異動】デンカ(1月1日付)2025年12月12日 -
 福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日
福島県トップブランド米「福、笑い」飲食店タイアップフェア 期間限定で開催中2025年12月12日 -
 冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日
冬季限定「ふんわり米粉のシュトーレンパウンド」など販売開始 come×come2025年12月12日 -
 宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日
宮城県酪初 ドローンを活用した暑熱対策事業を実施 デザミス2025年12月12日 -
 なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日
なら近大農法で栽培「コープの農場のいちご」販売開始 ならコープ2025年12月12日





































































