【特別寄稿】「恣意的」試算は議論の土台足りえない2017年12月29日
・鈴木宣弘・東京大学教授
・クローズアップ
◆生産性向上効果の恣意性
TPP11や日欧EPAの政府試算への信頼を回復するには「恣意性」を排除した値をまず示す必要がある。「価格が10%下落してもコストが10%以上下がる」と仮定すれば、GDPはいくらでも増やせる。「生産性向上効果」はドーピング剤だ。
政府試算では、(1)生産性向上メカニズム、(2)労働供給増加メカニズム、(3)供給能力増強メカニズム、の3つの成長メカニズムを組み込んでいる。
(1)生産性向上メカニズム
「貿易開放度(GDPに占める輸出入比率)が1%上昇→生産性が0.1%上昇(TPP12のときは0.15%)」と見込む。
2013年の当初試算では「価格1%下落→生産性1%向上」と見込んでいたのを上記のように改定してGDP増加は4倍以上に膨らんだのだから、これは「価格の下落以上にコストが下がる」と仮定しているのと実質的に同値とみなしうる。
◆賃金が上がるとは到底考えられない
(2)労働供給増加メカニズム
生産性向上が実質賃金を上昇させ、「実質賃金1%上昇→労働供給0.8%増加」と見込む。雇用の増加数をこんな単純に見込むことの大胆さにも驚くが、そもそも、賃金が上がるとは到底想定できない。例えば、ベトナムの賃金は日本の1/20~1/30である。投資・サービスが自由化されたら、アジアの人々を安く働かせる一方で、米国の「ラストベルト」のように、日本の産業の空洞化(海外移転か日本国内での外国人雇用の増大)による日本人の賃金減少・失業・所得減少こそ懸念される。米国民のTPP反対の最大の理由が米国人の失業と格差拡大だったことを想起すべきである。
(3)供給能力増強メカニズム
「GDP1%増加→投資1%増加」で供給能力が増強される。
これは単なる希望的観測である。
以上のように、価格下落以上に生産性が伸びるとか、下がるはずの賃金が上がるとか、GDP増加と同率で投資が増えるとか、どれも恣意的と言わざるを得ない。こうした勝手な仮定を置かずに、まず、純粋に貿易自由化の直接効果だけをベースラインとして示し、その上で、生産性向上がこの程度あれば、このようになる可能性もある、という順序で示すのが、「丁寧・真摯」な姿勢であろう。姑息な提示の仕方は逆に信用を失うことが、なぜわからないのか不思議である。
◆生産者損失の過小評価と消費者利益の過大評価
農林水産物も、価格が下がれば生産は減る。価格下落×生産減少量で生産額の減少額を計算し、「これだけの影響があるから対策はこれだけ必要だ」の順で検討すべきを本末転倒にし、「影響がないように対策をとるから影響がない」と主張している。政府の影響試算の根本的問題は、農産物価格が10円下落しても差額補填によって10円が相殺されるか、生産費が10円低下するから所得・生産量は不変とし、その根拠が示されていない点である。
例えば、TPP11で酪農では加工原料乳価が最大8円/kg下がると政府も試算している。8円/kgも乳価が下がったら、廃業や生産縮小が生じるはずなのに、所得も生産量も変わらないという。補給金が8円増加するわけはない。畜産クラスター事業の強化で生産費が8円下がる保証もないが、可能だと言うなら根拠を示すべきだ。しかも、加工原料乳価が8円下落しても飲用乳価が不変というのは、北海道が都府県への移送を増やし、飲用乳価も8円下落しないと均衡しないという経済原理と矛盾する。
ブランド品への価格下落の影響は1/2というのも根拠がない。例えば、過去のデータから豪州産輸入牛肉が1円下がるとA5ランクの和牛肉は0.87円下がるという、ほぼパラレルな関係にあるとの推定結果もある。
日本側の形式的評価と実際の影響が乖離する可能性は、輸出国側の評価でわかる。例えば、豚肉について、日本側は「差額関税制度が維持されたので9割は現状の価格で輸入される」としているが、EU側は「日本の豚肉は実質無税(almost duty free)になったも同然だ」と評価している。この意味は重大である。
また、牛肉・豚肉は赤字の9割補填をするから所得・生産量が変わらないというのも無理がある。農家負担が25%あるから実際の政府補填は67.5%で、平均的な赤字額の67.5%を補填しても大半の経営は赤字のままだから全体の生産量も維持できない可能性が大きい。
「食料自給率は変わらない」というのも説明不能である。輸入価格低下で輸入量が増加するから、かりに国内生産量が不変とした場合、食料自給率は低下するはずである。
◆野菜14品目だけで約1000億円の損失も
当研究室での試算では、主要野菜14品目に焦点を当てて関税撤廃の生産者・消費者への影響を推定した結果、生産額の減少総額は992億円と見込まれ、これだけで農産物全体の政府試算の最大値にほぼ匹敵し、政府試算がいかに過小か、そして野菜類への影響はほぼ皆無とみなす政府試算は重大な過小評価だとわかる。
一方、テレビなどで関税撤廃による消費者利益(注1)の大きさが強調されるが、輸入価格下落の50~70%程度しか小売価格は下がらない現実を考慮すると、野菜14品目の関税撤廃による消費者利益の増加総額は897億円と推定され、価格が完全に連動していると想定した場合の消費者利益の増加総額の推定値1448億円の6割程度まで縮小する。さらには、失う関税収入は野菜14品目だけでも101億円と計算される。
つまり、政府試算は「意図的に」生産者の損失を過小評価し、消費者利益を過大評価している側面が強い。
◆TPP10の可能性
さらには、カナダが抜ける可能性も考慮しないといけない。ケベック州(現首相の出身州)を中心にフランス文化圏の人口が多いカナダで、フランス文化圏の独自性を守る(出版、音楽ビデオ制作、テレビ・ラジオなどの文化産業を自由化の対象外とする)ことは極めて重大なことで、現行のNAFTA(北米自由貿易協定)でも例外としており(こうした事情についてJC総研の木下寛之顧問が詳しく整理している)、NAFTA再交渉でも死守する姿勢であるから、TPP11で簡単に認めることなどできない。「カナダがTPP11の大筋合意に応じなかったのが理解できない」と言った日本政府は愚かである。
かりにカナダが間に合わず、TPP10で走り出すことになれば、オーストラリアとニュージーランドは、日本がTPP12で差し出した酪農などの輸入枠を2国で満喫して喜ぶが、日本は最強の農業国から攻められて打撃が増す。そのうち、怒った米国からの日米FTAでの上乗せも必定とすれば、日本農林水産業の打撃はどこまで増幅されるか。こうした点も影響試算に考慮すべきである。
しかも「影響がないように対策する」と言いながら、出されている対策は、「看板の付け替え」の類(たぐい)が多く、影響を相殺できるような新味のある抜本的対策にはほど遠い。
以上のように、結局、国民や農林水産業者を欺く数字を「意図的に」出させた責任は誰がとるのか。欺かれた国民がツケを払わされるだけでは済まされない。
(注1)消費者利益=(自由化前の価格-自由化後の価格)×(自由化前の消費量+自由化後の消費量)/2
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
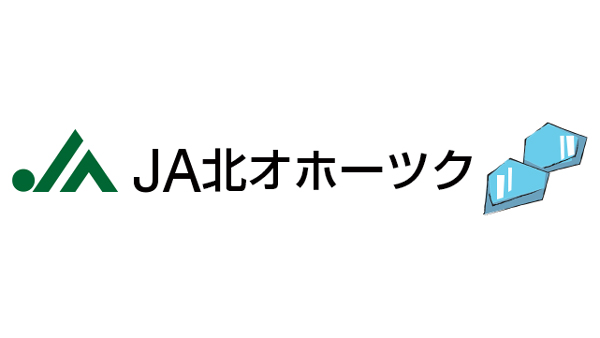 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































