【新自由主義への対抗】地域分散型へ農村から転換を 環境とエネルギー 小規模が優位性(金子勝立教大学特任教授)2019年6月19日
規制改革推進会議は第5次答申を6月6日に安倍首相に提出、政府はこれを受けて規制改革実施計画などが6月末にも決める見込みだ。農協改革について自己改革を促すなどの内容だが、同会議はこの間、林業や水産業などにも企業参入などを基本として改革を提言するなど現場に影響の大きい改革を進めていこうとしてきた。こうした政策の本質と農業、農村がどう新しい時代に向かうべきか、金子勝立教大学特任教授に聞いた。
◆大規模化は衰退への道
--規制改革推進会議などの政府諮問機関の答申を受けて「骨太の方針」など、6月末は政府が当面の政策を決定する時期です。この間の農業、農協改革もこうした諮問機関の意見が大きく影響しています。問題はどこにありますか。

農業分野でいえば、TPP11と日欧EPAの発効で牛肉、豚肉、チーズなどの輸入が大量に増えてきていますが、政府は、対策はすでに決定しているという。それはみな大規模化のための補助です。しかし、こういう考え方は的外れであることは数字的にも明らかです。
農地面積は減り、耕作放棄地も増えていますが、一戸あたりの規模は拡大し、平成22年の2.19haが30年には2.98haになっています(農業経営体、全国平均)。酪農、畜産も飼育農家数は減っていて飼養頭数も減っていますが、1農家あたりの頭数は増えている。
これはどういうことかといえば、どんどん弱小業者を淘汰して1戸あたりは規模拡大していても産業としての農業自体は衰えているということです。
しかし、規制改革推進会議の発想は基本的に水産業も林業も大手が参入すればうまくいくという、大規模化信仰、生産性向上信仰なんです。そこには持続可能なかたちで農業を維持していくという発想がない。結果として規模は拡大しているけれども、産業としては衰退している。そこにどういう間違いがあるのかということを現実に即して見なければいけないのに、現実と無縁な一部の専門家と称する人たちが真ん中に座ってドグマを振り回していることが失敗を招いている。
規模拡大のための補助金を受けた経営だけが生き残っていくとしても、海外とはくらべものになりませんから、そうなると、結局、日本農業は生き残れなくなってしまう。小規模な農家がどんどん淘汰されて大規模農家だけになり最後はそれもやっていけなくなる。今の政策で本当に日本農業を守れるのかということです。
(画像説明)金子勝 1952年東京都生まれ。経済学者。
東大大学院経済学研究科博士課程修了。法政大、慶応大教授などを経て立教大学特任教授。
近著『平成経済 衰退の本質』(岩波新書)
◆戦略なき新自由主義
--「新自由主義」の問題ということでしょうか。
価格を通じた市場メカニズムが一定の調整機能を持つのは確かです。しかし、新自由主義は個人間や地域間の格差を拡大するという問題だけでなく、この間違ったテーゼのもっとも問題なのは、産業戦略の失敗について責任を負わないということです。
規制緩和をして市場に任せればいい、それでダメになったら自己責任だ。こういうロジックです。みな市場の責任であり政府の責任ではない。これは「不作為の無責任」です。
要するに日本には産業戦略がない。市場メカニズムに任せれば新しい産業が生まれるという根拠のない言説がふりまかれました。日本の進んだ技術、などと今もテレビでいいますが、進んだ技術などほとんどなくなってしまった。スーパーコンピュータ、半導体、液晶、スマホ、カーナビなどなど、今やリチウム電池でさえ主導的地位を失いかけている。エネルギーも情報通信(IT)、バイオ医薬など先端産業をみな放棄して残っているのは自動車だけになって、それが日米FTA交渉で狙われている。
結局、バブル崩壊後の銀行の不良債権問題で企業トップや官庁の責任を問えず、経営者がほとんど責任を取らないで逃げ切る中で、本当に必要な産業構造の転換に向かっていかなかった1990年代初めの頃から問題です。そして福島原発事故が起きても企業と行政の責任を問えなかった。結果、エネルギー転換でも遅れをとった。市場に任せればいいという新自由主義ではうまくいかない。そして、景気が悪くなると財政出動と金融緩和を繰り返す。本質的に病んでいるところに手を突っ込まないのです。
◆有効求人倍率と地方衰退
--しかし、たとえば、有効求人倍率が全都道府県で1倍を超えたなど、政権はアベノミクスの成果を強調します。
都合のいい数字の取り上げ方です。
人口が増え成長していた時代には求職者が大幅に減ることはなく、景気がよくなれば求人数が増えるから、有効求人倍率は景気がいいという指標でした。
しかし、現在は、とくに地方では人口減少が進み、求職者もどんどん減っています。そして団塊の世代のリタイアでポストは空く。つまり、分母(求職者)が小さくなっている中で、求人数が同じであれば有効求人倍率は上がるに決まっているわけです。だから、有効求人倍率は景気の指標という面だけではなく、人口減少が厳しい地域衰退の指標にもなってしまったということです。
--農業、農村を含め日本社会にはどういう発想が求められますか。
農業でいえば競争の仕方は規模拡大だけではなくて、兼業の機会を増やしたり6次産業化のような垂直統合を進めることで農家の生活を成り立たせるというのが本来のやるべき改革で、それが農業の産業戦略ではないですか。
地方の工場がどんどん空洞化していくとしたら、エネルギー転換してドイツやデンマークのように小規模なエネルギーを農家がどんどん作っていって、それで副収入を得る。それと自分の農業を合体させれば十分にやっていけるといった新しい経営モデルを現実に即して作るべきだと思います。
ドイツはエネルギー転換をめざしシーメンスのように小さいエネルギーをAIでコントロールしたり、無人工場などファクトリーオートメーションを進化させたり、新しい交通システムを開発したりして生き残っています。北欧諸国はスエーデンのエリクソン、フィンランドのノキアとか、5Gの問題でいえば今やファーウエイと対抗できるのはこの2つです。これらはみんな国家戦略的にイノベーション投資をしています。
◆小規模分散型社会へ
新しい経営モデルづくりはコンピュータ技術の発展によって地域分散ネットワーク型社会に変わってきていることに着目すべきです。
今までのような重化学工業の集中メインフレーム型、規模、ロットを大きくして単価を下げるという方式はもう限界に達している。逆にコンピュータやAIが発達すれば小さな経営でも十分に効率性が上がる。JAも直売所をネットワーク化させていけば、お互いに買い合って足りないところを埋めることができるようになります。
分散型ネットワーク社会では、食と農、福祉、エネルギーといった人間の基本的ニーズに関わることは地域分散型でやっていくということになります。地元で売れるものは地元で売り、ロットの大きいものは大都市に出荷するというように。エネルギーも外から買って大手の電力会社にお金を払うよりは自分たちで発電して外に所得が漏れないようにして、余った電力を売っていくというようなことが望ましいモデルです。
環境や安全を大事にしたら小規模零細のほうがずっと優位です。ヨーロッパをはじめ世界の流れはそうなっています。ただ、どうしてもコスト高になるから、そのコストをどこで吸収していくかといえば必然的に6次産業化せざるを得ないということになる。そういう競争の仕方があります。環境や安全という価値を貫いていくなかで競争のロジックを働かせていくとドグマとはまったく違う世界が生まれる。小規模分散型がむしろ正しい。そうすると意思決定にみんなが参加できる。
新自由主義の本当の問題点と、日本の産業の衰退状況の中でドグマが一人歩きしている政策のあり方を根本的に批判して、それに対抗する農家経営モデルを立てて現場に即した対抗策をきちんと突きつけていかないと状況が変わっていかないと思います。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日
シンとんぼ(136)-改正食料・農業・農村基本法(22)-2025年4月5日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(53)【防除学習帖】第292回2025年4月5日 -
 農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日
農薬の正しい使い方(26)【今さら聞けない営農情報】第292回2025年4月5日 -
 【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日
【人事異動】農水省(4月7日付)2025年4月4日 -
 イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日
イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日 -
 農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日
農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日 -
 (429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日
(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日 -
 米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日
米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日 -
 「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日
「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日 -
 JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日
JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日 -
 素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日
素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日 -
 JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日
JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日 -
 真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日
真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日 -
 3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日
3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日 -
 自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日
自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日 -
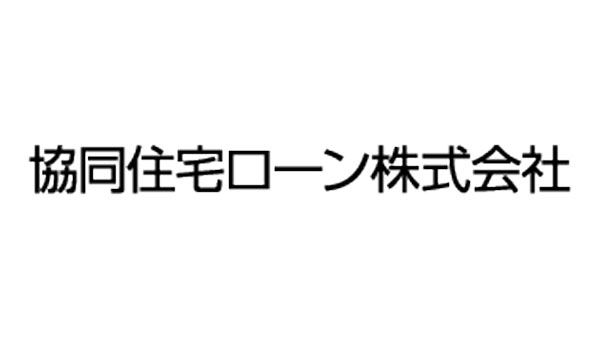 【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日
【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日 -
 大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日
大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日 -
 【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日
【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日 -
 鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日
鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日 -
 全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日
全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日

































































