「施策」厚く「動向」薄く 田代洋一横浜国大名誉教授【令和2年度農業白書を読む】2021年5月25日
コロナ禍のなかの令和2(2020)年度農業白書が、5月25日の閣議で了解され、6月中旬にも発表される。今回の白書について田代洋一横浜国立大学名誉教授に要点や見方を解説してもらった。
 田代洋一横浜国立大学名誉教授
田代洋一横浜国立大学名誉教授
コロナ「目玉」も乏しい経営分析
「戦略」・新技術が中心
冒頭にトピックスと特集、次に本来の食料、農業、農村を第1~3章で論じ、最後に災害復旧・復興の第4章がくる。
トピックスは、(1)輸出戦略(2)みどりの食料システム戦略(3)スマート農業、(4)デジタル変革(5)鳥インフル・豚熱(6)新品種の海外流出対策(7)フードテック(代替肉、健康食品、調理ロボット、昆虫利用等の新技術ビジネス)の七つと盛りだくさんで、「戦略」や新技術に集中している。トピックスというより、農水省が追求したい施策のリストアップである。
コロナ禍の影響と対策
「特集」は「新型コロナウイルス感染症による影響と対応」で、今年の白書の目玉だ。食料消費では、家庭内食、生鮮品(肉など)、調理品、スーパー売り上げ、テイクアウトなどが増え、外食が減った(図1)。米販売量は宣言下で中・外食を中心に減った。
農業現場への影響では、農業者の半数が売上高が減ったとし、また労働者確保への影響があった。半農半Xなど地方への関心が高まり、三大都市圏から地方への移住意向が増えた。政策面では、消費拡大、高収益作物の次期作・資金繰りなどへの支援等がなされている。
白書は、食料の安定供給ができたことを強調しつつ、感染症が不測時の食料供給リスクとして加わり、食料自給率や食料安全保障への期待が高まったとする。
記述は包括的だが、目新しい情報、農水省オリジナルデータはゼロで、他資料の加工・引用のみ。そのためか肝心の農業・農協経営などへの影響分析が乏しい。今年に入り食料消費そのものが減り、より厳しい状況になった。農業所得面では特に法人経営への打撃が大きい。
農村はこれまでのところは過密都市に対して「適疎」状況だったが、コロナは地方でも猛威を振るいだし、農村部に及ぶ危険性がある。国の行政なら可能なはずの、ビビッドな農業・農村把握の続報を望む。
みどりの食料システム戦略
「トピックス」の目玉は「みどり戦略」。菅義偉首相の2050年温室効果ガスゼロ宣言、9月の国連食料システムサミットをにらんだ促成「戦略」のようで、2050年に向け、農林水産業のCO2ゼロ、化学農薬50%減、化学肥料30%減を目標にする。
これを「アジアモンスーン地域の持続的食料システム」として、先行するEU等の国際ルール作りに対抗するという。しかし例えば有機農業面積について、EUは2030年の目標を25%としているが、対して日本は現状2.4万ha(0.5%)、2030年目標6.3万ha。それを2050年には一挙に100万ha(25%)にするという。
「みどり戦略」は極めて技術主義的で、EUが「欧州グリーンディール」という社会経済変革の一環としているのと対照的だ。現実から出発するのではなく、あるべき目標から逆算して計画を立てる「バックキャスティング」という手法に基づくので、どうしても「上から目線」の過大な目標になってしまう。
「持続」と「自給」 着地点に課題
みどり戦略と食料自給率
そもそも白書には、食料・農業・農村基本計画の進捗(しんちょく)チェックという法的義務があるが、カロリー自給率、生産額自給率ともに足踏み状態だ(第1章)。とくに自給力が低下傾向にあることが危惧される。
例えば有機農業100万ha化と自給率目標クリアは整合的かといった吟味をしなければ、自給率目標の達成困難を見越して、目標を「みどり戦略」にすり替えたと評されかねない。
日本は豪雨や台風などの自然災害が増えており、特に温暖化スピードが速く、地球温暖化対策が焦眉の課題となっている(第4章)。食料・飼料輸入大国の日本はフードマイレージ、輸送に伴うCO2排出が大きい。「みどり戦略」の前に、自給率を高めることこそがCO2排出削減に通じるのではないか。
白書はコロナ下のチーズなどの輸入増大を指摘しているが、通商関係では、日英EPAやRCEPを輸出拡大のチャンスとみるのみで(第1章)、TPPや日欧EPAの影響、牛肉のセーフガードについては触れていない。
要するに項目ごとのバラバラな指摘ではなく、<自然災害多発・コロナ―みどり戦略―基本計画―輸出入>といった関連分析が求められる。
持続的発展をめぐって(第2章)
農業総産出額、農業所得ともに減った。2020年センサス結果では、農業経営体も基幹的農業従事者も5年で各22%減り、前期5年よりスピードが高まっている。認定農業者数も減少している。いずれも高齢化と関連するが、新規就農者数も減少傾向なので、それだけではない。
担い手への農地集積率の上昇ポイントも年々落ちている。「人・農地プランの実質化」を法制化する動きもあるが、80%という集積目標、農地バンクへのルート一元化という政策自体に問題はないか。
米は、消費減少にコロナが拍車をかけ、6.7万haの作付け転換が必要とされる。白書は高収益作物への転換、輸出などに活路を求め、飼料用米については最後に「安定的な取引が重要」と指摘するのみで、現実にも飼料用米の作付け面積は減っている。白書は米問題が「正念場を迎えています」とするが、突破口を切り開くには飼料用米がポイントだ。
スマート農業が白書の影の主役になっている。実証プロジェクトでは、省力化効果は高いが、導入コスト増から利益は減少した。そこで白書は作業受託やサービス事業体の育成を掲げるが、集落営農などの協業促進を重視すべきだ。また未熟練若年労働力などにとってのメリットなど幅広に検討されるべきである。
新たな着目点など
女性の各方面への家族経営協定や収入保険への加入等の増加といった明るい面も指摘されている。また生産基盤整備関係に力を入れている。第3章では田園回帰が「節」に昇格した。地域おこし協力隊員の農村定着や「小さな拠点」などの紹介、コロナ禍の中で厚生連病院の活動など、新たな着目点もみられる。実践事例では農協のそれが多く取り上げられている。
第4章の大震災、原発事故、自然災害の復旧をトレースし続けることは、白書として極めて貴重である。
今年も400頁と分厚く、通して読むのはしんどい。ネットで「概要」をみてから、関心箇所を本体にあたるのも一つの手だろう。白書は年々、「これもやりました」という施策紹介に重点が移り「農政白書」化している。コロナの経営への影響分析や農業センサス分析を突破口に本来の「動向白書」を取り戻したい。
重要な記事
最新の記事
-
 イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日
イミダクロプリド 使用方法守ればミツバチに影響なし 農水省2025年4月4日 -
 農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日
農産物輸出額2月 前年比20%増 米は28%増2025年4月4日 -
 (429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日
(429)古米と新米【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月4日 -
 米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日
米国の関税措置 見直し粘り強く要求 江藤農相2025年4月4日 -
 「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日
「@スポ天ジュニアベースボールカップ2025」に協賛 優勝チームに「令和7年産新米」80Kg贈呈 JA全農とやま2025年4月4日 -
 JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日
JAぎふ清流支店がオープン 則武支店と島支店を統合して営業開始 JA全農岐阜2025年4月4日 -
 素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日
素材にこだわった新商品4品を新発売 JA熊本果実連2025年4月4日 -
 JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日
JA共済アプリ「かぞく共有」機能導入に伴い「JA共済ID規約」を改定 JA共済連2025年4月4日 -
 真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日
真っ白で粘り強く 海外でも人気の「十勝川西長いも」 JA帯広かわにし2025年4月4日 -
 3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日
3年連続「特A」に輝く 伊賀産コシヒカリをパックご飯に JAいがふるさと2025年4月4日 -
 自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日
自慢の柑橘 なつみ、ひめのつき、ブラッドオレンジを100%ジュースに JAえひめ南2025年4月4日 -
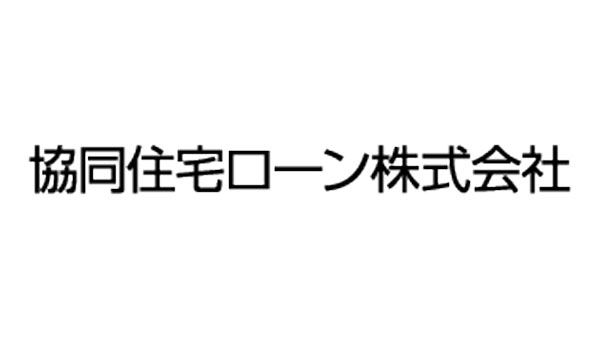 【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日
【役員人事】協同住宅ローン(4月1日付)2025年4月4日 -
 大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日
大企業と新規事業で社会課題を解決する共創プラットフォーム「AGRIST LABs」創設2025年4月4日 -
 【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日
【人事異動】兼松(5月12日付)2025年4月4日 -
 鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日
鈴茂器工「エフピコフェア2025」出展2025年4月4日 -
 全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日
全国労働金庫協会(ろうきん)イメージモデルに森川葵さんを起用2025年4月4日 -
 世界最大級の食品製造総合展「FOOMAJAPAN2025」6月10日から開催2025年4月4日
世界最大級の食品製造総合展「FOOMAJAPAN2025」6月10日から開催2025年4月4日 -
 GWは家族で「おしごと体験」稲城の物流・IT専用施設で開催 パルシステム2025年4月4日
GWは家族で「おしごと体験」稲城の物流・IT専用施設で開催 パルシステム2025年4月4日 -
 「農業×酒蔵」白鶴酒造と共同プロジェクト 発酵由来のCO2を活用し、植物を育てる"循環型"の取り組み スパイスキューブ2025年4月4日
「農業×酒蔵」白鶴酒造と共同プロジェクト 発酵由来のCO2を活用し、植物を育てる"循環型"の取り組み スパイスキューブ2025年4月4日 -
 令和6年度「貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金」に採択 ヤマタネ2025年4月4日
令和6年度「貿易プラットフォーム活用による貿易手続デジタル化推進事業費補助金」に採択 ヤマタネ2025年4月4日

































































