日本経済の強さから次第に円高に "地方への人の流れ"国も支援を 元大蔵省財務官・榊原英資氏に聞く2022年8月29日
1990年代後半に大蔵省(現財務省)財務官として、円安阻止の為替介入を進め、「ミスター円」と呼ばれた榊原英資さんは、国際金融論の専門家であるとともに、食文化などにも精通している。このところの円安ドル高傾向の為替の動向や日本経済の行方をどう見るのか、また、都市部への人の流れが止まらない中、地方の活性化策には何が求められるのか、考えを聞いた。(聞き手は加藤一郎・千葉大学客員教授)
 元大蔵省財務官 榊原英資氏
元大蔵省財務官 榊原英資氏
――はじめに円安ドル高についてお伺いします。最近は少し落ち着いていますが、この状況が日本経済にどう影響するか。ウクライナ情勢も踏まえて、経済や政治状況、農業へのインパクトなどについてのお考えをお聞かせください。
日本経済の強さが円を強くする
今の円安の最大の原因は、アメリカが金融を引き締め、日本が金融緩和を進めていることです。これでは当然ドル高円安になります。ただ、このところ少し状況が変わってきています。米国が2四半期連続でマイナス成長になり、金融引き締めの状況ではなくなってきました。逆に日本の来年度の経済成長率は2%や2.5%と予測されています。これまでは平均1%位でしたから、日本経済が従来以上に順調に成長していくと予測されています。こうした変化で円安からむしろ円高に次第に転じていくとみられます。つまり、日本経済の強さが円を強くする訳なのです。
食料に対する影響ですが、これも円安から円高に変化していくことは日本にとってプラスが大きく、農業政策にとってもプラスが大きくなると考えられます。今の円安は長続きしないという視点で情勢を見ることが大事です。円高になれば、海外での活動が有利になり、農産品の輸出も増加すると考えられます。
――円安が進むと日本の農業生産にも影響を及ぼしますが、日本の抱える問題として食料自給率の低さがあります。米国やフランスは農業国で自給率が高いのは当然ですが、1965年と2020年を比較すると、ドイツが66%から86%、英国も45%から65%に伸びているのに日本は73%から37%と一貫して下がっています。日本が海外からどんどん農産物を買える状況なら新たな第3次産業を中心とする社会を作ることも考えられますが、ウクライナ情勢などで肥料原料も入りにくくなり穀物価格も上昇する中、自給率の問題を解決せずに社会が安定するのかと考えさせられます。
自給率が下がっているのはかなり問題です。農家の高齢化や、若い人が都会に出てしまうことで日本の農業が衰退し、ここまで自給率が下がってしまった。やはり農業の衰退や農家の窮状を何とかしなくてはいけない状況に入っていることを忘れてはいけません。
食文化や食生活を育む農業を大事に
――榊原さんとは様々な会議でパネリストなどとしてご一緒しましたが、そこで感じたのは、榊原さんは"ミスター円"のイメージが強すぎて、「知的食生活のすすめ」などの著書があるほど食への造詣が深いことが一部にしか知られていないことです。改めて食への思いをお聞かせください。
食とはある意味で文化であり、この食文化を大切にすることはどの国でも大事なことです。日本の場合、戦後急速に多方面で制度化が進みましたが、米中心の食生活は大きく変わってはいません。そういう面で自国の食生活を育む農業を大事にすることは非常に重要です。国の文化であり、昔から受け継がれたものであるときちんと理解することが大事です。
――例えば米国と比較しますと、日本には駅弁文化といいますか、各地方に具材と料理法があります。ところが私は約5年あまり米国に駐在しましたが、マクドナルドなどのナショナルチェーンが目立ち、地方の素材を生かした料理を探すのに苦労しました。日本の食文化を日本人として誇るべきと考えます。
日本の地域の食文化は豊かですね。東京への一極集中が進んでも食については地域の特色が今も残り、それを地域文化として見直すことは非常に重要だと思います。ただ、戦後の食の欧米化で地方の食文化が若干消えてしまった部分はあります。例えば沖縄県はかつて日本で最も健康な県と言われていましたが、食生活がアメリカ化することで沖縄の方の健康が損なわれてしまった。今や若い人たちを中心に朝食はごはんよりパンを食べる方が多いでしょう。だから米の消費量が増えない。食の欧米化で変わってきている面があります。
森や里山を大切にしてきた日本人
――それと食文化とも通じますが、日本はとにかく水に恵まれています。春から秋は太平洋から雨を降らせ、川に流れて森と水田で保水される。冬には雪が積もって雪解け水が生まれる。欧米の硬水(硬度101以上)とは異なる日本の軟水は日本独特の素材そのものを活かす食文化を生み出したと思います。
まさに日本は森と水の国です。森林率が7割近くあって先進国で日本より高いのはフィンランド位です。これには仏教の影響もあって天台宗や真言宗の総本山が森の奥にあり、日本人にとって森は神聖なところでした。また、日本の雨量はヨーロッパの3倍くらいあって豊かで急峻な川をきれいな水が流れ、海に注ぎ込む。非常に豊かな自然があり歴史的に享受してきた国であることを大切に思わないといけません。
――それと日本の文化には「山辺」や「野辺」とか、"辺"の文化があります。境界線上のところを大切にする。こうした"辺"の文化は環境の時代にふさわしいのではないでしょうか。ウクライナのような戦争や国土の侵略が起こったときに考えてみますと、日本人は意外と"辺"や"際"を大切にしてきた民族ではないかと改めて思います。
里山とも言いますね。山と村のあいだの里山を非常に大事にしてきました。それも繰り返しになりますが、森の奥深くに宗教の総本山があり、神様が住む森を大切にするという日本人の特性が表れているのかもしれません。
都会から人を呼ぶ政策 地域で立案し国が支援を
――そうした自然が残る地方の活性化について伺いたいと思います。私が客員教授を務める千葉大学の園芸学部は半数以上が女子学生で、保護者からは彼女たちが地方に戻れば地方が活性化すると言われますが、一方で彼女たちからすると喫茶店やコンビニも遠い田舎に帰る気にならない。こうした中で地方活性化を進めるいい方策がないか頭を悩ませています。
やはり学生からすると東京にいるほうが自由ですからね。いろんなファシリティ(施設など)もあるし、あまり戻りたくないという気持ちは理解できます。地方活性化には相当ドラスティックな政策が必要であり、我々が考えていかないといけません。
――経済性だけで考えたら例えばIT関連産業と米の生産性を比較したら勝負になりません。ただ、地方で地元企業に勤めながら土日に水田で作業をし、年金収入も得るという収入の分散化が成り立つ面はありました。ところが現状のように米で一定の収入が得られにくくなるとやはり都会に集まってきてしまいます。こうした中で森や水といった経済価値にはつながらないものを守りながらいかに地方の活性化をはかっていくか重要な課題です。
例えば今はインターネットがありますから仕事は遠隔でできます。そういう意味で都会から人を呼んで地方で仕事をしてもらう政策を進めるべきで、それは可能だと思います。環境は地方にいたほうがいいです。そうした施策を各地域で立案して国の援助も得ながら地方で仕事をする人を増やしていく。最近はむしろ田舎に戻りたいという人も増えてきています。それなりの仕事ができれば戻る人は増えてくると思いますし、そうした政策をとる必要があると思います。
本社機能の地方移転が地域活性化生み出す
――確かに今の大学3年生などは1年のときからコロナ禍で対面授業がなくなり、実家に戻ってWEBで授業を受けるケースも多く、こうした中で地元の公務員や企業を目指す動きも出てきています。今、企業でも本社が東京でも例えば「コマツ」のように本社機能を石川県に移す動きもあります。こうした流れが起きてくると、変わってくるかなとも思います。
その可能性はありますね。地方に機能を移すことは企業にとってコストを安くできるなどのメリットもあります。また、地方自治体と連携することでまさに地域活性化につながります。東京に出てきた人たちがコロナ禍で地方に戻っていくという現象が少しずつ起きている今、そうした動きを加速する政策を取ることが非常に重要だと思います。
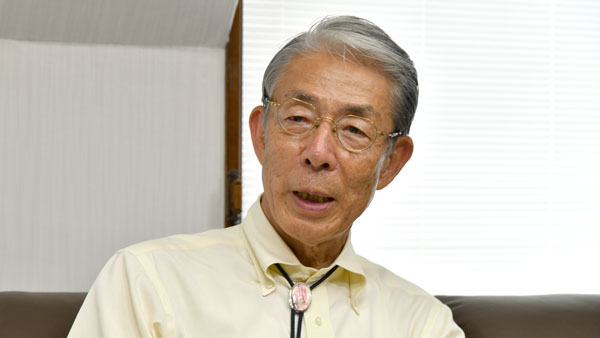 千葉大学客員教授 加藤一郎氏
千葉大学客員教授 加藤一郎氏
【インタビューを終えて】
榊原氏とは私がJA全農代表理事専務時代にたびたび「食」に関するシンポなどでパネラーとしてご一緒させて頂きました。2007年10月農業協同組合新聞「進む地球の温暖化やがて来る食糧不足」の特別対談では榊原氏は「日本は米を除く穀物を全面的に輸入に頼っています。その状況が維持できなくなります。日本として食料全体が不足する時代にどのように対応するか考えるべきです。恐らく2020年になったら相当の食糧不安になります。」と語りました。2022年、榊原氏の先見性が現実味をおびてきたと思います。(加藤一郎)
【略歴】
さかきばら・えいすけ 1941年生まれ。神奈川県出身。1965年に大蔵省に入省。財政金融研究所所長や国際金融局長を経て1997年に財務官に就任。1999年に大蔵省退官後、慶應義塾大学教授、早稲田大学教授を経て、現在、青山学院大学特別招聘教授や(財)インド経済研究所理事長を務める。経済学博士(ミシガン大学)。
重要な記事
最新の記事
-
 シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日
シンとんぼ(139)-改正食料・農業・農村基本法(25)-2025年4月26日 -
 みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日
みどり戦略対策に向けたIPM防除の実践(56)【防除学習帖】第295回2025年4月26日 -
 農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日
農薬の正しい使い方(29)【今さら聞けない営農情報】第295回2025年4月26日 -
 1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日
1人当たり精米消費、3月は微減 家庭内消費堅調も「中食」減少 米穀機構2025年4月25日 -
 【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日
【JA人事】JAサロマ(北海道)櫛部文治組合長を再任(4月18日)2025年4月25日 -
 静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日
静岡県菊川市でビオトープ「クミカ レフュジア菊川」の落成式開く 里山再生で希少動植物の"待避地"へ クミアイ化学工業2025年4月25日 -
 25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日
25年産コシヒカリ 概算金で最低保証「2.2万円」 JA福井県2025年4月25日 -
 (432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日
(432)認証制度のとらえ方【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月25日 -
 【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日
【'25新組合長に聞く】JA新ひたち野(茨城) 矢口博之氏(4/19就任) 「小美玉の恵み」ブランドに2025年4月25日 -
 水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日
水稲栽培で鶏ふん堆肥を有効活用 4年前を迎えた広島大学との共同研究 JA全農ひろしま2025年4月25日 -
 長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日
長野県産食材にこだわった焼肉店「和牛焼肉信州そだち」新規オープン JA全農2025年4月25日 -
 【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日
【JA人事】JA中札内村(北海道)島次良己組合長を再任(4月10日)2025年4月25日 -
 【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日
【JA人事】JA摩周湖(北海道)川口覚組合長を再任(4月24日)2025年4月25日 -
 第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日
第41回「JA共済マルシェ」を開催 全国各地の旬の農産物・加工品が大集合、「農福連携」応援も JA共済連2025年4月25日 -
 【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日
【JA人事】JAようてい(北海道)金子辰四郎組合長を新任(4月11日)2025年4月25日 -
 宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日
宇城市の子どもたちへ地元農産物を贈呈 JA熊本うき園芸部会が学校給食に提供2025年4月25日 -
 静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日
静岡の茶産業拡大へ 抹茶栽培農地における営農型太陽光発電所を共同開発 JA三井リース2025年4月25日 -
 静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日
静岡・三島で町ぐるみの「きのこマルシェ」長谷川きのこ園で開催 JAふじ伊豆2025年4月25日 -
 システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日
システム障害が暫定復旧 農林中金2025年4月25日 -
 神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日
神奈川県のスタートアップAgnaviへ出資 AgVenture Lab2025年4月25日






























































