農政:農水省政策プロジェクトリーダー
農水省 農林水産技術会議事務局 青山豊久研究総務官に聞く【スマート農業プロジェクト】2020年6月18日
先端技術の導入で現場に「気づき」も
リース、シェアリングの加速が課題
新たな基本計画では政策の具体化と遂行のために農水省の組織横断したした「プロジェクト」を設置することが盛り込まれた。プロジェクトによっては関係府省とも連携する。すでに新たに6つのプロジェクトが動き出しており、小紙ではプロジェクトリーダーにそれぞれの狙いや今後の課題などを語ってもらう。第1回はスマート農業プロジェクトリーダーの農林水産技術会議事務局の青山豊久研究総務官に聞いた。
 農林水産技術会議事務局
農林水産技術会議事務局青山豊久研究総務官
--スマート農業とは何か。改めてお聞かせください。
私たちが思い描くスマート農業とは、ロボット、AI、IoTなどの先端技術を使う農業です。現場の課題をこうした先端技術で解決していこうということです。政府全体でソサエティ5.0を打ち出し社会的課題を先端技術で解決していこうとしていますが、スマート農業はまさに農業版のソサエティ5.0です。
イメージはさまざまだと思いますが、私たちは3つに整理しています。
1つ目は自動化です。ロボットトラクターなどを使って作業をすべて自動で行うというものです。
2つ目は情報共有。経営管理ソフトを使って多くの人の間で作業情報などの共有、伝達を簡単に行えるようにしようというものです。ここのほ場はいつどんな作業を行ったか、という記録を残すことによって、たとえば農業法人に新しく入ったスタッフでもその記録を追って作業することが可能になるといった技術です。
3つ目はドローンや衛星を使ったセンシングです。得られたデータから、どういう積算温度になったらどんな肥培管理をし、いつ収穫を行うかなどをAIなども使って分析し、それに基づいて農作業をしていくという技術です。
スマート農業というと、大規模な農場に無人トラクターが走っているといったイメージになりがちですが、それぞれの地域の農業に応じて、スマート農業のかたちもいろいろあると私たちは考えています。そのすべてに応え、それぞれの現場で困っている課題を解決するために、それに適した先端技術を開発して使っていこうというのが私たちの考えです。
--現場ではどのような取り組みがありますか。
いちばん印象に残っているのは高知県の四万十町で経営管理ソフトを導入した集落営農組織の話でした。今までは新人に農作業をさせようとしても、新人はどの田んぼのことかよく分からないということがありましたが、タブレットを持って現地に行けば地図情報もあるので農地の場所が簡単に分かるようになったということでした。それまでは近くの人に場所を聞いていたそうですが、その手間が省けるようになったということです。
また、トラクターを運転してほ場に行っても、そのほ場にどこから入るか分からないということもありますが、昨年の作業ログが残っていれば、ここからほ場に入るんだということも分かる。作業した経験を共有することに役立つと思いました。
作業の効率化という点でいえば、南大東島のサトウキビ栽培でのドローンの活用が印象的でした。ドローンで上空から畑を撮影するわけですが、上空からの葉の色と地上で測定した光合成速度の相関を判断して、どこのほ場に水を分配していくかを決めていました。離島では水は貴重だからです。その後、どのくらいの糖度になったかも上空からの葉の色と積算温度データ・地上で実測した糖度の相関から判断して、効率的な収穫順を考えると言っていました。
鹿児島のJAのピーマン部会で聞いたのは、栽培データを組合員どうしで確認するということを始めてみると底上げにつながったという話です。今まではそれぞれが自分の栽培の仕方に自信を持っていたけれども、単収の違いがデータで示されると、何が違うのだろうと考え始め、それはハウス内の温度管理や肥料のやり方だと気づくようになったということです。こうした思わぬ「気づき」を生むのもスマート農業だと思います。みなさん10年も栽培していれば自信満々なわけですが、実はもっと上がいたということで、それを見習い、産地として栽培技術が底上げされたということでした。
私はいちばん重要なのは、こういうデータを共有できる経営管理ソフトではないかと思っています。理由は安くて効率を上げられるからです。今までも生産部会のなかで生産者どうしがコミュニケーションをとっていたとは思いますが、便利な先端機器を導入することによって、改めてみなさんで話し合うきっかけになっていると思います。
--プロジェクトとして当面、どのような課題に取り組むのでしょうか。
スマート農業の実証事業は昨年から全国で始めましたが、現場でいろいろな課題も見えてきました。機械を安くするためにどんなことが必要か、山のなかではそもそもワイファイが通っていない、ドローンはオペレーターが一緒に現場に来てくれなければ使えない、といった課題です。
今回のスマート農業プロジェクトは、推進していく上で浮かび上がってきたこうした課題を解決するには何が必要かについて、もう一度政策の中身を見直そうというのが狙いで、関係のある省内各課に集まってもらって議論しています。
たとえば人材育成が重要だといっても、そもそも農業高校や農業大学校に最新の機械がないわけですから、まずは若い人たちがスマート農業に触れる機会をどうやって作るかが大事だということになるでしょうし、機械が高いという問題については、リースやシェアリングといった取組で初期コストを安くしていくことをもっと進めなければいけないと思います。
これから、令和3年度の予算要求に向けて整理していきますが、大きく3つの視点があると思います。
1つ目は実際に実証してみて、どのくらいのメリットが生まれ、それにどのくらいのコストがかかるのかということです。実証地区の取組を精査してデータがまとまれば、たとえば品目別にメリットとコストを示すなど現場の農家の皆さんが判断できる材料を提供していきたいと考えています。
2つ目は現場でより安く導入するために、スマート農業を支援するサービスをどう育成していくか、です。
3つ目はスマート農業の周辺の政策です。スマート農業を前提にした農地整備や通信環境の確保、人材育成などにどう取り組んでいくかです。
--高齢化や人口減少が進む中山間地域でもスマート農業の導入は期待されています。
すぐにばら色の世界になると語ることはできませんが、人がいなくなって集落営農組織に田んぼがどんどん集まってくるというなかで、それを管理するのに有用なのはやはり経営管理ソフトだと思います。それに加え、人が少なくなるなか田んぼの見回りを減らすための水管理システムや、あるいは農薬散布はドローンで行う、草刈りは草刈機で行うというように、人手がかからない仕組みをできることから導入していくということだと思います。
中山間は地形が悪く農地も分散しており、劇的に効率を上げることは難しいかもしれませんが、そういう地域でも使える技術を開発して活用していくということだと思います。
--今回のコロナ禍はスマート農業にどんな影響が与えそうですか。
もともとスマート農業は人手不足への対応と付加価値の向上という2つを目標に掲げていました。、これに取り組んできたわけですが、新型コロナ感染症の拡大で外国人技能実習生が来日できなくなるといった事態となり、さらに新しい生活様式が求められるなかで人と人との接触を減らすということになれば、作業を自動化するロボット技術やドローンでの見回りといった技術はまさに求めらるものだと思います。
実際、今回の緊急経済対策では、AIを活用した野菜の自動収穫機や、体への負荷を軽減するアシストスーツ、ドローンを使った農作業などを試してもらう実証事業も今月から始めているところです。
--スマート農業の実装を進めるにあたってJAへの期待をお聞かせください。
全国145か所の実証地区のうちJAが実施主体になっているのが15、JAが参加メンバーになっているのが53ということですから、半分はJAが実証事業に関わっています。さらに、現場では個々の組合員のみなさんも参加しています。JAの生産部会などではこれまでもICTを活用して所得向上につなげる取組をしていただいていると思いますから、農家のみなさんがスマート農業を展開していくにあたっては引き続きその後押しをしていただきたいと思います。やはり農家単独では現場での実装が難しい面も多いですから、JAの役割の発揮に期待しています。
(令和2年8月3日付で大臣官房総括審議官)
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
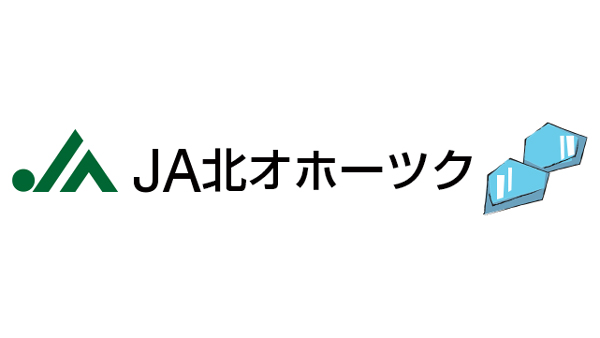 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































