農政:農水省政策プロジェクトリーダー
農水省 政策統括官付 平形雄策農産部長に聞く【麦・大豆増産プロジェクト】2020年6月24日
新基本計画では麦・大豆について意欲的な生産努力目標を掲げた。需要は着実に高まっており消費者ニーズを的確に捉えて増産することが自給率向上につながる。一方、主食用米の出来秋の供給量が過剰となることも懸念されており主食用以外への仕向けも喫緊の課題となっている。第2回は麦・大豆増産プロジェクトリーダーの平形雄策農産部長に聞いた。
消費者ニーズ追い風に着実に増産へ
主食用米は適正量確保を
--新たな基本計画では小麦の生産努力目標を76万t(平成30年度)を10年後に108万t(令和12年度)に、大豆を21万tから34万tに増産する意欲的な目標が示されました。こうした目標のもとになる麦、大豆をめぐる情勢からお聞かせください。
国産の小麦についてはここ数年、需要が生産を上回るという状況にあります。私の知る限り、これまでなかったことだと思います。大豆についても今後、国産大豆を使いたいという意向は高まっていて、実需者の方にアンケートをすると対前年でプラスになるという状況で堅調な需要が期待できます。
こういう状況のもとでも、生産サイドで作りたい品種を作るということになると、生産量は確保できますが、実需者が期待している品種ではないものが大量にできてしまうということになります。過去にもそのような要因で需給が緩んだことがあり、その結果、農家のみなさんも作らなくなってしまったということが何度かあります。米だけでなくやはり麦、大豆についても実需者が求める品種・量・価格を供給することによって需要に見合った生産を拡大していくことができる。せっかく需要が高まってきているわけですから、それに応えた生産をすれば着実に生産を拡大できると手ごたえを感じています。
--増産に向けた生産段階での課題は何でしょうか。
大豆については昔から品質はいいと言われてきましたが、収穫量のぶれが大きいことが課題とされてきました。一方、小麦については薄力粉になる品種しかなかったなかで、とくに平成20年以降、いろいろな新しい品種が出てきました。「ゆめちから」は代表的な品種ですが、パンや中華麺に向く品種が出てきたということが大きいと思います。
実は小麦は昨年は生産量100万tを久しぶりに超えて、ここ50年間ではいちばん生産量が多かった年になりました。ただ多くは北海道の畑作地帯での生産です。北海道では輪作のなかで小麦のシェアが高くなりすぎて、輪作体系上、かなり限界まで来ています。ですから、今後増産していこうとするなら、やはり水田地帯できちんと増産できるようにしなければならないということです。
水田地帯での課題は、湿田が多いために湿害によって品質のいいものがなかなかできないということで、これまでも作付け拡大に限界感がありました。
大豆は小麦ほど生産量が上がっていませんが、特に、都府県の生産量がずっと下がってきており、やはりこれも水田での大豆生産をもう一度定着させないと増産につながりません。ですから、麦・大豆の増産に向けては、水田地帯で品質のいいものを作れるようにするということがいちばん大きな課題です。
--湿害にはどういう対策がありますか。
近年は基盤整備事業がかなり充実しています。いわゆる公共事業で行う基盤整備のほかに、非公共ですが、農地耕作条件整備事業といった機動性の高い事業も出てきました。これらを活用して排水対策、つまり弾丸暗渠など導入してもらっています。そうした施策を現場でいかに臨機応援に使ってもらえるようにするかの工夫も必要だと考えています。
さらに、基盤整備とは別の視点から、実需者が求めるものをどう作付けするかを考えると、バラバラで作付けするよりも連担化、団地化して作付けすることで、コストを下げたり、品質を良くしたり、担い手が農地を引く受けやすくしたりするという課題もあります。そのため農地集積・集約を担当する経営局との政策の連携を検討する必要もあります。
そういう意味で、当局(政策統括官組織)だけなく、例えば、農村振興局や経営局と連携して、政策目標を共有化して、各局の施策の連携を進めていくことができるのは、こうした省内プロジェクト方式ならではだと思っています。
--とくに都府県では自分の水田農業経営に麦・大豆を取り込んでいくことへの現場の理解がなければ増産も実現しないと思いますが、生産現場はどう考えるべきでしょうか。
米もそうですが、麦も大豆も、「需要に応じた生産」ということに尽きると思います。米なら、こういう米がほしい、という人に向けて生産するのと同じように、こういう麦・大豆がほしいという人に向けてその麦・大豆をつくるということが大事だ思います。
つまり、必要としているものに応えて、自分の資源である農地や技術をどう活かして生産するか、考えていただくことが産地の経営そのものだと考えています。
規模の問題というよりは、今、地域にある資源をどううまく使い、最大限の生産につなげるか、ということをこのプロジェクトでは意識しています。連担化や団地化を進めようというのも、まとめて作付けすることによって生産量が安定し品質も向上しますから、狭い土地であっても工夫することによっていいものができる。それをもう一回、みんなで話し合って、克服できるよう取り組もうという意欲ある産地を支援したいと考えています。
産地という意味で言うと、通年で製造される商品に原材料を供給するには、例えば、小麦では年間600t程度の供給量が必要と業界の方から伺ったことがあります。そのぐらいの量になると個人では難しいですから、生産部会やJA単位、地域の再生協といったまとまりでの取り組みが必要です。そこで、生産部会などの方々が集まって、よく話し合っていただき、どの実需に対して何を供給するかという意思統一された目標を持っていただき、それに対して現状からどんな取り組みを行うのか、課題を具体化することが求められます。
その際、例えば、ある産地では小麦の増産のために乾燥調製施設や保管施設を整備して、そこに集約して出荷しようという計画があれば、それに対して必要な施策(事業)のメニューを用意していく、というやり方がこのプロジェクトでできないかと考えています。必要とするメニューは産地ごとに異なるので、たとえば基盤整備は終わっているものの、増産に向けては機械整備や土壌診断、たい肥施用等が十分ではないといったこともあるでしょう。それぞれの産地ごとに、何の生産をどの程度伸ばし、どこに売るのかという目標を立て、それに対して現状では何が十分でないか判断し、増産に向けた計画を立てていただく。国はできるだけ多くのメニューを用意し、必要な支援を行うというかたちで、意欲ある産地化をサポートする総合的な施策を作り上げることができないかと考えています。
「行き場のない米」懸念
--さて、2年産の主食用米の作付けについては過剰が懸念されています。どんな取り組みがこれから必要ですか。
主食用米の需要は毎年10万tの減少が続いていますが、本年2月末と4月末の時点で各県の作付意向を調査したところ、大半の県では作付面積が昨年並みということが判明しました。そもそも需要がどんどん減っているのに前年と同様の作付けをすれば過剰になります。近年、相対取引価格が高水準ということがあるのかも知れませんが、それは結果的に作況が100以下の年が続いたことが要因です。
ですから、需要に見合った生産をしなければなりません。ただ、今年は新型コロナウイルス感染症対策としての外出自粛要請等の影響で、2、3月は、量販店で米が非常に売れているというニュースが流れ、それを見た産地では主食用間の需要が回復したのだと受け止められた方が少なくなかったのだと思います。飼料用米については2月末時点より4月末時点のほうが、作付けを減少させる意向の県が増えていますから。
しかし、4月段階では、小売りと中食・外食を含めた総合的な米の販売量はすでに前年比でマイナスになり、5月では小売りも落ち着き、マイナスの影響はかなり出ています。
特に注意が必要なのは、令和元年産までの民間在庫(出荷+販売段階)が例年よりもかなり高い水準で推移しているということと、令和2年産の事前契約が今年は進んでいないという点です。この環境の下で、意向調査のまま主食用米が供給されると、行き場のない米、卸も引き取ってくれない米がかなり発生するおそれがあると懸念されます。
しかし、今は田植えが終わった段階ですが、仕向け先を主食用にするか、それ以外にするかという対応は、今からでも変えることができます。先日、本年産の営農計画書や、飼料用米、米粉用米などの取組計画について、8月末まで追加・変更を可能としました。自分のJAや県段階での在庫や、2年産の引き取り契約の状況を見て、主食用への仕向けは確実に売れる量にし、それ以外のものは主食用以外に仕向けるようにしないと、需給が大きく緩み、結果として農家の所得の確保が難しくなります。
そういう意識を産地や集荷団体の方々には持っていただきたいと考えています。主食用以外でも、飼料用米、新市場開拓米、米粉用米、WCSなど水田活用交付金の単価がしっかり設定されています。さらに、各地域ごとの産地交付金での上乗せ措置も考えれば、品代プラス水田活用交付金で、かなり所得は安定します。主食用米は一度過剰になってしまうと、販売価格が弱含みになるだけでなく、調整保管をしたとしても来年は今年よりさらに生産抑制を行うことになりますから、今年の段階で主食用は需要に見合ったボリュームにしておくというのが非常に重要だと思っています。
--JAに対する期待をお聞かせください。
実需先との結びつきを確立するのはJAの本来の仕事だと思っています。売り先があっての生産ということになりますから、作りやすいものを作って余りましたというのは産地にとっても悲しいことです。ぜひ信頼できる相手先を確保していただきたいと思います。それによって生産者も安心して作れることになりますから、JAらしい活動に期待しています。
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
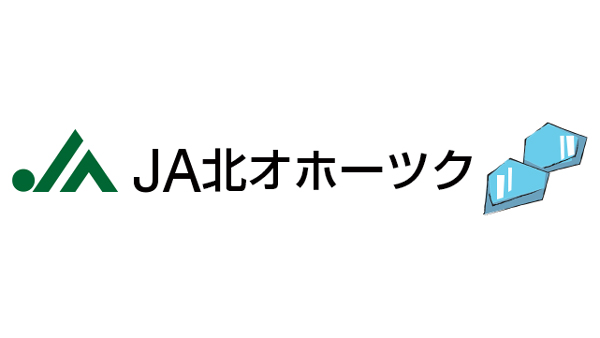 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日



































































