農政:平成26年度 「農業白書」を読む
国民が知りたいことに応えているか 政策の効果 厳しく点検を 田代 洋一・大妻女子大学教授2015年6月11日
・田園回帰は志向
・自給率と自給力
・家族経営充実を
・農地流動の動向
・各国の農業予算
政府は平成26年度食料・農業・農村白書を5月26日に閣議決定した。米価暴落、農協改革議論など農業関係者のみならず多くの国民が注目する課題も多い年だった。そのなかで白書は何を示したか。大妻女子大の田代洋一教授に問題点を指摘してもらった。
今年の白書は、特集として「人口減少社会における農村の活性化」と「新たな食料・農業・農村基本計画」を組んでいる。本論は、食料の安定確保(第1章)、強い農業の創造(第2章)、地域資源を活かした農村の振興(第3章)、東日本大震災からの復旧・復興(第4章)から成る。
白書は日本農業を政策面から俯瞰するには最適の書だが、何せ突っ込みが足りない。例えば、(1)この1年は農協・農委「改革」が吹き荒れた。しかしその背景・内容にはほとんど触れていない。(2)米価が暴落したが、その背景・要因分析がない。(3)TPPがどこまで進捗しているのかも分からない。
このような「広く薄く」をさらに要約する意味はほとんどないので、それは「概要」版をご覧いただきたい。せめてアクセントを付けようというのが「特集」の趣旨だろうから、そこを切り口にして見ていこう。
◆田園回帰は志向
昨年の話題は「地方消滅」だった。それに対して白書は「田園回帰の動き」を捉えている。しかしそれはなお多分に「志向」であって、統計量的な「動き」には至っていない。これまでも景気と人口移動は相関していた。今回も企業・好景気、国民・不景気のなかでの現象なのか、それともライフスタイルの歴史的転換なのか、なお見極める必要がある。
地域資源の活用、それと結びついて田園回帰については事例豊富である。こういう点については事例紹介は活きるといえ、今年の白書で一番面白かった点だ。しかし事例は北海道の一例を除き、ことごとく西日本である。なぜ「お天気は西から変わる」のか、そこを知りたい。来年は東日本版を期待する。
◆自給率と自給力
特集ではもうひとつ、新基本計画を取り上げている。基本計画は、自民党の農業・農村所得倍増戦略については名前の紹介にとどめ、農業・関連所得の増大に向けての農業経営の「マクロ」「ミクロ」の道筋を示したとしている。そこに倍増戦略と基本計画との間の苦しい関係がほの見える。 白書は、食料自給率を「国内の食料消費が国産でどの程度賄われているかを示す指標」だとしているが、それは正確か。自給率=国内生産量/国内消費仕向量、とされる。この分子には輸出も含まれる。自給率が「国産でどの程度賄われているか」だとすれば、分子は「国内生産量―輸出仕向量」でなければならない。白書は1節を設けて輸出を強調するが、輸出が増えるほど、この矛盾が大きくなる。
自給率の分子に輸出量を含めたのは、いざという時(不測の事態)には国内消費に向けられるから、という意識があろう。それに対して食料自給力は、まさに不測の事態に備えて「国内生産による食料の潜在生産力」を示すものとされる。自給力の構成要素は土地・人・技術だとされるが、指標としてとりあげられるのは農業資源を穀物・いも類にシフトさせた場合のカロリー供給量である。
自給率はこのところ39%程度で横ばいを保っているが、その影で食料供給力は年々下がっている。そのことに警告を発したのは基本計画の新機軸である。しかし疑問もある。 第一に、自給力指標(いも生産力)と、自給力の構成要素とされる土地・人・技術との論理的関連が分からない。やはり自給力は端的に土地・人・技術として示されるべきではないか。
第二に、自給力概念は「不測の事態」に対応したものである。このところ安保法制の整備など、政府は安全保障上の「不測時の事態」への対応に余念がない。いまこの時期に自給力指標を打ち出したことが、そのことに対応していなければ幸いである。
◆家族経営充実を
今年の組替集計の一つは年齢階層別の基幹的農業従事者数の推移である。それを図1に引用した。細かいので男性について要約すると、(1)5年前の55?59歳層と5年後の60?64歳層を比較すると大幅増である。定年帰農の動きだ。(2)5年前の60歳代層は5年後に大きな増減はない。営農継続である。(3)5年前の70歳代層は5年後に大幅減である。リタイアの動きである。その結果、かつては山を成した65?74歳層が大幅に減っている。ここに日本農業の危機が端的に示されている。
(図1)年齢階層別の基幹的農業従事者数の推移
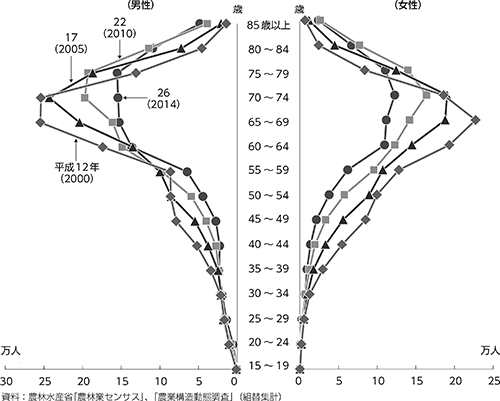
白書は青年就農給付金で青年新規参入者(農外からの参入)が倍増したことを強調している。しかし彼らは青年新規就農者の1割に過ぎない。過半は新規自営農業就農者で、それは減っている。青年就農給付金は家族経営の足元を固める方向で充実すべきというのが白書の結論になるのではないか。なお新規参入者の事例で里親農家研修の敷居が高いという声が紹介されている。自治体等が取り組んでいる里親制度だけに白書として不用意ではないか。
◆農地流動の動向
白書は農地流動化は着実に進展しているが、担い手への集積率は50%で停滞的で、その原因を「認定農業者を要件としない施策が実行されたこと」に求めている。民主党農政批判である。その施策も今年からナラシ・ゲタで復活した。しかし白書によれば肝心の認定農業者数が2010年をピークに減っている。白書は農地中間管理機構が始動したと報じているが、その初年度実績は目標15万ヘクタールの2割程度に低迷している。
これら三点、すなわち認定農業者対象のゲタ・ナラシで担い手集積率が高まるのか、認定農業者減にどう対策するのか、農地中間管理機構はワークするのか、しないとしたらどこに問題があるのか、これらは来年の白書が避けて通れない論点である。
白書は、認定農業者や集落営農に占める法人の割合は増加していると指摘する。今年の組替集計で経営組織別の法人数が明らかにされている。それをみると稲作単作と準単一複合経営が多い。後者は恐らく「稲作プラスα」だ。これらが米価下落や米戸別所得補償の減額でどう推移するのか。ゲタ・ナラシでカバーされるから大丈夫ということになるのか。最近は雇用者を入れた法人が多くなっており、それが困難に陥らないか懸念される。白書はそろそろ農業雇用労働者にメスを入れるべき時でもある。
◆各国の農業予算
白書は農村の章で日本型直接支払に言及している。「直接支払」は正確には「直接所得支払」であり、本来は農業所得増に貢献するものとして農業生産の第2章でとりあげられるべきものだ。それがそうはならないのが「日本型」のつく所以でもある。白書は、1990年代以降、農業の交易条件指数(農産物価格指数/生産資材価格指数)が、一貫して低下しているとする(図2)。労働農業所得(家族)は農業所得2.9兆円の48%に過ぎない。
(図2)農業物価指数等の推移(平成22(2010)年=100)
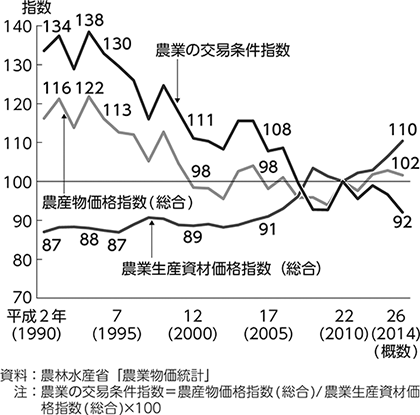
このような厳しい状況下で、農業予算は農業生産にどれほど貢献しているか。白書のコラム「各国の農業政策」の表を加工して引用したのが表1だ。日本の農業予算の国家予算比はヨーロッパ以下、アングロサクソン並だ。農業総生産額に対する予算の割合は日本は米国よりは高いが、ヨーロッパには劣る。違いは直接所得支払の多寡だろう。
(表1)各国の農業予算の比重(2013年)
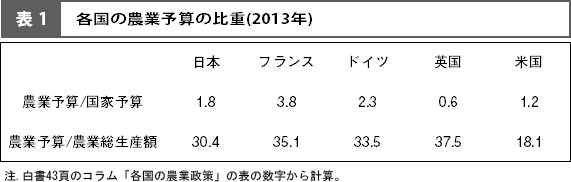
米価が低迷している。生産調整政策(国による配分)は廃止される。TPPはどうなるか。どうなろうと日米2国間協議の到達点はチャラにならないだろう。前述のように食料自給力は低下の一途をたどる。
白書は国民の知りたいことに即してもっとメリハリをつけるとともに、政策トータルの比重や効果がどうなのかを厳しく自己点検する必要がある。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日
【特殊報】コムギ縞萎縮病 県内で数十年ぶりに確認 愛知県2025年4月18日 -
 3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日
3月の米相対取引価格2万5876円 備蓄米放出で前月比609円下がる 小売価格への反映どこまで2025年4月18日 -
 地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日
地方卸にも備蓄米届くよう 備蓄米販売ルール改定 農水省2025年4月18日 -
 主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日
主食用МA米の拡大国産米に影響 閣議了解と整合せず 江藤農相2025年4月18日 -
 米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日
米産業のイノベーション競う 石川の「ひゃくまん穀」、秋田の「サキホコレ」もPR お米未来展2025年4月18日 -
 「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日
「5%の賃上げ」広がりどこまで 2025年春闘〝後半戦〟へ 農産物価格にも影響か2025年4月18日 -
 (431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日
(431)不安定化の波及効果【三石誠司・グローバルとローカル:世界は今】2025年4月18日 -
 JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日
JA全農えひめ 直販ショップで「えひめ100みかんいよかん混合」などの飲料や柑橘、「アスパラ」など販売2025年4月18日 -
 商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日
商品の力で産地応援 「ニッポンエール」詰合せ JA全農2025年4月18日 -
 JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日
JA共済アプリの新機能「かぞく共有」の提供を開始 もしもにそなえて家族に契約情報を共有できる JA共済連2025年4月18日 -
 地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日
地元産小粒大豆を原料に 直営工場で風味豊かな「やさと納豆」生産 JAやさと2025年4月18日 -
 冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日
冬に咲く可憐な「啓翁桜」 日本一の産地から JAやまがた2025年4月18日 -
 農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日
農林中金が使⽤するメールシステムに不正アクセス 第三者によるサイバー攻撃2025年4月18日 -
 農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日
農水省「地域の食品産業ビジネス創出プロジェクト事業」23日まで申請受付 船井総研2025年4月18日 -
 日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日
日本初のバイオ炭カンファレンス「GLOBAL BIOCHAR EXCHANGE 2025」に協賛 兼松2025年4月18日 -
 森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日
森林価値の最大化に貢献 ISFCに加盟 日本製紙2025年4月18日 -
 つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日
つくば市の農福連携「ごきげんファーム」平飼い卵のパッケージをリニューアル発売2025年4月18日 -
 日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日
日清製粉とホクレンが業務提携を締結 北海道産小麦の安定供給・調達へ2025年4月18日 -
 森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日
森林再生プロジェクト「Present Tree」20周年で新提案 企業向けに祝花代わりの植樹を 認定NPO法人環境リレーションズ研究所2025年4月18日 -
 「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日
「バイオものづくり」のバッカス・バイオイノベーションへ出資 日本曹達2025年4月18日






























































