農政:緊急特集・衝撃 コロナショック どうするのか この国のかたち
【衝撃 コロナショック どうするのか この国のかたち】山下惣一(農民作家):多極分散国づくりめざせ2020年4月23日
過疎、過密、格差ない未来を
山下惣一(農民作家)
新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐため「人との接触を減らせ」と日本中で叫ばれている。そんなか佐賀県在住の山下さんは「会いたくても人がいない田舎」で今日も夫婦で畑に出ているという。今、実感しているのは、人間は自然界に生きている存在であり、ウイルスとの共生をめざすしかないという。そのために私たちは何をなすべきかを農村から提起してもらった。

◆百姓の強みを実感
未だ終息せず、いつ収束するかもわからない「新型コロナウイルス」騒動だが、思いもかけないこの厄災によって教えられたことがいくつもある。
まずは私たち田舎の農家の暮らしが恵まれているということだ。それはコロナウイルス騒動が教えてくれた田舎暮らしの安全・安心である。そして「食」を生産・保有していることの盤石の強さだ。考えてみれば百姓の暮らしとしては昔から当り前のことだが、これを強みだとは自覚していなかった。都市の方ばかり向いて、少しでも都市に近づくことが発展であり幸福への道だという幻想に長い間とりつかれていた。だから農村から人が減ることを憂え、農業後継者不足を嘆き、年ごとに増えていく荒廃農地に心を痛めてきた。だが、その結果として今回のような感染症にはきわめて強い安全地帯となったのである。村に残ったものが頑張って元気に幸せに暮らしておれば、いずれそう遠くない時期に帰郷する人たちが出てくる。時代状況がそうなってきた。
逆に都市はその脆さ、生活のあやうさが浮き彫りになった。ウイルス感染の要因として「三密」が指摘されている。「密閉」「密集」「密接」だが、これこそまさに都市機能そのものではないのか。満員の通勤電車、エレベーター、ラッシュ時の駅のホーム、タクシー待ちの行列などなど想像しただけでわかる。
そんな都市で現在よりも人との接触を80%減らすなどということができるのだろうか。もし出来たとしたら、それで都市は生き残れるのか。
◆田舎で見えてきたこと
「不要不急の外出自粛」が要請された3月。私が出かける用件のすべてが中止となり、我が家を訪ねる人たちの予定は全部キャンセルされ、どこにも行かない、誰も来ない1か月を私は初めて体験した。ちょうどミカンの剪定時期で、毎日のように女房と軽トラックで畑とわが家を往復した。
玄界灘を見下す台地の田や畑に人影はない。都会では人に会うなというが田舎では会いたくても人がいないのだ。そんな無人の風景から家に戻ればテレビでは毎日コロナウイルスの話題ばかりで「オーバーシュート」だの「クラスター」など耳慣れない言葉が飛び交っていて、まるで別の国の放送を見ているような気分であった。だからこれを「人ごと」ではなく「我がごと」として認識するようにといわれてもそれは無理だ。人間はまだ何とかなると思っている間は行動を変えない生き物である。かくして1か月間、どこにも行かず、誰も来ない暮らしをしたら、財布の中身がほとんど減らなかった。それで私たちには何の不都合も不自由もない。これはカネ依存ではなくモノで暮らしている者の強さだ。これもコロナウイルスに教えられたことである。
◆共生へ 人間が変わる
さて、そこで今回のコロナウイルス禍が私たちに教えてくれているのは一体何なのかを考えてみた。農業を営んでいる私たちにはよくわかっているが、それは「人間は自然界に生かされて生きている生物の一種であって自然の支配者ではない」ということにつきるだろう。
大きな話からいけば地球上にすむ生物の総数は870万種類でその86%が未だ発見されずしたがって名前もない。人類が発見して分類しているのは全体の15%弱の120万程。その地球でもっとも繁栄した哺乳類が私たち人類だがそれでも全生物量の0.01%だという。
ウイルスは顕微鏡でしか見えない細菌のさらに50分の1の大きさで、生命の最小単位である細胞を持たないので自己増殖ができない。そのため他の生物の細胞を利用して自分を複製させて拡大していく。その唯一の目的は子孫を残すことだといわれている。人類は20万年前にアフリカで誕生したが、ウイルスは4億年前に生まれている。コロナウイルスは60年前に分類されたがその共通の先祖は紀元前8000年頃に出現してコウモリなどを宿主として現代まで生きのびてきたのだそうだ。私たち人類の大先輩である。
だから、この大先輩を撲滅しようとしても無理な話である。仮に一時的に制圧できたとしても次にはコロナウイルスを天敵としていた別のウイルスが急増するか、コロナウイルスが姿や形を変えより強力になって再登場してくるだろう。農業では「リサージェンス」というが、殺虫剤をかけたことで別の虫が大発生することはよくあることだ。だから、新型コロナウイルスも敵として闘うのではなく人間に対して無害のただの隣人として共存、共生を目指すべきだ。農業をやっている立場から私はそう考えるがどうだろうか。
ということは、ウイルスの側ではなく私たち人間の方からウイルスを無害にする環境を作っていくということである。感染症が発生していないところをモデルにすればいいのだ。
◆一極集中からの転換を
事実が証明しているように発症は大都市に集中している。地方は少なく農村にはほとんどない。岩手県は現在(4月20日)でもゼロだから、早い話が岩手県みたいになればいいのだ。人口の集中が病根だからこれを改善するのが本筋だが、これは容易ではない。
だから対症療法となるわけだが、現代の科学も医学も疫学もほとんど役に立たないのだからすごい話ではある。
「3密」を避けることが奨励されている、すなわち「密閉」「密集」「密接」を避け、マスク、手洗い、外出自粛などが対応策だから首をすくめて嵐が過ぎるのを待っているようなものだ。
発生の根本原因がそのままだから、必ずまた同じことが起こるだろう。日本列島の首都圏への人口集中は農村の過疎と背中合わせの現象である。この根本原因の解消に本気で取り組むべきではないのだろうか。一極集中から多極分散型の国づくりである。実はそう遠くない過去にその機運が盛り上った時期があったのである。
今から32年前の1988年、元号では昭和63年、国の「第4次総合開発計画」は「多極分散型国土形成促進法(法律63号)」という立派な法律を作っているのである。東京に集中している国の行政機関を東京圏から地方へ分散させる大胆かつ斬新な未来図がそれには示されていた。その発端となった大平正芳首相(1879年~1980年)の「田園都市国家構想」に私たちは熱い期待を寄せたものだ。しかし現職の首相が70歳で亡くなるという不幸があり、同時に世界ではとんでもない大変革が始まっていた。
第二次世界大戦後、東西に分断されていたドイツのベルリンの壁が双方の市民たちによって打ち壊され(89年)その2年後には社会主義陣営のリーダーだったソビエト連邦が崩壊したのである。誰もが予想もしていなかったそれこそ驚天動地の大変化であった。そして「新自由主義」と呼ばれる規制緩和と総自由化の時代になった。その象徴が「TPP」で、これはカナダから北米、オーストラリア、アジア、日本と太平洋をぐるっと取りまく12か国で関税など貿易の障害となっている規制を取り払って自由貿易をやろうという協定で、英語の「トランス・パシフィック・パートナーシップ」の頭文字をつないで「TPP」と呼ばれた。これでは日本の農業は壊滅する。私たちは農協を中心に猛烈な反対運動を展開した。
これは問答無用の強い者勝ちのルールで「ジャングルの掟」である。
ところが協定推進をリードしてきた米国が離脱し米国抜きの7か国で2018年の暮れに発効しているが、どんな影響が出ているのか、出ていないのか私にはわからない。
◆千里の道も一歩から
ま、そんなことがいろいろとあって現在があるわけだ。そして私は5月25日の誕生日で満84歳になる。正直いって新型コロナウイルスへの不安はない。タバコが原因の肺気腫という病気を持ってはいるがすこぶる元気である。どこまで生きるのか、生きられるのか未知の世界へ老いの一人旅をしている気分だ。
だから私たちはもういい。だが、孫たちやその次の世代の世には過疎も過密も格差もない、そして今回のような感染症にも強い社会になってほしいと思う。昔から「千里の道も一歩から」という。今回の新型コロナウイルス禍を奇貨として、幸せへの希望の第一歩を踏み出してほしいものだ。とはいえウイルスとの闘いはまだ続いている。4月17日7都府県に出されていた「緊急事態宣言」が全国に拡大された。もうしばらくは続きそうだ。心してしっかりと生きたい。
【緊急特集・衝撃 コロナショック どうするのか この国のかたちの記事一覧】
・田代洋一 横浜国大・大妻女子大名誉教授:日本の「歪み」映し出すコロナは「鏡」
・鈴木宣宏 東京大学教授:一部の利益でなく国民の命が守られる社会に
・山下惣一(農民作家):多極分散国づくりめざせ
・金子勝 立教大学特任教授:東アジア型に新型コロナ対策を転換せよ
・普天間朝重 JAおきなわ理事長:「さあ、始まりだ」。協同組合が終息後の社会の中心軸に
・姉歯暁 駒澤大学教授:コロナ禍の真の災禍とは何かを考える
・森田実 政治評論家:コロナショックによる世界の大変動と日本の選択
重要な記事
最新の記事
-
 備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日
備蓄米 「味に差なく、おいしく食べてほしい」 江藤農相2025年4月24日 -
 関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日
関税発動で牛肉の注文キャンセルも 米国関税の影響を農水省が分析2025年4月24日 -
 トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日
トランプ関税で米国への切り花の輸出はどうなる?【花づくりの現場から 宇田明】第58回2025年4月24日 -
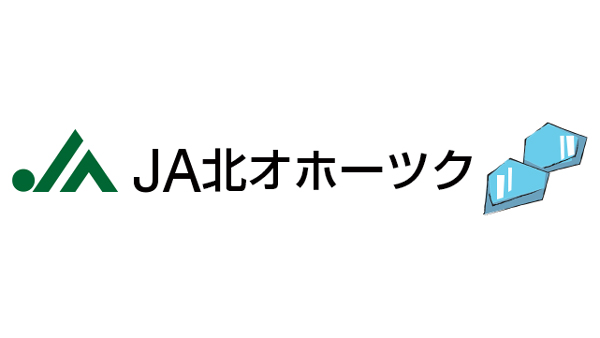 【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日
【JA人事】JA北オホーツク(北海道)吉田組合長を再任2025年4月24日 -
 三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日
三島とうもろこしや旬の地場野菜が勢ぞろい「坂ものてっぺんマルシェ」開催 JAふじ伊豆2025年4月24日 -
 農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日
農林中金 ロンコ・インベストメント・マネジメントに資本参画 不動産分野の連携強化2025年4月24日 -
 積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日
積雪地帯における「麦類」生育時期 推定を可能に 農研機構2025年4月24日 -
 日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日
日本曹達 微生物農薬「マスタピース水和剤」新たな効果とメカニズムを発見 農研機構2025年4月24日 -
 棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日
棚田の魅力が1枚に「棚田カード」第5弾を発行 農水省2025年4月24日 -
 みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日
みずほ銀行と食農領域の持続可能な発展に向け戦略的提携 クボタ2025年4月24日 -
 【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日
【人事異動】兼松(6月1日付)2025年4月24日 -
 日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日
日本生協連「フェアトレード・ワークプレイス」に登録2025年4月24日 -
 旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日
旭松食品「高野豆腐を国外へ広める活動」近畿農政局 食の「わ」プログラムで表彰2025年4月24日 -
 群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日
群馬県渋川市の上州・村の駅「お野菜大放出祭」26日から 9種の詰め放題系イベント開催2025年4月24日 -
 JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日
JA蒲郡市と市内の飲食店がタッグ 蒲郡みかんプロジェクト「みかん食堂」始動2025年4月24日 -
 適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日
適用拡大情報 殺菌剤「バスアミド微粒剤」 日本曹達2025年4月24日 -
 倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日
倍率8倍の人気企画「畑でレストラン2025」申込み開始 コープさっぽろ2025年4月24日 -
 農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日
農業・食品産業技術開発の羅針盤「農研機構NARO開発戦略センターフォーラム」開催2025年4月24日 -
 雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日
雪印メグミルク、北海道銀行と連携「家畜の排せつ物由来」J-クレジット創出へ酪農プロジェクト開始 Green Carbon2025年4月24日 -
 山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日
山椒の「産地形成プロジェクト」本格始動 ハウス食品など4者2025年4月24日


































































