農政:東日本大震災10年 命を守る協同組合
【特集:東日本大震災10年 命を守る協同組合】被災地で「新しい農業」へ挑戦(2)宮城・やまもとファームみらい野2021年3月10日
3・11東日本大震災に伴う大津波は、東北の太平洋沿岸の農地に壊滅的な被害を与えた。震災後10年経ち、その復旧がほぼ終わった。区画整備も進んだが、肝心の農家の営農意欲は、必ずしもこれに伴わず、耕作放棄されている農地も少なくない。そのなかで、施設園芸や規模のメリットを生かした新しいスタイルの農業に挑戦する生産組織が生まれている。条件不利地の岩手県三陸海岸で、規模は小さいものの、新たに施設園芸に取り組む農事組合法人と、耕地条件に恵まれJAグループがモデル的経営として期待する宮城県の大規模農業生産法人の挑戦をルポする。(取材・構成:日野原信雄)
農地委託の受け皿に
雇用創出へシステム化も
宮城・(株)やまもとファームみらい野

3月末から出荷が始まるトマトハウスと馬場常務
東日本大震災後、宮城県南部、太平洋沿岸部の農村風景が一変している。沿岸部を縦断する常磐高速道路を走るとよく分かる。ほ場は土地改良できれいに区画整備され、建設中を含め、あちこちに施設ハウスの団地がみられる。農業機械も施設も失った農家を中心に、復旧した農地を有効に活用し、土地利用型の大型経営や施設園芸で、あらたな農業の活路を切り開こうと、施設園芸を中心とするさまざまな経営体が生まれた。(株)やまもとファームみらい野もその一つだ。
山元町には、津波で水田と畑を合わせて約2400haの農地があり、うち1300ha余りが塩と泥を被った。同町は隣接の亘理町とともに、東北で最大規模のイチゴ産地だったが、津波で壊滅した。同町は2012年から農業復活に、大型施設栽培施設を集約した生産拠点づくりを進めてきた。
JA出資型法人設立
同町東部地区も被災した地区で、43戸の被災農家が地権者組合をつくって発起人となり、園芸の拠点づくりに取り組んだ。JAみやぎ亘理、JA全農、農林中金などの支援を得て、震災4年後の2015(平成27)年に、イチゴ農家で被災したJAの役員を代表に、JA出資型農業生産法人を設立した。宮城県の震災復興基金などを活用し、事業を立ち上げた。
同法人のほ場は、県営事業で基盤整備した約120haで15年度から順次、たい肥、麦、ソルゴーなどを栽培して土づくりを始めた。全体の基盤整備が終わった18年度から本格的に野菜栽培を開始。栽培作物は生食用のほか、業務・加工用の野菜が中心で、機械作業による土地利用型農業が可能な長ネギ(25ha)、サツマイモ(15ha)、タマネギ(19ha)などの土地利用型作物を基幹に、施設栽培のトマト、イチゴなどとなっている。地力増進のための大豆はあるが米は作っていない。
基幹作物であるサツマイモは焼き芋・干し芋ブームを反映し、今年度の売り上げは前年の3倍に伸びた。施設栽培のトマトも10a当たり50tの収量を安定的に確保するなど、生産は順調で、「今年度からなんとか収支がとれる見通し」と、同ファームの馬場仁・常務取締役は見通す。
施設栽培のトマトは、オランダ式環境制御ハウスで、長期多段取りの国内でも最先端の施設で栽培。もともとこの地区はイチゴの産地で、当初、経験のある施設イチゴも考えたが、夏季に冷涼な浜風のある同地の気候は夏越しトマトの栽培に向いており、最先端の環境制御型大型ハウス(6600平方メートル)の導入になったという経緯がある。

大型機械によるタマネギの収穫
最先端技術・施設で
同ファームは、その基本理念に、(1)山元東部地区での生産を再開し、農地を保全でき、永続的な営農を行う(2)地域農業者の生活再建に向けた「住民参加型」の生産をめざす(3)将来にわたって持続可能な経営ができる「新しい農業」をつくる――を掲げている。被災地域農業再建のモデルになろうとするJAグループとしての思いがこもっている。
そのため、トマトのオランダ式ハウスや、ほ場や経営管理のGPS(全地球測位システム)利用のZ―GIS、GAP(農業生産工程管理)など、新しい技術やシステムは積極的に取り入れている。
また馬場常務は、「持続可能な営農を展開し、地域農業の創造的復興と被災農家の雇用機会の確保をめざす」と、法人の役割を挙げる。同法人の体制は、役職員合わせて16人に、季節によって差があるが、パート従業員80人前後。農業から撤退を余儀なくされた地域の農家や新規参入を希望する若者などの雇用機会創出の役目を果たしている。
これまでの「みらい野」の実績から、農業経営を成り立たすためにポイントとして、馬場常務は第1に、事前の計画性を挙げる。地域や気象条件に合わせた作目の選択と販路、それにはしっかりした資金計画を立てる必要があるという。
次いでマーケットインの生産。当初、サツマイモは当初、「出口」がなくて苦労した。その反省から契約出荷の販路を開拓し、今は目いっぱい作付けを増やしている。タマネギは昨年、約750tを完売。規格外品がさばけるため「昨年はコロナ禍でも順調な販売で、廃棄野菜がなかった」と、馬場常務は、マーケットインの重要性を強調する。
そのためには契約栽培が必要で、馬場常務は「安定供給のためには量の確保が必要で、将来は県域を超えた法人間の連携が必要」と、リレー栽培など、法人間のネットワークづくりにも挑戦する。
農地の執着心に変化
一方、「みらい野」のような農業生産法人の存在は、農地に対する農家の考えを変えつつある。ともすれば、区画整理を終えた農地は、換地をめぐって利害対立が表面化することが多い。また、営農ができなくなっても、他人に農地を預けることに不安を持つのが普通だが、「みらい野」では、委託をやめたいという農家はいない。逆に励ましを受けるといい「大津波で土地に対する農家の考えが変わったのではないか」と馬場常務はみる。宮城県南の被災地の復旧農地では、こうした法人による農地利用が広がっている。
【取材を終えて】
信頼得てこそ
農業の経営規模拡大の場合、しばしばネックになるのは農地の集積であり、農政の肝入りで発足した農地中間管理機構も、期待通りの成果をあげていない。根底には農民の土地に対する強い執着心がある。山元町では、換地する前の段階で法人に集積した。農機や施設など全てを失い、小規模な家族経営では営農再開が困難なうえ、地形が変わるほどの大規模な区画整理だったという被災地の特徴はあるものの、土地改良と農地集積の方法および農家の信頼を得られるJA出資法人の一つのあり方を示している。(農協協会参与・日野原信雄)
被災地で「新しい農業」へ挑戦(1)岩手・農事組合法人「大槌結ゆい」
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日
【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日 -
 【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日
【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日 -
 鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日
鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日 -
 「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日
「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日 -
 「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日
「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日 -
 米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日
米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日 -
 【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日
【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日 -
 北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日
北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日 -
 全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日
全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日 -
 Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日
Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日 -
 国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日
国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日 -
 農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日
農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日 -
 農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日
農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日 -
 7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日
7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日 -
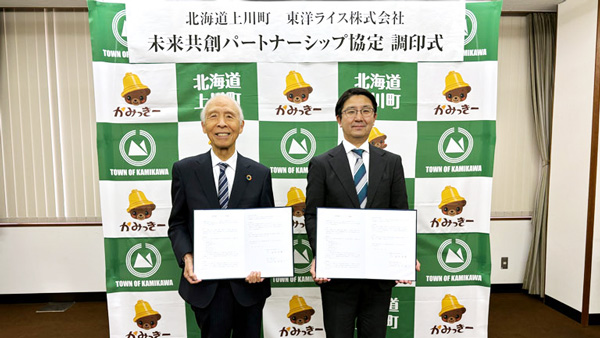 北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日
北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日 -
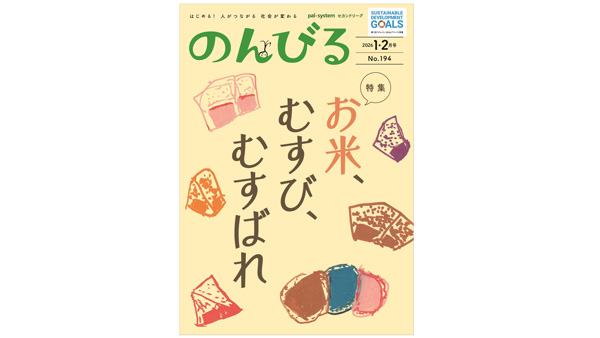 米が結ぶ人のつながり特集 情報誌『のんびる』1・2月号受注開始 パルシステム2025年12月16日
米が結ぶ人のつながり特集 情報誌『のんびる』1・2月号受注開始 パルシステム2025年12月16日 -
 天然植物活力液HB-101「フローラ公式ネットショップ」サイトリニューアル2025年12月16日
天然植物活力液HB-101「フローラ公式ネットショップ」サイトリニューアル2025年12月16日 -
 静岡県発いちご新品種「静岡16号」名前を募集中2025年12月16日
静岡県発いちご新品種「静岡16号」名前を募集中2025年12月16日




































































