農政:迫る食料危機 悲鳴をあげる生産者
【迫る食料危機】肥料、飼料も自給力を 「国消国産」へ国民理解の醸成を JA全中・中家徹会長に聞く2022年8月9日
日本の食料自給率の低さが問題であることは、常々言われていることだが、肥料や飼料、燃油などの生産資材の自給にも目を向けなければならない。コロナ禍やウクライナ侵攻などによる農業生産資材の不足・高騰は、改めてその重要性を我々に教えた。JA全中の中家徹代表理事会長は、輸入に頼るのではなく、国内資源を有効活用して、食料不足のリスクに備えるとともに、食と農の重要性について、国民理解醸成の必要性を強調する。改めて詳しく聞いた。
 JA全中 中家徹代表理事会長
JA全中 中家徹代表理事会長
肥料価格高騰は中長期的対策を 耕畜連携に国産飼料生産も
――肥料を中心とする生産資材価格の急騰は農業者の経営を圧迫しています。緊急および中・長期的にどのような対策が必要でしょうか。
かつてないほど生産資材価格が急騰し、農家は悲鳴をあげています。JA全中は先月の22日、緊急全国大会を開き、政府・与党に直面する課題への対策を要請しました。この問題は個々の農家やJAグループだけでは対応できないため、国の支援が必要です。こうした現場の声に応え、肥料価格の値上がり分の7割を国が支援する趣旨の施策が措置されることになりましたが、この状態が続くと、さらなる中・長期的な対策が求められます。
――中・長期的な対策として肥料・飼料の自給が求められていますが、どのような方法がありますか。
JAグループは、国の「みどりの食料システム戦略」もふまえ、化学肥料や農薬の使用を減らす取り組みを進めています。重要なことは、輸入に頼りすぎるのではなく、できる限り自国で肥料や飼料を賄うことです。
改めて耕畜連携への取り組みが重要となっています。そのために必要な施設整備など、国の支援を求めています。肥料のすべてを国内で自給するのは困難ですが、今日のような情勢とならないよう、可能な限り国内の資源を有効活用し、国産飼料の生産をすすめるべきです。
持続可能な農業の確立と消費者の理解を
併せて防除暦・施肥設計の見直しが必要です。標準の施肥量を示す施肥設計では、土壌条件によっては過剰になっているケースもあり、現状確認が必要です。過剰を防ぐにはほ場の土壌分析を徹底し、適正な施肥量を把握しなければなりません。
ただ減らすだけではリスクがあります。化学肥料・農薬の使用を減らしすぎて品質や収穫量に悪影響が出ないようにする必要があります。我々の使命は日本の食料に責任を持つ、持続可能な農業の確立です。こうした取り組みを消費者に理解していただきたいと考えています。
例えば、ある農産物を作る過程でどれだけ環境に配慮したかを指数で表せないか、それを消費者が評価する仕組みができないかと考えています。また、農産物は見た目がきれいなもの、形がいいものばかりではないという実態を知っていいただく必要があります。そして、農産物は需給で価格が決まるので、生産費の高騰を価格に転嫁することが非常に難しいです。そのため我々は、先日も、再生産のために必要な価格形成ができるような仕組みの構築について、政府・与党に要請しています。
また、畜産では特に酪農が危機的な状況にあります。飼料用の輸入牧草の値上がりが続いており、水田転作や休耕地の活用を進め、飼料自給率を高めなければなりません。全農が中心となって子実トウモロコシの実証を進めていますが、国内資源を活用した飼料生産に向け、これにも国の支援が不可欠です。
――耕畜連携は、日本の農業を変えるでしょうか。
国内資源の活用という意味でも耕畜連携は重要な課題です。すでに実践をすすめている地域も多くありますが、問題の一つは畜産と耕種の産地が離れているため流通コストがかかることです。この機会に、もう一度、耕畜連携の構築を重要な政策課題として取り組むべきだと考えています。
――食料生産の場である農業・農村の弱体化が進んでいますが。
これまで、食料自給率が低下し続けていることは、常に言われてきたことですが、問題は自給率だけでなく「自給力」の低下にあると考えています。高齢化や人口の減少による農業従事者の急激な減少、休耕地や荒廃農地の増加など、農業の生産基盤そのものが弱体化しています。食料自給は農家の経営が持続できないと成り立ちません。これ以上、農家と農村の弱体化が進むと自給力回復は望めなくなります。
"国消国産"へ消費者の行動変容目指す
――食料自給の必要性に対する国民の理解を深めるには、どのような取り組みが必要でしょうか。
食料自給率の低下に、どこかで歯止めをかけなければなりません。平成の30年間、日本の農業は右肩下がりが続きました。平成の終わりごろ、農業総生産額の減少ペースが鈍り、何とか下げ止まりにしたいと思っていたところにコロナ禍、ウクライナ問題です。
食料に関する国民の皆さんの理解は進んできていると感じますが、まだまだ時間がかかります。そのキーメッセージになるのが、我々が提唱している〝国消国産(こくしょうこくさん)〟です。国連が定めた世界食料デーである10月16日を国消国産の日とし、10月の1カ月間、様々な運動を展開します。一過性のものにするのではなく、JAグループ一体となって、情報発信を強化し、最終的に消費者の行動変容に繋がるようにしていきたいと思っています。
――食料・農業・農村基本法の見直しの動きがありますが。
最初の基本法が1999年にできて20年経過していますが、現場とのずれもみられます。当初、大規模農家を育てて農村を守り、肥料や飼料は輸入を前提にしたものでしたが、現実はそうはいかなかったと考えています。
農村を守るのは多様な担い手
農業は担い手経営体だけでなく、兼業・副業など多様な担い手の役割を、食料安全保障の面からも見直すべきです。基本計画の政策審議会企画部会委員として私が言い続けてきたことですが、農業・農村は誰が守っているのかということです。大規模経営の農家だけでなく、小規模な家族経営、あるいは兼業農家など多様な担い手がいてこそ農村は守られているのです。
そもそも海外の大規模な農業と競争すること自体が問題です。これまでの基本法では、その視点が抜けていたのではないでしょうか。農業と農村政策、つまり産業政策と地域政策は「真」の意味として車の両輪で、農村をどうするかがセットで議論されるべきです。
基本法見直しの声が出ることは、農政の流れが変わったのだと思います。併せて国民理解の醸成が必要ですが、これは短期間で成果があがるものではありません。欧州諸国のような理解を得るのは5年、10年と、地道な働きかけが必要となります。
5つのリスクが現実に 時間かけて国民理解醸成を
――食料自給について国民理解の醸成にはどのように取り組みますか。
かねがね私は、わが国の食料をめぐる5つのリスクを挙げ、警鐘を鳴らしています。①食料自給率の低迷②農業生産基盤の弱体化③自然災害の多発④世界的な人口増加⑤国際化の進展です。特にここにきてこうしたリスクが現実のもとなりつつあります。
食料の安定生産、安定供給する役目を担う立場として、JAグループはこの状況について国民の理解を広げなければなりません。コロナ禍のときのマスク騒動を挙げるまでもなく、需要に対してすぐ応じられるマスク等の工業製品とは異なり、農業は、緊急的に必要なものがあっても、それを供給するには何か月、あるいは数年かかります。国民理解の醸成は有機肥料と同じようなもので、すぐには効かなくても時間がたってじわっと効いてきます。そのような長期的な取り組みが必要です。コロナ禍、ロシアのウクライナ侵攻による食料危機は、食と農を考える契機になったと思います。10月16日の「国消国産の日」はその具体的な一歩です。この日を中心に国民理解の醸成に向けた情報発信を全国のJAグループが一体となってすすめていきます。
重要な記事
最新の記事
-
 米価上昇止まらず 4月7日の週のスーパー販売価格 備蓄米放出効果いつから2025年4月21日
米価上昇止まらず 4月7日の週のスーパー販売価格 備蓄米放出効果いつから2025年4月21日 -
 【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日
【人事異動】農水省(4月21日付)2025年4月21日 -
 【人事異動】JA全農(4月18日付)2025年4月21日
【人事異動】JA全農(4月18日付)2025年4月21日 -
 【JA人事】JA新ひたち野(茨城県)新組合長に矢口博之氏(4月19日)2025年4月21日
【JA人事】JA新ひたち野(茨城県)新組合長に矢口博之氏(4月19日)2025年4月21日 -
 【浜矩子が斬る! 日本経済】四つ巴のお手玉を強いられる植田日銀 トラの圧力"内憂外患"2025年4月21日
【浜矩子が斬る! 日本経済】四つ巴のお手玉を強いられる植田日銀 トラの圧力"内憂外患"2025年4月21日 -
 備蓄米放出でも価格上昇銘柄も 3月の相対取引価格2025年4月21日
備蓄米放出でも価格上昇銘柄も 3月の相対取引価格2025年4月21日 -
 契約通りの出荷で加算「60キロ500円」 JA香川2025年4月21日
契約通りの出荷で加算「60キロ500円」 JA香川2025年4月21日 -
 組合員・利用者本位の事業運営で目標総達成へ 全国推進進発式 JA共済連2025年4月21日
組合員・利用者本位の事業運営で目標総達成へ 全国推進進発式 JA共済連2025年4月21日 -
 新茶シーズンが幕開け 「伊勢茶」初取引4月25日に開催 JA全農みえ2025年4月21日
新茶シーズンが幕開け 「伊勢茶」初取引4月25日に開催 JA全農みえ2025年4月21日 -
 幕別町産長芋 十勝畜産農業協同組合2025年4月21日
幕別町産長芋 十勝畜産農業協同組合2025年4月21日 -
 ひたちなか産紅はるかを使った干しいも JA茨城中央会2025年4月21日
ひたちなか産紅はるかを使った干しいも JA茨城中央会2025年4月21日 -
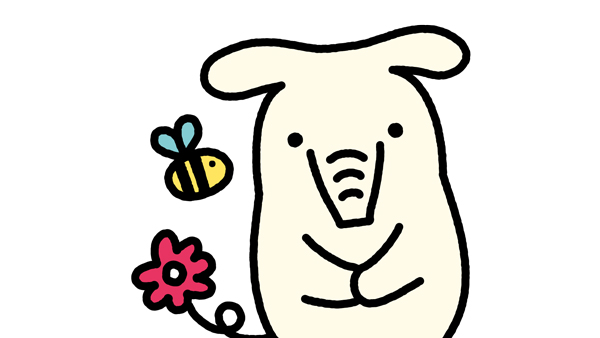 なじみ「よりぞう」のランドリーポーチとエコバッグ 農林中央金庫2025年4月21日
なじみ「よりぞう」のランドリーポーチとエコバッグ 農林中央金庫2025年4月21日 -
 地震リスクを証券化したキャットボンドを発行 アジア開発銀行の債券を活用した発行は世界初 JA共済連2025年4月21日
地震リスクを証券化したキャットボンドを発行 アジア開発銀行の債券を活用した発行は世界初 JA共済連2025年4月21日 -
 【JA人事】JA新潟市(新潟県)新組合長に長谷川富明氏(4月19日)2025年4月21日
【JA人事】JA新潟市(新潟県)新組合長に長谷川富明氏(4月19日)2025年4月21日 -
 【JA人事】JA夕張市(北海道)新組合長に豊田英幸氏(4月18日)2025年4月21日
【JA人事】JA夕張市(北海道)新組合長に豊田英幸氏(4月18日)2025年4月21日 -
 食農教育補助教材を市内小学校へ贈呈 JA鶴岡2025年4月21日
食農教育補助教材を市内小学校へ贈呈 JA鶴岡2025年4月21日 -
 農機・自動車大展示会盛況 JAたまな2025年4月21日
農機・自動車大展示会盛況 JAたまな2025年4月21日 -
 秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛の限定焼肉メニューは「真夏星」 JAタウン2025年4月21日
秋元真夏の「ゆるふわたいむ」おかやま和牛の限定焼肉メニューは「真夏星」 JAタウン2025年4月21日 -
 「かわさき農業フェスタ」「川崎市畜産まつり」同時開催 JAセレサ川崎2025年4月21日
「かわさき農業フェスタ」「川崎市畜産まつり」同時開催 JAセレサ川崎2025年4月21日 -
 【今川直人・農協の核心】農福連携(2)2025年4月21日
【今川直人・農協の核心】農福連携(2)2025年4月21日




























































