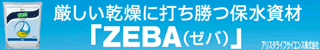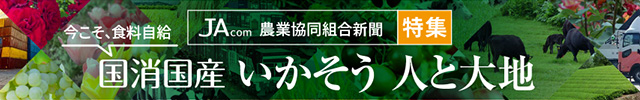農政:今こそ 食料自給「国消 国産」 いかそう 人と大地
【今こそ食料自給・国消国産】座談会 求められる価値観転換 今こそ食と命守る『協同戦略』を(2)2022年10月27日

【出席者】
ワーカーズコープ理事長 古村伸宏氏
蔵王酪農センター理事長 冨士重夫氏
農協協会会長 村上光雄氏
(司会・進行)文芸アナリスト 大金義昭氏
求められる価値観転換 今こそ食と命守る〝協同戦略〟を(1)から続く
基本法見直す好機 EU農政も参考に
大金 「国消国産」を具体的な成果に結びつけるためには、どんなことが求められますか。
村上 このタイミングで「食料・農業・農村基本法」見直しが農政審議会で開始されました。20年たっての改正ということで、時宜を得たことです。私たちは戦後、素晴らしい地域にしていこう、明るい農村を築こうとやってきたわけです。しかし、今の状況は、荒れ放題でとても持続できそうにない。先ほども申し上げた戦後77年の検証と総括の上に立って見直しをしてもらいたいと思います。
それと、今ウクライナ問題のなかで「防衛費をNATО並みのGDP比2%にしよう」という議論がなされています。「EU並み」というなら、ヨーロッパの農政も勉強して見習ってもらわないと困ります。ヨーロッパの農政は、環境を大事にして農業者を大切にし、手厚い支援で地域農業を守っています。
突破口の一つは「学校給食」
古村 私は、食料自給や地域農業の復興の突破口の一つは「学校給食」だと思っています。二つ意味があって、学校という「学びのコミュニティー」をどう再生していくかということと、子どもという存在を日本社会はどのように位置づけるかという、これがある意味、最大の尺度ではないかということです。
地域で育てた食べ物でも環境でも一番いいものをまずは子どもたちが享受する。子孫を優先しない生き物はこの世にいない。これは生き物としての基本原理です。「学校給食」に有機農業を採り入れようという動きが広がっていますが、単に食料の話ではなく地域文化ですよね。その結節点に「学校給食」があるんじゃないかと思っています。西洋にはない日本の最大の特徴は「里山」と「八百万(やおよろず)の神」でしょう。そのあたりを突破口に、「子どもや地域と食」をどうつなげるか。そこに文化的基盤としての農業をはじめとする第1次産業の役割もあると思います。
冨士 基本法の見直しですが、その哲学や理念は何なのか。それはWTO体制下での自由貿易推進が、そのバックボーンになっています。だからどんどん、農産物の関税率も下げていく。国内農業対策として農家に直接所得補償をするのはWTО上の黄色の政策とされて、それはできないから、代わりに多面的機能といった価値に着目してお金を払おうという考えです。しかも、基本方向は「プロの農家しか支えない。全国30万~40万戸でいいんだ」ということまで言いました。これを今回は根っこからひっくり返さなきゃダメなんです。
酪農からいうと、当時は年間800万トン体制でした。飲用牛乳が500万トンで加工が300万トン。今は飲用が350万トンで加工が450万トン、飲用と加工が逆転しました。少子高齢化で、飲用は減っていくだけ。需要が増えているのはチーズです。そういう乳製品やチーズにどうやったら日本の生産量を向けていけるか。乳価制度自体を用途別に不足払いして国産が成り立つ仕組みに変えないと、将来を支えていくことにならないのです。高騰する生産費を確実に価格転嫁できるような制度、例えばフランスの製造コストを基本に交渉する納入価格形成制度のような仕組みも整えてほしい。
地域の助け合いで活性化 開かれた農協ぜひ
大金 蔵王酪農センターが酪農を起点に取り組んでいる「6次産業化」の事業展開は、古村さんのお話に重なりますね。
冨士 取り組んでいるのは「食農教育」の一環です。小学校と、コカ・コーラの工場から出る「爽健美茶」の茶殻を活用した飼料を作って、コカ・コーラ工場の従業員・家族を招いて酪農研修、チーズづくりや乳製品づくりをしています。またJA女性部と、地元の農産物を使った料理教室を開いています。
このようにいろいろな人とつながりを持った事業展開を心がけており、地域の酪農家支援のための育成牛受託をしたり、農家の自給飼料とセンターから出るホエーを混ぜて配合飼料にするという拠点になったり、地域の和菓子メーカーと連携したクリームチーズを入れた大福、仙台イチゴにバターをかけたイチゴバターを作ったりと、地元の企業と連携しながら一緒になって新製品も作っています。地域社会においてはさまざまな人々がお互いが助け合うことで互いのいいところを結び合わせ、活性化していきます。
大金 果たすべきJAグループの役割は大きい。運動を農業復興・復活の発火点にするためには、どうすればいいでしょうね。
村上 国民の理解が今こそ問われているんじゃないか。コストの転嫁でもそうですし、「国消国産」でもそうです。ヨーロッパの農業は国民の理解を得て厚い助成金をもらっています。政策的に支えていかないと、農業は持続可能にならない。
その時に農協として何ができるかですが、まずは「地域に開かれた農協づくり」です。「食農教育」とか、女性組合員を増やすとか、准組合員さんも農協経営に参画するとか。進んだ取り組みをしている農協もありますが、まだ一部です。国民の理解醸成のためには、「子ども食堂」や「学校給食」に農協も積極的に関わるべきだし、JA全中を中心とした広報面での努力も必要でしょう。
子ども食堂を地域の結節点に
古村 ワーカーズコープの事業の拠点はたぶん全国500カ所以上ありますが、そういうところが結節点となりながら地域の人たちと一緒に、「子ども食堂」を100以上は運営していると思うんです。私たちの問題意識でいうと、亡くなられた内橋克人さんがずっと唱えてきた、食べ物のことだけ切り出すというよりは生存に必要な基本的な条件を地域のなかでまかない合おうじゃないか。それが食べ物(F)でありエネルギー(E)でありケア(C)です。そういう自給と循環の結節点、あるいは集約地を地域に見えるかたちで示していくことがすごく大事だと思います。
われわれは「総合福祉拠点」「みんなのおうち」と呼んできました。名前は何でもいいのですけれど、「共にこの地域で生きていきましょうというよりどころ」があって、そこに行けばいつでもお金がなくてもごはんが食べられるとか、エネルギーは地域のもので賄われているとか、いろんな困りごとを持ち込んでもいいし、いつでも誰でも来ていい。そうした多様な拠点が個性的なかたちでできていく。「子ども食堂」は、子どもはただ。働いている人はボランティア、食材もなるべく安く、ないしは無料で支援してもらったりしている。一方でフードバンクという仕組みも動いています。これらを有機的につなげる場です。
もう一つ、力を入れているのが「小農」の活動なんです。学童保育とか児童館とか保育園とか、とにかくあらゆる場所で、プランターでもいいし、缶でもいいから何か農作物を自分たちで育てる。すごく盛り上がっています。進んだところは、家庭から出る生ごみをコンポストに入れて堆肥にします。家庭ごみが劇的に減りますし、堆肥づくりは生き物を育てる感覚です。
食や循環を都市部で感じる取り組みは、「田舎に行きたい」「農家と交流したい」という動きにつながります。このような細くても多様なつながりを、多くの人たちが感じられるような拠点があったら、「眺める運動」じゃなくて「参加している運動」になり、「農」が他人事でなくて自分事になっていく。
農産物にある命の営み伝える必要
大金 「開かれた農協」という村上さんのお話や国連の「家族農業の10年」などと、「関係人口を増やす」古村さんのお話はしっかりクロスしますね。
冨士 情報発信で重要なのは、農産物は単なる製品とか商品じゃないということです。動植物という生き物を育て、それを殺生して頂く。そこには命の営みがありストーリーがあります。酪農でいえば、乳搾りばかりではなく、牛は子どもを産まなければ乳は出ないから繁殖が重要なわけです。子どもを産んだら、40リットルの血液循環があって乳腺を通って1リットルの乳が出る。そういう生き物としてのストーリーがあるし、その地域、地域で生きている固有品種などの自然との関わりによる物語がある。JA職員はこうした物語を消費者に伝えていく必要があります。
現在の農協の大きな課題は、いまの組合員が協同組合を作ってきた世代ではないということです。農協はすでに最初からあった。だから私はJA全中やJCAの役員時代から、組合員の組織づくりを通じた協同運動を提唱してきました。作物の組織や暮らしの組織を作っていくなかで、協同組合を疑似体験していく。そこに今、労働者協同組合法ができました。これを生かして総合農協の中に「ミニ労協」をいくつも作っていけないか。耕作放棄地や農作業受託組織などさまざまな「協同労働」が求められるものを「労協」という形にして地域に働く場を作っていく協同組織として発展する姿を描いていきたいのです。
労協拠点に共生めざす
古村 協同組合を作った経験者が少なくなっているということですが、労働者協同組合は法的には簡単に作れます。労働者協同組合は、協同組合を作る経験を反復するだけではなく、人間が共に生きていくという協同の営みを反復し直す仕組みともいえます。協同がしづらい世の中だからこそ、もっと協同組合を作って協同を取り戻す。それをコミュニティーと呼ぶとしたら、企業であっても学校であっても、入ってこられない人はいないでしょう。ここへ来れば困ったことは助けてもらえる。助けてあげられる。助け合える。
そういうよりどころ、人間としての根拠をなす場が形としてあることが大事です。こういう動きにコミットしようとする若者はものすごく増えていると思います。気候の問題も、日本では圧倒的に若者しかやってない。車でも住まいでも、占有から共有へ。「私だけ」ではなく「みんなで」。「共生・共存・共有」というマインドが強く、そういう匂いを感じないところには入ってきません。ワーカーズもまだ、若い人たちが大手を振って入ってこられるようになっていないのは、そのあたりに課題があるのかなあという気がします。協同組合全体もそうかもしれませんが、考えていることはかなり接点があるので、あとは醸し出す匂いとか音とか空気が勝負どころだと思います。
村上 国民みんなが「農」に関わることが大切だと思います。たとえば町の人がプランターで野菜を作ることで「農」への理解も深まるし、命の大切さもわかってもらえます。「農的な生活」が日本にはふさわしい。コロナ禍が徐々に収束していくと、問題が忘れられかねません。今が、ピンチであるとともにチャンスです。われわれも性根を据えて、国に言うべきことは言い、農協の役割、「協同労働」、食と農への理解を広げていきましょう。
大金 ありがとうございました。
座談会を終えて
国家・国権主義的な動向が国の内外で強まるなかで、そうした風潮に絡めとられることなく「国消国産」を真に実効性のある運動にしていく。その中心に協同組合があるのだなということを、改めて教えられた。いうまでもなく、軍拡よりも食料自給だ。
(大金)
重要な記事
最新の記事
-
 米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日
米価水準 「下がる」見通し判断増える 12月の米穀機構調査2026年1月8日 -
 鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日
鳥インフルエンザ 兵庫県で国内14例目を確認2026年1月8日 -
 創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日
創業100年のブドウ苗木業者が破産 天候不順で売上急減、負債約1億円 山形2026年1月8日 -
 花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日
花は心の栄養、花の消費は無限大【花づくりの現場から 宇田明】第76回2026年1月8日 -
 どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日
どんぐり拾い【酒井惇一・昔の農村・今の世の中】第371回2026年1月8日 -
 劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日
劇中でスマート農業に挑戦 ドラマ「ゲームチェンジ」が本日よりで放送開始 中沢元紀や石川恋をはじめ丹生明里らが出演2026年1月8日 -
 露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日
露地デコポン収穫最盛期 JA熊本うき2026年1月8日 -
 徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日
徳島県育ち「神山鶏」使用 こだわりのチキンナゲット発売 コープ自然派2026年1月8日 -
 長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日
長野県で農業事業に本格参入「ちくほく農場」がグループ入り 綿半ホールディングス2026年1月8日 -
 新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日
新潟・魚沼の味を選りすぐり「魚沼の里」オンラインストア冬季限定オープン 八海醸造2026年1月8日 -
 佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日
佐賀の「いちごさん」17品の絶品スイーツ展開「いちごさんどう2026」2026年1月8日 -
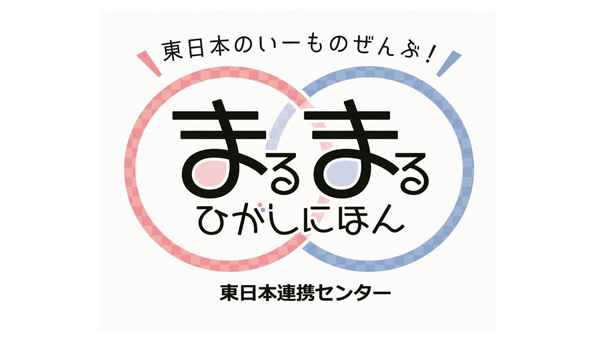 まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日
まるまるひがしにほん「青森の特産品フェア」開催 さいたま市2026年1月8日 -
 日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日
日本生協連とコープデリ連合会 沖縄県産もずくで初のMELロゴマーク付き商品を発売2026年1月8日 -
 鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日
鳥インフル 米国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -
 鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日
鳥インフル 英国からの生きた家きん、家きん肉等 輸入を一時停止 農水省2026年1月8日 -
 人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日
人気宅配商品の無料試食・展示会 日立市で10日に開催 パルシステム茨城 栃木2026年1月8日 -
 住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日
住宅ローン「50年返済」の取扱い開始 長野ろうきん2026年1月8日 -
 埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日
埼玉で「女性のための就農応援セミナー&相談会」開催 参加者募集2026年1月8日 -
 熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日
熊本県産いちご「ゆうべに」誕生10周年の特別なケーキ登場 カフェコムサ2026年1月8日 -
 外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日
外食市場調査11月度 2019年比89.6% 5か月ぶりに後退2026年1月8日