【アグリビジネスインタビュー】持続性を追求 食料の安定生産に貢献 クミアイ化学工業 高木誠代表取締役社長2023年5月25日
食料安全保障への関心が高まり、国内の食料生産基盤の強化が求められるなか、今後は持続可能な農業も重要になる。系統農薬メーカーとしてどう農業を支えていくか、2021年の就任後、サステナビリティー基本方針を打ち出した系統メーカーであるクミアイ化学工業の高木誠社長に聞いた。
 クミアイ化学工業 高木誠代表取締役社長
クミアイ化学工業 高木誠代表取締役社長
農薬は食料生産と直結
――わが国の食料、農業、さらに農薬業界をめぐる情勢、課題をどう考えていますか。
コロナ禍による世界の物流停滞に加え、ウクライナ情勢の悪化により、関係諸国からの小麦、肥料の輸出が制限を受け、世界中が大混乱しました。すべての商品の価格が上がり農業従事者も消費者も本当に大変な状況だと思っています。特に穀物の安定供給は世界全体の食料問題に大きく関わっており、これがどんなに大切かを改めて実感する機会になったと思います。
日本国内に限定すると、いわゆる高齢化、少子化で農業就業人口が大きく減少し、耕作放棄地の面積が増えているなか、手放された農地を集約して経営する農業法人の数が増えている状況です。
しかしながら、当社が独自に行ったアンケートでを労働力不足を経営課題に挙げる農業法人が約6割を超えており、当社としても農業の省力化は非常に大きな課題であると認識しています。
当社が生産・販売している農薬は、安定的な食料生産に不可欠な生産資材であり、私たちは創業以来、効果と安全性が高く環境負荷の低い、農業の省力化に資する製品の開発・販売を行ってきました。引き続きこのような製品の開発・販売を通じ、農業が抱える課題の解決に大きな貢献していきたいと考えています。
今後、さらに農作業の効率化を加速させていくためには農業機械メーカーやIT企業をはじめ、農業に関わる異業種の方々との交流や情報交換などを通して日本農業全体の生産性を上げていくことが非常に重要だと考えています。
当社の国内営業担当は全国の生産者や流通関係者、指導機関とのパイプを有しており、現場が抱えているニーズをすぐにつかむことができます。それらをうまく生かしていくことで業界の枠を超えて、新しい資材や散布方法の開発などに取り組み、日本農業が抱えている課題の解決に貢献していきたと思っています。
みどり戦略「問題なし」
――経営の基本指針の1つであるサステナビリティー基本方針では、「みどり戦略」にも触れられていますね。
サステナビリティー基本方針は私が社長に就任した2021年11月に策定したものですが、ちょうどその年の5月にみどりの食料システム戦略が策定されていたため、サステナビリティー基本方針の中に含めることにしました。
みどり戦略ではKPI(重要業績評価指標)の一つとして2050年までに化学農薬の使用量をリスク換算で50%低減するということが掲げられています。これは一見、非常にセンセーショナルなKPIで、当社の事業が将来半分になってしまうのではないかと不安を覚えた社員もいたと思いますが、私は社員に対して、「何もうろたえることはない」と伝えました。
みどり戦略が目指すのは、やみくもに農薬の使用量を半分にすることではなく、イノベーションで新しい技術を生み出すことによって生産性を向上させ、同時に環境への負荷を減らしていくことであり、それは、当社が創業以来進んできた方向性と何も変わりません。
これまで当社は少量で高い効果を発揮する農薬の開発を続けてきました。10a当たり3キロだった水稲用除草剤の散布量は、今では12分の1となる250グラムにまで減少しました。また、安全性の指標であるADI(一日摂取許容量)の数値は徐々に上昇しており、安全性も向上しています。このように当社の農薬は、農作業の省力化はもちろん、安全性の向上や環境負荷の低減にも大きく貢献してきました。今後も少量で高活性な新農薬の開発を継続していくことこそが、みどり戦略ひいては持続可能な農業の実現につながると考えており、自信をもって事業に取り組んでいきます。
さらに当社では化学農薬だけではなく、バイオスティミュラントや微生物農薬、作物の免疫システムに働きかける、抵抗性誘導剤などの開発も進めています。みどり戦略が目指すIPМ(総合的病害虫管理)の推進にも積極的に取り組んでいきたいと考えています。
社長就任以来、強力に推し進めてきたサステナビリティー経営ですが、昨年、マテリアリティ(重要課題)に対するKPIを外部に発表しています。一番の課題である温室効果ガス排出量については、2030年までに2019年度比で30%削減することを目標としています。
具体的にはグリーン電力への切り替え、あるいは工場の熱源ボイラーの燃料を重油からガスへ切り替えるなど、コストは上がりますが、可能な限り排出削減につながるよう全社を挙げて進めています。
また、水田から排出されているメタンガスを抑制する技術の実用化に向けた研究開発も継続しています。
若者が夢持つ農業に
――新しい研究所も稼働するとのことですね。
当社の化学研究所は創薬研究センターと製剤技術研究センター、プロセス化学研究センターの三つの組織から成り立っています。静岡県に点在する、これらの研究センターを静岡市清水区に集結させた新研究所Shimizu Innovation Park(ShIP)が今年の秋に稼働する予定です。静岡県の各地に散らばっていた研究員が一カ所に集まることでシナジーが生まれ、新しい事業の芽を作り出す夢のある拠点になると期待しています。
――JAグループへの期待を聞かせてください。
農産物は非常に長いサプライチェーンがあり、いろいろな業種の会社が足並みをそろえて日本農業を盛り上げていくという取り組みをしていかなければいけないと思っています。そのなかでJAグループはこれまで長い間培ってこられたノウハウや各業界とのつながりをお持ちですから、業界同士をひもで結びつけるような、バインダーとしての役割が非常に大きくなっていると思っています。
当社もJAグループと一緒になって日本農業をサポートし、若者が農業に対して明るい未来を感じられるように、農業を変革していくお手伝いをさせていただければと思っています。
【会社概要】
主な事業は農薬および化成品の製造販売。事業セグメントは「農薬及び農業関連」、「化成品」、「その他」。1949年に「庵原農薬株式会社」として静岡市清水区で設立。1962年に「イハラ農薬株式会社」に、1968年に「クミアイ化学工業株式会社」に称号を変更した。2017年にイハラケミカル工業と経営統合。2022年に東京証券取引所同プライム市場に指定。本社所在地は東京都台東区池之端1丁目4番26号。国内に7支店(札幌、東北、東京、名古屋、大阪、中四国、九州)、2研究所(化学研究所、生物科学研究所:静岡県)、3工場(原体製造:静岡県、製剤製造:宮城県、兵庫県)を保有。企業理念は『私たちは創造する科学を通じて「いのちと自然を守り育てる」ことをメインテーマとし、安全・安心で豊かな社会の実現に貢献します』。
【高木社長プロフィール】
たかぎ・まこと 1957年12月静岡市生まれ。1981年慶応義塾大学工学部卒業、クミアイ化学工業㈱入社。入社後は社長室(現経営企画部)を7年間経験。1988年に入社当初からの希望だった国外部に異動し、その後24年間にわたり海外営業に携わる。2013年から3年間グループ会社である日本印刷工業の社長を務めた後、常務取締役として帰任し、2021年に代表取締役社長に就任。
重要な記事
最新の記事
-
 【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日
【特殊報】果樹などにチュウゴクアミガサハゴロモ 県内で初めて確認 兵庫県2025年12月16日 -
 【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日
【特殊報】トマト青かび病 県内で初めて確認 栃木県2025年12月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(1)2025年12月16日 -
 【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日
【プレミアムトーク・人生一路】佐久総合病院名誉院長 夏川周介氏(中)農村医療と経営は両輪(2)2025年12月16日 -
 鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日
鳥インフルエンザ 兵庫県で国内7例目を確認2025年12月16日 -
 「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日
「第3回高校生とつながる!つなげる! ジーニアス農業遺産ふーどコンテスト」受賞アイデア決定 農水省2025年12月16日 -
 「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日
「NHK歳末たすけあい」へ150万円を寄付 JA全農2025年12月16日 -
 米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日
米の流通に関する有識者懇話会 第3回「 研究者・情報発信者に聴く」開催 JA全農2025年12月16日 -
 【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日
【浅野純次・読書の楽しみ】第116回2025年12月16日 -
 北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日
北海道農業の魅力を伝える特別授業「ホクレン・ハイスクール・キャラバン」開催2025年12月16日 -
 全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日
全自動野菜移植機「PVZ100」を新発売 スイートコーンとキャベツに対応 井関農機2025年12月16日 -
 Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日
Eco-LAB公式サイトに新コンテンツ開設 第一弾は「バイオスティミュラントの歴史と各国の動き」 AGRI SMILE2025年12月16日 -
 国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日
国内草刈り市場向けに新製品 欧州向けはモデルチェンジ 井関農機2025年12月16日 -
 農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日
農機の生産性向上で新製品や実証実験 「ザルビオ」マップと連携 井関農機とJA全農2025年12月16日 -
 農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日
農家経営支援システムについて学ぶ JA熊本中央会2025年12月16日 -
 7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日
7才の交通安全プロジェクト 全国の小学校に横断旗を寄贈 こくみん共済coop2025年12月16日 -
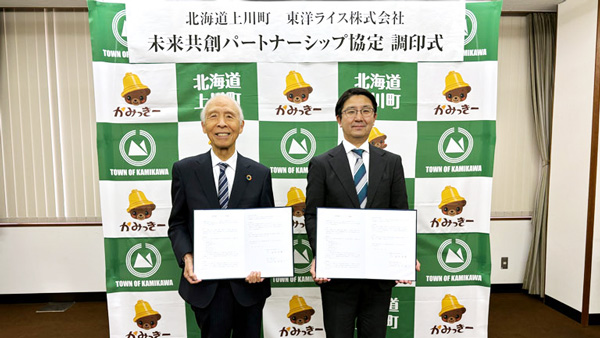 北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日
北海道上川町と未来共創パートナーシップ協定を締結 東洋ライス2025年12月16日 -
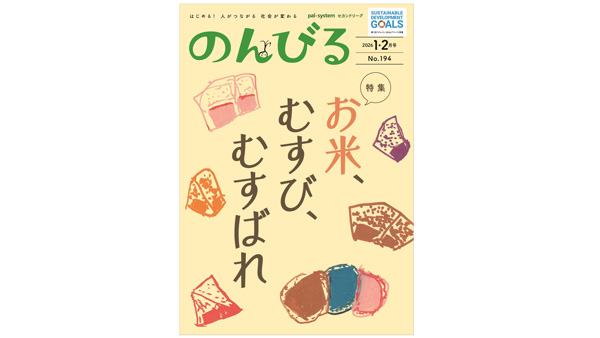 米が結ぶ人のつながり特集 情報誌『のんびる』1・2月号受注開始 パルシステム2025年12月16日
米が結ぶ人のつながり特集 情報誌『のんびる』1・2月号受注開始 パルシステム2025年12月16日 -
 天然植物活力液HB-101「フローラ公式ネットショップ」サイトリニューアル2025年12月16日
天然植物活力液HB-101「フローラ公式ネットショップ」サイトリニューアル2025年12月16日 -
 静岡県発いちご新品種「静岡16号」名前を募集中2025年12月16日
静岡県発いちご新品種「静岡16号」名前を募集中2025年12月16日




































































