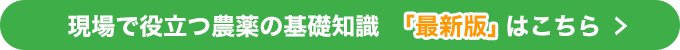農薬:現場で役立つ農薬の基礎知識 2013
【現場で役立つ農薬の基礎知識 2013】[7]土壌消毒剤の上手な使い方2013年6月21日
・ショウガ根茎腐敗病、雑草、ネコブセンチュウ
・ピーマンピーマンモザイク病、ネコブセンチュウ、疫病
・キュウリキュウリ緑斑モザイク病、ネコブセンチュウ
・メロンメロンえそ斑点病、黒点根腐病、ネコブセンチュウ
地域特性を活かした特産品のブランド化や産地形成に向けた取組みの中で、高品質な農作物を持続的、安定的に生産していくために避けて通れないのが連作障害の克服である。単一作物を長年にわたり作付けし続けると土壌中に病原菌や害虫が特異的・選択的に増殖し、収量や品質の低下を招くことになるからだ。連作障害には肥料成分のアンバランスや微量要素の不足などを要因とする場合もあるが、本特集では土壌病害虫とその防除薬剤を中心にまとめてみる。
土壌病害虫の総合的な防除薬剤として長年にわたり使用されてきたのが臭化メチル剤。ウイルスや病害虫への効果のほか、除草効果も期待でることから生産現場で中心的な役割を果たしてきた。しかし、1992年の「モントリオール議定書」の中でオゾン層破壊関連物質に指定されたことから、95年以降、先進国では使用規制が実施され、この間、代替技術や代替薬剤の開発が難しい不可欠用途(特例措置)に限って使用が認められてきた。わが国ではキュウリ、メロン、トウガラシ類、ショウガおよびスイカについて継続使用が認められていたが、これらについても昨年12月末で全廃となり、農業現場は臭化メチル剤を全く用いない栽培体系へと全面移行することになった。
臭化メチル全廃の動向をにらんで2008年度から5年間にわたり、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)中央農業総合研究センターを中心に地域試験研究機関などが参加した「臭化メチル剤から完全に脱却した産地適合型栽培マニュアルの開発」が進められた。その研究成果は、脱臭化メチル栽培マニュアルとして昨年12月に公開されており、研究開発はさらに向こう2年間延長されることが決まり、より地域に適合した技術開発が展開されることになった。以下、その脱臭化メチル栽培マニュアルの概要について作物ごとに防除薬剤を中心に紹介する。
(写真)
露地ショウガ栽培で欠かせない土壌消毒剤
【ショウガ】
露地ショウガについては、栽培面積458ha、生産量2万1000トン(平成23年度)と国内最大の産地である高知県の高知県農業技術センターがまとめている。防除ポイントは根茎腐敗病、雑草およびネコブセンチュウ。根茎腐敗病は土壌中に残ったショウガ残さが伝染源となる。このためほ場に残さを残さないように管理するとともに、残った残さの腐熟促進に務め、これに先だって健全な種根茎の重要性を指摘している。
根茎腐敗病やネコブセンチュウの土壌消毒剤としては、クロルピクリン、クロルピクリン+DーD、ダゾメット、DーD(いずれも有効成分、以下同様)などを前年度の発生程度に合わせて使い分けることを薦めている。
また収穫後に根や根茎をできるだけ除去してセンチュウ密度を低下させ、冬期間に石灰窒素を散布してセンチュウの死滅を図るとしている。
尚、ショウガをはじめ臭化メチルの代替剤として近年、全国的に普及活動が行われてきた薬剤にヨウ化メチルがあるが、供給メーカーはこのほど、主原料であるヨウ素の世界的な需給ひっ迫を背景に原料確保のめどが立たないとして土壌用ヨウ化メチル剤の販売を本年末で終了させることを明らかにしている。
【ピーマン】
日本一のピーマン産地である茨城県の茨城県農業総合センターは、主要な土壌病害虫としてトウガラシマイルドモットルウイルス(PMMoV)によるピーマンモザイク病、ネコブセンチュウ、疫病をあげている。モザイク病についてはエライザ法により土壌中のウイルス濃度を診断し、そのエライザ値に応じて抵抗性のL4品種栽培、さらに定植時の紙包み法、生分解性ポットや植物ワクチン(弱毒ウイルス)の利用をマニュアル化している。新技術としてプランターの利用により根圏を隔離する養液土耕栽培も提案している。
また促成栽培ピーマンについては鹿児島県農業開発総合センターがマニュアルをまとめている。主要病害虫としてあげているのはモザイク病、青枯病およびネコブセンチュウ。モザイク病については栽培終了後、土壌汚染度を測定し汚染度に応じてフェーズ3(汚染度:高)では植物ワクチンの接種、同2(中)では生分解性ポットの使用、同1(低)では残さ腐熟促進という三段階の技術導入を経て、ウイルスフリーの慣行栽培を目指すモデルを提案している。
ネコブセンチュウには耕種的防除や熱利用の物理的防除などのほか、薬剤としてクロルピクリン、クロルピクリン+DーD、DーD、カーバムナトリウム塩などの効果的利用を薦めている。
【キュウリ】
キュウリ緑斑モザイクウイルス(KGMMV)によるキュウリ緑斑モザイク病やネコブセンチュウが主要病害虫となっている。キュウリ緑斑モザイク病では有効な抵抗性品種や弱毒ウイルスがないため、感染原となる残さ除去や腐熟処理など感染拡大の防止策が中心となり、宮崎県総合農業試験場や愛知県農業総合試験場がマニュアルを作成している。
まん延防止策としては次亜塩素酸カルシウムや第3リン酸ナトリウムによる摘果ハサミの消毒などもある。またネコブセンチュウの登録薬剤にはクロルピクリン、クロルピクリン+DーD、DーD、カーバムナトリウム塩などのくん蒸剤のほか、ホスチアゼート、オキサミル、イミシアホスなど。
【メロン】
千葉県農林総合研究センターはメロンえそ斑点病、黒点根腐病のほか、ネコブセンチュウを中心にマニュアルをまとめている。
メロンえそ斑点病が発生した場合は、抵抗性品種を導入するとともに、作付前のクロルピクリン+D―Dによる土壌消毒で、えそ斑点病の媒介菌密度を下げこと、またトマトの輪作も薦めている。トマトの作付前の土壌消毒としては、ネコブセンチュウが発生した場合にDーD、黒点根腐病が発生した場合にクロルピクリン、両方が同時発生した場合にはクロルピクリン+DーDによる土壌消毒を行うとしている。
中央農業総合研究センターと地域試験研究機関がまとめた栽培マニュアルは、作型や気象条件、土質など各地域で異なる条件を加味して導入する必要がある。
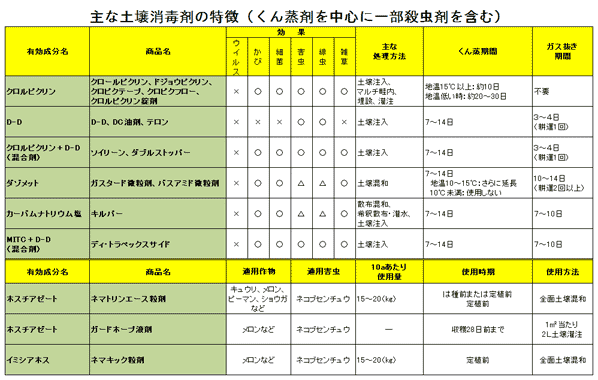
土壌消毒には、太陽熱消毒、熱水・蒸気消毒、土壌還元消毒などの物理的手法をはじめ低濃度エタノールを使用した方法も確立されており、薬剤による防除を含めて生産現場の状況に応じて最適な対策を実施していくことが重要になる。主な土壌消毒剤(一部、殺虫剤を含む)を表にまとめた。最新の農薬登録情報・ラベルを確認した上で活用していただきたい。
重要な記事
最新の記事
-
 米農家(個人経営体)の「時給」63円 23年、農業経営統計調査(確報)から試算 所得補償の必要性示唆2025年4月2日
米農家(個人経営体)の「時給」63円 23年、農業経営統計調査(確報)から試算 所得補償の必要性示唆2025年4月2日 -
 移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日
移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(1)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日 -
 移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日
移植水稲の初期病害虫防除 IPM防除核に環境に優しく(2)【サステナ防除のすすめ2025】2025年4月2日 -
 変革恐れずチャレンジを JA共済連入会式2025年4月2日
変革恐れずチャレンジを JA共済連入会式2025年4月2日 -
 「令和の百姓一揆」と「正念場」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月2日
「令和の百姓一揆」と「正念場」【小松泰信・地方の眼力】2025年4月2日 -
 JAみやざき 中央会、信連、経済連を統合 4月1日2025年4月2日
JAみやざき 中央会、信連、経済連を統合 4月1日2025年4月2日 -
 サステナブルな取組を発信「第2回みどり戦略学生チャレンジ」参加登録開始 農水省2025年4月2日
サステナブルな取組を発信「第2回みどり戦略学生チャレンジ」参加登録開始 農水省2025年4月2日 -
 JA全農×不二家「ニッポンエール パレッティエ(レモンタルト)」新発売2025年4月2日
JA全農×不二家「ニッポンエール パレッティエ(レモンタルト)」新発売2025年4月2日 -
 姿かたちは美しく味はピカイチ 砂地のやわらかさがおいしさの秘密 JAあいち中央2025年4月2日
姿かたちは美しく味はピカイチ 砂地のやわらかさがおいしさの秘密 JAあいち中央2025年4月2日 -
 県産コシヒカリとわかめ使った「非常時持出米」 防災備蓄はもちろん、キャンプやピクニックにも JAみえきた2025年4月2日
県産コシヒカリとわかめ使った「非常時持出米」 防災備蓄はもちろん、キャンプやピクニックにも JAみえきた2025年4月2日 -
 霊峰・早池峰の恵みが熟成 ワイン「五月長根」は神秘の味わい JA全農いわて2025年4月2日
霊峰・早池峰の恵みが熟成 ワイン「五月長根」は神秘の味わい JA全農いわて2025年4月2日 -
 JA農業機械大展示会 6月27、28日にツインメッセ静岡で開催 静岡県下農業協同組合と静岡県経済農業協同組合連合会2025年4月2日
JA農業機械大展示会 6月27、28日にツインメッセ静岡で開催 静岡県下農業協同組合と静岡県経済農業協同組合連合会2025年4月2日 -
 【役員人事】農林中金全共連アセットマネジメント(4月1日付)2025年4月2日
【役員人事】農林中金全共連アセットマネジメント(4月1日付)2025年4月2日 -
 【人事異動】JA全中(4月1日付)2025年4月2日
【人事異動】JA全中(4月1日付)2025年4月2日 -
 【スマート農業の風】(13)ロボット農機の運用は農業を救えるのか2025年4月2日
【スマート農業の風】(13)ロボット農機の運用は農業を救えるのか2025年4月2日 -
 外食市場調査2月度 市場規模は2939億円 2か月連続で9割台に回復2025年4月2日
外食市場調査2月度 市場規模は2939億円 2か月連続で9割台に回復2025年4月2日 -
 JAグループによる起業家育成プログラム「GROW&BLOOM」第2期募集開始 あぐラボ2025年4月2日
JAグループによる起業家育成プログラム「GROW&BLOOM」第2期募集開始 あぐラボ2025年4月2日 -
 「八百結びの作物」が「マタニティフード認定」取得 壌結合同会社2025年4月2日
「八百結びの作物」が「マタニティフード認定」取得 壌結合同会社2025年4月2日 -
 全国産直食材アワードを発表 消費者の高評価を受けた生産者を選出 「産直アウル」2025年4月2日
全国産直食材アワードを発表 消費者の高評価を受けた生産者を選出 「産直アウル」2025年4月2日 -
 九州農業ウィーク(ジェイアグリ九州)5月28~30日に開催 RXジャパン2025年4月2日
九州農業ウィーク(ジェイアグリ九州)5月28~30日に開催 RXジャパン2025年4月2日